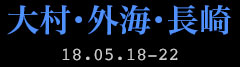
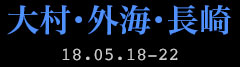

|
 |
 |
 |
|
オオムラザクラ。八重桜を二つ重ねたような花が咲くそうです。国の天然記念物。
|
玖島稲荷神社。1480年に領主が京都の伏見稲荷から分霊したのが始まり。 | 藩主の御居間跡の碑。明治初期に少年鼓手浜田謹吾の父が建てたもの。 |
 |
 |
 |
| 板敷櫓台。1614年の改修で築かれたもの。櫓は再建。 | 新蔵波止。1686年、幕府が官米三千石を運んで預けた時、二つの蔵と共に築かれた波止。 | 大村藩御船倉跡。四代藩主純長が十七世紀末から十八世紀初めに作ったもの。御座船など藩の船を格納したもの。往時は屋根があったそうです。 |
 |
 |
 |
| 身代わり観音。家老が幼い次代藩主の身代わりとして、三歳の自分の娘を刺殺。それを祀るもの。 | 殺された家老の娘亀千代の墓。二代藩主純頼が急死、幼い子どもは跡継の届け出もまだで、さらに大病になり、藩は取り潰しの危機。 | 家老大村彦衛門は自分の娘の命を差し出すと神仏に祈願。相続の許可がおりると、ほんとに自分の娘を殺しちゃったという野蛮な話。こちらは家老の墓。 |
 |
 |
 |
| 雨風が強くなる中、寺島へ。1661年に妙音寺という円融寺の末寺が創建されたので寺島。伊予の大洲を出た大村氏が初めて上陸したところとか。 | 細い通路で港と結ばれているんだけど、風が強くて、とても怖い。 | 妙音寺は1694年に移転したけど、祀られていた弁財天や大黒天は廃仏毀釈で市杵島(いちきしま)神社となって、今に至ります。竜神社も明治八年に遷座。 |
 |
 |
 |
| 夫婦岩。994年、大村氏がここに船をつないで上陸したとか。 | 武家屋敷街に戻り、これは五教館御成門(ごこうかんおなりもん)。大村藩の藩校で、武士の師弟だけでなく一般にも聴講を許したとか。 | 石井筆子(ふでこ)像。幕末の生まれで、女性教育に貢献し、子どもが知的障害児だったことから、日本初の知的障害児施設滝乃川学園を創設した人。 |
 |
 |
 |
| 久原城跡。大村氏が最初に入った城の跡。塀は民家のもの。手前の坂は異国の囚人などを入れる牢があったので、牢屋の坂と呼ばれているそうで。 | 小姓小路。線路で分断されています。 | 小姓小路近くの日向平武家屋敷街にある中尾家。五色塀もあるとても美しいお屋敷。 |
 |
 |
 |
| 小姓小路。坂道に延々石垣と植え込みが続いています。 | これは稲田家家老屋敷跡。お城のような石垣。 | 謎のインターネットのお店? 十分百円とありますが。 |
 |
 |
 |
| 片町稲荷神社。 | 境内にある川原悠々の句碑。幕末の大村藩士で俳人。全国俳諧十指に数えられたとか。 | 大村龍踊りの龍はまるでキングギドラ。 |
 |
 |
 |
| 本殿です。 | 隣は片町公民館。 | アーケードに戻って、ここはかつての長崎街道大村宿本陣跡。後ろはデパートだったようです。 |