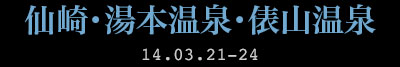
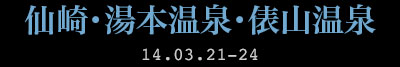

|
 |
 |
 |
|
大寧寺への旧参道の入口です。馬頭観音が祀られているので、観音坂。お地蔵さんも並んでいます。
|
参道を進むと温泉街入口の踏切です。左手にトンネルがあります。 | いろいろ祀られています。 |
 |
 |
 |
| 赤い帽子のお地蔵さんが点々と連なっています。 | 大寧寺(たいねいじ)に到着。1410年創建の西の高野と言われるお寺。大寧寺川にかかる赤い橋は虎渓橋。 | 盤石橋は1668年に架けられ、1764年に再建。自然石の組み合わせでできています。錦帯橋、虹橋(現存せず)と合わせて防長三奇橋と言われた橋。 |
 |
 |
 |
| 山門跡。1677年に再建された巨大な門があったけど、明治末に倒壊。現在再建資金集め中。 | 本堂。1640年に野火で焼失した後、焼け残った衆寮(僧侶の宿舎)を1829年に本堂として移築したもの。 | 大きな建物ですが、焼失前のものはもっと大きかったとか。梵鐘は1396年に筑前で鋳造された古いもの。 |
 |
 |
 |
| 経蔵跡。1551年、大内義隆が陶隆房らの反乱にあい、この地に逃げ込んだ時、家臣の冷泉隆豊が割腹して天井にはらわたを投げつけたというところ。 | 大内義隆主従の墓所。山口に京文化を開花させた人だけど、文弱が反乱を招く。青海島から海路逃れようとするも、悪天候に阻まれ大寧寺で自害。 | たくさんの墓石が並んでいます。戦乱で七堂伽藍は灰となりました。 |
 |
 |
 |
| 斜面に江戸時代初期からの萩藩重臣の墓が無数に並んでいます。 | 様々な様式の墓が並び、墓石の博物館のようと案配板にありました。 | 長門豊川稲荷。明治初め、藩内の対立で豊川稲荷に身を寄せていた住職が、廃仏毀釈でつぶされそうになった豊川稲荷の救済に力を貸した御縁とか。 |
 |
 |
 |
| 釈迦三尊と十六羅漢。江戸初期のもの。元は大寧寺川の向こう岸の三笑岩という岩場にあったけど、県道工事で岩場は破壊されてしまったとか。 | ここから俵山温泉。湯本温泉からバスで二十分ほど。これはバス乗り場です。 | いい名前の食堂です。 |
 |
 |
 |
| 名物三猿まんじゅうなどを売るお店。 | こちらも三猿もなかに三猿まんじゅう。元祖と書いてありますが。もう一軒あるようです。 | 俵山温泉の町並み。狭い道沿いに宿が並んでいます。ほとんどの宿には内湯がなく、外湯に入りに行くという古典的スタイル。 |