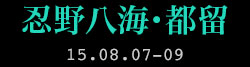
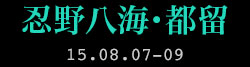

|
 |
 |
 |
|
忍草に戻る途中にある浅池。かつて浅太郎というおじいさんがこの湧き水の池で水車を回して精米製粉をしていて大賑わいだったとか。今は食堂の庭園。
|
忍野八海の一つ、出口池。ここは水が湧いているあたり。一番大きな池。 | 出口池の石碑は1843年に富士講の一つ大我講が禊の池として八つの池に立てたもの。他にも幾つか残っています。 |
 |
 |
 |
| 出口池は離れたところにあるので、人も少なくて静か。 | 富士吉田の北口本宮富士浅間神社を再訪。これは仁王門の礎石。明治の神仏分離で三重塔、鐘楼と共に失われたもの。 | これは神楽殿。 |
 |
 |
 |
| 西宮本殿。1594年に谷村城主浅野氏が建立したもので、国の重文。 | 東宮本殿は1561年に武田信玄が富士権現を造営した時のもの。国の重文。 | 境内にある諏訪神社。創建未詳で、元々諏訪神社があった地に浅間神社を勧請したようです。 |
 |
 |
 |
| 諏訪神社にあった富士山型神輿。 | 富士急行普通列車の車内。のれんは水戸岡鋭治の得意技。CTはCommuter Trainの頭文字。 | 都留市駅はなかなかおもしろいデザイン。 |
 |
 |
 |
| 駅前通りの建物。銀行か何かだったのでしょうか。 | 菱形の明り取りが面白い家。 | 円通院(えんづういん)。1467年に開創、1633年に城主が現在地に移す。何か、ごちゃごちゃ感のあるお寺。 |
 |
 |
 |
| 山門は覚雄殿という名前。1748年のもの。 | これは報恩塔。染物工場の古材使って1968年に着工。設計は当時の住職さんとか。六角堂を重ねたようなおもしろい建物。 | これは五雲閣という建物。会堂でしょうか。 |
 |
 |
 |
| 円通院境内の元坂(もとざか)の石橋。江戸時代前期のものを移築。元坂というところにあったもの。 | ふるさと会館にある芭蕉の句碑。「山賤のおとがい閉るむぐらかな」という句。谷村藩の一揆の情報を聞き出そうとしたことを詠んだとは井伏鱒二の説。 | 芭蕉が逗留した桃林軒という建物が再建されていました。 |
 |
 |
 |
| 全面なまこ壁の蔵。 | 洒落た洋館がありました。 | 四つ角にある洋風建築。何のお店だったのか。 |