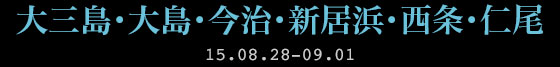
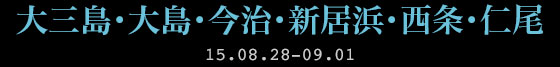

|
 |
 |
 |
|
大山積神社。1691年の別子銅山開業時から移転しつつずっと祀られているそうで。今でもお祭りは新居浜の住友系企業がやっているそうです。
|
記念館の入口は地下に入ってくように作られています。中は撮影禁止ですが、非常にこぎれい。海面下まで続く坑道の模型は見ごたえありました。 | 入口に置かれた銅鉱石。 |
 |
 |
 |
| 四阪島大煙突記念碑。亜硫酸ガスによる煙害防止に1924年に作られた大煙突。煙害は1893年から1939年まで続きました。2013年に老朽化で解体。 | 記念館脇にある生子橋(しょうじばし)と精練夫の像。かつては木製で、鉱山鉄道の駅から銅山記念館前にあった精練所に鉱石を運ぶのに使われたそうです。 | 下を流れる国領川は別子ライン(ライン川になぞらえている)といわれる渓谷美。 |
 |
 |
 |
| 生子橋の向こうは内宮(うちのみや)神社。これは急な方の石段。ちなみにサイトは一見の価値あり(笑)。 | 左が内宮神社、右は稲荷神社。 | 内宮神社拝殿。伊勢神宮の内宮(ないくう)から勧請して706年に創建されたとか。 |
 |
 |
 |
| これは摂社の一つ。苔むしていい感じ。 | 内宮神社本殿。特に古くはなさそうですが、石塀の苔が雰囲気あり。 | 新居浜太鼓祭りでは、この石段を数トンもある太鼓台が駆け上がるのだそうです。すぐ脇に山根収銅所があります。 |
 |
 |
 |
| 内宮神社の参道途中には鉱山鉄道の跡が続いていました。右側のコンクリは坑道から収銅所へ続く水路。収銅所には山根駅がありました。 | バスで山を登りマイントピア別子へ。鉱山観光の施設。1930年から採鉱本部があった端出場(はでば)というところ。 | 大ばく(おおばく、ばくは金偏に白)。元旦の大ばく祭に大山積神社に奉納されていた良質な鉱石。300キロあります。今も小ばく祭なるものが行われているとか。 |
 |
 |
 |
| 精練所のある四阪島で使われていたミゼットの消防車。 | アノードと呼ばれる粗銅。 | こちらは新居浜太鼓祭りで使われる太鼓台。これは小型の子ども用。 |
 |
 |
 |
| 鉱山鉄道の路線を使った観光用の鉄道が走っています。 | 別子一号機関車を模した機関車は電動です。 | 途中で渡る打除(うちよけ)鉄橋は1892年の貴重なもの。住友が設計してドイツの製橋会社が制作。日本鉄橋百選の一つとか。 |
 |
 |
 |
| 端出場駅跡に展示されている4トン蓄電池式機関車。坑内で充電したのだそうです。 | 端出場駅跡。港の方の惣開(そうびらき)駅とを結ぶ別子鉱山鉄道下部線の終点。ここから山の上の上部線とは索道(ロープウェイ)でつながっていたそうです。 | 人車。坑内で作業する人たちが出入りするのに乗ったもの。カゴ電車は一般の人も乗ったけど、こちらは坑夫さん用らしいです。 |
 |
 |
 |
| こちらは2トン蓄電池式機関車。主に小さな坑道で使われたそうで。 | 大空600型ローダー。坑道を作るときに掘った鉱石や石を鉱車に積み込むためのもの。圧縮空気で動きます。ちょっとカワイイ。 | 鉱山観光の坑道入口。火薬庫として使われていたところだとか。 |