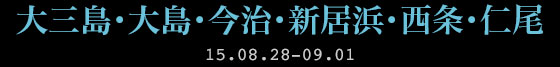
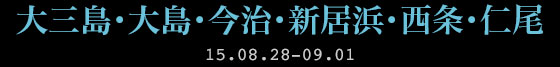

|
 |
 |
 |
|
これは1905年に煙害解決のため、新居浜沖20キロの四阪島(しさかじま)に作られた精練所。ところが煙害はかえって広がり、1939年まで解決せず。
|
ちょいと不気味な坑内の照明。 | 江戸ゾーン入口は1691年に開かれた最初の坑道歓喜坑の再現。銅山の前途を祝して抱きあって歓喜したからこの名前。標高1210メートルの山の上にあります。 |
 |
 |
 |
| つぼと呼ばれる堀場。つちとのみの手作業。左端に見えるのは梯子。 | 坑内の水を抜くための手動のポンプ。昼夜絶え間なく排水を続ける必要がありました。何で賽銭あげるかなあ。 | 延々地上までこのポンプが続きます。うーん、ものすごく大変そう。 |
 |
 |
 |
| 歓喜坑を出るとすぐ風呂場が作られていたそうです。 | 砕女(かなめ)小屋。砕女と呼ばれる女性が金槌で鉱石を砕き、色で選別。 | 精練の様子。輸出用も作っていたそうです。 |
 |
 |
 |
| 仲持ち(なかもち)。運搬夫/婦のこと。銅山から粗銅を運び出し、帰りは米や味噌を運んだそうです。 | 山(さん)神社。坑内でも大山積神を祀っていました。 | なかなか雰囲気ある照明。 |
 |
 |
 |
| 鉱山鉄道が開通した明治以降の様子を再現した大ジオラマ。 | 人形が動いたりして、なかなか味わいがあります。 | 鉱山鉄道も走ります。 |
 |
 |
 |
| 走る鉱山鉄道。日本初の山岳鉱山鉄道だとか。今も山の上に遺構が残ります。 | 山の上の住居で宴会する人々、背後には何やら夢を語る?経営者。煙害と伐採ではげ山となり、1899年には別子大水害が発生、五百名以上が亡くなっています。 | 中央付近に見えるのは索道。鉱石を運ぶロープウェイです。 |
 |
 |
 |
| 火薬が爆発した時の爆風の抜け穴として作られた立坑。 | 坑内水を流すための煉瓦水路。強酸性の鉱毒水を山根収銅所まで流した水路の一部。 | 外から見た打除鉄橋。奥に見える中尾トンネルも鉱山鉄道開通時のもの。 |
 |
 |
 |
| 第四通洞。1915年に開通した別子銅山の大動脈。長さ4600メートル。1973年の閉山まで使われました。 | 中を覗いてみました。温度差で白い霧が立ちこめ、怪しい雰囲気。線路が残っています。 | 第四通洞坑口前の鉄橋、四通橋。1919年開通。 |
 |
 |
 |
| マイントピアのマイクロバスで東平(とうなる)へ。1916年から1930年まで採鉱本部があったところ。遺構が残っています。手前は貯鉱庫跡。下は索道基地跡。 | インラクイン跡。生活用品や資材を運ぶため、一種のケーブルカーがありました。今は220段の階段。マイクロバスはガイド付きでちょっと慌ただしい。 | 索道基地跡。1905年に完成した鉱石、生活用品、木材などを運ぶロープウェイの基地。 |