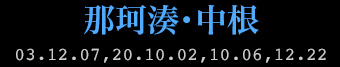
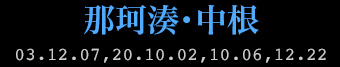

|
 |
 |
 |
|
大きな建物はその名残なのでしょうか。これはその増築?部分。
|
那珂湊天満宮。創建は鎌倉時代。当時は満福寺泉蔵院というお寺で神仏混交。徳川光圀の時代に神仏分離で神社になった模様。 | 鳥居と社殿の間の御中座という場所。元は山上にあったけどい賓閣建設でここに遷座、さらに享保年中に今の場所に移ったので、ここを御中座というそう。 |
 |
 |
 |
| 和田町若者中と刻まれた石碑。三百年くらい前に周囲の石垣を築造した記念碑らしいです。 | 現在の拝殿はコンクリート。今もお祭り(八朔祭)の時には神輿を一度御中座に泰安するそう。 | ちょっとユーモラスな狛犬がいました。 |
 |
 |
 |
| 本殿は木造でした。享保年間(十八世紀前半)のもので、徳川光圀が元禄年間に奉納した御神体の菅原道真像も健在だそう。 | 湊公園は徳川光圀が1698年につくらせた水戸藩の別邸い賓閣の跡。建物は幕末の元治甲子の乱で焼失。この広場はミステリー・サークルみたい。 | 建物はありませんが、光圀が明石から取り寄せたと言う松は健在。樹齢三百年以上。2003年より支えの棒が減っています。 |
 |
 |
 |
| 湊公園のイワレンゲの群落。絶滅危惧種だそうで、市の天然記念物。 | 湊公園から那珂川、大洗方面を見る。往時は海防見張番も置かれ、異国船の監視をしたとか。左の建物は大洗水族館。右の大きな橋は海門橋。 | 湊公園の文学碑。右は与謝野晶子。左は小山いと子の小説『海門橋』。できた時から歪んでいたという四代目海門橋建設に材をとった作品だそうです。 |
 |
 |
 |
| 湊公園ふれあい館。1972年に那珂湊勤労青少年ホームとして開館。今は公民館的なものに。白亜紀荘といい、こういうデザインが流行ったのでしょうね。 | お寺の門かと登っていったら、那珂湊第一小学校の門でした。ここは徳川斉昭がつくった藩校文武館の跡。尊王攘夷の拠点になったとか。 | 華蔵院(けぞういん)は1163年頃の創建。派手な仁王門は1957年の再建。 |
 |
 |
 |
| 最近塗り直した感じですね。元治甲子の乱では燃えなかったものの、明治三十五年の台風で倒壊してしまい、五十年後の再建とか。 | 龍神堂は1999年の再建。1864年に海上交通の安全を期して勧請したそうです。 | 仁王門の裏側には三面六臂の大黒天がいました。 |
 |
 |
 |
| 梵鐘は1339年のもの。幕末に大砲鋳造のため鋳潰されそうになったけど免れたとか。 | こちらが本堂。元治甲子の乱で七堂伽藍は燃えてしまい、明治十四年に再建したようです。二階部分は1974年の増築。 | これは薬師堂。1934年の再建らしいです。 |
 |
 |
 |
| 明治四十三年の暴風雪で亡くなった439人の漁民の慰霊碑。 | 山門の上の猫。華蔵院の猫が野原で猿や狸と宴会、見かけた村人が和尚さんに話すと猫は姿を消したとか、和尚さんのおかみさんを食い殺したとかいう民話。 | 山門も比較的新しそう。左右の端に猫がいます。 |
 |
 |
 |
| 稲葉屋という和菓子屋さん。反射炉のてっぽう玉という黒飴が名物。創業は明治初期、建物は明治二十年のもの。まちかど博物館の一つ。 | 那珂川の対岸に見えるのは那珂湊マリーナ。 | 崖沿いにある水神宮。 |
 |
 |
 |
| 屋根が重なるような家。 | ちょっと登ったところにある稲荷神社。詳細は不明ですが、ほどよく古びていました。 | その近くの西瀧不動尊の霊水。古来より枯れたことがないそう。 |