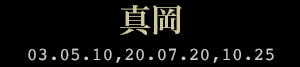
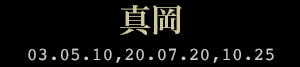

|
 |
 |
 |
|
レンタサイクルで二宮尊徳資料館に向かいます。これは途中にあった三嶋神社の摂社で八龍神社。
|
こちらが三嶋神社。 | 観音寺。かつて二宮尊徳が鐘を奉納したとか。 |
 |
 |
 |
| 彫刻が見事です。 | 中をのぞくと立派な社が幾つもありました。 | 穴川に架かる報徳橋。報徳とは二宮尊徳の経済思想、学説。報徳とは経済と道徳の融和を訴える思想のようです。 |
 |
 |
 |
| すぐ近くの農家の石蔵。 | 大きな農家でした。 | 二宮尊徳資料館に到着。これは報徳訓の碑。報徳の教えが刻まれているようです。 |
 |
 |
 |
| 二宮尊徳資料館。銅像は例の薪背負ってるものではありません。中は撮影禁止。小学生とかも意識したわかりやすい展示。 | 桜町二宮神社の狛犬。白い石の台座が不自然ですが、元はどうなっていたのでしょう。 | 桜町二宮神社は二宮尊徳の没後五十年の明治三十八年に創建。社殿は没後八十年の1936年にここに移って新しくなったもの。 |
 |
 |
 |
| 桜町陣屋。1823年、尊徳が桜町復興に着任した時に建てられたもの。二十六年間、ここに住み、周辺の村々の復興に尽くしたとか。 | 奥の次の間で仕事をしていたそうです。この地で報徳仕法という独自の農村経営と思想哲学を編み出したそう。 | 上段の間から見る。板戸に清濁?月などと書いてあります。 |
 |
 |
 |
| 報徳田と呼ばれる田んぼが復元されていました。尊徳は明治以降、修身の教科書に取り上げられたりして、国家に献身する政策に利用されます。 | 陣屋の入り口の部分は土塁で升形のようになっています。往時は長屋や書物蔵など建物がいろいろ建っていたそう。 | お隣の蓮城院というお寺にある尊徳像。いわゆる負薪読書図ですが、本当にこんなことしていたかは不明。石像は石材業者が流行らせたとか。 |
 |
 |
 |
| 蓮城院の尊徳の墓碑(右端)。1865年に日光で仕事中に今市で亡くなり葬られたけど、門人が娘の墓のあるここに遺髪を葬ったもの。 | 蓮城院。1851年に尊徳が桜町仲宮からここに移転再建したそう。 | 蓮城院の謎の倉庫? 灯篭がたっていますが、何なのでしょうね。 |
 |
 |
 |
| 駐車場は桜町史跡公園として、池など整備されていました。 | 専修寺(せんじゅじ)を目指して行くと、親鸞橋という橋がありました。 | 専修寺の門前。親鸞が稲田に滞在布教していた時に、真岡城主大内氏に懇請されて作られたのが始まりとか。1225年の創建。境内全域が国の史跡。 |
 |
 |
 |
| 総門は茅葺き。これはただ一つ残っている創建当時の建物で、国の重文。 | 総門と直角に建てられている長屋門。 | 親鸞お手植えという古木が保存されていました。創建から七年あまりをここで過ごし、東国布教の中心となったとか。 |