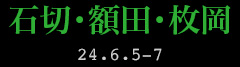
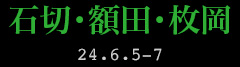

|
 |
 |
 |
| 石切駅のオペレーターは男性でした。名前はないのかな? | 枚岡駅で降りるとすぐ枚岡神社です。 | ここにも剣が立っています。 |
 |
 |
 |
| なで鹿というものがいました。祭神の一柱、武甕槌尊(たけみかづちのみこと)が神鹿に乗って鹿島立ちしたからだそう。1846年、日下の小平次という名工の作だそう。 | 拝殿は明治十二年の再建。式内社で河内国一宮。 | 本殿。祭神が四柱いるので、四つあります。いずれも1826年の再建。粥を煮て、篠竹についた粥の多少で豊凶と占う粥占神事なるものが行われているそう。 |
 |
 |
 |
| 摂社が並んでいます。 | 陶器の中華風?狛犬がいました。 | 神社横手にある姥が池。困窮して御神灯の油を盗んで売っていた老婆が身を投げたという伝説あり。 |
 |
 |
 |
| 創建の地だという本宮に行ってみようと歩き出しましたが……。 | 紫陽花がきれいでしたが、行けど行けども行き着かない。 | こんな洒落た側溝?がありました。 |
 |
 |
 |
| エッチな木もありました。 | 枚岡展望台に到着。 | 大阪の街が一望。左手の高い建物がアベノハルカス。 |
 |
 |
 |
| どうやら本宮の入口のようです。 | 神津嶽本宮に到着。建物は1993年に建てられた新しいものなのでした。 | 暗(くらがり)峠を目指して進みます。石造りの側溝が続いていました。 |
 |
 |
 |
| 春紅葉がきれいです。秋にはすごいだろうなあ。 | 椋ヶ根(くらがね)橋に到着。この先が暗峠への道。 | すんごい急坂が延々と続きます。奈良時代に難波と平城京を結んでいた暗越(くらがりごえ)奈良街道です。今は何と国道308号。 |
 |
 |
 |
| 暗越奈良街道の碑。後ろの石は長持石というらしいです。 | 芭蕉の句碑。山津波で不明になったのを明治二十三年に再建。芭蕉は奈良から暗峠を越えて大阪に入り亡くなっています。「菊の香に くらがり登る 節句かな」 | 途中にあった法照寺というお寺。 |
 |
 |
 |
| 大きな塔のような建物もありました。 | 赤い橋は豊浦橋。紅葉の名所。あたりは枚岡公園となっています。 | 滝もありました。川は豊浦川。暗渓(あんけい)という渓谷です。 |
 |
 |
 |
| 観音寺というお寺です。 | 境内の豊浦川沿いに立つ不動明王。 | 境内には旧奈良街道が残っていました。参勤交代にも使われたというんだけど、ここを大名行列?! |