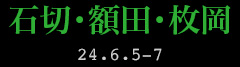
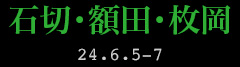

|
|
大阪と奈良を隔てる生駒山、その大阪側の山麓を彷徨。2020年の正月のテレビドラマ『贋作 男はつらいよ』は、柴又と雰囲気が似ているという石切劔箭(いしきりつるぎや)神社参道が舞台。行ってみようと思ったけどコロナやら何やらで頓挫して四年、やっと実現。
近鉄石切駅から急な坂道を下るとすぐに石切神社門前の商店街。狭い坂道沿いにごちゃごちゃとお店が続いているけど、半分くらいは占いの館(笑)。いったいここは何?と思いつつ坂道を下るも行けど行けども占い。怪しい和風・中華風の古道具を並べてやたらと賽銭箱のある店など壮観。漬物屋や名物よもぎうどんの店などもあるけど異様な雰囲気。坂道を下りきった石切神社にはお百度石をこより?を折りながら往復する十数人の老若男女。時代劇ではよく見るけど、本当にお百度を踏んでいる人は初めて見ました。いったい、ここは?(笑)。線路を挟んで山裾の上之社や周辺にちょっと残る古い屋敷も見る。 二日目は枚岡神社から大阪と奈良を結ぶ暗(くらがり)峠に挑む。枚岡(ひらおか)神社の奥の院に行ってから、と思ったのが大間違いで思わぬ山登り。たどり着いた奥の院はピカピカに新しい社殿でした。暗峠に向かうも場所によっては三十度以上という坂道が延々続く。途中の滝や寺社に寄り道して進むも、堪え難い急坂で三分の二ほどで挫折。坂道を膝をガクガクさせながら引き返す。午後は額田から枚岡の街中に点在する寺社回り。 三日目は石切から山裾を登って興法寺へ。細い坂道沿いに石仏が点々と続いている。川沿いに再現された水車はもう朽ちかけていました。何ヶ所か脇道があって、奥にはお寺。でも、これが普通の民家のような謎の寺ばかり。後で調べると朝鮮寺といって、在日韓国・朝鮮人の方の主に女性が信仰する民間信仰的なものらしいです。廃虚になっているところもあって、ちと怖い。急坂の石段を息を切らして登ると興法寺。でも本堂はコンクリ(笑)。山を下りて、旧生駒トンネルとか、かつては観光地だったという池や街中の社寺をまわる。斜面にずらりと並ぶ住宅街はそれはそれで壮観。 三日間、ひたすら坂道を上り下りの旅でしたが、別世界が見られたようで、おもしろかったな。 |
 |
 |
 |
|
近鉄大和西大寺駅にいたインフォメーション・ロボットのアリサちゃん。人型をしていることが大事なのでしょう。四カ国語対応なり。
|
石切駅を降りて、参道商店街入口にたつ歓迎の看板と灯篭。 | 泊まった宿のすぐ前を近鉄の電車が引っ切りなしに通っていました。 |
 |
 |
 |
| すぐ側にある願掛け地蔵と墓地。1711年の建立開眼。 | 石切参道商店街の入口。ここから下り坂に沿って、延々とお店が連なっています。 | 入ってすぐにある三階建ての衣料品店。 |
 |
 |
 |
| その隣の古典的荒物屋さん。 | こういう洗濯ばさみ、まだ売っているんですねえ。大阪ではピンチと言うの? | 参道沿いにある千手寺(せんじゅうじ)の入口。七世紀頃、役行者が創建という伝説。 |
 |
 |
 |
| 桂文之助の句碑。明治時代に活躍した上方落語の名人だそう。「業平と背中合せのぬくさかな」とは芭蕉のパロディだそう。 | 在原業平と菅原道真を祀ったお堂。 | こちらが本堂のようです。 |
 |
 |
 |
| こちらが山門なのでした。 | 門前にある在原業平公腰掛石。戦乱で消失するも在原業平が再見したという伝説。 | 石切大仏。日本で三番目だそうですが、何が? |
 |
 |
 |
| 坂本正胤という人が1980年に建立。 | 大仏境内にある蝮塚。阪本正胤は赤まむしの阪本漢方製薬の当主で、蝮供養のためのもの。 | 大仏の向かいにあるなかなかすごいデザインのレストラン。 |
 |
 |
 |
| さらに進むと石切不動明王。ロウソク一本と線香三本、セットで五十円とありました。 | ちょっと困ったような不動明王。 | 三玉屋食堂ではウサギがちょっと一休みと誘っていますが、やっていないようでした。 |
 |
 |
 |
| ここら辺から占いの館が並んでいます。右手の豊八大黒殿をのぞいて見ると……。 | 七福神に手作り感あふれる賽銭箱が。 | 中華風の狛犬、奥には大黒様と賽銭箱が。 |
 |
 |
 |
| 半円形で作るのけっこう大変そうな賽銭箱です。 | 長屋形式で中が仕切られているけど、元は何だったんでしょうね。よくわからないけど、賽銭箱。 | 下から見た大黒殿。向かいも占いの館。 |
 |
 |
 |
| ズバリ当るタロットって、もう何でもあり。 | 占い銀河の舟って、名前はいい感じ。 | 右側は手相がメインのようです。 |