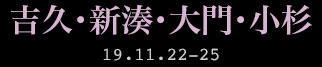
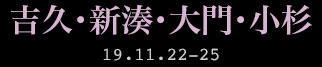

|
 |
 |
 |
|
八百屋さんの鏝絵。八百屋画廊なるものがあるらしいです。
|
小杉展示館では子どもの絵画展が行われていました。明治四十四年建築の旧小杉貯金銀行本店です。 | 金庫が残っていました。 |
 |
 |
 |
| 金唐革紙(きんからかわかみ)。和紙を革に似せて加工したもの。明治始めから戦前にかけて、貴重な輸出品にもなった高価なもの。 | 古小杉焼の緑釉瓢大徳利。1816年頃から1890年頃まで小杉で作られた焼き物。緑色が美しい。 | 独特の形の鴨徳利。明治になり藩の保護もなくなり、安価な瀬戸や有田の陶磁器に押されて廃窯となりましたが、現在は一つの窯が復興。 |
 |
 |
 |
| トタンが見事な家。 | 十社大神(じゅっしゃおおかみ)の参道。1215年に蓮王(れんのう)寺境内の十社を合祀した十社大明神が始まりとか。 | 宝物殿には鎌倉時代の木造狛犬や室町時代の能面、竹内源造らの鏝絵の絵馬などが収められているそう。 |
 |
 |
 |
| 宝物殿にかかっていた鏝絵。昭和二年にさらに伊勢領神明社など三ケの十四社を合祀して現在の十社大神になったそう。 | 十社大神の社殿。伊勢神宮の1993年の式年遷宮で出た古い部材を譲り受けて作られたらしいです。 | 境内の摂社の一つ。 |
 |
 |
 |
| 神明社は富山新港建設で全員立ち退きになった片口村のものを1971年に遷座。 | 水上北莢(みずかみほくらい)顕彰碑。幕末の人で書画や陶芸などに通じ、熱心な寺子屋の師匠でもあったとか。明治初年のもの。 | 社殿をのぞいてみました。天岩戸の絵馬は水上北莢の手になるものらしいです。 |
 |
 |
 |
| 神馬殿前の紅葉。今回、紅葉らしい紅葉はここぐらいでした。 | 白黒の神馬。白馬は1821年のもので伊勢神宮からとか。黒馬は天保年間(1831〜1845)のものらしいです。雨乞いは黒馬に晴れ乞いは白馬に祈るとか。 | 伊勢神宮の遥拝所がありました。 |
 |
 |
 |
| 別の参道にあるおかげ橋は竹内源造の晩年の作品。 | 二体が収められたおんぞはん。 | 蓮王寺境内の藤原秀郷(俵藤太)の五輪塔。 百足退治の後、任国の下野国に帰る途中、この地で病没したとか。上の二つは南北朝、他は室町時代のもの。 |
 |
 |
 |
| 蓮王寺の不動明王。 | もっと大きな不動明王。 | 鏝絵は、百合若大臣が愛鷹の供養のために建立とか、立山を開山した佐伯有頼の父越中国司有若が鷹の供養のために建立したとかいう話から。 |
 |
 |
 |
| 本堂は1966年のもの。創建は701年とか。 | 本堂の中。 | 本堂の小杉大仏。平安時代に建立されるも戦火で焼け、頭と手だけが残ったとか。胴体は江戸中期のもの。 |