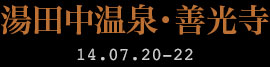
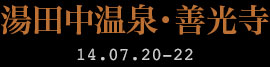

|
 |
 |
 |
|
仲見世はいつも賑やか。
|
山門。1750年の建築。平成大修理で建立当時と同じサワラの板を使った栩葺き(とちぶき)に戻されたとか。以前に行った時はその修理中でした。 | 山門はいつもは上がれない二階内部を公開中でした。重要文化財。 |
 |
 |
 |
| 山門二階から見た仲見世です。 | 本堂はいつ見ても巨大さに圧倒されます。1707年の建築。国宝。間口24メートル、奥行き54メートル、高さ26メートル。 | 善光寺資料館は日本忠霊殿に移されていました。 |
 |
 |
 |
| 牛に引かれて……というわけで、乳牛親子象が森永から寄贈されていました。母親が喜子さん、娘が光子さん。 | 本堂の裏のあたりは少し整備されたような感じがしました。 | 迷子郵便供養塔。年間180万通もあるという配達不能の郵便を供養するもの。1971年の建立。生け花の花を供養する花霊碑なるものもありました。 |
 |
 |
 |
| 徳川大奥供養塔。家光の正室や春日局などの供養塔。徳川家は善光寺を篤く信仰していたとか。 | 千人塚または二斗八塚。江戸初期、慶長年間の百姓一揆の犠牲者を供養するもの。延宝年間の一揆二斗八騒動で処刑された人々の供養塔とも。 | 確か以前はこの建物が資料館だったような気がするのですが。 |
 |
 |
 |
| 斜め後ろから見た本堂。とにかく巨大です。 | 鐘楼は1853年の再建。柱が六本なのは珍しい。梵鐘は1667年のもので今も時鐘として使われています。重要美術品なり。 | 経蔵。1759年のもので重文。中には八角形の回転する輪蔵があります。 |
 |
 |
 |
| むじな灯籠。むじなが人に化けて参拝、灯籠を寄進したかったけど、お風呂で正体がばれて逃げ帰る。不憫に思った住職が建てたというもの。 | 善光寺本坊大勧進。善光寺のすぐ前にあります。善光寺の住職はここと尼寺の善光寺大本願の住職が二人で務めます。右から護摩堂、位牌堂、萬善堂。 | 源義経の忠臣佐藤兄弟のものといわれる宝篋印塔。片方には1397年の銘があり、この地方最古のもの。 |
 |
 |
 |
| 大勧進の大門。1789年のもの。 | 大勧進の放生池。十八世紀の天命大飢饉に大勧進が貧民救済に蔵米を放出した時、関係者の奉仕で作られたという池。亀がたくさんいました。 | 善光寺門前東側には宿坊が並んでいます。左が福生院、右が吉祥院。 |
 |
 |
 |
| 全部で三十九もあり、宿泊することができます。これは蓮華院。 | 宿坊の一つ世尊院の釈迦堂。重文の鎌倉時代の珍しい釈迦涅槃像があるお寺。973年に漁師の網にかかったとか。 | 白蓮坊。むじな灯籠のむじなが泊まったのはこの宿坊だそうです。ちなみにむじなは下総国からやってきたそうで、今の茨城県五霞町。 |