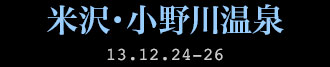
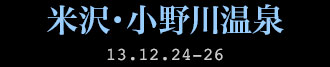

|
 |
 |
 |
|
近くにある滝の清水。小野小町の開湯以来、千年湧き続けているとか。水道が通る前は唯一の生活用水だったとか。
|
不二乃湯二階堂旅館。春になれば、藤の花で彩られるのでしょうか。 | 豆腐地蔵。豆腐をお供えすると子どもの夜泣きがなくなるとかいうお地蔵様。雪で近づけませんでした。近くに明治時代創業の豆腐屋さんもあります。 |
 |
 |
 |
| 小野川名物豆もやし場と看板にありました。温泉の熱で、冬場に豆もやしを作っています。 | 豆もやし場。湯気とブルーシートで幻想的な雰囲気。 | ここはもやしを洗うところなのでしょうか。 |
 |
 |
 |
| 柿の実がまだたくさん木についていました。 | 河川公園では木々に霜がついて美しい風景。 | 小町山の登り口。千二百年前に小野小町がこの上にしばらく住んで湯治したとか。 |
 |
 |
 |
| 小町山の甲子(きのえね)大黒天本山。弘法大師が作った甲子大黒天を祀っているそうです。 | 甲子大黒天の上にある観音堂。その上には小野小町の居住跡があるそうですが、雪が深くて行けませんでした。 | 甲子大黒天から温泉街を見下ろす。 |
 |
 |
 |
| 温泉街に戻り、扇屋旅館。明治三十四年の大火の後、建て替えたもの。上杉家当主や『泣いた赤鬼』の浜田広介らも泊まったそうで。 | 扇や旅館の右端には小町観音が祀られていました。小野川の奥地から平成十四年にここに移したとあるのですが、小町山の観音様なのでしょうか。 | 温泉街の中心にある外湯の尼湯と、手前は浜田広介の歌碑。米沢の隣の高畠町の生まれで、帰郷すると小野川温泉に立ち寄ったとか。 |
 |
 |
 |
| 高砂屋。創業は江戸時代のようです。小野川温泉は美人の湯として売り出し中。戦国時代には伊達政宗も湯治にきたとか。 | 薬師堂。小野小町建立という湯の神。父を捜す旅で、病に倒れた小野小町は、峯の薬師の導きで温泉に辿り着いて治癒したとか。 | 薬師堂入口にある小町の休み石。病を得た小野小町が休んだという石。当時小町は十八歳だったとか。 |
 |
 |
 |
| 亀屋万年閣。百二十年くらい前の建物。ちなみに、秋田の湯沢の方には、小野小町が生まれ、亡くなったところだという話が伝わっています。 | 大樽川は蛍の生息地。夏にはほたるまつりもあるそうで。蛍供養塔なるものがありました。 | 川沿いにある露天風呂小町の湯。冬はお休み。 |