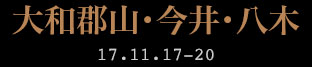
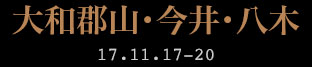

|
 |
 |
 |
|
佐保川沿いにある枳殻(きこく)地蔵。奈良時代は船着場で街道の分岐点で、地蔵が祀られたのが始まり。
|
中にはお地蔵さんがいっぱい。河川改修工事などで出土したものだそうです。枳殻とはからたちのことで、かつてはからたちの木が植えられていたとか。 | 佐保川の堤を歩きました。 |
 |
 |
 |
| 川沿いのお墓。 | お墓の側、榎の下に六地蔵が立っていました。 | 稗田(ひえだ)の環濠の脇を走る下ツ道。古代からの幹線道路。平城京の朱雀大路につながっています。 |
 |
 |
 |
| 稗田環濠集落の入口。環濠(堀)で囲まれた集落です。大和の環濠集落の代表例。 | 堀沿いに見える大和棟の家。室町時代には今のような堀に囲まれた形になっていたとか。 | 稗田の街並み。古事記編纂者の一人稗田阿礼(ひえだのあれ)を輩出した稗田一族の里。 |
 |
 |
 |
| 道が見通せるところがほとんどなく、道路側に窓がほとんどありません。 | 賣太(めた)神社のかたりべの碑。稗田阿礼を祀る神社だから。稗田阿礼は日本のアンデルセンだと、1930年から阿礼祭なるものを行っているそうで。 | 賣太神社。創建は不明ですが、1400年くらい前らしいです。 |
 |
 |
 |
| 境内にあった稗田橋の石柱。近代の創作童話のアンデルセンと古代の歴史書の稗田阿礼を並べるのは無理があると思いますが。 | 賣太神社裏手の大きな家。 | こういう細い通りが入り組んで走っています。 |
 |
 |
 |
| 必ず視界が遮られるようになっています。 | 行き止まりの先に門があったりします。 | 整備された環濠と蔵。 |
 |
 |
 |
| 堀におりる石段がありました。 | 若槻環濠集落。こちらの環濠はかなり改変されて細いものになっていました。 | 若槻の街並み。稗田と同じような感じです。十五世紀中ごろには堀が作られたようです。 |
 |
 |
 |
| 渋い土壁の蔵。 | 天満神社の牛と池? | 天満神社拝殿。 |
 |
 |
 |
| 天満神社本殿。境内には観音堂もありました。 | これも環濠の名残なのでしょうか。 | 道祖神でしょうか。 |