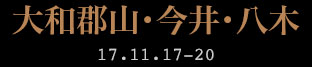
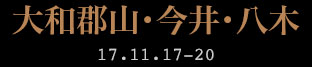

|
 |
 |
 |
|
黒壁に袖壁のついた家。
|
明治中期に建てられた家だそうです。 | 谷三山(たにさんざん)の生家。幕末の儒学者。幼い頃聴力を失うも、勉強して私塾「興譲館」を開いたりした人。頼山陽や吉田松陰とも親交があったとか。 |
 |
 |
 |
| 谷三山生家と道を隔てた家。こちらも古そう。下ツ道沿いです。 | 下ツ道沿いの路地。左は谷三山生家。 | 後ろから見た谷三山生家。 |
 |
 |
 |
| 福島家。高取藩の下屋敷で、参勤交代の起点となった家。1725年の建築。御殿部屋があるそうです。 | 岡本家のお洒落な避雷針。明治からの呉服屋さん。 | こちらも丸い虫籠窓。 |
 |
 |
 |
| 井戸の辻という十字路を渡ったところにある岸の竹酒造。 | 古びた魚屋さんがありました。 | 洋風の防火壁のある家。 |
 |
 |
 |
| JR畝傍駅に着きました。神武天皇陵参拝のために作られた駅。建物は1940年の皇紀2600年祭典に合わせて建てられたもの。 | 団体用の出口らしきところ。今はひっそり。 | 待合室のこの一角は売店の名残? |
 |
 |
 |
| 皇族用に作られた貴賓室だそうで。 | 駅近くにある八木春日神社。 | すぐ隣は延命院八木寺。長谷寺を開いた徳道上人が729年に開山したお寺の後身とか。 |
 |
 |
 |
| 延命院八木寺。本堂は1821年のもの。本尊の十一面観音は長谷寺のものと同じ木から作れたとか。 | こちらは八木春日神社。建物は明治末のもの。かつては八木寺とつながりがあったのでしょうね。 | 大和国分寺。重文の平安時代の十一面観音を所蔵。建物は火事で焼けちゃって近年の再建。一般的には東大寺が大和国国分寺だけど、こっちだという説もあり。 |
 |
 |
 |
| 畝傍高校。1933年の建築。いわゆる帝冠様式的なもの。 | 畝傍高校にあった古い木造の建物。資料館とありました。 | 大和郡山に戻りました。キューピー堂というお店。おもちゃ屋さんだったのでしょうね。 |
 |
 |
 |
| 近鉄の駅近くの飲み屋の金魚チューハイ。ブルーハワイに赤いグミのようなものが入っていました。 | 平城京の羅城門跡あたり。橋は九条大路だった道。川は佐保川。 | 橋桁の下にある羅城門跡の案内板。朱雀大路の南端で都の玄関口だったところ。 |