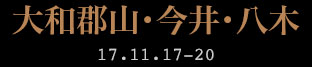
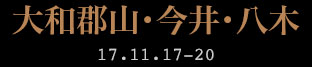

|
 |
 |
 |
|
山尾家。十八世紀後半の建築。肥料や木綿、両替も行った大商家。県指定の文化財。
|
吉村家。元は上田家。こちらも肥料商など。1805年の建築。県指定の文化財。 | 順明寺。元は稲田で親鸞の弟子になった僧が1217年に興し、1626年に今井に移る。門は江戸初期のもの。 |
 |
 |
 |
| 順明寺本堂。江戸初期のものを縮小改築したもの。 | 順明寺付近の町並み。 | 角の家。 |
 |
 |
 |
| 中町筋の町並み。 | 西光寺。江戸時代以前からあったお寺。本堂は十九世紀前半の再建。 | 蘇武井(そぶのい)。今井千軒を潤したという井戸。聖徳太子が水を飲んだとかいう伝説あり。 |
 |
 |
 |
| ここから八木。これはお伊勢参りの接待場(せんたいば)にあった大神宮灯籠。 | 喫茶店か何かだったのでしょうか。お洒落な建物。 | 恵比寿神社前の通り。 |
 |
 |
 |
| 恵比寿神社の門ですが、正面には薬師堂が見えます。 | 恵比寿神社と薬師堂。門と薬師堂は廃寺になった正福寺というお寺のもの。神社は創建不明ですが、江戸初期にはあったようです。 | 境内の稲荷神社。 |
 |
 |
 |
| 虫籠窓の残る平井洋服店。 | 半九(はんく)旅館。かつては下ツ道に面していたという江戸末期創業の老舗の旅館。 | 駒形切り妻の洋風の家がありました。 |
 |
 |
 |
| 下ツ道沿いには古い家が並びます。北に進めば平城京です。 | 河合家。絞り油屋を営んでいたとか。1842年以前の建築。 | 河合源七郎家。明治二十年代後半の建築。 |
 |
 |
 |
| 芭蕉の句碑がありました。1688年に八木に宿泊。句は「草臥て宿かる比や藤の花」というもの。 | 札の辻にたつ西の平田家という旅籠だった家。札の辻は横大路と下ツ道という古代からの幹線道路が交わるところ。 | 八木札の辻交流館は、東の平田家という旅籠。十八世紀後半から十九世紀前半の建築。二階はかつての客室。 |
 |
 |
 |
| 札の辻。縦に走っているのが横大路(伊勢街道)。横に走っているのが、下ツ道。江戸後期に高札場があったので、この名前。 | 丸に十字の虫籠窓? | 古い家は幾らでも続いていて果てしがない(笑)。横大路で。 |