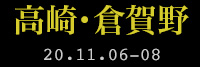
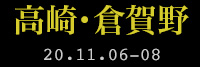

|
 |
 |
 |
|
手水は地面より低い不思議な作り。
|
本堂前の赤い柱の屋根からは銅鑼が下がっています。 | 本堂は1988年に四百年振りに全面改修したとか。本堂の裏は何と安楽寺古墳。 |
 |
 |
 |
| これは異形板碑(いけいいたび)。鎌倉末から南北朝前半のもので、市の史跡。 | 勝軍地蔵尊。脇本陣なども努めた須賀一族の先祖が建立したという説があるそう。 | 二十二夜堂。国定忠次一家の代貸し空っ風の長四郎が宗本寺の哲誉上人から「幻の火伏の名号」(?)の巻物を授与されたところとか。 |
 |
 |
 |
| 七世紀後半の古墳を半分削る形でお寺が建てられています。本尊は鎌倉時代に古墳の石室の内部に彫られた七体の薬師如来で十二年に一度の御開帳。 | 古墳の上の胞衣(えな)捨て場。胞衣とは胎盤のことで、昔は寺の墓地に捨てていたとのことで、左下の石の囲いがその場所。石碑は1965年のもの。 | 左から二番目の石塔は鼠供養塔。本陣の須賀庄兵衛が家の蔵の鼠のためにたてたとか、河岸の米蔵を解体した時に死んだ鼠の供養のためにたてたとか。 |
 |
 |
 |
| 安楽寺から中山道を高崎方面に進むと近年植えられた杉並木があります。 | 昭和七年に建てられた左道通行の道標。中山道が拡幅されたときに元あった並木が中央分離帯となり、そこに建てられたもの。紆余曲折の末、ここに。 | 浅間山古墳。171.5メートルもある前方後円墳。四世紀末から五世紀初めのもの。築造当時は東日本最大規模。 |
 |
 |
 |
| 横から見た浅間山古墳。右が前方部。群馬県内で二番目、関東でも三番目の大きさ。ちなみに関東二番目は石岡の舟塚山古墳。 | 下正六の観音様。この地の豪族が1226年にこの地の守護神として安置したものだそう。 | お堂の中です。秘仏だそうで、約六センチの正座観音とか。今でも祭日が行われているそう。 |
 |
 |
 |
| 大鶴巻古墳。四世紀末から五世紀初めのもので全長123メートル。 | 登ってみました。前方部から後円部を見たところ。二段型になっています。 | すぐ隣の小鶴巻古墳。全長87メートル。こちらは五世紀後半という推定。 |
 |
 |
 |
| 永泉寺は1573年に最後の倉賀野城主金井秀景が開いたお寺。城主夫妻のお墓などあるそう。鉄道開通時はこの寺の狢が騒音に耐えかねて悪さをしたとか。 | 明治四十二年までここに八坂神社があり、天下一角兵衛田子屋の獅子という獅子舞が今も残っています。これは獅子頭等を納める蔵。 | 雁(かりがね)橋。倉賀野城主の紋所は雁だったそう。下は五貫堀。 |
 |
 |
 |
| 倉賀野小学校前の案内板にあった以前の閻魔堂。 | 高崎に戻って、これは東口。巨大なヤマダ電機がありますが、これが本社。 | 高崎名物だるま弁当を食べながら帰りました。地味においしい。 |