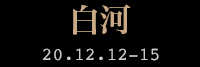
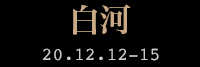

|
 |
 |
 |
|
棚倉藩小池理八供養碑。白河口の戦いで足に重傷を負い、戦いを続けられないと自決した人。
|
こちらの鳥居は健在。池と築山があります。 | 紅葉の季節には遅すぎました。 |
 |
 |
 |
| 左手は結城桜と言われる枝垂れ桜。正面は本堂ではなくて、結城廟。関川寺を造営した白河城主結城宗広を祀るもの。1938年の建築。 | 結城宗弘像。白河結城氏の二代目で白河城を築く。 | こちらが本堂。1865年に火災に遭っているので、その後のもの。 |
 |
 |
 |
| 銅鐘は1761年の鋳造。かつては町民に時を知らせていた鐘。 | 鐘楼ではなく、ちょっと変わった感じ。 | 本田東陵(とうりょう)の墓。松平定信が開いた藩校立教関の教授として藩士子弟教育に当たる。 |
 |
 |
 |
| 墓地には古い墓がたくさん並んでいます。 | 石仏もありました。後ろの土手は土塁の跡で、背後は谷津田川。 | こちらは苔むしていました。 |
 |
 |
 |
| 川向こうの常宣寺同様、杉木立が美しい。 | 元は関錢院といい、関銭(通行料)を取っていたとか。 | 結城宗弘の墓。鎌倉幕府討伐に活躍、北朝成立後も後醍醐天皇方として戦い、1338年に病没。白河城址の感忠銘は、宗広・親光親子のその忠烈を伝えるもの。 |
 |
 |
 |
| 墓地裏から見た蛇行する谷津田川。木立の奥は常宣寺。 | 結城廟裏の観音像。 | 関川寺脇の月心院(げっしんいん)というお寺。結城氏十二代義親が1586年に母の七回忌にたてたお寺。桜は地蔵桜と呼ばれています。 |
 |
 |
 |
| 関川寺の西側には土塁と空堀の跡が残っています。鎌倉後期に築かれた結城氏の居館の跡。 | 月心院隣の妙徳寺。元は常陸の豪族が建てたお寺とか。 | 妙徳寺の市川方静の墓(多分、左端)。白河藩士の子として生まれ、測量術を習得、明治十九年には測量器「方静儀」が工部省に採用されたそう。 |
 |
 |
 |
| 妙徳寺の源清桜。四百年前に片岡源清が寺を再建?したときに植樹したとか。 | 戦死者供養塔。明治二年に建てられた白河口の戦いの奥羽越列藩同盟の死者を供養するもの。市内最小とか。 | 妙関寺。藩主松平大和守家の位牌を祀っていた永寿寺が転封で去った後に永寿寺の僧が創建したとか。 |
 |
 |
 |
| 妙関寺本堂。 | 乙女(おとひめ)桜の幹。伊達政宗が将軍家へ桜の苗木を献上、途中ここで休息、住職が一本もらったものとか。濃いピンクの花で艶やかなのでこの名前。 | 妙関寺の墓地。風花が舞い始め、とても寒い。 |