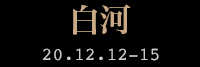
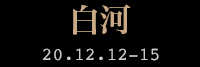

|
 |
 |
 |
|
小崎医院は別のところで開業中のようです。
|
新蔵町の老舗通りにある大野屋染物店。昭和四年の建築。土間には藍染めの甕があるそうです。 | 同じく老舗通りの本家富川屋染物店。江戸中期創業で、建物は明治中期のもの。この通りには明治・大正期には四五軒の染物店が並んでいたそう。 |
 |
 |
 |
| 谷津田(やんた)川沿いの料亭?か何かだったような建物を裏から見る。 | 谷津田川にかかる新橋。手前の新蔵町も向こう岸の向新蔵(むかいしんくら)も飲み屋街。 | 新蔵町の蔵を改装した家。 |
 |
 |
 |
| 新橋からのながめ。左端は裏から撮った建物。玉き屋は微妙に斜めに作られています。 | バスに乗って白河の関へ。関跡の白河神社のすごい蔦? 八九世紀頃まで機能していた国境の関。蝦夷の南下を防ぐヤマトの軍事的要衝。 | 古関蹟(こかんせき)の碑。関の廃止後、場所もわからなくなっていたのを、1800年に藩主松平定信が文献を調べ、ここが関跡だと断定して建てたもの。 |
 |
 |
 |
| 白河神社。135年に白河国造を祀ったのが始まりというお話。 | 妙に目張りの効いた狛犬。 | 拝殿。建物はそれほど古くはなさそうです。式内社です。 |
 |
 |
 |
| 古歌碑。平兼盛、能因法師、梶原景季の和歌が刻まれています。関が失われた後には和歌の名所として、都人の憧れの地となったとか。 | 本殿です。1615年に伊達政宗が社殿を改築奉納したというのですが、その時のものなのかはわかりません。 | 神社周辺には空堀と土塁があります。 |
 |
 |
 |
| 旗立(はたたて)の桜。1180年、源義経が平家追討の戦勝祈願に訪れ、この桜に源氏の旗を立てたとか。 | 従二位の杉。鎌倉前期の歌人、従二位藤原家隆が手植えしたという杉。樹齢八百年。すごい巨木です。 | 関跡に隣接する白河関の森公園の芭蕉・曽良像。『おくのほそ道』でこの地を訪れています。 |
 |
 |
 |
| 展示施設らしきものもありましたが、閉鎖中。 | これは江戸時代の関所を再現したもの。白河の関にこういうものがあったわけではありません。 | 何か誤解を招く展示のような気もしますが。かつては竪穴式住居の再現などがあったようなのですが、見当たりませんでした。 |
 |
 |
 |
| 古民家が移築されていました。 | まあ、これはこれで良いのですが。 | 庄司戻しの桜。1180年、平家追討に向かう義経に庄司(荘園の役職)佐藤元治が子の継信・忠信を従わせ、ここまで見送り桜の杖を地に刺し…… |
 |
 |
 |
| 忠義が本物なら根付くだろうと言ったそう。兄弟は討死、桜は大樹となったとか。これは南湖入り口にある建物。レストランか何かだった? | 南湖開削碑。1801年、藩主松平定信が荒れていた溜池を公園として築造したことを記した碑。1804年のもの。南湖十七景の一つ、月待山に建っています。 | 北端から見た南湖。定信は士民共楽という理念で塀や柵を設けず、身分の別なく誰でも楽しめる公園として作ったそう。 |