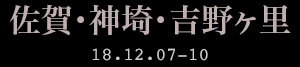
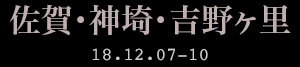

|
 |
 |
 |
|
米屋さんです。
|
野中烏犀圓(うさいえん)。滋養強壮剤を製造販売する1626年創業の老舗。藩の秘薬だったものを領民のためと1796年に下賜されたとか。 | 文字鯛恵比須。文字の下に鯛と波模様が彫られています。1822年のもの。 |
 |
 |
 |
| 水路が交差する街並み。 | 日が傾いてきました。 | 佐賀託児センターとあります。 |
 |
 |
 |
| 石橋もあちこちにあります。 | 肥前通仙亭。煎茶の祖、高遊外売茶翁(こうゆうがいばいさおう)や地場産品の展示を行う。売茶翁は佐賀出身の禅僧で、晩年京都で煎茶を売り、禅を説いた人。 | 旧福田家。実業家福田慶四郎が大正時代に建てた家。佐賀歴史民俗館のひとつ。時間が遅くて入れず、残念。 |
 |
 |
 |
| 横尾京染店。老舗っぽいですね。 | これは揚柳亭という料亭。明治十五年創業。庭には佐賀民謡「梅ぼし』の碑があるそうです。 | 佐嘉神社周辺に残る餅とまんじゅうのお店、鶴乃堂本舗。肉まんじゅうが名物らしいです。 |
 |
 |
 |
| 市営バスには、「愛の戦士ムツゴロウvs甲殻の騎士シオマネキ」が。サイトをご覧あれ。 | バスセンターにも佐賀の七賢人。徹底しています。これからバスで古湯温泉へ。 | 泊まった古湯温泉の街並み。二千二百年前に秦の始皇帝の命で不老長寿の薬を求めてやってきた徐福が発見したとか。 |
 |
 |
 |
| 街中にあった洋風の建物。もとは病院か何かのような感じですが。 | 街外れにある淀姫神社。元は嘉瀬川沿いにあり、明治初期に悪疫が流行った時に避病院として使われて解体、ここに諏訪神社と合祀して移されたとか。 | 拝殿です。1336年、後醍醐天皇を擁した軍勢の阿蘇九郎惟成が足利尊氏に破れて、ここに逃げ込み、温泉で傷を癒して一宇を建立したとか。 |
 |
 |
 |
| お堂は九郎堂と呼ばれたそうですが、それがこの神社の始まりなのか、よくわかりません。狛犬は迫力あり。 | 相棒です。 | 地元の人たちが、お祭りか何かの準備をしていました。 |
 |
 |
 |
| 瀧泉寺は石段を上った上。 | 内には岩屋のようなものがあり……。 | お地蔵さんがいました。 |
 |
 |
 |
| 1791年に温泉を再発見した庄屋稲口三右ェ門を祀る三右ェ門薬師如来、右は徐福温泉恵比須とありました。 | 斎藤茂吉の歌碑がある旅館鶴霊泉の庭。稲口三右ェ門が鶴が傷を癒すのを見て発見したから鶴霊泉。 | 温泉街の裏手を流れる嘉瀬川。カジカガエルも棲んでいるそうです。 |