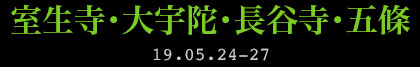
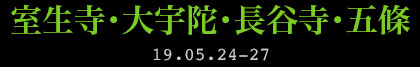

|
 |
 |
 |
|
鐘楼の尾上(おのえ)の鐘。新古今和歌集の藤原定家の歌に出てくるそう。
|
上廊と中廊をつなぐ蔵王堂。1577年の創建。1650年の再建。 | 一茶の句碑がありました。「我もけさ 清僧の部なり 梅の花」1798年元旦にここに来て詠んだそう。 |
 |
 |
 |
| 六坊の一つ、金蓮院(こんれんいん)。1653年の再建。 | 三部権現社。江戸前期に勧請されたもの。 | 繋屋から見た中廊と下廊。 |
 |
 |
 |
| 中廊を外から見る。 | 月輪院(がちりんいん)。六坊の一つ。牡丹の花がまだ咲いていました。 | 月輪院。お抹茶席などあります。 |
 |
 |
 |
| 月輪院から見た登廊。 | 慈眼院。1665年の建立。六坊の一つ。 | 宗宝蔵。いわゆる宝物庫。六坊の一つ、清浄院跡にあります。 |
 |
 |
 |
| 梅心院脇の石段。 | 本坊の入り口です。 | 閼伽井(あかい)。潅頂などの重要な儀式に使う水を汲む井戸。 |
 |
 |
 |
| 本坊から見た本堂や登廊。 | 本坊。元は根来寺から来た専誉(せんにょ)が住んでいたところ。江戸前期のものが明治四十四年に焼失。大正十三年に再建。重文。 | 道明上人御廟塔。長谷寺を開いたとされる僧の墓。 |
 |
 |
 |
| 本尊の十一面観音特別拝観の看板。近くの初瀬川に流れ着いた巨木を開祖徳道が観音像にしたのが始まりという言い伝え。現存のものは1538年のもの。重文。 | 仁王門の前。松が屋根代わりの手水がありました。 | 長谷寺から見た門前町。 |
 |
 |
 |
| 門前町にあった渋い蔵。 | 三輪そうめんと草餅が名物。 | 初瀬川を渡ると與喜(よき)天満神社への道。これは手前にあった男女石。宮司さんの作とか。 |
 |
 |
 |
| 途中にあった泊瀬(はせ)稲荷社。 | 與喜寺跡。長谷寺の子院があったそうです。 | 與喜天満神社への石段。手前左右の杉は夫婦杉。 |
 |
 |
 |
| 石段を登ると石垣があります。 | 手水鉢は1650年、徳川家光が寄進したもの。本居宣長や松尾芭蕉もここで手を洗ったとか。 | 石垣の上が本殿。946年の創建で、菅原道真を祀る日本最古の天神とか。菅原道真の先祖の野見宿禰(のみのすくね)は初瀬の出身とか。 |