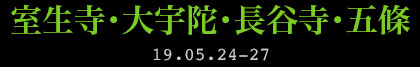
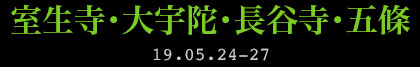

|
 |
 |
 |
|
登廊は上中下の三つに分かれ、上廊は1650年、中・下廊は明治二十七年の再建。いずれも重文。下廊は繋屋で折れ曲がって、中廊へと続きます。
|
中廊です。登ったところには蔵王堂があります。 | 蔵王堂からさらに上廊が続きます。 |
 |
 |
 |
| 巨大な本堂が見えてきました。手前にあるのは三百余社。1650年のもので、重文。 | 本堂の入り口です。1650年のもので、国宝。 |
本堂の礼堂(らいどう)。正面は崖に迫り出した舞台造りになっています。 |
 |
 |
 |
| 本堂の舞台の部分からの景色。仁王門や六坊、本坊が見えます。 | 本堂の礼堂と正堂(しょうどう)をつなぐ相の間の部分。右側が正堂。本尊の巨大な十一面観音は1558年のもので重文。特別拝観中でしたが撮影は禁止。 | 本堂から見た三百余社と登廊、鐘楼。 |
 |
 |
 |
| 本堂右奥には鳥居が並んでいました。 | 鳥居の上は三社権現。733年の創建で、1650年の再建。江戸時代までは神仏習合。 | こちらは愛染堂。1588年の建立。 |
 |
 |
 |
| 本堂の舞台部分。 | 本堂右手奥に進むと日限地蔵尊。 | その奥、能満院前にいた犬。番犬見習いの「たび」という犬で、さわらないでください、とのこと。 |
 |
 |
 |
| 斜め後ろから見た本堂。巨大で複雑な建物です。左は鐘楼と登廊。 | 本堂左手にある大黒堂。 | 本堂の裏側です。 |
 |
 |
 |
| 本堂から左に進むと本長谷寺、一切経蔵、五重塔。 | 一切経蔵。1561年の再建。 | 本(もと)長谷寺。686年に道明上人がこの地に三重塔を建てたのが、長谷寺の始まりという伝承。 |
 |
 |
 |
| 本長谷寺をのぞいて見ました。真ん中の金ぴかの四角いものは、国宝の銅板法華説相図のレプリカ。本物は奈良国立博物館にあり、698年制作と言われる重文。 | 三重塔跡。江戸時代初期に再建されるも、明治九年に焼失。 | 五重塔は1954年の建立。 |
 |
 |
 |
| 広い境内にはお墓があちこちあります。初瀬共同墓地。 | これは無縁仏でしょうか。 | 奥の院の興教(こうぎょう)大師祖師堂。興教大師覚鑁(かくばん)が興した新義真言宗という宗派に十六世紀以降はなっているから。 |
 |
 |
 |
| 本願院。長谷寺を開山した徳道上人が晩年住んだとか。1533年の再建。 | 開山堂。727年に聖武天皇の勅願で長谷寺を創建、本尊十一面観音を安置した徳道上人を祀ってありますが、伝承です。 | 開山堂あたりから見た本堂。 |