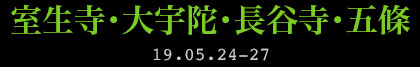
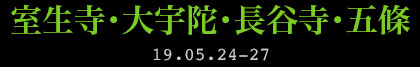

|
 |
 |
 |
|
北側の街外れまで来ました。道標が残っていました。
|
少し戻って散策。これは先刻の渋めのお宅の主家側。 | 片側だけ扉のついた虫籠窓。 |
 |
 |
 |
| これは大和棟の家。 | 道標のある十字路。 | 街の南端、道の駅の裏手にある大願寺。歴代藩主織田家(織田信長の次男の家系)の祈願所。 |
 |
 |
 |
| 緑に覆われたきれいなお寺。聖徳太子が蘇我馬子に作らせたという言い伝えあり。 | 大願寺のおちゃめ庚申。1843年のもの。絵柄がかわいいので、そういう名前。 | 左の毘沙門堂は1693年、室生の大杉一本で作られたとか。奥の本堂の観音像は長谷寺建立の大願を込めて作られ、火事にも焼けなかったので「焼けずの観音」。 |
 |
 |
 |
| 仏足石。1804年に森野薬園の賽郭の孫が寄進したもの。 | 帰りはバス。車窓からみた猟路(かりじ)の桜。万葉の昔、このあたりは宮廷狩猟の場で、猟路の池(つづみ)という湿原だったことから名付けられた桜並木。 | ここから長谷寺。これは大和川(初瀬川)を挟んで宿の反対側にあった古い家。 |
 |
 |
 |
| 宿の二階から見た大和川沿いの風景。左奥に見えるのが長谷寺。 | 泊まった宿大和屋の二階階段付近。古くて狭いですが、趣あり。 | 宿の前は参道。長谷寺はすぐ近く。 |
 |
 |
 |
| 宿のすぐ脇は中之橋天満神社と中之橋詰御旅所。菅原道真が946年に初めて神として現れ、下の初瀬川(大和川)で禊をして、休んだところとか。 | 橋を渡って、川沿いに歩くと古い大きな家がありました。 | 玉鬘(たまかずら)神社への入り口。 |
 |
 |
 |
| 石段を登ると道は左右に分かれています。 | 左に行くと玉鬘神社。新しいもののようです。『源氏物語』に出てくる姫君玉鬘が長谷寺に母を捜す願を掛ける話から能の『玉鬘』が作られ…… | 信仰に取り入れられ、玉鬘観音が置かれ玉鬘庵で尼僧によって祀られてきたとか。これは境内にあったその玉鬘庵の尼のお墓。 |
 |
 |
 |
| これは奥にある素盞雄(すさのお)神社。左のイチョウの木は奈良県最大という天然記念物。 | 素盞雄神社.。948年の與喜天満宮創建の時に、この地與喜山は天照大神降臨の地なので、その弟の素盞雄命を祀ったとかいう話。 | 川沿いに古めの宿らしき建物が見えました。 |
 |
 |
 |
| 右に行くと鍋倉神社。式内社だったけど、明治四十一年に素盞雄神社に合祀されたのを、玉鬘神社を作るのと共に2018年に再興。 | 川沿いの建物の表側。もう宿はやっていないようです。 | 長谷寺の仁王門。明治二十七年の再建。重文。創建は八世紀前半だそうで。 |
 |
 |
 |
| 仁王門を潜ると登廊(のぼりろう)。399段あるそう。元は1039年に作られたもの。 | 登廊の左右には長谷寺六坊と言われる塔頭が並んでいます。これは歓喜院(かんぎいん)。1701年の再建とか。 | 六坊の一つ、慈眼院脇の石段。 |