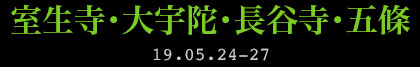
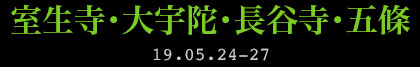

|
 |
 |
 |
|
1449年にこの地へ遷座とか。疫病を鎮める健康の神とか。
|
奥の本殿は1864年に春日大社の旧本殿を移したもの。 | 宇太水分(みくまり)神社下社。九世紀ぐらいからある古い神社。 |
 |
 |
 |
| 田園風景の中を宇陀川沿いに大宇陀を目指します。日差しが強くてちょっとしんどい。 | 途中にまた別の水分神社がありました。平尾というところ。 | 木立に囲まれて静かなところ。田植え神事が県の無形文化財になっているそう。 |
 |
 |
 |
| 拝殿はなく古びた本殿が三つ並んでいました。 | 少し先にあった白山神社からの眺め。 | 大宇陀の入り口あたりにある慶恩寺というお寺。695年の創建とか。1186年に東大寺再建のための五分の一の試作を作って、伽藍としたとか。 |
 |
 |
 |
| ここから大宇陀の古い街並み。これは日乃出館という古美術のお店。 | 日乃出館。ゴチャゴチャ感が楽しい。 | 三つの大学の大宇陀研究室の看板がかかっていました。 |
 |
 |
 |
| 新聞屋さんです。縦長の窓が珍しい。 | 春日神社参道の入り口。左の家は大学の研究室が入っている家。 | 春日神社。うっそうとした木立。 |
 |
 |
 |
| 五輪塔地輪。鎌倉時代、1291年のもの。五輪の塔の地輪を改造、水鉢にしたもの。 | 春日神社の境内。石垣を築いてその上に社殿というのがこのあたりのスタイルらしいです。 | 創建は不明。春日大社を勧請したものらしいです。十六世紀にはあったようです。 |
 |
 |
 |
| 装飾つきでふんぞり返った狛犬。 | 石段を登って左手にあるのは阿弥陀堂。 | 右側にあるのが拝殿なのでしょうか。 |
 |
 |
 |
| 本殿はさらに上。 | 石垣下にあった霊宝石。古代に祭祀に使われたものらしいです。 | 境内奥にあった伊太祁曽(いだきそ)神社。木の種を広めたという神。近年和歌山からB雲霊して作られたもの。 |
 |
 |
 |
| 羽衣桜という木がここにあったようです。 | 街並みに戻り、これは平五薬局。大宇陀は薬の街。 | オットピンというネーミングはすごいなあ。 |
 |
 |
 |
| こういう家並が続いています。 | 洋館は珍しい。 | 床下の換気口?もデザインされています。 |