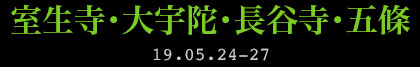
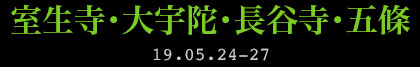

|
 |
 |
 |
|
奥の院は赤い太鼓橋の上の方。
|
けっこうな急坂です。 | 奥の院の常燈堂(位牌堂)が見えてきました。 |
 |
 |
 |
| 奥の院です。手前が常燈堂。奥が御影堂です。 | 常燈堂。 | 御影堂は弘法大師を祀るもの。鎌倉時代後期のもので、重文。 |
 |
 |
 |
| 奥の方にあった石塔。 | 上から見るとちょっとこわい石段。 | 石段の途中にあるお地蔵さんと石塔。 |
 |
 |
 |
| 下に戻って、これは本堂近くにある北畠親房のものだというお墓。まあ、よそにもあるようですが。でも、重文。 | 本堂と奥に五重塔をのぞむ。 | これは護摩堂。 |
 |
 |
 |
| その脇にあった蔵。 | 室生寺を出て、龍穴神社に向かいました。門前町の外れにあった駐車場の看板です。 | 瓜出渕。弘法大師がここに地蔵と恵比須大黒碑を作った時に、龍王がこの渕から現れて爪で彫るのを助けたとか。九穴八海といって、他にも龍神伝説あり。 |
 |
 |
 |
| 室生龍穴神社。雨乞いの神を祀る神社で、延喜式にも載っている室生寺よりも古い神社。 | 龍穴神社の連理の杉。夫婦杉ともいわれる夫婦和合の神。 | 室生寺は龍穴神社の神宮寺ともいわれ、龍王寺と呼ばれた時代もあったとか。 |
 |
 |
 |
| 本殿です。もっと山の方に入ると、天岩戸とか龍穴とかあるのですが、日が暮れそうなので断念。 | 而二不二(ににふに)の神木。而二不二とは二つにして二つではない、という意味。 | 棚田が広がっていました。 |
 |
 |
 |
| 宿に鎮座していた龍やら雀やら獅子やら梟やら猫やら。 | 宿の古民家部分。囲炉裏がありました。 | 花のそのという観光施設の跡。花がたくさん植えられていたのでしょうね。 |
 |
 |
 |
| 山の下が室生寺です。 | 室生口大野駅に戻り、近くの海神社へ。山の中に海神社とはこれいかに。 | 室生龍穴神社から1396年に龍神を勧請したものを、明治に海神社と改称したらしいです。雰囲気のいいところ。 |
 |
 |
 |
| 海神社本殿。江戸初期のもので、もとは二棟だったものを改築、ひとつの屋根をかけたもの。県の指定文化財。 | 近鉄で榛原(はいばら)駅へ出て、レンタサイクルで散策。宇陀川の赤い橋を渡ると墨坂(すみさか)神社。 | 記紀に記述があるという古い神社。 |