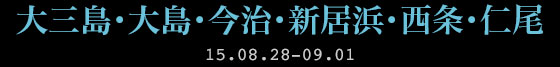
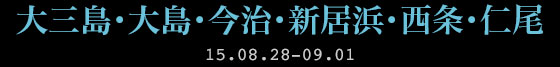

|
 |
 |
 |
|
貯鉱庫跡。掘り出した鉱石を運ぶ前に一旦貯めておくところ。1905年ごろの完成。
|
往時の保安本部の建物。階段も当時のもので、下には鉱山鉄道のホームがありました。1904年ごろのもの。 | 東平歴史資料館。往時の東平の様子などを展示しています。 |
 |
 |
 |
| 娯楽場のジオラマ。山の斜面には社宅が並んでいます。小学校や接待館などもありました。 | 鉱山の通学路を歩く子どもたち。「落石注意、気をつけて速く通れ」と書いてあります。 | 東平の中心部。大きな駅です。上部に今も残る階段と保安本部が見えます。 |
 |
 |
 |
| チャンバラごっこをする子どもたち。背後の斜面にはずらりと社宅が並んでいます。 | 霧が晴れてきました。向こうに見えるのは新居浜の港でしょうか。住友関連の工場が今もたくさんあります。 | 小マンプ。東平から第三坑道へ続く鉄道のトンネル。マンプというのは坑道の意味の間符(まぶ)から。上にはプールがあったそうです。 |
 |
 |
 |
| 帰りのバスの中から社宅の跡が見えました。植林されて山は緑を取り戻しています。一時は四千人近くが住んでいたそうで。 | 端出場に戻ってきて、これは仲持ちの銅像。男は45キロ、女性でも30キロもの荷物を持って、山道を歩いたそうです。 | 1912年完成の端出場水力発電所。当時日本一の596メートルの落差を利用して発電。四阪島の精練所まで海底ケーブルで電気を送ったとか。 |
 |
 |
 |
| 端出場貯鉱庫跡。1919年の完成。上部を鉱山鉄道が通っており、鉱石を落として貯めるようになっていたそうです。 | 端出場から山根に続く鉱山鉄道の跡です。 | バスがないので、延々歩いて帰るはめに。これは途中にあったつり橋。 |
 |
 |
 |
| 緑の中に鉱山鉄道のトンネルが見えました。煉瓦造りです。 | 煙突山の上に煉瓦の煙突が見えました。 | 山の中に水路らしきものが見えます。発電用でしょうか。 |
 |
 |
 |
| 新居浜の市街地に戻ってきました。水路沿いの道は登り道という新居浜浦と銅山を結んだ道。 | 水路が二股に分かれていました。 | 往時をしのばせる常夜灯。石柱は明治時代のもののようです。 |
 |
 |
 |
| 金毘羅街道と登り道が交差するところにある喜光地商店街の入口。道標が幾つも立っていました。 | 往時は賑わっていたという喜光地商店街。 | 右の魚屋さんはやっているようです。 |
 |
 |
 |
| 木造三階建ての旅館でしょうか。 | 薬局です。 | かつては喜光寺というお寺があったようです。今は豊川稲荷。 |