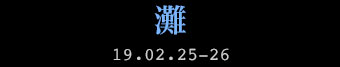
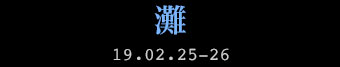

|
 |
 |
 |
|
昔の甕や徳利です。
|
まあ、展示されているものは、どこも同じですね。当たり前か。 | 阿弥陀車です。ここでは、お酒を搾るために使われています。 |
 |
 |
 |
| 酒を搾るために入れる槽(ふね)という搾り機。搾って残ったものが酒粕。 | 柄杓のようなものがたくさんありますが、それぞれ名前と用途が違います。 | 酒を搾る槽場(ふなば)の遺構。再建時の発掘調査で出土したもの。江戸〜昭和初期まで使われていたもの。丸い穴は酒を入れる甕が置かれていたところ。 |
 |
 |
 |
| 二階の阿弥陀車。 | 狐桶。酒を搾るとき、醪を酒袋に入れるための桶。 | 手前はひねり餅の型。奥は猿またはこまという、甑の底で蒸気を分散させる道具。 |
 |
 |
 |
| 樽廻船。これで大消費地の江戸へ樽酒を送っていました。新酒を江戸に送る速さを競う新酒番船というレースに江戸っ子は興奮したそう。 | 庭にあった神社。竹石大明神と書いてありました。 | 沢の鶴の向かいにあった樽屋さんです。 |
 |
 |
 |
| 住吉神社がありました。 | 都賀川の岸にある大石ポンプ場は何か不思議な建物。 | 都賀川を渡ると西郷(にしごう)。これは川沿いの新在家西公園にある水車のモニュメント。 |
 |
 |
 |
| 沢の鶴のタンクです。 | 沢の鶴の工場。 | お酒用の通い箱(運送用の箱)が山と積まれていました。 |
 |
 |
 |
| 若宮神社がありました。 | オエノンプロダクトサポート(合同酒精)と塀にありましたが、元は富久娘。 | 西郷酒蔵の道という道。 |
 |
 |
 |
| こうべ甲南武庫(むこ)の郷は甲南漬という漬物のお店。震災で倒壊した本店の跡地に作られています。 | 武庫の郷の甲南漬資料館。建物は昭和初期の社長の邸宅。明治三年に焼酎の製造を始め、その後明治三十七年に奈良漬を作り始める。 | 玄関にあった洒落た手洗い。 |