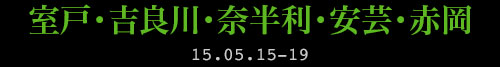
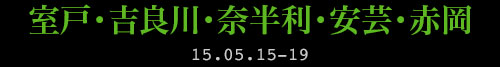

|
 |
 |
 |
|
角に窓があるちょっと変わった建物。
|
二階軒の模様が洋風中の中華風なのか不思議。 | 二棟が前後に連結したようなお肉屋さん。 |
 |
 |
 |
| 魚屋さんの看板です。 | 映画館を発見しました。 | 安芸太平館という大映系の映画館だったようです。 |
 |
 |
 |
| 窓越しに看板が見えました。安芸に住んだ少年時代の川谷拓三がポスター貼りなどしたところだとか。 | 要塞のような雰囲気になっている建物。 | 簡易郵便局とハイヤー事務所という組み合わせはあまりないかも。 |
 |
 |
 |
| 古典的雑貨屋さん。 | 土居橋。反対側には弘田龍太郎の『三日月』の碑がありますが、竹久夢二との関係は不明。道の向こう側は『雀の学校』の碑。 | 安芸駅前の「靴が鳴る」の像。 |
 |
 |
 |
| 乗った列車はデッキ付きでしたが、平日は?開放されておらず、残念。 | あかおか駅にはやなせたかしのごめん・なはり線キャラクターが勢ぞろいしていました。 | あかおか駅のあかおかえきんさん。赤岡に住んで芝居屏風絵を描いた絵師絵金から。 |
 |
 |
 |
| 豊能梅の高木酒造。どろめ祭りでは、ここのお酒で大杯飲み干し大会が行われます。明治十七年創業。どろめとは生のちりめんのこと。 | 一本松。かつては宿場の入口で大きな松があったそうです。松は何代目かのもの。海辺で作られた塩を内陸に運ぶ塩の道があり、赤岡には塩市が立ったとか。 | 香宗川の赤岡大橋あたり。江戸時代には海には港はなく、このあたりに船着き場があったそう。茶店などもあったそうです。 |
 |
 |
 |
| 赤岡大橋から登っていく横町の通り。左は山城屋。廻船業だったらしいです。右は銘菓梅不しの西川屋。土佐藩の菓子司だったお店。 | 山城屋。明治期は桑の種を信州へ送り出していて、採種のために桑の実を潰して香宗川が真っ赤になったとか。 | 絵金蔵。高知生まれの弘瀬金蔵は土佐藩家老の御用絵師となるも、贋作の嫌疑をかけられ、赤岡で町絵師となる。血みどろの屏風絵で高名。ここはその美術館。 |
 |
 |
 |
| 田んぼの向こうは須留田八幡宮。すみやかに水がのく田んぼという意味だそうです。火の神で鍛冶と焼き物の神様。 | 須留田八幡宮。夏祭りでは絵金の芝居屏風絵が蝋燭の明りの中、商店街に飾られます。 | 絵金の屏風絵は、この神社の夏祭りのために氏子が奉納したもの。これは絵金の絵を元にした鏝絵。 |
 |
 |
 |
| 謎の建物ですが、絵金の屏風絵を展示するためのものらしいです。この日は何もなし。 | 拝殿。回り舞台があり、天保の改革で地方芝居が禁止された後も奉納芝居という形で行っていたとか。芝居屏風絵も芝居の禁止によって生まれたようです。 | 本殿は高い石垣の上にあります。1807年の再建。 |