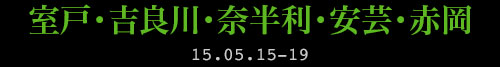
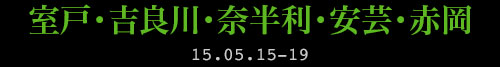

|
 |
 |
 |
|
上から見ると下が見えないほどの急勾配。恐いので裏の車道から戻りました。
|
御田八幡宮本殿。 | 鯉のぼりが泳いでいました。こうした名前入りののぼりも立てるようです。 |
 |
 |
 |
| 広末でお昼。古典的な味のチャーハン。 | 吉良川の海です。 | 堤防に置いてあった謎の道具。 |
 |
 |
 |
| バスで奈半利に到着。これは魚梁瀬(やなせ)森林鉄道の跡地。魚梁瀬杉を運ぶための鉄道、1964年に廃止。トンネルや橋など重文もあるけど、行けず。 | 津波非難タワー。南海地震で津波が起きると、町内はほとんど水没するようです。 | 濱田家。1934年の建築。地主の屋敷。 |
 |
 |
 |
| 濱田家の蔵は明治後期のもの。大きな蔵です。 | 東山家。明治三十八年の建築。 | 東山家。蔵は改築されて薬局です。 |
 |
 |
 |
| こちらが主家。 | 虫籠窓にガラスが入っています。 | 東山家向かいの古い家。 |
 |
 |
 |
| まとまった街並みはありませんが、こういう家がところどころにありました。 | 正覚(しょうがく)寺。山内一豊が1601年に入国した時の宿所。この石積みが何なのかは不明。 | 正覚寺。左が本堂、右が日本一とかいう黄金の鈴堂。空海を祀るもの。 |
 |
 |
 |
| 正覚寺の石垣。 | こうした石塀があちこちにありました。 | 竹崎家。明治二十三年ごろの建築。樟脳業で栄えた家。今は喫茶店。大きなのぼりはフラフという端午の節句のもの。明治の終わり頃から広まったもの。 |
 |
 |
 |
| なかなか渋い床屋さんです。 | 側溝で何かを釣る子ども。このあたりの側溝には何がいるのでしょうか? 右側にいしぐろのような石塀の名残が見えます。 | これはまた別の津波非難タワー。 |
 |
 |
 |
| 浜田家の煉瓦の蔵。明治後期のもの。煉瓦は船がバラストとして積んできたものを利用するようです。 | 二棟がつながった蔵。 | 西尾家は江戸末期の建築で旅籠屋だった家。 |