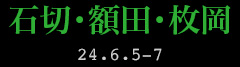
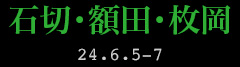

|
 |
 |
 |
| あたりには溜め池が幾つかありました。 | 大龍寺は元は聖徳太子が創建し厳松寺と言ったとか。応仁の乱、大阪の陣で焼失。1692年に大阪の豪商の寄進により再建。総門は1700年のもの。 | こちらが仏殿のようです。1700年のもの。中国様式らしいです。 |
 |
 |
 |
| これは開山堂。 | 大龍寺近くの蔵のあるお宅。 | 素敵な石塀。 |
 |
 |
 |
| 日下東地蔵尊。いろいろ並んでいますが中央の本尊?は1774年のもの。他は十九世紀、江戸末期のもの。 | 渋い緑のトタンで覆われた屋根。 | 石橋?と石垣、木の洞に出窓といい感じの情景。 |
 |
 |
 |
| やや崩れた瓦屋根が見事な構成美。 | 旧河澄家。この地、日下村で代々庄屋を務めた家。主屋は江戸初期の様相を残しているそう。 | 民具が1200点も残っているのだそう。 |
 |
 |
 |
| 棲鶴楼(せいかくろう)という奥の建物。十七世紀中頃に隠居所として作られ、1835年に改築されて現状に。 | 棲鶴楼の欄間。『雨月物語』の上田秋声も訪れた一種の文芸サロンになっていたそう。 | 蔵もあります。今は二棟が残っていますが、往時は七棟もあったそう。 |
 |
 |
 |
| 中には様々な民具を展示。 | お歯黒道具。魏志倭人伝にも倭人はお歯黒しているという描写があるとか。右は蘭引(らんびき)という蒸留装置で、酒や薬の他、化粧水も精製したとか。 | 河澄家庭園は江戸初期に作庭されたもの。 |
 |
 |
 |
| 河澄家近くのお地蔵さん。日下四地蔵尊というらしいです。 | 近くの原始蓮群生地。ちょっと蓮には早い季節、菖蒲か何かが咲いていました。 | ここは上田秋成隠棲の地。ここにあった正法寺に四ヶ月逗留したそう。正法寺は明治初期には郷学校という学校になっていたそう。 |
 |
 |
 |
| 横尾忠則先生が描きそうなY字路がありました。 | 丹波神社は江戸初期にこの地を治めた曽我丹波守古祐(ひさすけ)を祀ったもの。用水池築造などを領主負担で行い、慕われたそう。棲鶴楼はその隠居所。 | くさかみちという道標がありました。車は通れませんね。 |
 |
 |
 |
| 石切駅から乗った近鉄の電車は鹿電車(笑)。吊り革も鹿。 | 車内にも鹿。 | 車外の鹿とお姉さん。 |