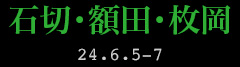
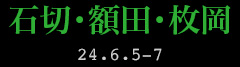

|
 |
 |
 |
| 紅葉に覆われています。 | 興法寺の門前。お寺ですが、堂々と鳥居が立っています。役行者の創建と伝えられ、平安時代にはあったそう。 | 聖天堂(本堂)です。ええー、ここまで来てコンクリ(笑)。 ちょっとがっかり。本尊の観音像は平安後期のものだそう。 |
 |
 |
 |
| 鳥須瑟磨(うすさま)明王、不動明王、観世音菩薩が祀られた護摩堂。 | その内部。右端の明治のベンチが何だかいい味わい。 | 大きな金灯篭のあるお堂。 |
 |
 |
 |
| 山門前にある手水と石仏。興法寺からさらに先に進むと生駒山の宝山寺に通じているそう。 | 緑がとてもきれいでした。 | 戻って、三昧尾(さんまいお)石造十三重塔の方へ進みました。ちょっと行くと聖良橋という小橋がありました。 |
 |
 |
 |
| その先には白瀧白龍王というものが祀られていました。 | そのちょっと先の大岩は木花咲耶姫を祀るもの。 | 石仏が並んでいます。 |
 |
 |
 |
| 小山を登ると……。 | 三昧尾石造十三重塔は、興法寺の僧両辨(弁)が建てたもので、平吉国という石工の手になるもの。お墓ではないようです。 | 苔で髪が生えたような石仏。 |
 |
 |
 |
| 辻子谷に下ってきました。緑に埋もれゆく家。 | 赤い橋の向こうも朝鮮寺のようです。 | ガードレールに指で?書かれた道標。 |
 |
 |
 |
| 移動スーパーが来ていました。ここに住んでいれば必要だろうなあ。 | 天水庵なる看板があったので行ってみました。すごい細い道。 | イノシシ注意の看板の向こうは東仙寺というお寺のようです。 |
 |
 |
 |
| さらにその先にあるのが天水庵。何やら賑やかです。 | 鼠漆喰のお宅の前には一丁の道標がありました。 | 石切駅近くから見下ろした大阪市街。左の高いビルがアベノハルカス。斜面沿いにずーっと住宅地が広がっています。 |
 |
 |
 |
| 近鉄の生駒トンネル。1914年開通。工事では多くの朝鮮人労働者が犠牲に。右は白龍大神という神社、プラットホームは旧孔舎衛坂(くさえざか)駅のもの。 | 石切の街中をちょっと探訪。駅からほど近い日下新池の畔はヒトモトススキという市の天然記念物が生えているようですが、うーん、わからない。 | 日下新池。大正末には日下遊園地というものがあったそう。今は桜の名所のようです。 |
 |
 |
 |
| その後、ここに孔舎衙(くさか)健康道場という施設ができ、入院した太宰治のファンが療養日誌を大宰に贈り、そこから『パンドラの匣』が書かれたそう。 | 近くの日下神社。元は古墳だったそう。 | 日下ほたる公園に生息する巨大蛍(笑)。周辺の川には蛍が棲むそう。 |