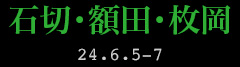
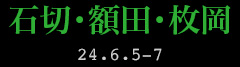

|
 |
 |
 |
| こちらは剣を持った人。祭神の饒速日尊(にぎはやひのみこと)と可美真手命(うましまでのみこと)? | 親子連牛像。農耕用の牛の労をねぎらう行事があったからだそう。 | お百度詣りをする人々。時代劇の中のことだとばかり思っていたので、びっくり。手にこよりのようなものを持って、数を数えていました。 |
 |
 |
 |
| お百度詣りの人々は老若男女、皆真剣な表情でした。腫物や病気を癒す神社とされているそう。これは水神社。亀がいっぱい。 | 摂社の五社明神社と神武社。神武社は神武東征の時、神武天皇が蹴り上げた巨石を祀っているそう。 | 拝殿と本殿、合わせて本殿と呼ぶようです。左側のクスノキは市の天然記念物。 |
 |
 |
 |
| 千羽鶴納所と神輿殿。 | 乾明神社。江戸中期に、飢饉と重税に苦しむ人々の代表として直訴して処刑された庄屋を祀ったもの。 | 後ろから見た本殿。 |
 |
 |
 |
| 穂積殿。明治初期に宮司が学校を開いた穂積堂は1970年に焼失、その跡地の建物。 | これは祈り亀というもの。願い事を記して腹中に納めるのだそう。 | 穂積堂前の穂積神霊社。穂積堂に祀られていた神霊を祭るもの。 |
 |
 |
 |
| 神霊社の前の石には九頭神とありました。 | 本殿と授与所の間の太鼓橋。 | やたら大きい授与所。並んだ机は祈祷申込書の記入台。屋根付きです。 |
 |
 |
 |
| 馬もいました。 | 神社の斜向かいにある明治大正昭和阪本昌胤第二記念館。やってはいないようです。石切大仏を作ったのと同じ人ですね。 | 参道も神社を過ぎると静か。お婆さんが子安延命地蔵にお参りしていました. |
 |
 |
 |
| でもまだ占い等のお店は続きます。こちらは霊感師で「電話で病気治す」のだそう。 | 近くの石切藤地蔵尊。1850年頃に藤の木が自然に生えて育ち、明治の中頃から藤地蔵尊と呼ばれるようになったそう。 | 石切藤地蔵尊。1340年頃に建立、大坂夏の陣の時に地蔵の首がなくなり、それから病気平癒の御利益が生ずるようになったとか。 |
 |
 |
 |
| 参道に戻って駅への道を上りました。しんどい(笑)。これは途中の脇道にあった道標? 讃岐国云々とあるようです。 | 石切駅に戻り、駅の反対側にある古めの建物。 | 中央の建物はふとん店だったようです。 |
 |
 |
 |
| 家と家の間にある井戸。 | 駅の反対側も坂道が続いています。これは石切観音院なるもの。 | あやしい人には近づかない! という怪しい看板。子どもが描いたんでしょうね。 |
 |
 |
 |
| 辻子谷(ずしだに)石仏像の一番太子堂。明治中頃に音川沿いの辻子谷の道沿いに弘法大師と四国八十八ヶ所の本尊を並べたものの一番目。 | その向かいにある爪切地蔵。室町時代のものらしいです。 | 爪切地蔵。弘法大師が一夜で爪で刻んだという伝説あり。 |