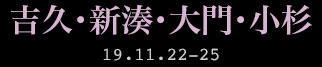
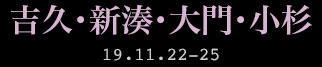

|
 |
 |
 |
|
社殿は1863年の再建で、放生津の宮大工高瀬輔太郎の作。放生津という地名は創建以来続いているという放生会という殺生を戒める儀式から。
|
巨大な木造の狛犬は1846年のもので、地元の彫刻家矢野啓通の作。十九歳だったそう。気比住吉神社もそうですね。 | 狛犬のお尻です。がっしりした力強い作風。七五三で境内にはアンパンマンの歌などが流れ、奇妙な雰囲気。 |
 |
 |
 |
| 横から見た社殿。拝殿はお寺のよう。秋の例大祭では神を迎える築山行事というものが行われます。築山とは祭壇のこと。これを動かしたのが曳山らしいです。 | 大伴家持の万葉集の歌碑。東(あい)の風が吹く早春の奈呉の浦を歌ったもの。松尾芭蕉の句碑もありました。 | 大伴家持を祀る祖霊社。越中守として五年間、伏木で政務を行ったそう。 |
 |
 |
 |
| 放生津八幡宮隣にある魚取(なとり)社。恵美須神を祀ってあるようです。 | 板張りの大きな家。 | 光照寺というお寺だったようです。本尊は光明寺に遷座したので、そちらで参拝をという張り紙がありました。 |
 |
 |
 |
| 勝光寺。親鸞が越後へ流されたとき、高岡の如意の渡しで乗った船の船頭が親鸞の弟子となって開いたお寺だとか。 | 勝光寺にあった石塔。阿弥陀○、池中出現と書いてあります。 | 光明寺前のおんぞはん。 |
 |
 |
 |
| 大小いっぱい並んでいました。 | 光明寺。701年にインドから来た人が開き、1628年にここに移転。お寺だけどおみくじがひけるとか。ボケ封じもあります。本尊は金比羅大権現。 | 気になる角の家。洒落た窓です。 |
 |
 |
 |
| 光山寺。十八世紀後半に光山寺と改名されたお寺。本願寺蓮如の書いた南無阿弥陀仏という六字御名号があるそう。 | 光山寺前の大きなおんぞはん。 | 光山寺の新湊大仏と千体仏のある金堂。ステンドグラス付き。鍼灸の治療院もやってます。 |
 |
 |
 |
| 新湊大仏と千体仏。千体仏は1864年に発願されたもので、今は三千体を超えているとか。 | 義常教会。1453年に大法寺として建立。江戸時代に高岡に移転する際に、義常庵ができたそう。別名わらじ寺。 | 義常教会の大わらじ。世界平和と人類の福祉をねがい、戦後作られたもの。現在のものは1984年に製作されたもの。 |
 |
 |
 |
| 日本高周波鋼業富山製造所の建物。特殊鋼、特殊合金を作る会社。 | 八幡町の愛宕社とおんぞはん。 | 愛宕社横のおんぞはんは、鏝絵の名人竹内源造の手になるもの。 |
 |
 |
 |
| 荒屋神社。足利義材を助けた神保長誠の放生津城と八幡宮の間で、神保氏や義材の関係者が多く住んでいたあたりとか。加賀藩の米蔵もこのあたりにあったそう。 | 荒屋神社の松尾芭蕉句碑。芭蕉がこの地を訪れて詠んだ句が刻まれています。大正時代のもの。右側はお祭りに使うんでしょうね。 | 西福寺というお寺。不動尊が本尊らしいです。手前にはおんぞはん。 |