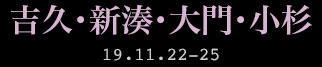
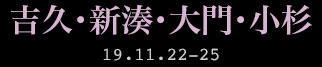

|
 |
 |
 |
|
妙蓮寺横の通りはトタン張りの家並。
|
東橋袂のおんぞはん。 | 法土寺町の愛宕社。十六世紀末に勧請し、伏木の気多神社に祀られていたものを、幕末の放生津大火を機に1866年にこの地に遷座したもの。 |
 |
 |
 |
| 東橋。スペインの建築家セザール・ポルテラ設計の屋根付き橋で1992年のもの。 | 東橋袂にあった船型のベンチ。 | 東橋。1845年の大火で焼けて以来の再建?らしいです。 |
 |
 |
 |
| 東橋から見る内川。 | 放生津橋袂のおんぞはん。 | 放生津橋の足利義材像。室町幕府十代将軍で、1493年、細川政元の反乱で放生津に逃れる。五年間をすごし、越中公方と呼ばれる政権を樹立。 |
 |
 |
 |
| これは放生津橋隣の水道管の橋。 | 今井竹材店とありました。 | 山王橋。地元出身の彫刻家竹田光幸制作の手の彫刻付き。 |
 |
 |
 |
| これは心。 | これは人。 | これは愛。 |
 |
 |
 |
| これは夢。どれも大理石。 | 山王橋から見た内川。奥に立山連峰。 | 神明宮近くの古い家。 |
 |
 |
 |
| 放生津八幡宮近くの神明宮。962年の創建で、かつては放生津三宮の一つだったとか。 | 八幡宮近くの天満宮。 | 道のあっちとこっちにあるおんぞはん。奥のものには寺町地蔵尊とありました。 |
 |
 |
 |
| 続く古い家並。 | 松原酒店は江戸時代から続く老舗。 | 八幡宮前の荒井米穀店。数年前に『鶴瓶の家族に乾杯』に出たそう。 |
 |
 |
 |
| 八幡宮前の卯尾田毅太郎(うおたきたろう)の像。この地の生まれで新湊町長などを経て衆議院議員になるも、1945年に空襲で亡くなった人。 | 放生津八幡宮の鳥居。746年に大伴家持が越中国司として赴任したときに奈呉の浦の風光を哀史、宇佐八幡を勧請して奈呉八幡宮としたのが始まりとか。 | これは霊松殿という御輿庫。1751年の建築。 |