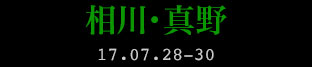
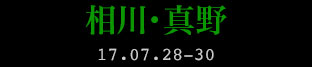

|
 |
 |
 |
|
居房棟。最大18人収容可能。
|
独居房。右奥の凹みはトイレです。 | 庭に展示されていた石細工の生活用品。播州から渡ってきた石屋たちが石切り場を開いたそうです。 |
 |
 |
 |
| 整備されて公開されている鉱山住宅。 | 二世帯分で一つの長屋になっています。 | こちらは現在もお住まいの鉱山住宅です。 |
 |
 |
 |
| 鉱山長の住宅はカフェになっていました。 | 京町通りの街並み。江戸時代初期には三階建てもあったという最盛期の繁華街。西陣織の店などもあったそうです。 | 相川町ふれあい集会所は元副鉱山長の住宅。屋根瓦には三菱の紋章があるそうです。 |
 |
 |
 |
| 時鐘楼と煉瓦塀。鐘は1871年頃まで時刻を報せていたそうで、近年復活して朝夕撞かれているとか。 | 煉瓦塀は裁判所のもので、今は版画村博物館になっています。 | 長坂の上から海を見る。相川は坂の町です。 |
 |
 |
 |
| 西坂。上ると佐渡奉行所に出ます。1719年に開かれたもの。 | 佐渡版画村美術館。版画家高橋信一が起こした版画村運動の作品の展示館。建物は1888年建築の相川簡易裁判所。 | 佐渡奉行所の堀。急斜面と堀で防御を固めています。木橋は高級役人の家族が役宅へ出入りするためのもの。 |
 |
 |
 |
| 復元された佐渡奉行所の入口。佐渡は金山発見とともに天嶺となり1603年に佐渡奉行所が置かれました。 |
奉行所内の御白州。 | 金の精練に使われた鉛板。奉行所敷地の発掘で大量に発見。長さ70センチで重さ41キロ。国の重文。 |
 |
 |
 |
| 奉行所の敷地に設けられている勝場(せりば)。鉱石を砕いて精練する工場。 | 金場(かなば)という鉱石を砕く場所。 | 砕いた鉱石を石臼ですり潰して……気の遠くなるような工程です。一トンの鉱石から二グラムの金が採れれば採算があったそうですが。 |
 |
 |
 |
| 案内のお姉さんの実演付き。水の底に沈んだ鉱石の粒。 | ねこ場。鉱石を含んだ水を流して布に付着させます。 | これは精練所の遺構の竃の複製。 |
 |
 |
 |
| 北沢地区施設群。明治以降の佐渡鉱山の一大拠点。 | 相川郷土博物館はレトロな雰囲気。法然寺に奉納されていた龍神。手の上には道の燈籠が載っていたそうです。1830年のもの。 | これは多聞院の蔵の扉。ムカデは本尊毘沙門天の使いなのだとか。無数の脚が坑道のようだというので、縁起物だとか。 |