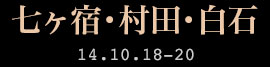
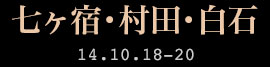

|
 |
 |
 |
|
刈田嶺神社は、蔵王連峰の刈田嶺にもあり、そちらは奥宮、こちらは里宮。神体は夏は奥宮、冬は里宮と遷座するそうで。この時は里宮にいるはず(笑)。
|
役小角の叔父が修業した僧坊の跡とか、それ以前からあったとか諸説あり。蛙のような狛犬はユーモラスなような奇怪なような。 | 刈田嶺神社の上の権現山には幾つかの神社があり、散策路になっていました。これは愛宕神社の鳥居。 |
 |
 |
 |
| 湯神神社。1695年に石碑を建てたのが始まり。お湯かけ祭りというのがあるそうです。 | もうちょっと上にある古峰(こばはら)神社。明治初期に建てられた火伏せの神社。今でも古峰講が続いているそうで。左の展望台はもう登れませんでした。 | 蔵王に沈む夕日。 |
 |
 |
 |
| これが湯神神社の元となった石碑なのでしょうか。 | 籠山観音堂。すぐ側の岩崎山金山で講堂でお湯が噴き出して亡くなった坑夫を弔うために、講堂に観音像を安置したのが始まり。 | 岩崎山金山。伊達政宗が仙台城築城の費用を賄うために掘らせたとか。江戸中期にはすでに廃坑になっていたそうで。出水が原因とも言われています。 |
 |
 |
 |
| 人一人がやっと入れるくらいの坑道が縦横無尽に掘られているので、籠山という別称が生まれたとか。 | 遠刈田温泉はこけしで有名。みやぎ蔵王こけし館というのもあります。 | 壽の湯という共同浴場。もう一つ、神の湯という大きな施設もあります。 |
 |
 |
 |
| 看板代わりの巨大な天狗の面です。 | 片倉家歴代廟所。初代から十代までの墓が並んでいます。代々小十郎を名乗ったそうです。愛宕山から白石城を望む地。 | 少し登ったところにある滝の観音の狛犬。ちょっと不気味。 |
 |
 |
 |
| 滝の観音。すぐ上に片倉小十郎の姉で、伊達政宗の乳母、喜多の墓がありますが、関連はわかりません。向かいにある田中家は明治の建築。 | 喜多の墓。この辺りに草堂を結び余生を過ごしたとか。名君を育てた聡明な女性だったそうで。 | あたりには、幾つもお墓がありました。 |
 |
 |
 |
| 田村清顕の墓。伊達政宗の正室愛姫の父で三春城主。後代、領地を失い片倉家家臣となり、二代後の定広は真田幸村の娘を娶る。ここには幸村の墓もあるとか。 | 白石市街地はまとまって古い建物があるわけではないけれど、こういう建物もぼちぼちと。大正くらいでしょうか。 | なかなかお洒落なお宅です。 |