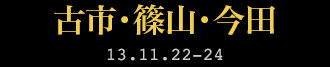
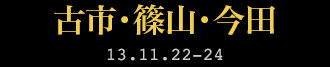

|
 |
 |
 |
|
住吉神社本殿。江戸時代くらいのものなのでしょうか。屋根はこけら葺きのようです。
|
住吉神社の紅葉。木々に覆われ、美しいところ。 | 畑の中に納屋がありました。 |
 |
 |
 |
| 屋根に穴があいていますが、焼き物の工房だったのでしょうか。 | すぐ隣にある登り窯です。丹波立杭焼きは平安末期から続く焼き物。登り窯の中で、松の薪の灰が釉薬と化合して渋い色模様が出ます。 | 住吉神社の鳥居。 |
 |
 |
 |
| 上立杭公民館。ちょっとレトロでいい感じ。 | 窯の壺坂。斜面にそって細い道が走り、たくさんの窯元があります。 | 石垣に甕が載っていました。 |
 |
 |
 |
| 洒落たショウウィンドウです。 | 入母屋の元は茅葺きだった家。 | 段差があるため、家々の屋根が道路と同じ高さになっています。 |
 |
 |
 |
| 大正稲荷神社。北西部に大正時代に築かれた大正窯があるから、大正稲荷。別名白鳥稲荷で、できものの治療にご利益があるとか。 | 大正稲荷のすぐ上にある登り窯。これが大正窯でしょうか。 | きれいな湧き水がありました。 |
 |
 |
 |
| 野面坂の途中から家並を見下ろす。 | 反対を向いて見上げた図。 | あちこちで成形した粘土を干してありました。 |
 |
 |
 |
| 平行四辺形の家。 | 路面にはいろいろな焼き物のタイルが埋め込まれていました。 | そうたろう坂。風呂薮惣太郎という日本各地を渡り歩いた伝説の陶工からの名前。左は陶器神社。元は江戸時代の名工吉兵衛の自家祭神の稲荷神社だとか。 |