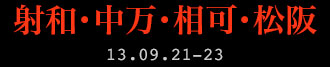
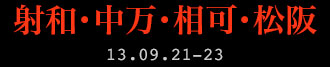

|
 |
 |
 |
|
二階の書斎は柱掛鈴から鈴屋(すずのや)と言われていました。昼間、町医者として働き、夜はここで研究に耽る生活。
|
鈴屋に上がる箱階段。上がると階段の下を取り外して、研究に没頭したとか。 | 鈴屋遺跡保存会の旧事務所は、明治四十二年に旧宅が城跡に移築されたときに建てられたもの。今は桜松閣という茶席になっています。 |
 |
 |
 |
| 城から見た御城番屋敷。 | 本居宣長記念館の外観です。 | 城の周辺は四五百森(よいほのもり)という木々に覆われています。 |
 |
 |
 |
| 本居宣長ノ宮。明治はじめに創建された本居宣長を祀る神社。 | すぐ隣の松阪神社の長寿樟。樹齢九百年とか。 | 赤壁(せきへき)校舎。旧三重県立工業学校製図室。明治四十一年のもの。実験で使う硫化水素で黒変しないように硫化水銀の朱で塗られたそうです。 |
 |
 |
 |
| 武家屋敷街。ずっと槇(まき)の生け垣が続いています。 | 御城番屋敷は長屋形式で、生け垣の中に一戸ずつ玄関があります。今も子孫の方々が住んでいます。 | 一戸だけ、見学できるようになっています。明治維新の時に、苗秀社という会社を作り、今も存続しているそうです。 |
 |
 |
 |
| ぞれぞれに庭がついていて、意外と広いつくりです。 | 1863年の建築。重要文化財。 | きれいな生け垣です。 |
 |
 |
 |
| 御城番屋敷土蔵。幕末の米蔵で、明治になって苗秀社に払い下げられたもの。松阪城の唯一の現存する建物。 | 来迎寺鐘楼門。1821年の完成。除夜の鐘もつくそうです。 | 鐘楼門には三猿がいました。 |
 |
 |
 |
| 来迎寺本堂。大火の後、1731年の再建。三井家の菩提寺で、再興費をいっぱい出したみたいです。重要文化財。 | 元三大師堂は近年の再建らしいです。炎の祭典というお祭りをするようです。元三大師は比叡山中興の祖で、おみくじの元祖。 | これは裏門。大火以前の1625年のもの。 |