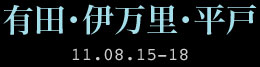
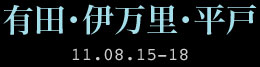

|
 |
 |
 |
|
ここから大河内山(おおかわちやま)。入口にある鍋島藩窯橋。ここで作られた最高の技術を結集した焼き物を「鍋島」と呼びました。
|
再現された唐臼。水力で磁石を砕くものです。 | めおとしの搭。めおとしとは、焼き物を叩いて音で選別する技。そのイメージで作られた機械仕掛けの風鈴。 |
 |
 |
 |
| 唐臼はこうなっています。 | 陶工無縁塔。高麗人(朝鮮人)をはじめとする無名の陶工の墓です。毎年、春には供養が行われているそうです。 | 鍋島藩窯橋を下から見たところ。 |
 |
 |
 |
| 大河内山のメインストリート。せまい坂道に窯元が並んでいます。 | 加藤清正を祀る清正公堂と大公孫樹。樹齢二百五十年。手前の緑地は、藩役宅跡。 | 蛸のような妙な壺。 |
 |
 |
 |
| 家並みの背後にそびえるトンゴ岩と呼ばれる岩山。 | 鍋島藩窯公園のトンバイ橋。 | 陶工の家に再現された登り窯の内部。 |
 |
 |
 |
| すぐ側に、こんな祠がありました。 | 清源下窯跡。出土した焼き物がアクリルで覆われて、幻想的な雰囲気。 | 展望台にある陶磁器の大壁画。 |
 |
 |
 |
| 展望台から見た屏風岩。 | お経石窯跡。全長四十七メートル。あちらこちらに登り窯の跡があります。 | こちらは現役の登り窯。昔のものと比べれば、はるかに小さいもの。若い職人さんがついていました。 |
 |
 |
 |
| 江戸時代の建物は、ほとんど残っていませんが、これは当時の米蔵を移築したもの。 | 左端が副島勇七の墓。名工でしたが、逃亡して砥部や瀬戸に行き、三年後に捕らえられ、斬首されてしまいました。 | 岳神社への上り口です。 |