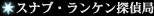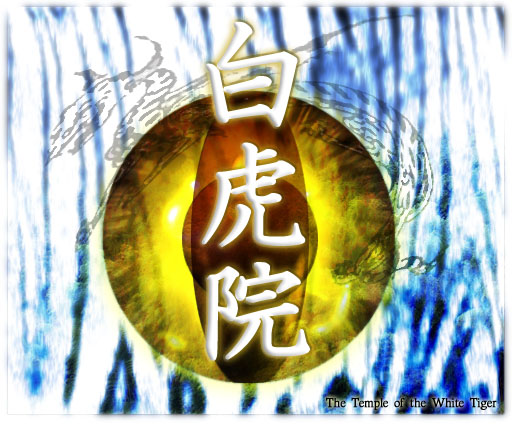
風にざわめく鬱蒼とした竹林を抜けると、その寺院が見える。澄んだ水が流れる急峻な谷を頼りない吊り橋で渡り、切り立った崖に掘られた石段を百段も息を切らせて上った頂近くに、小さな広場のようになった平地があり、さらにその奥にそびえる岸壁を背にして、くすんだ朱色の屋根瓦の建物が建っている。
元来は、アニャチの寺院の多くのように金色に朱赤、群青や緑といった鮮やかな塗りが施されていたのだろうが、歳月と風雨が、そのほとんどを剥ぎ取り、今は乾いた壁と柱の濁った白、それにかろうじて色が残っている屋根の朱色の二色となっている。
周囲に露台をめぐらし、幾本もの柱で支えられた反り返った屋根という造りは普通のものだが、三階まであり、半ば塔のようにもなっているのは、この地では珍しいといってよかった。
屋根の頂には、大鷲のような翼を持った虎の石像が鎮座していた。
寺の名前は白虎院といった。アニャチ帝国の都、魔都ハイナッシャグを震撼させた事件から逃れた私は、この大国の西のはずれ近くにまで至っていた。新皇帝即位での混乱もあり、追っ手の影を見ることも久しくなくなっていた。
クム・ルーンの山裾にあたるこの辺りを抜ければ、バラカッシュの国に至ることができるはずだった。
山裾とはいうものの森は深く道は険しかった。大河ヤンスーカもこの地では深い峡谷を流れる急流となり、川沿いの道も途切れがちだった。
猟師道らしき小道に分け入り、笹が生い茂る仄暗い森の中を抜けると、小さな滝がそこにあった。二十イート(約六メートル)程の高さから、午後の陽光にきらめきながら清流が流れ落ちており、澄んだ水がゆるゆると動く小さな滝壺は、白や薄黄色の小さな花々に囲まれ、小楽園といった趣がある。
滝壺には白い人影があった。木々の葉越しに見えるそれは、小柄な女の裸身だった。こちらに背を向けて彼女は沐浴をしていた。白磁の肌と濡れ羽色の髪からこぼれ落ちる水滴が、光を浴びて虹のように輝き、彼女を桃源郷の仙女のように見せていた。
彼女が脱いだのであろう白い衣、それに何故か、白虎の毛皮が近くの木の枝に掛かっている。毛皮は頭こそついていなかったが、真っ白い艶やかな毛並みに、墨絵のように美しい黒い縞が入った見事なものだった。
私はしばし、彼女の引き締まった細い腰や形良く盛り上がった小さな尻の美しさに見とれていたが、どうやら、近くに御同輩がいることに気付いた。
がさごそと笹をかき分ける音が聞こえ、幾人かの男の話し声が聞こえる。
「おい、見ろ、あれだ、間違いないぞ」
「これで、こんな山奥とはおさらばできる」
「おまけに裸の女までついてるとは、俺たちにも運がまわってきたってことだ」
下卑た笑い声も聞こえてきた。
女は気が付く様子もなく、白い肌に磨きをかけている。私は藪の中に身を沈め、男たちの正体を見極めんとした。
右手の方から、武具がふれあう音が聞こえ、五人の兵士が姿を現した。革の胴鎧に鍔のない簡素な兜を被っている。腰には短めの湾刀、二人は背中に弓矢も背負っていた。位は低いのだろうが、鎧に描かれている龍と黄色い星の紋章は、彼らがアニャチ帝国軍の兵士であることを示していた。
「おい、女、我らは新皇帝モル・ナンロン陛下の命を受けて、白虎の毛皮を探し求めるものだ。そこに掛けてある白虎の毛皮、譲り受けたい」
隊長格らしい男が、威圧的な物腰で言った。
女は、兵士たちが姿を現すと「あっ」と短く声をあげ、水中に体を沈めた。
「その白虎の毛皮は、代々受け継いだ大事な宝でございます。どうかご堪忍願います」
水面から顔だけを出し兵士たちに背を向けながらも、彼女はしっかりした口調で言葉を返した。
「礼はここに用意してある」
兵士は懐から矩形の金貨を三枚取り出した。
「どんなにお礼を戴きましても、その宝には代えることができません。どうか、ご容赦を」
「なに、皇帝陛下の命であっても、断るというのか」
女は何も答えず、兵士たちの方に顔を向けた。
私からは彼女の顔は見えなかったが、まるでその視線に気圧されたように、兵士たちは一瞬身を引いた。
「ええい、身の程を知らない女だ。かまわぬ、毛皮を取れ!それから、この女に口の利き方を教えてやれ!」
隊長が怒鳴った。後方にいた二人の兵士が毛皮に手を伸ばし、前方の二人は、飛沫を上げて水に入り、女に手を伸ばした。
私は剣の鯉口を切りながら、茂みから飛び出した。
私の出現に驚いた兵士たちがこちらを振り向いた刹那、大きな水飛沫があがった。
白い裸身が兵士たち二人の頭を蹴りつけて宙を飛んだ。そのまま隊長の頭も蹴り飛ばし、呆気にとられている残る二人の前に飛び降りると、一瞬で二人の首筋に手刀を叩き込む。
二人が叢に倒れ込むよりはやく、女は掛けてあった膝上までの白い上衣をまとい、細腰に帯を締め終えた。
私も兵士たちも、呆けたように、しばし彼女を見つめていた。
背後で揺れる白虎の毛皮のように彼女の肌は白く艶やかで、うなじ辺りでざんばらに切られた濡れた黒髪には、二房三房の白銀が混じっている。
巴旦杏のような大きな瞳は、目尻が吊り上がり、少しだけ上を向いた小さな鼻と尖った小さな顎と相俟って、猫を思わせる愛くるしい美貌だった。
小さな体躯からすれば、十四五の小娘のようにも見えたが、全身から発する刺すような気と眼光が、彼女を何か名状し難い存在に見せていた。
先刻兵士たちをたじろがせた彼女の瞳は、ほとんど黄色に近い琥珀色だった。神像に象嵌された宝石のように、陽光と水面の光を受けて透き通り、強い輝きを発していた。
彼女は両手を胸の前に突きだし、寸分の隙もない構えを見せていた。
隊長は女から目を離すと、今度は私の方に視線を向けた。彼女に蹴られた頬にはくっきりと赤い痣がついている。
「貴様も邪魔だてする気か。皇帝陛下の兵士に刃向かう者に命はないぞ!」
「そうかい、じゃあもう僕は百辺くらい死んでなきゃならないな」
隊長は怒りで顔を真っ赤にさせ、怒鳴る。
「こいつを斬れ!女と毛皮は斬るなよ!」
最初の驚きから立ち直った兵士たちが刀を抜いて斬りかかってきた。多勢に無勢、一人は丸腰の女と見て、気を取り直したらしい。
水に入っていた二人が私に襲いかかってきた。反りの強い幅広の刀を振りまわし、迫ってくる。
先に切っ先が近づいた剣を跳ね上げ、前に出て二人目の刃と組み合った。鍔迫り合いで突き放し、後ろからかかってきた一人目を振り向きざま袈裟懸けにした。二人目の次の手を避けながら、胴を薙ぎ払う。
二人を倒し、彼女の方へ向かおうとしたが、すでに対峙しているのは、隊長だけになっていた。先刻、手刀をくらった二人は、今度は致命的な一撃を受けたようで、異様な角度で首をかしげて、血を吹いて倒れている。
隊長はついさっきの上気した顔はどこへやら、今は血の気を失い、頬には汗が浮かんでいた。
女は、花のような顔に不敵な薄笑いを浮かべている。小さな唇の端から桃色の舌先がちらりとのぞいた。
女がじりっと間合いをつめる。
隊長は半歩下がり、私の方へ目線を走らせると、「うおう!」と叫びながら、こちらへ突進してきた。
部下よりはさすがに剣技もあり、膂力も強い。必死の形相で続けざまに打ちかかり、私は後退った。
隙をついて、隊長は私の横をすり抜け森の中へ逃れようとした。
私のすぐ側を白い幻のようなものが駆け抜けた。麝香のような芳しい香が、一瞬私の鼻孔をくすぐる。
宙を跳んだ彼女は、背後から男の肩口に跳び蹴りを見舞った。
骨が折れるような音がして、隊長は苦悶に身を捩らせる。着地した女の拳がその顎の辺りを捉えた。
男は大きく体の均衡を崩すと、本流の方へ落ち込んでいる急な斜面を転がり落ちていった。
女は狼藉者がヤンスーカ河に落下する水音を聞くと、私の側に寄り、両の手を合わせて一礼した。
「お助けいただき、ありがとうございます。旅のお方とお見受けしますが、この辺りは夜ともなれば虎も出歩き危のうございます。何のお持て成しもできませんが、今宵は私どもの寺にお泊まり下さい」
私がいなくとも、彼女は窮地を容易く脱することができたような気もしたが、夜露をしのげる場所を供じてもらえるのは、ありがたかった。
彼女の透き通った琥珀色の瞳からは、先程までの強烈な眼光は消え、蠱惑的と言ってもいい密やかなきらめきがあった。
「ありがとう。助かるよ。僕はスナブ・ランケン。放浪の旅の者だ」
彼女が微笑を浮かべると、左の頬に小さなえくぼができた。
「私は、フーツィンと申します。この上の寺で、老師様と暮らしています」
フーツィンは、白虎の毛皮を大事そうに丸めて布の筒の中にしまった。干してあった白い下履きや袴を手に取ると、こちらを見てにやりと笑った。
「駄目ですよ、覗いていては」
私は肩をすくめ、後ろを向いた。寺までの道程は険しく、私は肩で息をするようだったが、フーツィンは「慣れているから」と意に介する様子もなく、軽やかな足取りで跳ねるように登っていった。
瓦の重みに耐えかねた屋根が傾きかけている門をくぐると、庭を掃き清めている一人の老人がいた。
白い簡素な上下に身を包んだ小柄な老人は、穏やかな表情でこちらを見やった。禿頭に艶のあるきれいな白髭を伸ばしている。高齢のようだが背筋は伸び、肌には張りがあった。
フーツィンが事の次第を話すと、老人は軽く頭を下げて一礼した。
「お世話になり申したな。この娘は、ちと元気がありすぎましてな、時折厄介事も起きます。いやあ、ありがとうございました」
老人は、両手を合わせて、もう一度感謝の意を表した。
その夜は、魚や沢蟹、山菜などの質素だが美味な食事と、老人が造ったという白い甘みのある酒で持て成しを受けた。
老人はフーヴァイと名乗った。フーツィンは親類筋にあたる娘だが、幼い頃に両親を亡くしたので、引き取って育てたと語った。
私がメルカーのサンジェリィから大海を越えて来たというと二人は驚き、しばらく私は故郷の話と道中の話を語ることになった。
話が一段落すると、私は昼間見たフーツィンの飛鳥のような技について尋ねた。
「アニャチの国に来て、幾人かの武芸者と出会い、拠無く、刃を交えたこともありますが、あのような早業と身のこなしは見たことがありません。一つ、手合わせと御教授をお願いできないでしょうか」
私は、アニャチの風習に従って、叩頭し願った。
頭を上げると、フーヴァイ老人は少し困ったような顔つきをしていたが、フーツィンは悪戯っぽい笑みを浮かべていた。
「いいじゃないの、老師様。ランケン様は私の恩人だし、剣技も素晴らしいものをお持ちだわ」
老人はしばし黙っていたが、やがて仕方ないといった顔つきでうなずいた。
「では、翌朝、少しばかり手合わせをしてみよう」
「ありがとうございます」
私は再び叩頭した。
老人は先に休むと言って、奥の間に姿を消した。
「どうもありがとう。君が口添えしてくれたお陰だよ」
「いいのよ。私も退屈していたところだし、“弟子”ができてうれしいわ」
フーツィンは、黄色い瞳を囲炉裏の灯りにきらめかせて笑った。
「“先生”、何とぞお手柔らかに」
彼女は舌先を少しだけのぞかせて、唇をなめ、謎めいた笑みを浮かべた。まだ朝靄の残る境内に、私は二イート(約六十センチ)あまりの木の枝を持って立っていた。
五六歩離れたところに素手のフーツィンが立っている。
「まずはランケン殿、お主の剣技を見せていただこう」
フーヴァイ老師は、露台に登る正面の階段に腰を掛けて、悠然とした口調で「始め」と言った。
私たちは一礼し、私は正眼に構え、フーツィンは右半身の構えをとった。昨日、滝壺で兵士たちと対決したときのような、張りつめた気はないようだったが、隙のなさには変わりはない。
「どこからでも」
フーツィンはにやりと笑い、左の頬にえくぼができた。
私は正面から斬り込んだが、彼女は軽く上体を右に振り、いとも容易くそれを躱した。
続けざまに打ち込むが、右に左に見事な動きで躱し続ける。一度引くと見せて、肩口に打ち込んだが、左肩を後ろに引いて苦もなく躱された。
ほんの少し上体が泳いだかと見て、胴を薙ぐと、彼女は軽業のような跳躍を見せ、私の木剣は空を切った。
休みなく突きを送るが、左に跳んで避ける。
次の一撃を、彼女は両の掌で木刀を挟み、受け止めた。
彼女が素早く両手をひねると、木剣は私の手から奪われ、宙を飛んで森の中に消えた。
「そこまで」
フーヴァイ老師の穏やかな声が響いた。私たちは一礼し手合わせを終えた。
フーツィンは汗一つかいてないように見えた。
私はかつてサンジェリィのスレプクレージュ剣術道場でも、一二を争う腕だった。彷徨の旅路で、幾度となく無法の相手と斬り結んできたが、その経験も彼女相手には、ほとんど役に立たないようだった。
「ふむふむ、フーツィン相手にそこまでできれば、なかなかのものじゃろう。次は空手でやってみなされ。お主、何か拳法の心得は?」
「サンジェリィの剣術道場で、余技として少しだけ習ったことが……」
後は、港での破落戸相手の喧嘩や、道中のもめ事で幾らか鍛錬しただけだった。
果たして、私が突き出した拳は、彼女の小さな白い掌で、簡単に受け止められた。次の瞬間には、臑に強烈な足払いを受け、私は転倒した。
身を起こす間もなく必殺の手刀が首筋に寸止めになっていた。
目前にあるフーツィンの美しい顔が、またにやりと笑みを浮かべた。
「教え甲斐のありそうなお弟子さんね」
「やれやれ、月謝を惜しまず、後二つ三つ他の道場にも行っておくべきだったかな」
ふうっと溜息をつき、立ち上がると背中を冷や汗が滴り落ちた。一月ばかりの修行の後、私は、ごく基礎的な身のこなしと技を会得することができた。もちろんフーツィンと素手で対等に渡り合うことなどはできなかったが、「私がいないとき、剣をなくしたとき、死ななくてすむ」程度には身に付いたと、フーツィンは笑って言った。
朝早く起き、掃除をし、食事の準備をし、洗濯をした。フーツィンと共に、森に木の実や山菜を取りに行き、河で魚を捕った。
私たちはどちらからともなく求め合い、交わった。彼女は寝床の上でも、しなやかで鋭敏だった。
フーヴァイ老師は、私たちの閨での仲を承知のようだったが、何も言わなかった。
フーツィンの寝室は寺院の二階にあり、私は三階の小さな部屋をあてがわれており、互いに行き来していたが、老師は一階の本堂の奥、裏手の崖をくり抜いて造られた奥の院の方に寝起きしているらしかった。
老師は時折、深夜、本堂の広間に香を焚き、夜空を見つめて瞑想に耽った。しばらくたってから、蝋燭の炎の下で巻物を開き、何事かを書き記していた。そういうとき、私たちは、老師の邪魔をしないように、三階の私の部屋で、竹林の上に輝く白銀の月を見ながら、静かに酒を酌み交わした。
「フーツィン、老師はいったい何をあの巻物に書いているんだろうか」
「知らないわ。知らない方が良いこともこの世にはたくさんあると、老師様はおっしゃるわ」
彼女はこの話題はこれで終わりだとばかりに、言葉を短く切ると、私の白磁の酒杯に濁り酒を注いだ。
彼女が本当に知らないのかは疑問に思えたが、私はこの寺での暮らしに安らぎを覚えていたので、その疑問には封をしておくことにした。芽生えた疑問は、やがて自ら封を破り、答えを出してしまうことがあることを、私はまだ知らなかった。ある午後、私は最初にフーツィンと出会った滝の側で、香草と木の実を採っていた。滝壺のある開けた場所に近づくと、またあの時のような人の声と武具のふれあう音が聞こえた。
今度は前回のように数人というわけではなかった。三十人近い龍と黄色い星の紋を飾った兵士たちが、滝壺の近くで野営を張る準備をしていた。
藪の中に身を潜め、様子を伺うと、二人の見知った顔があった。
一人はあの時、斜面をヤンスーカ河へ転げ落ちていった隊長格の男だった。左腕を添え木で固定し肩に吊っている。フーツィンに蹴られた顔の痣は消えていた。
もう一人は朱塗りの豪華な鎧を身につけた髭面の男だ。私は彼と魔都ハイナッシャグで出会った。名前をゴウレンといったはずだ。皇帝直属部隊の将軍の一人だ。
魔術とも科学ともつかぬ忌まれた業によって生み出されたあの巨大な怪物が都を蹂躙した事件の最中、私は彼と対峙した。逃げまどう人々を犠牲にして軍を進めていた男を私は殴り倒し、彼の作戦は頓挫した。
「クチャッカ、確かにこの滝で出会ったのだな」
ゴウレンは獅子鼻をこすり上げるようにしながら、傲慢そうに隊長に尋ねた。
「は、確かに。実に見事な白虎の毛皮を持っておりました。が、これが仙女かと思えるほどの身のこなしでして、何とか抑えようとしたのですが……神仙の術を使っているとしか思えぬほどでして……おまけに異国人の邪魔者まで入りましては……」
「もうその話は聞き飽きたわ!麓の村での話では、白虎院なる寺には小娘と年寄りがいるだけだ。いかに武術に秀で、助っ人がいたとて、この人数では勝敗は明らかだ」
ゴウレンは、視線を落として不安気な面持ちになっているクチャッカを、蔑んだ目つきで睨んだ。
「あの時、邪魔が入らなければ、あの化け物を倒して皇帝陛下の御覚えも確かなものになったものを!それが、新帝陛下の御命令で、ゴウレンたる者が、こんな辺境でいるのかいないのもわからぬ白虎探しとは!」
赤い鎧の男は、苛立たしげに歩き回り、手にした軍扇を振り回した。
「だが、これで聖獣たる白虎の毛皮を持ち帰ることができれば、神仙好きのナンロン陛下のことだ、お引き立ての目もあるはず!」
左遷されたらしい武将は、自らに言い聞かせるように荒々しく言葉を放った。しばし、宙を睨んでいたが、ふと何かに思いあたったように、表情を変えた。
「クチャッカ、その異国人の男というのは、どんな風貌をしていた」
「は、異国人と申しましても、半ばは我らハン人のようでもありまして、しかし半ばはタルケシュ人にも似ておりまして、髪は黒く目も黒く、目つきの鋭い……」
隊長はだらだらと私の容貌を述べ立てた。
「もうよい。そうか、どうやら一挙両得ということもあるやもしれんな」
ゴウレンは、髭だらけの顔に残忍な笑みを浮かべた。
どうやら白虎院は二重の災禍を背負い込んでしまったようだった。寺に戻り、滝での話をしたが、フーヴァイ老師もフーツィンも、さして慌てるということもなかった。
「あの男、悪運強く生きていたのね」
夕餉の席で、フーツィンは老師に濁り酒を注ぎながら、言った。
「様々な運というものがあるからな、この世には」
老師は意味ありげな言葉を口にした。
「僕がここでお世話になっていることで、余分な災いを呼び込んでしまったようです」
老人は柔らかい笑みをしわの多い顔に浮かべた。
「何々、時折来るのじゃ、欲の皮のつっぱった不届きな輩がな。お主がここにおろうとおるまいと、奴らめは来よったじゃろう」
フーヴァイ老師は私に酒を勧めた。
「何も案ずることはない。まあ、今宵あたり、それこそ虎でも出て、二三人喰われて逃げ帰るのが落ちじゃろうて」
「そうよ、ランケン。都の兵隊なんて、そんなものなのよ」
そう言って笑ったフーツィンの琥珀色の瞳に、ほんの少しの名状し難い光を見たような気がしたが、急に催してきた眠気と酔いの中で、それは幻のように消えてしまった。
それでも、明日の朝、兵士たちが来るかもしれないからと、老師は今日は早めに休むようにと言った。
私はフーツィンに白虎の毛皮について、詳しく尋ねようと思ったが、寝床に入った途端に襲ってきた睡魔に抗うことはできなかった。どこか遠いところから恐ろしい絶叫が聞こえてきた。身を起こし、どこから聞こえてくるのか、何が起こっているのか、確かめたいと思ったが、瞼は縫いつけられたかのように動かない。
頭の中に泥がつまっているかのような混濁した意識の中で、遠くから、恐怖と苦痛に満ちた叫び声が、長く長く、響き続ける。
体も泥人形になってしまったかのように、いくら起き上がろうとしても少しも動きはしなかった。悲鳴は消えるとすぐ次の声が始まり、何度も何度も聞こえてくる。
悲鳴に混じって、何か低くつぶやくような声も聞こえる。人の名前を読みあげているようにも聞こえる。
ごろごろと唸るような音も聞こえる。
悲鳴が消え、つぶやく声も消えると、唸るような音が次第に大きくなり、獣の吼声となる。すぐ耳元で吠えているようだ。喰い殺されるというもの凄い恐怖感が、動かない全身を駆けめぐる。獣の臭いがする。
突然、私は目覚めた。ひどく寝汗をかいている。飾り格子の窓の向こうに、かけ始めた月が醒めた白い光を放っている。
半身を起こし、隣を見ると、フーツィンがこちらに背を向けて、静かな寝息をたてていた。肩から腰までの柔らかい線が月光に浮かび上がっている。
そうっと頬に触れてみた。いつもより心なしか温かいような気がした。
彼女は寝返りを打った。白い面の中で、唇だけが、驚くほど赤く、艶々と潤っているように見えた。翌朝、兵士たちは、耳障りな武具の音を響かせて、境内に入り込んできた。
昨日見たときは三十人ほどの手勢だったが、今は二十と四五。何人かは、真新しい鮮血に染まった包帯を巻いている。
先頭に立つゴウレンの厳つい顔は憤怒に染まり、朱塗りの鎧と同じくらい赤かった。
「この寺の主はおらぬか!」
ゴウレンの大音声に、驚いた鳥が飛び立った。
「白虎院の主は、この私めにございますが、何かご用でしょうか」
フーヴァイ老師が一人静かに出迎えた。私とフーツィンは、まずは堂内にいるようにと言われていた。
小柄な老人は、鎧兜に身を包んだ大柄な武将の半分ほどにしか見えなかったが、全身から発する見えない何かが、ゴウレンと兵士たちに張りつめた空気をもたらしていた。
「我らは新皇帝モル・ナンロン陛下の命を受けて、帝国に幸運と繁栄をもたらす霊獣白虎を求めている。この寺に白虎の毛皮があることは、先刻わかっている。即座に引き渡せ!さらに、この寺には過日我が兵士を四人殺害した娘と旅の男がいるはずだ。即刻引き渡せ!」
ゴウレンが大声で言った。この男が小声でしゃべる姿は想像し難かった。
フーヴァイ老師は、いつもと変わらぬ柔和な笑みを浮かべたままだった。
「さてはて、何の事やら私めにはわかりかねますな。お見かけしたところ、兵の中には怪我をしていらっしゃる方もおりますな。虎にでも襲われましたか。お手当して差し上げましょう」
兵士たちの剣や鎧が小さくがちゃがちゃと音をたてた。一瞬、彼らの間を見えない恐怖が駆け抜けたかのようだった。
ゴウレンは怒りに体を震わせ、さらに大音声をあげた。
「昨晩、我が兵士たちが虎に襲われた。その虎は夜目にも白く、この寺の方へ崖を駆け上っていったと言う兵士もいる。面妖だ。貴様、何者だ!」
老師は小さく嘆息し、懐より巻物を取り出し、広げた。
「上帝より、あなた方の名前が、鬼籍に入るべき者として伝えられております。しかし、運命とは大河を流れゆく小舟のようなもの、時に流れが弱まり、また水が涸れることもありましょう。押し流されるにはまだ間がありますぞ」
「戯言だ!このゴウレン、運命など一太刀で切り裂いてくれるわ!」
ゴウレンはいきなり両刃の大剣を抜くと、老人に斬りつけた。巻物が二つに裂け、宙を舞う。
だが、フーヴァイ老師は瞬時に六イートも跳び退り、飛んだ巻物をつかみ、再び広げる。
「致し方ありません。それでは、今ここで定めが現実のものとなるということですな……。ゴウレン、クチャッカ、リンシールン、カーヴェイ……」
老師は、巻物に書き連ねてあるらしい名前を低い声でゆっくりと読みあげていった。名前を読みあげられた兵士たちの間に、引きつった表情が次々に広がった。
「臆するな、我らを謀る戯言だ!白虎を手に入れれば、都に戻れるぞ!探し出せ!殺せ!」
ゴウレンの声に、兵士たちは勇気を奮い起こしたようで、「おおー!」と鬨の声を上げると、老人と本堂の方へ突き進んだ。
「出番よ、ランケン」
フーツィンが囁くと同時に、本堂の扉を開いて飛び出した。私も後を追う。
私たちは、まだ死の名前を読み上げている老師の前に立った。兵士たちがどよめき、足が止まる。
「こ、こいつらです。この牝猫とその男が四人を殺したのです」
後列にいたクチャッカが半ば怯えた声で叫んだ。だが、その声はゴウレンの大声でかき消された。
「貴様!やはり、そうだったか。スナブ・ランケンとか言ったな、貴様のせいで、俺は宮廷を追われて、こんな山の中で虎探しだ!覚悟しろ!」
「民人を平気で見殺しにするような武将に、宮廷にいる資格はあるまい。この静山にしても、お前のような輩がいては迷惑千万だろう。お前の居場所は冥土が相応しいってことだろうな」
ゴウレンは激怒し、赤鬼のような形相となった。
「お前たちの欲しがる白虎の毛皮は、ここにあるよ。(と言って、フーツィンは背中に背負った筒を指さした)取れるものなら、取ってごらん」
フーツィンの挑発に、一斉に兵士たちの白刃の輪が迫る。
はっという気合いの声と共に、白衣の女は跳躍すると、両足を開いて最初に届かんとしていた剣を蹴り返した。
足下の兵士の兜を蹴って宙返りで、背後に降り立つと、目にも止まらぬ速さで数人の兵士たちを蹴り倒す。
唖然とする兵士たちが次の手を繰り出すよりも速く、さらに二人三人の兵の喉元に手刀と拳を叩き込む。鮮血を吹き出しながら、兵士たちが倒れる。
フーツィンの小さな体は旋風のように舞い、宙を駆け、襲い来る兵士たちを薙ぎ倒していった。
もちろん私は彼女の闘いを見物しているわけではなかった。兵士たちの半数は私に向かって刃を振るってきた。
私はフーツィンのように、流麗な動きで敵を倒すことができるわけではなかったが、陽光にきらめく何振りもの曲刀が一時に向かってきたとき、一月ばかりの修業の成果を感ずることができた。
兵士たちの動きが、妙にゆっくりとしたものに感じられたのだ。ほとんど同時に襲いかかってくる刃が、まるで型の練習でもしているかのように、一つ一つ順繰りに向かってくるように見えた。
敵の動きが見えれば、後はそれを躱して、こちらの刃を振り下ろすだけだった。
最初に突き入れられてきた剣を跳ね上げ、開いた脇の下に剣先を突き刺した。引いた刃で二人目の首を払い、さらに剣を返して三人目の胴を突いた。
たちまちの内に私たちのまわりは血飛沫飛び散る修羅場と化した。
何人かの兵士が、私たちの後ろへ回り込んで、フーヴァイ老師の方へ向かった。
巻物を読み終えた老師は、悠々とそれを懐に入れ、襲いかかる兵を出迎えた。
私は老師に一瞬視線を向けたが、助けに行く必要はなさそうだった。
剣先が近づくや否や、ゆったりとした動きで両手を少しだけ回すように動かすと、兵士の手から刀はもぎ取られ、ほとんど相手の体に触れているようにすら見えないのに、投げを打たれたように、屈強の兵がもんどり打って地面に転がされた。
むしろ、老師を気遣った一瞬の隙を突かれて、私の方が、二の腕に浅い傷を負ってしまった。
私は剣を振るい続け、フーツィンは掌と拳と足を恐ろしい武器として舞い続けた。
兵士たちも、戦い方を知らないわけではなかった。最初の幾人かが倒されると、闇雲に突進するのを彼らは止めた。私たちの動きをじっくりと見ては、寄せては返し、少しずつ私たちに傷を負わせ、力が減ずるのを待つ作に出た。
私の剣は朱に染まり、鎧と肉と骨を断ち続けたが、刃は次第に鈍っていった。
フーツィンの人間離れした早業も、少しずつ速さが鈍り、白い衣は何ヵ所も裂けて、兵士のものではない血も滲んでいた。
周囲には十人ばかりの死骸が転がっていたが、未だ敵は十四五は残っており、次第次第に押されて、私たちは本堂の前に囲まれていった。
「さあ、後一息だ。白虎の毛皮を手にして、我らは都へ凱旋するぞ!」
ゴウレンが闘いの輪の後ろから檄を飛ばす。都を追われた武将は、未だ一度も私たちと刃を交わそうとしていなかった。
兵士たちが、さらに包囲の輪を縮めようと身構える。フーツィンは私の顔を見て、ほんの少し眉間にしわを寄せ、哀しげな顔をした。
私はそこに隠されているものがわからなかった。
フーツィンは瞼を伏せ、私から視線を逸らすと、老師と目線を交わし肯き合った。さっと背中の筒を取り、中の毛皮を取り出した。
「そんなに、この毛皮が欲しいのかい、都の痩せ犬ども!ならばいっそのこと、生きている白虎を生け捕りにでもしてみたらどうだい!」
フーツィンの気迫に押されて、兵士たちがわずかに刃を引く。
フーツィンは、燃えるように輝く琥珀の瞳で私を見やり、再び哀しげな顔をしたが、すぐに小さなえくぼを見せて微笑むと、美しい白と黒の縞の毛皮をばさりと広げた。
花のような香が鼻孔をくすぐった。
瞬時に起こった変化に私は我が目を疑った。
フーツィンがまとった白虎の毛皮は、するすると伸びるように全身を包み、彼女自身と一体になっていく。愛らしい顔は、和毛で覆われ、鼻と口が突きだし、鋭い牙が唇からはみ出す。
白銀と墨色の毛皮に覆われた背中を丸めると、フーツィンだったものは、鉤爪の生えた前足を地に着き、しなやかな尻尾をぴんと立てて咆吼した。
私が、枕をともにし、歓を尽くした女は、人間ではない何かだった。
ざざっと境内に土埃を立てて、兵士たちが後退った。兜の下の顔は、皆一様に驚愕と恐怖に引きつっていた。
強欲と剛胆の将ゴウレンも、赤ら顔を蒼白にして、只々、眼前で起こった恐るべき怪異に見入るのみだった。
「こ、これは……人虎というものか……本当にいようとは……」
もう一声吠え声をあげると、白虎は兵士たちに襲いかかった。
逃げ遅れた一人がたちま々ち喉笛を噛み切られて、絶叫をあげる間もなく、鮮血を迸らせながら息絶える。
白虎は白銀に輝く毛皮を血に染めて、次の得物に飛びかかる。剣を放り出して逃げ出す兵士の革鎧を巨大な爪で紙のように引き裂き、喉元に食らいつくと、勢い余って兵士の首は引きちぎれ、真っ赤な生血を飛び散らかせながら、転がっていく。
もはや恐慌に陥っている兵士たちは、悲鳴をあげて逃げ惑った。
「怯むな!戦え!相手は獣一匹だ!」
声を嗄らしてゴウレンが叫んだが、誰も聞いている者はいないようだった。三人目、四人目が手足を喰いちぎられ、はらわたを引きずり出されて、血みどろの肉塊に変わる。
門の方へ逃げ出そうとする兵士たちを、白虎はフーツィンであったときの身の軽さを思わせる跳躍で追いかけると、まとめて二人三人を打ち倒して、血の海に沈めた。
絶望的な叫び声をあげて、一人の兵士が白虎の背中に斬りかかった。だが、虎は、人間であるかのような素振りで振り返り、体を躱すと、爪の一撃で兵士の刀を吹き飛ばし、肩口に牙を深く突き立てると、ばりばりという音と共に、半身を食いちぎり、兵士の体を二つに引き裂いた。
逃げる兵士を右に左に追い詰めて、フーツィンだった獣は、「狩り」を続けた。
私は、半ば畏怖の念を感じながら、この恐ろしい様を見ているしかなかった。白い毛並みを血に染めて、しなやかな動きで殺戮を続ける白虎は、恐ろしくもあり、また美しくもあった。
私のすぐ隣では、フーヴァイ老師が静かに佇んでいた。穏やかな表情ではあったが、目には厳しい光があるようにも思えた。この柔和な老人もまた、人ではない名状し難き存在なのだろうか。
視界の隅の方で、赤い何かが動いているのに私は気付いた。
朱塗りの甲冑の男が、死んだ兵士の箙から取り出した矢を番えて、白い虎の方へ鏃を向けていた。
「ゴウレン!」
私は叫びながら、駆け寄ったが、私の刃が届く前に、矢は放たれた。
フーヴァイ老師が宙を飛び、手を伸ばしたが、矢はそのわずか先を飛び抜け、白い虎の背中に深々と突き刺さった。
虎の苦悶の咆吼の中には、女の悲鳴が織り交ぜられているように、聞こえた。
私は剣を振り下ろし、ゴウレンの弓を真っ二つに断ち切った。
「今だぞ!虎は怯んだぞ!」
ゴウレンは叫びながら、弓を放り投げ、剣を抜いて飛び退る。
生き残っていた兵士の一人が、恐怖に囚われながらも、狂ったような声をあげて、傷付いた白虎に剣を振り下ろそうとする。虎は前足の一撃で、剣と兵士を諸共吹き飛ばしたが、門の影から近づいたもう一人の兵が投げつけた短槍を躱すことはできなかった。
槍は背に突き刺さり、白虎は倒れて苦痛に身を捩らせる。
「やった!は、ははは、俺がやったぞ!は、ははは……」
狂気じみた笑い声をあげているのは、左腕を包帯で吊っているクチャッカだった。
「フーツィン!」
私は、彼女の下へ飛んでいきたかったが、それには、ハイナッシャグから来た将軍を倒さねばならなかった。
「次は貴様だ、スナブ・ランケン!」
獅子鼻の男は、両刃の大剣を振り回し、気勢をあげた。
だが、ゴウレンの声は背後から湧き起こった雷鳴のような音でかき消された。
はらわたを震わせるようなその大音声は、倒れたフーツィンの前に屈み込んでいる白衣の老人から発せられたようだった。
私もゴウレンもクチャッカも、生き残った兵士たちも、動きを止めて、屈み込んだ小柄な老人に視線を注いだ。と言うよりも、フーヴァイ老師から発せられている、恐ろしい何かが、その場にいる全ての人間を金縛りにしていると言った方が良いかもしれない。
晴れ渡っていた朝の空は、急にかき曇り、鼠色の雲が渦巻いた。湧き起こる風に、竹林がざわざわと大きく揺れて、木の葉が舞い飛ぶ。冷気が辺りを包み、激しい闘いで汗ばんだ体が急に冷えていく。
しゃがみ込んでいた老師が、今度は囁き声で何かを言うと、大きく腹を波打たせて苦しげな息をしていた白虎は、人の仕草のようにうなずき、息も幾許か楽になったかのように見えた。
フーヴァイ老師は、さらに背中を丸めて全身に力を込めて身を震わせた。白金の光が老師の体から上り立ち、その光に包まれて小柄な体躯が倍ほどにも大きくなったかに見える。
柱のように立ち上った光が、一瞬捻れたように見え、それは巨大な鷲のような翼になった。
丸めた背中に光の輪が走ったかと思うと、それは見事な白と黒の縞模様となり、耳を劈く咆吼とともに身を伸ばせば、そこには九イート(約二・七メートル)はあろうかという巨大な有翼の白虎が現れ出でた。
白虎は、大きく羽ばたくと、その巨体からは信じられない動きで宙に舞い上がり、立ち尽くしていたクチャッカの頭上に迫った。
強運の隊長は、為す術もなく目を見開いて、空から迫る死の顎を見つめていた。牙を剥き出した白虎の口が、クチャッカの頭を丸ごと飲み込み、一瞬で噛み砕いた。
主を失った体は、噴水のように血を噴き出しながら、頽れる。
生き残っている兵士は後二人。フーヴァイだったものは、身を切るような冷たい風を巻き起こして、再び宙に上ると、恐怖に駆られて闇雲に剣を振り回す二人に襲いかかった。
二振りの鋼の刃が、木の枝のようにへし折られて、飛んだ。わずかの間をおいて、二組の手足が赤い血飛沫の軌跡を描きながら、四方に乱れ飛ぶ。八つ裂きにされた真紅の人間の残骸のようなものが、どさりと音をたててゴウレンの足元に投げ出された。
有翼の巨大な虎は、髭面の将軍の前に歩み寄る。
ゴウレンは喉の奥で笛のような音をたてると、後退った。自慢の髭がふるえているように見える。汗の滲んだ顔は鉛色に変じ、朱塗りの鎧まで色褪せたかに見える。まるで、塗りが剥げ朽ち果てようとしている出来の悪い彫像のようだった。
「……貴様を……倒して……俺は宮廷に……」
ゴウレンは肩で息をしながら、長剣を握り直した。
白虎は一声吼えると、跳びかかった。前足で薙ぎ払うと、大剣は真っ二つに折れ、都から来た男は、ひーっという甲高い女のような悲鳴をあげた。下あごから胸元までを一気に食いちぎられて、ゴウレンは絶命した。
「フーツィン!フーツィン!」
私は倒れている白虎の下に駆け寄り、血みどろの牙の生えている頭を抱きすくめた。老師が何らかの術を施したようで、息は静まり、出血も止まっていたが、苦しげな様子に変わりはない。
琥珀色の瞳の訴えに応じて、私は背中に突き刺さった矢と槍を引き抜いた。再び息が荒くなり、傷口からは新たな血が流れ出した。
白虎は大きく背中を丸めると、全身を震わせ苦しそうに小さく吼えた。
瞬時に、その身が縮まり、私の腕の中には血にまみれたフーツィンの愛おしい姿があった。
「フーツィン!」
「ランケン、大丈夫よ、このぐらいでは……死なないのよ……でも……」
かすれる声でそう言うフーツィンの黄色い瞳は、未だ縦に細い虎の瞳だった。薄紫色になっている唇からは小さな牙がのぞいている。
「でも?でも、何なんだ……フーツィン!」
フーツィンの小さな体は私の腕の中で、徐々に冷たくなっていくように感じられた。
「ランケン、お主は行かねばならない」
フーヴァイ老師はいつの間にか変身を解き、元の穏やかそうな小柄な老人に戻っていた。だが、その白い衣はどす黒い血の染みで斑模様になっている。
「老師、それはどういうことです」
「お主は見てはならぬものを見た。さらに、ここに留まれば、さらに見てはならぬもの、見るべきではないものを見ることになる。我らは、人ならぬものだ。お主は人の世で生きるのじゃ」
フーヴァイ老師の声はいつになく厳しく、異を唱えることはできないように聞こえた。
「しかし、老師……」
私には腕の中で苦しい息をしている愛しい女から手を離すことはできなかった。
「ランケン、我らは今一度虎にならねばならない。我らは、人とは違って、面白おかしく狩りをするわけではない」
私は老師の言うことの意味がすぐには理解できなかった。ただ、腕の中の愛しいものから手を離したくなかった。
「ランケン、フーツィンはひどく傷を負っている。急がねばならない。お主にできることは、ここを去ることだけじゃ」
私は、どうして良いかわからなかった。
「……ランケン、行って、お願いだから……」
「フーツィン!」
彼女がすうっと息を吸い込むと、白い頬にほんの少し血の気が戻り、琥珀の瞳は丸い人間のものとなり、牙は小さな糸切り歯になった。
身を起こして、柔らかい唇を彼女は私の唇に押し当てた。
次の瞬間、私は目に見えない力で吹き飛ばされ、本堂の広間に転がっていた。
「奥の院の洞窟をどこまでも進むのじゃ。バラカッシュの国に抜けることができる。決して、振り返ってはならぬ。さらばじゃ、ランケン」
老師の声は、頭の中に直接届いて響いているように聞こえた。血にまみれた兵士たちの骸の中に立つその姿は、白金の霞に包まれている。背後に上り立つ光の柱は、また翼となるのだろうか。
「ランケン、さよなら、とても楽しかったわ……」
フーツィンの鈴の音のような声が耳元で囁いた。
琥珀色の瞳が潤んで、美しい金色の光を放っているように見えた。ほのかに微笑むと、左の頬に小さなえくぼができた。
彼女は血まみれのその身を、大きく広げた白虎の毛皮で、再び包んだ。
滲んだ涙で視界が曇り、これから起こることをわずかな間覆い隠した。
私は人ならぬものとの日々に背を向け、暗闇に包まれた奥の院へ歩き出した。大広間から仄暗い廊下を抜けると、壁は岩肌に変わり、外の光はどこからも届かなくなった。
壁龕の燭台を手に取り、その灯りを頼りに私は歩き続けた。
背後から、弱い風に乗って幽かな音が聞こえてくる。何かが砕けるような音、何かが引き裂かれるような音、柔らかい何かをぴちゃぴちゃと噛んでいるような音。
酸っぱいような血の臭い。
私は、すべては幻だ、と自分に言い聞かせ続けながら、洞窟を進んだ。
しばらく行くと、洞窟は広がり小さな部屋になっている所へ出た。何本かの蝋燭が点いており、橙色の光の中に浮かび上がっているものが見えた。
粗末な低い寝台があり、小さな机には筆と硯と紙が置かれている。ここが奥の院で、フーヴァイ老師が寝起きしているところなのだろうか。
床には、何本かの、まだ真新しい人骨があった。
この部屋はこれ以上詮索するべきではないようだった。
部屋の奥には、傾いだ木の扉があった。開けるとさらに洞窟は続いていた。
左右の壁には岩肌を穿って作られた何段もの棚があった。蝋燭の灯りを寄せると、そこには無数の髑髏がぽっかりと空いた虚ろな眼窩を晒していた。
何百何千の髑髏が、洞窟の壁を埋め尽くしていた。何も見えない黒い瞳と、何も語らぬ永遠の薄笑いを張り付かせた口が、どこまでもどこまでも連なっていた。
私は通廊を走った。汗が噴きだし、喉が干上がり、胸が焼け付き、意識が朦朧とするまで走り続けた。蝋燭が消えると、暗闇の中を走り続けた。
やがて行く手に光が見えた。足が萎え、這うようにして光の方へ進んだ。上り坂を身を引きずるように上がると、真っ青な空に白い筋雲が流れていくのが見えた。
私は草に覆われた洞窟の出口から、何とか体を引っ張り上げた。
なだらかな斜面に草原がどこまでも広がっていた。雪が残る青い山々が遙かに見える。
私はバラカッシュの国に着いたことを知った。
振り向くと、叢の中、岩山にぽっかりと洞窟の口が開いている。風雨に晒され、蔓草に覆われ、しかとはわからなくなっているが、入り口の上には、歪んだ怪物じみた有翼の獣の像が彫り込まれている。左右には苦悶に身を捩っているかのような歪な人骨が彫られていた。
私は黒々とした洞窟の奥の闇をじっと見つめた。風に叢がざわめく音に交じって、幽かな水音が聞こえてくるような気がする。闇の中に、きらきらと光る水滴が踊っている。
黒い歪な円の中に、滝壺で沐浴するフーツィンの美しい裸身が浮かんできた。蠱惑的な笑みを浮かべ、琥珀の瞳が艶やかな光を放つ。
滑らかな白い肌を水滴が転がり落ちていく。水滴は落ちながら朱に染まり、滝は血飛沫を上げる真紅の水流となった。
フーツィンは全身を血に染めながら、嫣然とした仕草で、水浴を続けた。滝壺の中には血まみれの頭蓋や肋、肉や臓物が浮かび上がっている。
血の臭いが自分の体の中から湧きあがってくるような気がする。
目を閉じ、頭を打ち振る。涙に滲む目を開くと、幻影は消え、ただ黒い洞窟だけがそこにあった。
私は踵を返し、草原へと歩き出した。
この幻から解き放たれるまでには、ひどく長い歳月が必要だった。