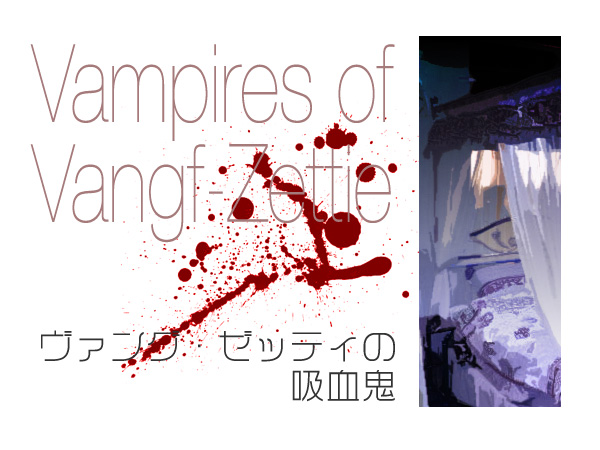
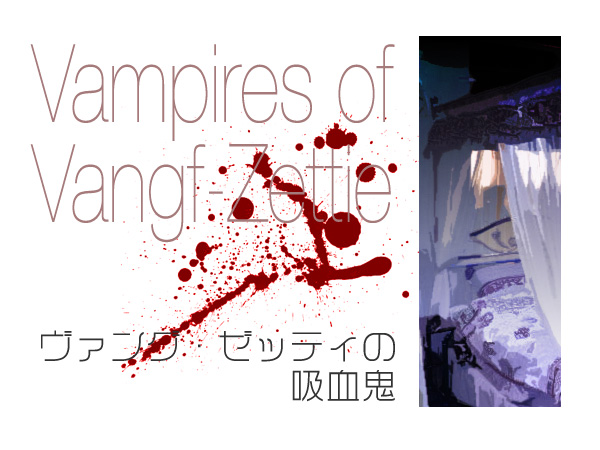
その頃私は探偵などという妙な生業にはついておらず、只の宿無しの風来坊だった。確固とした目的を持っているわけでもなく、定められた轍から逃げだしたい一心と、世界には西方随一の大都サンジェリィにもない驚異と神秘があふれているに違いないという思いから、ひとりふらふらと世界をさまよっていた。
腰に吊っているのは街道筋のはずれで野盗から奪った、いささか刃こぼれのある剣であり、挨にまみれたえんじ色の外套と帽子といういでたちで沓底をすりへらして歩いた。年月を経てサンジェリィにスナブ・ランケン探偵局などというものをひらいている今の私とその頃の私とでは、変わってしまった点も少なくないだろうが、ひとつだけ確かに変わっていないことがある。つまり私は妖怪変化魑魅魍魎の類にやたらと縁があるということだ。
ヴァング・ゼッティという一風変わった響の名を持つその村は、サンジェリィのはるか北東、オルケイ山脈を越えた山あいにあるひなびた村だ。東方諸国は今も“東の王座”を争って無益な戦さをくり返しているが、ヌバダー公国の北端に位置するこの小村にまでは戦さの手はのびてきてはおらず、活気というものはないものの平穏なたたずまいを見せていた。
私がくたびれた馬の背に揺られて細い山道を下って村にはいったのは、ぎらつく夕日も穏かな色合いとなってオルケイの山々の向こうに没もうとしている頃だった。木と土でつくられた白っぽい家々が並ぶ村の通りを歩きながら、道行く村人に私は村に宿屋がないかと尋ねた。だが私の旅人としてはごく当り前の質問に、村人たちはまるで自分の葬式の日取りを尋ねられたかのように、無愛想で不気嫌な答を返してくれた。
三人目に尋ねた若い農夫は朴訥な顔を曇らせて只一言、「ディスカードン館がある」と言って目顔で細い分かれ道を指し、足早に歩み去った。
私は漠とした不安を感じはしたが、こうした小さな村では他者に排他的な態度をとることが住々にしてあるものだという常識的解釈をとることにして、若者が示した小径を行くことにした。
道は山あいのわずかな平地を利用して耕されている貧相な野菜畑の間を抜けて幾分上り坂になっていった。やがて大きく右に曲がり急な坂となり、その向こうに青い夕闇を通して一軒の家が見えてきた。
曲がり角の道端にひとりの老婆がうずくまっていることに私は気づいた。乞食のような身なりの老婆は私が近づくと立ちあがった。
「旅の男よ、ディスカードンの家には近づかん方がいい。そなたの身の為じゃ」
「何故だ」
「あの館にはとりついておるものがある。決して消えない赤いしみがあるのだ」
老婆は歯の欠けた口を歪めて皮肉っぽい笑い声をあげた。
「おまえの言うことはわけがわからないね。私は今夜、寝床と食事が必要なのだ」
「ならば、行くがいい。最高の食事と寝床が用意されておるぞ」
老婆は再びいやな笑いをあげて、背後の藪の中に姿を消した。
私は一瞬躊躇したが、館の窓からもれる暖かそうな灯の色の誘惑に負けて馬首をめぐらせた。
「ディスカードン館−宿と食事−」と金文字でかかれた比較的新しい看板を掲げたその家は小じんまりとした二階建ての建物で、最近壁を塗り直した様子があったが、古びて黒ずんだ色相の木の肌と白い壁のとりあわせはひどく不似合いに見えた。
風雨にさらされてつやをなくした扉を叩くと四十がらみの主人が出て、迎えてくれた。不吉な老婆の言葉や村人の態度とは裏腹に主人−レギリィと名乗った−は明かるく屈託のない人物に見えた。温かい山鳥のスープと山菜の料理を用意しながらレギリィは語った。
「あたしはまだここに来て三年ほどなんですよ。ちょいとわけがありまして、田舎でのんびり宿屋でもやろうかと思いましてね、たまたまこの村に湯治に来たとき−ここには万病に効くという鉱泉があるんですよ−この宿屋が空き屋になっている話を聞きましてね、買いとって住みついたわけですよ。どうも村の連中は他者に対して冷たくてねえ、もう三年もいるってのに妙な噂を流してる奴がいて困りもんです。婆さん?ああジスコの婆さんか、ありゃもう半分気狂いみてえなもんですから、気にしないでくだせえ。最近、古いけどいい家具をいれましてね、実に居心地のいい部屋を用意しますよ。まあ、のんびり湯につかって旅の疲れを癒してくださいよ」
確かにここの風呂は何か特別の功能があるらしく、湯をつかったあと私は体の隅々まで新たな活力が満ちるのを感じた。
宿の客は私ひとりというわけではなかった。東方風の岩風呂を出て自室に戻るときすれちがったのだが、若い夫婦がとまっていた。夫の方は肉づきのよい丸い目をした男で、小金のある商売人といった風体であり、妻の方は夫とは対称的に痩せすぎの、だが美しい女だった。
私が二階の露台に置かれた椅子にすわり、二十年ものだという村名産のフィチィ酒を飲んでいると若夫婦があらわれた。
「今晩は、御邪魔してもよろしいですかな」
男がいんぎんな口調で言った。
「ええ、もちろん。どちらからおいでですか」
「イリヴァーツからです。妻の病にこの鉱泉が効くと聞いたものですから」
「おや、具合が悪いのですか」
「ええ、たいしたことはないのですが、生まれつき血の薄い体なんですの」
女が細く透きとおるような声で答えた。ほっそりした体同様、脆くて壊れそうな声だった。空はよく晴れ、満ちようとしている月が青い光を放っていた。女の肌は月光と同じくらい青白かった。
「あなたはどちらから」
「放浪の身ですよ」
私たちはあたりさわりのない会話をとぎれとぎれにかわし、やがて夫婦は自室へと引っ込んだ。私はフィチィを飲み干すまで月をながめていた。
翌朝、女の悲鳴で目がさめた。フィチィは以外とねばり強く頭で足踏みしていたが、私は起きあがり、剣をつかんだ。
夫婦の部屋は私の部屋の向いの左隣だった。扉を叩く。返ってくるのは弱々しい泣き声だけだった。扉をあけて中に入った。
私の部屋より幾分広く、昔は天蓋付きだったらしい寝台を二つ並べて置いてあった。東側の窓から朝陽が窓掛けをつらぬいてさし込んでいた。
陽光のあたらない壁際の寝台の上で白い寝間着姿の女が細い骨ばった指で顔をおおい泣いていた。もうひとつの朝日のあたる寝台の上では小太りの男が妻よりも青白い顔で横たわっていた。
「目がさめたら主人が、主人が……冷たくなっていたんです!」
若い妻はあえぎながら、そう叫んだ。私は男の冷たい胸に耳を押しあてた。心の臓は動いていた。息もある。
「奥さん、大丈夫。御主人は生きてる」
自分の麻袋の中から気付け薬を取ってきて紫色の唇に流しこんだ。窓掛けをあけて暖い日光をとりいれる。私たちは冷えきった男の手足や胸をけんめいにこすった。騒ぎを聞きつけた宿の主人がやってきて部屋の暖炉に火をともした。
しばらくすると男の体にぬくもりが少しずつ戻ってきた。息も胸の動きもずっとしっかりしてきた。やがて彼は目を開いた。
「おお、ドロウク」
若妻は夫の胸にしがみつき、泣きじゃくった。ドロウク・タクソンは周囲の状祝をすぐにはのみこめなかったらしく、眠そうな赤い目でぼんやりと私たちの顔を順ぐりにながめていた。
「御病気なのは奥さんではなかったのですか」
「ああ、わからない、こんなことは初めてなんだ。夜中に何かひどい夢を見たような気がする。何か……熱い激しい…何かだ……それからすうっと体が冷えていったんだ。苦しいわけではなかった。体が軽くなっていくようで、心地よいだるさが……ああ、わからないよ」
タクソンは今度は安らかな息で眠りこんだ。私とレギリィはタクソン夫人に、もう大丈夫だからと声をかけ、ひとまず部屋を出ようとした。
そのときタクソンが寝返りをうち、青白い首筋の左側が私の目にはいった。そこには指先ほどの赤いしみが浮き出ていた。
「奥さん、御主人にはここに以前からあざがあったのですか」
「え、いえ、あざなんて気がつきませんでしたわ」
レギリィは、この近辺の山にたくさんいる毒虫に刺されたに違いないと言った。この病もその虫の毒のせいだろうと彼は推測した。
「なあに、この静かな宿で栄養のいいもん食って三、四日休めば元気になりますって」
そう主人は自信ありげに太鼓判を押した。彼はある種の伝説については無知であるらしいと私は考えた。そうでなければそういうことを頭から信じない類の人間であるかだ。そういう人間は少なくない。
タクソンは夕食の頃にはかなり元気をとり戻し、我々と一緒に階下で食事をとった。たいした量は食べなかったが、夫にあわせてか、夫人の方もあまり食事には手をつけなかった。
夫人は昼にも夫につきっきりで、ほとんど何も食べていなかったようだが、その割りには青白い頬にはほんのりと赤味がさし、咋日よりも健康そうに見えた。もっとも月光の下ではどんな人間でも肺病持ちのように見えることがあるものだが。
タクソン夫妻は早目に自室に戻り、私は二階の露台に陣どった。今夜はフィチィは一杯だけで我慢することにした。
咋日よりも丸みを増した月が傾きだすと仕事にとりかかった。露台からすぐ手が届くところに運よくアジュームの葉が繁っていた。その濃い緑の葉を二十枚ばかり集め、廊下を忍び足でタクソンの部屋へ歩いた。
聞き耳をたてるが、微かな寝息しか耳に届くものはない。私は懐から大蒜を一個とり出した。先刻、台所から失敬してきたものだ。それを夫婦の部屋の扉のまわりにこすりつけた。強い匂いが広がる。次にアジュームの葉を扉と框の間に一枚ずつ差し込んでいった。
それからが少々やっかいだった。露台からタクソンの部屋の濡れ縁へと物音をたてないように注意をはらって乗り移った。窓にはちゃんと鍵がかけられている。中では二人とも安らかに眠っているようだ。窓にも扉と同様の処置を施し、露台から廊下へ戻った。これでとりあえずは完了である。
私は自分の部屋にも大蒜とアジュームの呪いを施し、寝台へともぐりこんだ。
翌朝は悲鳴で起こされることはなかった。かなり陽が高く昇ってから目をさまし、服を着て廊下に出た。タクソン夫人は私の眠りをさまたげぬようにという心配りからか、今日は静かにすすり泣いているだけだった。扉のアジュームの葉は咋夜、私がはさめたままだった。
中にはいった。窓は咋日の朝と同じく窓掛けが閉められたままであり、今日も朝日はタクソン夫人の悲しみには無頓着に室内に侵入しようとしている。夫人は咋日と同じように白い寝間着を着て顔をおおい、すすり泣いている。隣の寝台にはこれまた咋日と同じようにタクソンが蒼白な顔で横たわっている。だが、その顔色は咋日よりもいっそう青白く、死人じみているようだった。
私は何も言わず若い男の脈を調べ、鼻の上に手をかざした。今日はまちがいなく死んでいた。
窓掛けをあけてみたが、窓は開けられた様子はなく、アジュームの葉もそのままだった。私はひとつため息をつくと主人のレギリィを呼びに階下へ行った。
墓地はディスカードン館のすぐ裏手にあった。小さな林にさえぎられ宿からはほとんど見えないのだが、そこにあったのだ。レギリィの話によると村で只ひとつの墓地だということだが手入れする者もいないようで、草々はのび放題、苔むした墓石がひねこびた蔦にからまれてかしいでたっている、寂れはてた所だった。
タクソン夫妻はイリヴァーツ市民の例にもれず、ジャクレン教徒だったが、村にその信者はひとりもいないので、夫人自らが祈りを唱えることになった。
葬儀と埋葬はその日の夕方、行われた。ジャクレン教徒は死体を前にして長々と文句を言いあう習慣はない。死出の旅への護符である小さな木の礼を死体の額にかけ、夫人が祈りをあげ、後は村にたったひとつある寺院−ミネゴン教のものだ−から大急ぎで持ってきた白木の棺に死骸を収めて埋めるだけだった。
私の呪いは何の効果もなかった。誰もいや、何も侵入してくるものはなかった。タクソンはたちの悪い毒虫にやられて死んだのだ。首の赤いあざは倍ほどにふくらんでいた。
タクソン夫人−マライネという名だった−は朝から夜まで泣き続け、顔をあげたのは夫の天界への旅の安全を祈る唱句を唱えるときだけだった。涙が頬に黒ずんだ痕を残し、鳶色の目は泣きはらして真っ赤だった。にもかかわらず彼女は美しかった。青白い肺病疾みのような肌は頬と唇だけが強い赤味を示し、悲嘆にくれたその面差しは何か心騒ぐものがあった。
レギリィと私は交互に棺の上に土をかぶせていった。棺の蓋のミネゴン教の印である二重の三角ははぎ取られ、かわってマライネ・タクソンの手によってジャクレン教の聖句が書きつけられていた。やがてそれも土におおわれて見えなくなり、タクソンは我々の世界から姿を消した。
そのときはそう思ったのだ。私の経験は浅く、頭は鈍かったのだ。
その夜は廊下をぎしり、ぎしりときしませる重い足音で目が覚めた。
二階には私と今日からタクソン未亡人となったマライネの二人しかいないはずだった。その足音は少くともマライネのものでないことは確かだった。彼女の倍は目方のありそうな、葬式のあった夜中に聞くにはあまり向いていないといえる足音だった。
不吉な足音は次第に近づいてくるようだった。階段の方からゆっくり進んでくる何者かがいるのだ。
私は寝台からそっとおり、剣を握った。足音は私の部屋の前まで来ていた。扉を開いた。廊下の突き当たりの露台からさしこむ月光がそいつのおぞましい姿を照らし出していた。
毒虫の毒はよくきいていなかったらしい。それとも特別な毒なのかどちらかだ。とにかくそいつはタクソンだったものだった。そう、半日前まではだ。
そいつは頭から爪先まで汚らしい泥にまみれていた。手足には棺の蓋をこじあけたときのものらしい傷が幾つも口をあけ、白っちゃけた桃色の肉を見せていた。咋日死んだ男にはとても見えない。腐っているというわけではないのだが、異様な変化があらわれていた。落ちくぼんだ目は白く濁り、半透明の膜の下から黄ばんだ光を放っている。肌は緑と紫の入りまじったぞっとする白色で、水死体のように膨れ、たるんでいた。虚ろに開いた口からは血の混じったよだれをたらしており、吐き気を誘う悪臭がただよっている。首筋の赤あざは、子供の拳ほどにも膨らみ、じくじくと黄緑色の膿と、どす黒い血を吐きだしていた。
腐った肉孔のような口が歪んで、聞きとりにくい声で何かを言った。
ただひとこと、それは私には「血!」と聞こえた。
死臭とともに奴は襲いかかってきた。爪のはがれた血みどろの指が私の喉をとらえんと、突き出される。
私がふるった剣を奴は右腕で受けとめた。刃身が骨に食い込む。だが奴は痛がるようすもなく、左腕で私をはね跳ばした。とんでもない馬鹿力だ。これだけは生前より向上したところだろう。
私は廊下を這いずるようにして露台の方に逃げた。青白い月が私のみっともない姿をひとりで見ている。
タクソンは右腕に私の剣を食い込ませたまま、こちらへ向かってくる。右腕からしたたる黒ずんだ血が廊下を汚し続ける。吐き気をもよおす死臭が近づいてくる。
私は露台へ追いつめられた。奴は黄色く濁った目を飢えに輝かせて、私の喉笛に手をのばす。腕をふりはらうことができない。恐しい力が私の首を絞めあげ、露台の手摺に押さえつける。
泥にまみれた死人の顔が迫ってくる。醜く歪んだ唇にねばつくよだれがわきでて、ぞっとする白さの喉へとしたたり落ちていくのが目の前に見える。これが最後の口付けとはあんまりだ。
そのとき私の頭に何かが触れた。がさがさと葉むらのすれる音。私は自由になる右腕をのばすと夢中でアジュームの葉をむしりとって、奴の顔に押しつけた。
犬のような悲鳴をあげてタクソンは私を解放した。奴の黄色い目からは膿のようなものが、じくじくと出ている。奴らがアジュームの葉を嫌うという伝説の真実が証明されたわけだ。
私は化け物の右腕にとびつくと、剣を奪いかえした。奴はアジュームの葉を顔から剥ぎとり、狂ったように襲いかかってくる。
必殺の一撃を首筋に叩きこんだ、はずだったが、刃は奴の右腕に食い込んだ。今度は右腕が肘から斬り落とされてふっとんだ。
タクソンは天をあおぎ、青々とした月に向かってひと声叫ぶと、すさまじい形相でつっこんできた。露台が揺れる。二度目はしくじらなかった。剣は化け物の首をすっぱりと斬り落とした。頭をなくした体は、血を噴きながら露台の手摺を壊して地面へと落ちていった。
次の瞬間、おそろしい悲鳴があがった。高く喉のはりさけるような女の悲鳴だった。
マライネが露台の入り口のところに白い夜着姿で立ちつくしていた。見開かれた鳶色の目は露台に転がっているかつての夫の血みどろの首を見つめたまま動こうとはしなかった。悲鳴はいつまでも続いていた。
私とレギリィは二日続きで同じ人物の死体を埋めるはめになった。レギリィは自分が埋められてでもいるような顔つきで鍬を握っていた。マライネは咋夜の凄惨な場面に気を失ってからずっと眠り続けていた。その方が本人にとって幸せであることは確かである。
タクソンの首の上に百クワンほどの土がかぶせられたところで我々はふと手をとめた。黙ってしばらく立っていた。死骸の臭いを嗅ぎつけたのか大きな黒い鳥が林の上空を舞っていた。
「こんな凄い毒虫がいるとは知らなかった。僕もこれで結構あちこち歩きまわっているけど、こんなのは見たことないね。用心しないと……」
レギリィは土で汚れた手を見、堀り返された地面を見た。かさかさに乾いた唇が震えているようだった。
「知っていたのか」
目を伏せたまま答えた。
「迷信だと…思ったんだ。愚かな山の民の馬鹿げた妄想だと思ったんだよ……三年前、この宿を只みたいな値段で買ったとき、ちらりと聞かされたんだが…あの気狂い婆さんはしつこかった…信じられなかったんだよ。そんなものはもうとっくの昔に伝え話の中に引きこもったもんだと思ってた……」
「三年間は何もなかったのか」
「ああ、何もねえ。村の奴らは決して泊まらねえが他からは結構、湯治の客がくる。そこそこはうまくいってたんだ。それが…くそっ…何なんだこいつは……」
レギリィは丸めた肩を震わせていた。怒っているよりは泣いているように見えた。
黒い鳥は餌物にありつくのをあきらめたか、耳ざわりな鳴き声を残して飛びさった。また、陽が暮れようとしていた。
その夜は私とレギリィが二人してマライネの部屋にとまり、交代で見張りをすることになった。私は咋夜と同様に吸血鬼よけの術を施したが、その効果にはあまり自信は持てなかった。私たちは首にアジュームの葉を紐でつないだものをかけ、レギリィは物置から見つけ出したぶ厚い刃の山刀を持った。
かつては吸血鬼や諸々の魔物に対してある種の印が万能に近い力を持っていた時代があったと、幾つかの魔道書は語っているが、今の世にはそんなものは存在しない。主である神を失った象徴に何の意味もないのだ。
マライネは白い掛け布にくるまり、白い顔を時折、苦しげに歪めて横たわっている。どんな悪夢が彼女を襲っているのか、知る術もないが、しばし短かい悲鳴を発し、我々の心を曇らせた。蝋のように白い肌にはうっすらと汗が浮かび、微熱でもあるように頬と唇が赤く染まっている。
私は先程、宿の物置から見つけ出した挨だらけの小さな本を紐解いていた。何かこの宿にとりついている怪異の謎をとく鍵はないかと採しまわって見つけたものだ。黒い革で装丁されたその本はどうやらこのディスカードン館の前の主人の日記であるらしかった。質の悪いインクを用いたらしく文字がひどく薄れているうえに、この地方特有の一風変わった綴り方で書かれているので、読むのはえらく難しかった。
レギリィがディスカードン館について知っていることはほとんど無かった。百年ばかり前に建てられたということ、ここ三十年近く誰も住むものがなかったということ、その理由としてかつてここで吸血鬼が出たという漠然とした噂しか彼は知らなかった。
私はランプの明かりを頼りに苦労しながら日記を読みすすめていった。レギリィは肘掛け椅子に座わり山刀を抱えて眠っている。マライネもどうやら今は悪夢から解放されているらしく、静かな寝息をたてていた。私が頁をめくる音だけが、かさりかさりと部屋に響いた。
日記はしばらく何事もなく田舎の宿屋の毎日を単調に書きつづっていた。たまに宿賃を払わずに夜逃げする客とかフィチィに飲まれて怪我人がでるといったことが変化といえば変化だった。
途中を読みとばして日記の終わりの方に目を移した。最後の記述から数頁前に最初の異変が書き記してあった。ひとりの若い女の泊まり客が変死をとげたのである。その喉もとには小さな赤い傷があったと日記は述べていた。
それから一週間ほどのおぞましい吸血鬼騒ぎを日記の主は控えめではあるが、しっかりとした筆で書き記していた。判読できない部分がかなりあり、事の詳しい真相は明らかではない。東海岸の方から来た“ひどく痩せて青白い男”がそれの源であったらしい。奴は東部を追われて西方へ逃亡中だったらしいが、この宿で空腹に耐えかねたものか、正体を現してしまったようだ。結局三人の泊まり客が死に、いずれも恐しい姿で蘇り、再び殺された。だが最後にもうひとりの犠牲者が出た。ディスカードン館の若い娘が人々の知らない間に毒牙にかかっていたのだ……。
ふと私は三十年前から現在に強引に引き戻された。何かが床にしたたり落ちる音が聞こえたような気がしたのだ。雨でも降り出したのかと、窓から外をのぞいてみたが、満月がこうこうと照りはえ、夜空はきれいな緑青色に晴れあがっていた。
振り返るとまたびちゃりという音がした。生ぐさい臭いもだ。
足下の床に何かがたまっていた。青い月光の中、それは黒ずんで見えたが、昼の光の中ではそうは見えまい。背筋を冷たいものが伝って落ちた。胸のあたりに妙な息苦しさがある。
私は部屋の反対側に置いてきたランプをとると、壁際の寝台に横たわるマライネを照らした。
真っ赤だった。白い肌も、白い夜着も、白い寝具も、真紅に染まっていた。マライネの痩せた胸もとからじゅるじゅると赤いものが噴き出し、部屋中を朱に染めようとしているのだった。
女の息づかいが荒くなっていく。まるで手におえない情欲の虜になったかのように口をなかば開き荒い息を吐き出す。唇はぎらつくように赤く、ひくひくと動くまぶたは赤黒く変色していた。
マライネは目を開いた。赤い隈取りの中の黄色く濁った目が私をねめつけた。
彼女は起きあがった。すでに血は寝台の上にたまっており、起きあがると乱れた黒髪からぼとぼとと赤いものがしたたり落ちる。血を吸って重くなった寝間着がべっとりと体に張りつき、体の線をあらわにしたが、色事を考えているときでないのは確かだった。
寝台の上に立ちあがった血みどろの女は死んだ夫と同じ台詞を吐いた。
「血!」
黄色い犬のような牙が口からのぞいた。レギリィの絶叫が響いた。不幸にも彼は目をさましてしまった。怪物と化したタクソン夫人を指さし、何か云おうとしていたが、全ては悲鳴にしかならなかった。
マライネは騒々しい声をあげた男の方に振り向き、全身から血をしたたらせて、寝台の上からレギリィに跳びかかった。哀れな主人はアジュームの枝をかざすことも、山刀をふるうこともできなかった。マライネはレギリィの首からアジュームの葉をはぎとり−一瞬、苦しげな声をあげたが、それだけのことだった−喉首に喰らいついた。肉の裂ける音とずるずるちゅうちゅうという胸の悪くなる音がした。
私はアジュームの葉のついた枝を握った。レギリィの喉に顔をうずめるマライネの背中にそれを打ちおろした。ぎゃっという声をあげて女吸血鬼はのけぞり、レギリィを突き離した。背中からは白い煙と黄色い膿のようなものと悪臭が噴き出す。
口のまわりから喉までべっとりと血に染めたすさまじい形相のマライネがこちらを向いた。太い牙には肉片がくっついて揺れていた。
今一度、アジュームの枝を叩きつけた。だが、マライネはそれをぐいと、鷲づかみにしたのだ!白煙があがり、苦悶の叫びがほとばしる。怪物はそれを部屋の隅へほうり投げ、私の血を求めて膿みただれた両の手をつき出してきた。
思わず後ずさりした私の足が肘掛け椅子の脚にひっかかった。尻餅をついた私に怪物がのしかかってくる。もの凄い血の臭い、腐った膿の悪臭が私の頭をくらくらさせる。焼け焦げて形の崩れた左手が肩を押さえつけ、右手が頼を押さえ、よだれをしたたらせた牙が首筋に迫ってくる。
私は必死でマライネの腹を蹴とばし、頭の向こう側に投げとばした。彼女の左手が布地と肩の肉を少々むしりとった。静かに、すばやく血みどろの鬼女は起きあがった。
「血!」
赤いよだれをだらだらたらしながら、そいつは叫んだ。
愚かなことに私の剣は彼女の背後の壁にたてかけてあった。血に淫した獣が襲いかかってきた。
私はとっさにランプをつかむとマライネの顔に投げつけた。
長い尾を引く叫びが部屋の中に響きわたった。炎に包まれた顔をおさえて、吸血女は踊るようにぐるぐるとまわった。私は剣にとびつき、しっかりと握るとマライネの血で真っ赤になったうなじへと叩き込んだ。
重い手応えがして、首と両手が胴からはなれて跳んだ。噴水のように血をほとばしらせて彼女の体はなおも歩きまわり、天井と壁に赤い摸様をつくった。
ランプからとびちった炎は寝具に燃え移り、橙色の大きな炎があがっていた。マライネの体はその炎の中に倒れて動かなくなった。炎はその力をまし、天井を焼き焦がし始めた。
私はレギリィがすでにこときれているのを確かめると、厩でいなないていた馬にまたがり、ディスカードン館を後にした。
結局のところ全ての謎がときあかされたわけではない。むしろわからないことの方が多いのだ。私は夜通し馬を駆って比較的開けたディーヌオンという村にはいった。その村で、怪しげな噂とは縁がないと思われる安宿に転がり込み、血にまみれた体と服を洗い、宿の主人がつくったという火酒を二杯飲みほして、日記の残りの部分を読んだ。
そのひどく読みづらい文面からわかったことといえば、三十年前のあの兇事の最後の犠牲者となったディスカードン館の娘が死んだのはタクソン夫妻が泊まったあの部屋のあの寝台の上だということだけだった。
誰も手をふれたがらなかったのか、館のどこかへ封じられていたその寝台をレギリィは見つけだし、それとは知らずにあの部屋にいれたものらしい。三十年前あの部屋のあの寝台の上でディスカードン館の娘は胸に杭をうたれ、首を斧で斬り落とされて死んだのだった。
レギリィは安い買い物だったはずのものに、この世でもっとも高価な代価を支払うことになったわけである。