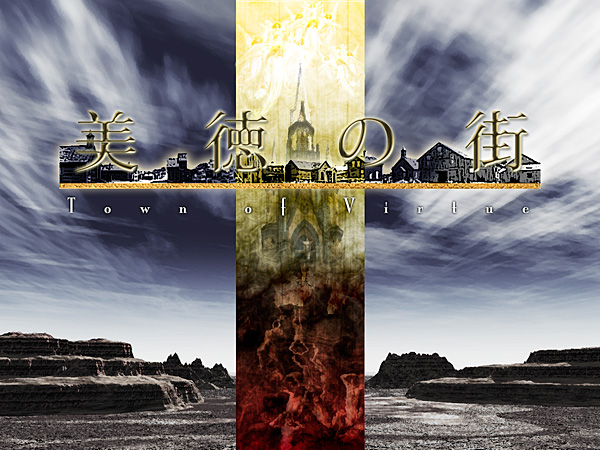
ポジュイルは小さな街だった。漆喰がはげ落ち石塊が露出した低い壁に囲まれた市街には無人の家が目立った。人のいない家はすぐに古びてくるものだ。ここでも静けさの浸食を受けている廃屋があちこちに見られた。
私はかさかさに乾いた石畳の路を街の中へと歩いた。旅の埃にまみれた長沓の下で灰色の土埃が巻き起こり沓に新たな彩りを加えた。南東の空に一筋の黒い煙がたちのぼっていた。
さして歩かぬうちに町の中心部にさしかかった。このあたりにはさすがに廃屋は見当たらなかったが、店々に活気などと言うものはありはしなかった。きれいに整えられた魚屋の店先で青灰色の仕事着の若い男が光のない瞳で何処かを見つめていた。前を通ったとき、わずかな腐臭がしたのは気のせいかもしれない。
その店に限ったことではなかった。何処の店でも売り子の声など聞くことはできなかった。街を行く人々もまた寡黙だった。彼らは押し黙って路を歩き、曇った眼つきで何処かを見つめていた。
見知った人と出会ったり、店先で売り子と応ずるとき、彼らは口を開いたが、私には何を言っているのか聞き取ることはできなかった。彼らは互いに顔を近づけ、誰かに聞かれるのを恐れるがごとく、ぼそぼそと低い声で何事かをささやくのだった。私には彼らが皆同じことを言っているように感じられた。あちらこちらで低くかわされる言葉は全て同じ言葉のくり返しであるかのように思われた。その言葉を聞きとることはできなかった。
しばらく歩いた後、私は一人の婦人に声をかけた。大きな黒い眼と赤い唇を持った派手な顔立ちの若い娘だったが、老人の着るような濃い茶色の長衣をそっけなくまとっていた。
「もし、この近くに白馬亭という宿屋はないでしょうか。道を知りたいのですが」
娘は生気のない眼を私に向けようともせず、ぼそぼそと聞きとりにくい返事をした。
「白馬亭なら次の角を左に曲がって、三つ目の横丁をはいるとすぐですわ」
ありがとうという間もなく娘は歩き去った。今の体験はあの娘の頭にたとえ数刻でも残るのだろうかと私は思った。
宿はすぐ見つかった。古い木造の二階屋で軒に下がった木の看板には、ほとんど消えかかった白い馬の絵と一昔前の飾り文字で白馬亭という文字がかかれていた。
看板のすぐ脇に下がったあるものが私の眼を引いた。薄べったい板でできた二重の四角い枠を丈夫そうな紐でむすんであった。板の表には青と赤の絵の具で渦巻き模様や星形が描かれていた。ヴィンズク教徒の護符だった。この宿の主はヴィンズク教徒なのだろう。
扉を開いて中に入ると、そこはすぐ食堂になっていて幾つかの丸い卓と椅子が並んでいたが、昼食時には遅すぎるせいか誰も客は居なかった。
帳場で苦い顔で眼をつむっていた男が起きあがり、私の前に出てきた。
「これはいらっしゃいませ。ようこそお越し下さいました。御食事でございますか、それとも御泊まりでございますか」
主らしい背の低い男は笑みを浮かべて台詞を並べた。浅黒い肌の頭のはげた健康そうな男だった。
「泊まりだ。三四日、あるいはもっと滞在するかもしれん。よろしく頼むよ」
「はい、それはもう。何せここんとこ開店休業の有り様で。最上の御部屋を用意させていただきます」
主人は職業的とも天性のものともいいかねる笑みを褐色の顔に浮かべて愛想よくしゃべった。
「おーい、ラープト、御客様の荷物を」
「はい、お父様」
帳場の奥から女が現れた。二十才ぐらいの若い娘だった。父親ゆずりの浅黒い肌と黒い瞳を持っていたが、背は高く、真っ赤な胸の大きく開いた衣服を身につけていた。美人だった。
彼女は踊るような足どりで私の側によると旅行用の布袋を持とうとした。
「いらっしゃいませ。ようこそ。さ、御部屋に案内いたします」
「ああ、いやちょっと行くところがあるんだ。まず食事がしたい。そちらを先に頼むよ」
「はい、かしこまりました」
親子はそろって言うと、食事の支度にとりかかった。
私は窓辺の席に座り、外の様子をうかがった。相変わらず、とろりとした眼の人々がぽつぽつと見受けられるのみだった。宿の中に眼を移すとそこには生命が宿っているように感じられた。ここの親子は明らかにちがっていた。まっとうな生きた人間だった。では外を歩いている奴らは何だ?
私は懐から私がこの街、ポジュイルに来ることになった理由の手紙を出し、再び広げてみた。黄色い紙に黒いひどく読みづらい文字で書かれたそれは、私のシュヌベル大学時代の友人でポジュイルに住むイシャホトムという男からのものだった。文面は次のようなものだった。
拝啓、突然の便りに驚かれたこととも思う。貴君とは最後に言葉をかわしてから、もはや三年の年月がすぎさってしまった。貴君のことであるから、さぞや波乱に満ちた月日を送っていることと思い、冒険談など聞きたいと考えてはいたのだが、何分こちらもこんな田舎町に住みついてしまった由、なかなかその機会もなく今日に至ってしまった次第だ。
さて、この手紙は何も昔話をする為に書き送ったわけではない。実は我ヶ街ポジュイルに起こりつつある、ある事件について貴君の力を借りたいと思うのだ。貴君が探偵なる職業に就き、様々な怪異なるもの、霊妙なるものと関わる事件を解決していることは、一年程前、我が家を訪れたケンゾンの話で聞いていたのだよ。
ポジュイルで起きていることはまさしく貴君の助力を必要とすることに違いないと私は考える。
街は表面的には静かだ。不気味なくらい静まり返っている。そしてこの静けさこそが最大の恐怖なのだ。我々がこの静寂の裏にある想像もつかない凶悪な何かを見定めることができないでいるうちに、街はあれよという間に生命を抜き取られてしまうだろう。やがてはそう遠くない未来にポジュイルは死人の街となるにちがいない。
貴君も知っての通りポジュイルは数十年前は金鉱の街として栄えたところだ。今ではほとんど鉱脈も尽き果て、当時の思かげはないうらさびしい街になっているが、それでもここは生きた人間の住む、生きた街だ。いや、だったというべきか。まだ事態がそこまで進んでいないことを私は祈る。祈る、これは恐ろしい言葉だ。この街では……
手紙はそこで終わっていた。もともと字のへたな男だったが、手紙の終わりの方はひどく乱雑な書き方で読みとるのにひと苦労だった。
イシャホトムはつまらない冗談で人を困らせるような男ではなかったし、こんな偽りの手紙を私に出すような理由も考えられなかった。彼は父親の遺産を持ってポジュイルに住み着き、詩作と生き物の研究というおよそ結びつかない仕事に打ち込んでいたはずだった。
かくして私は緑の外套と帽子、灰色の沓、腰にはファバーン剣を吊って馬と徒歩で四日程の小旅行の末、サンジェリィの南西に位置する小都ポジュイルへとやってきたのだった。アムアッサはいつも通り、水晶球に布をかけたまま、「気をつけて」と言った。
「お待ちどうさま」
ラープトと呼ばれた主人の娘が、私の前に湯気のたった料理を運んできた。うまそうな匂いだった。実際、以前イシャホトムに聞いたとおり、料理はうまかった。
私は料理について娘と主人の腕をほめ、二三の質問と、どうでもいいような会話を交わした。
「御客さん、どこから来なすったねえ」
「サンジェリィですよ」
「まあ、都から来たの」
娘が眼を丸くして声をあげた。利発そうな大人びた様子のある娘だったが、やはり都にはあこがれるのだろうか。
「一度私も行ってみたいわ。サンジェリィ、ねえ、何か都のお話を聞かせて下さいな」
「これ、ラープト」
「いえ、かまいませんよ」
私はサンジェリィのラグラン大通りの店々のことや春のロキオネンズ祭の山車のことやエイマン王の噂話などを話してやった。娘は「まあ」とか「ええ」とか感嘆の声を所々に交えて楽しそうに私の話を聞いていた。
いつまでも物見の案内をしていても仕方ないので、私は話題を切りかえることにした。
「それにしても、この街は静かなものですねえ。あちこち旅もしましたが、こんなに物静かなところは初めてですよ」
とたんに親子の表情から輝きが消えた。二人とも眼を床に向けて、すり減り具合でも見ているかのようだった。だが、すぐに主人は笑い顔になり、腰を浮かせた。
「さあ、スープをもう一杯いかがですか」
「いや、もう結構、出かけなくちゃなりません」
ラープトはまだ床を見ていた。床を見たままかわいい唇を歪めて言った。
「前はこんなところじゃなかったわ、前はこの街だって……あいつのせいよ。あいつらが来て……お父様、もういやよ。都へ行きましょう。サンジェリィで新しい暮らしをするのよ」
「ラープト、御客様の前で……」
主人は娘の肩をつかむと店の奥へとひっぱっていった。その顔には怒りの表情も浮かんでいたが、それは娘に向けられたものではないようだった。同時に彼は何かにおびえ警戒しているようだった。主人はつぶやくように言った。
「うちは大丈夫だって。まだまだヴィンズク様のお守りがある。大丈夫だ……」
私は静まり返った午後の街へと出た。
二
太陽はもう傾きかけており、家々の影が路上に落ちていた。横丁から大通りらしい通りに出たが、静けさは変わりはしなかった。
子どもが三人、私の前を横切った。七つか八つぐらいの男の子が二人、女の子がひとり。三人とも歩いていた。何処の街でも子どもははねまわるものだが、ここではちがうものらしい。遊びつかれた様子もなく、来ている薄茶色の貫頭衣も小ぎれいに整っていた。けれども彼らは死の間際の老人のような生気のない顔でとぼとぼと歩いていた。
空はすみきって青く、午後の陽がふりそそいでいたが、街には見えざる暗雲が垂れ込めていた。黒雲は流行病のように私の心中にも押し寄せ、お決まりの、胸のあたりの苦いものが感じられた。
イシャホトムの家は街外れの高台にあった。以前、もらった手紙に地図がかかれており、その時には行けなかったのだが、今それは役目を果たすことになった。二回程、道行く人に尋ねてみたが、きちんとした返事は返ってくるものの、妙によそよそしい無関心な態度は二人とも同じだった。只、二人目に道を聞いた白髪まじりの女が、かすかな嫌悪の表情を向けたのが、宿屋の親子以外のこの街の住人から初めて見ることができた表情らしきものだった。
かつての鉱夫たちの住みかだったらしい朽ち果てたみすぼらしい住居が並ぶ坂道を下り、大きなブエルの木のある角を曲がって坂を登ると、それらしき家が見えてきた。
白っぽい木で造られたなかなか洒落た雰囲気のある小じんまりとした家だった。かつての鉱山主が一山あてて建てた別宅を買い取ったものだと聞いていた。
扉を叩くと幾らも待たせず足音が聞こえ、扉は開いた。
「やあ、久し振りだね」
扉を開けたのは私と同じ位の背格好の同年輩の男で白い半袖の上衣と黄褐色の洋袴を身につけていた。丸顔の色白で、黒い髪は短くもなく長くもない。きれいに髭をあたっていた。かつて彼は私の友人のイシャホトムという名の男だった。彼の茶色い眼を見たとき、今でもそうなのか私にはわからなくなった。
「おお、ランケンか。本当に来てくれたんだな。ありがとう。さ、はいってくれ」
彼はそう言ったが、さほど熱心にそう思っているとは思えない口調だった。
家の中も庭と同様にきちんとかたづけられており、そうじも行きとどいているようだった。
客間に通され、質素な木の椅子に腰をおろした。この部屋には他に椅子が三つ、卓がひとつあった。絨毯はない。一方の壁には暖炉がしつらえてあったが、この季節には無用のものだった。
眼を引くものはその炉の上にかかっていた。人の背丈程もある薄い木板に描かれたジクロイス教の宇宙図だった。縦に長い板の最下部には赤いどろどろしたものの中でもがく人間が描かれ、中程には寺院で祈る人々、上部には黄金に輝く天上人の姿があった。天界の中央にはひと際大きく、聖なるジクロイスの顔が収まって部屋を見降ろしていた。教徒が主張する程、慈愛に満ちた顔とは思えなかったが、絵描きの腕のせいかもしれない。
イシャホトムがよい香りのするマシュウ茶を注いでくれた。卓をはさんで向かい側に彼は座り、茶をすすった。
「手紙を読んでとんで来たんだ。いったいこの街に何が起こってるんだ」
「手紙?」
イシャホトムは私の方を見ていたが、まだ私に興味を持てないでいるようだった。
「ああ、ああ手紙か。いや、もういいんだ。何でもなかったんだよ。俺は……私は、少し疲れていたのさ。ちょっと根をつめすぎたせいで、頭がどうかしていたんだ。……ああ……あんまり、あんなつまらん詩作なんかにふけるものじゃないね。は、は……」
彼は昔と変わらず優しそうな顔で笑ったが、茶色の眼は相変わらず死んでいるようだった。
「なるほど、ではあの手紙は幻想詩とやらに入れ込みすぎたせいで、一時頭がおかしくなってかいたもんだと言うんだね」
「そ、そうさ、そうなんだ。君にはまったくすまないことをしたさ。ほんとにすまないと思っているんだ。そうなんだよ。わ、私は、ああ、もう大丈夫なんだ。そうさ、もう大丈夫なのさ」
私の方を見たままマシュウ茶をすすったが、大方こぼれて白い上衣にしみができた。
「しかしイシャホトム、俺はあんたを昔から知っている。あんたはああいうものを書いてても、決して妄想の中に埋ずもれるという種類の人間じゃないことぐらい知っている。いったい何があったんだ。俺は今日この街に着いたばかりだが、どう考えても尋常じゃないな、ここは。話してくれ、イシャホトム」
彼はゆっくり首を振って私から眼をそらさず茶碗を卓に置いた。
「あ、いや、本当な……んだ、ランケン。昔とちょっと違うのさ、私は。長年一人で暮らしているとね、どうしても変わってくるのさ。街がおか……しいって。そりゃここは田舎だからね。サンジェリィとは違うんだよ。違ってたってちっとも不思議じゃない。き、君もすぐなれるさ、すぐね」
私は少なくともイシャホトム自身は自分の言っていることを信じているのではないかという気がしてきた。
「そうか、ならいいんだが」
私は壁の板絵をちらりと見て言った。
「いつから宗旨変えしたんだい」
この問いは正確ではなかったかもしれない。以前の彼は神仏とは関わりのない男だったのだから。イシャホトムはちょっと困ったような顔をした。
「ああ、これかい。ああ、そうなんだ。今の私は聖なるジクロイスの僕なんだ。そうなんだ。今までの私とは違うのさ。僕なんだ、聖なるものの」
「お前さんは神仏の類は信じない人間だと思っていたがね」
「ああ、昔はそうだったさ。私は……間違っていたのさ。傲慢だった。天を知ろうともしなかった。あらゆるものは理性と知性によって解きあかされると思っていた。生命の謎すら解明する心づもりでいた。ああ……(そこで彼は悩み多い人のように額に手をやった)そうさ、何て恐れ多いことを考えていたのだろう。今思うとぞっとするね。あのままだったら私は地獄の底で永遠の責め苦にあえぐ身となっていただろう。
「でも、もう大丈夫なんだよ。あの方がいらっしゃって私に言ってくれたんだ。まだ間にあうってね。それで私は救われたんだよ。そうさ、救われたのさ。身も心も聖なる主にささげたんだ。もう何も心配はいらない。ジクロイス様の教えを守って生きてゆくんだ。ほら、黄金の天が見えるだろう。私は永遠の魂を約束されているんだ」
私は少なからぬ衝撃を受けていた。知らぬ内にマシュウ茶のはいった碗をつかんだ手に力がこもっていた。口に運ぶともう茶はさめかかっていて、甘さが口の中に残った。
イシャホトムはそんな男ではなかったはずだった。街頭の説教師の垂れる言葉を真に受けて寺院に貢ぐような奴ではなかったはずだった。私などより、はるかに理性的な頭のきれる学者肌の男だったはずだ。
ジクロイス教徒については私も知っていた。サンジェリィにも幾つか寺院はあったが、まだまだ一部の人々が信仰するのみの弱小会派だった。詳しい教義は知らなかったが、イシャホトムがしゃべった程度のことは知っていた。ごちゃごちゃと道徳的な戒律があり、特に肉体的なものにはほとんど嫌悪の念を抱いている感があった。愛と平和を求める宗教のはずだったが、事と次第によっては行動に訴えることがあるのは、『ハルロッツの瞳』をめぐる騒動のおかげで知っていた。あれ以来、彼らと関わりになることはなかったのだが、今、予期せぬところで彼らは現れた。しかしサンジェリィの信徒たちはこんな呆けたようなところはなかった。少なくとも私の知る限りにおいては。
「ずい分変わったものだな、イシャホトム。生き物の研究はどうしたんだい。あの何とか虫の……」
イシャホトムは気分が高揚してきたらしく、私の台詞をさえぎってしゃべりだした。
「ああん?そんなものはもうやめたのさ。あれは罪深いことだった。私の犯した最も大いなる罪だよ。人間は主のなさることに手を出してはいけない。全てをあるがままに受け入れるのだ。全ては天のジクロイスのおぼし召しなんだよ。我々はこの地上の生を教えに従って全うし、永遠の魂を手に入れるんだ……」
私はだんだん気分が悪くなってきた。私は盲信というやつが大嫌いだった。盲信は何ももたらしはしない。人間を愚考に走らせるだけだ。イシャホトムがそんな愚か者になりさがっているのを見るのはつらかった。
いつの間にかイシャホトムは数枚の紙切れを手にしており、私に最近作の詩を朗読すると言い出した。予期した通り彼の口から流れ出る言葉は、聖なるジクロイスをほめたたえ、天界の美しさを歌い、この世がいかに罪深いものであふれているかをくどくどと述べたものだった。かつての彼の作品にあふれていた機知も、素晴らしい夢幻的雰囲気もかけらもありはしなかった。天の国をほめそやすのに忙しくてそれ以外のことには考えが及ばなかったらしい。
不快の念はますます強くなっていった。彼がこうなったのにはきっと何らかの特別な理由があるはずだったし、街を歩いている光のない眼の連中が皆この調子だとすると、この街には恐るべき何かが起こっているはずだった。だが、そういった考えを押しつぶす程、私の心には不快な怒りが渦巻きつつあった。「やめろ」という言葉が喉まで出かかったそのとき、遠くで鐘が鳴った。ガランガランと鐘が鳴った。サンジェリィでも聞いたことのあるジクロイス寺院の鐘だった。
イシャホトムは、はっと顔を上げた。紙切れを卓の上に置き、口を半開きにして首をねじって妙な呆けたしぐさをした。
「あ……ああランケン、時間なんだ。私は寺に行かなければならないんだ、彌撒の時間なんだよ。これは最も大切なお勤めなんだ。行かなければならないんだ。ああ、そうだ。君も一緒に行こう。新しい信徒を連れていけばきっとあの方はおよろこびになる。さあ、君も行くんだ。新しい世界が開けることは確かだ。さ、行こう」
彼は言葉とは裏腹に私がついてくるか確かめもせず、くるりと背を向けるとすたすたと玄関に向かって歩き出した。私は彼の後を追った。
三
通りに出ると人々がぞろぞろと歩いていた。皆、無言で前を向き寺院へと向かっていた。陽はほとんど家並の向こうのぎざぎざした山の陰に沈み、人々の顔を見定めるのは難しくなっていたが、皆あの眼をしているであろうことは想像に難くなかった。
生ける亡者の群れを見るかのようだった。だが彼らはさらに始末の悪いものだった。曲がりなりにも彼らは生きた人間なのだから。
イシャホトムは私のことなど忘れたかのように、ゆったりとした足どりで路を行った。
寺院は中心街をはさんで街の西側にあるらしく、人々の足は私が来た路をほぼ逆にたどっていた。やがて私は見覚えのある、白馬亭のすぐ近くの通りを歩いていることに気付いた。
「いやよ! やめて、帰ってったらぁ!」
聞き覚えのある声だった。ラープトとかいった宿屋の娘だ。私は悲鳴にも感心がないらしい連中を押しのけて、宿屋の方へ駆けた。
横丁にとびこむと数人の人の輪が宿の前をとりかこんでいた。輪の中に主人と娘の顔が見えかくれした。おびえた顔だった。
「畜生、帰りやがれ、うちはジクロイスなんて関係ねえんだ。先祖代々ヴィンズクの信徒なんだ。ほっといてくれ!」
主人がどなりちらしたが、囲んだ人々はいっこうに気にかけていない様子だった。私は彼らの肩をつかんで押しのけ、親子の前に立った。とり囲んだ人々は例の顔つきだった。中年の男が三人、女が二人、若い男が一人、どいつもこいつも死んだ魚の眼だった。誰かが口を開いた。
「おお、よその方ですな、あなたは。さ、あなたも行きましょう。天の国が待っています。さあ、お二人も。いつまでも邪教の虜になっていてはいけません」
さっきのイシャホトムと同様、こういう話になると奴らはある種の生気を帯びてくるようだった。
「この人たちはもう神様は間に合ってるそうだぜ。人のおせっかいは止めてさっさと行かないと時間に遅れるぜ」
「いいえ、今日は何としてでもお寺の方へ行っていただかねばなりません。あの方がそうおっしゃっております」
しゃべっていた真ん中の男は両手を頭のあたりに振りあげて表情のない顔でこちらを見た。そして手をのばしてきた。私はそれを振り払った。他の五人も私たちを捕えんと襲いかかってきた。誰かの手が私の左腕をつかんだ。恐ろしく強い力だった。私はそいつの腹を思いきり蹴り飛ばし、隣の若い男の顔を殴りつけた。
「きゃあ!」
後ろで髪を振り乱した女が娘につかみかかっていた。親父は他の女と男を相手に奮戦している。私は女の髪をひっつかみ娘から引きはがすと、一発突きを入れて眠らせた。主人にかかっていた二人を背中から殴り倒し、起き上がろうとしていた若い男と中年の男をも一度蹴り倒した。鼻か口が切れて血まみれの顔になった。残ったしゃべる男は相変わらず不器用に両手を突き出してきた。両腕を打ち払って首根っこに一発くらわせると、ひっくり返ってうめいた。
六人はそれぞれに痛むところを押さえてもごもごと呪いだか祈りだかをつぶやいていたが、やがてのろのろと立ち上がって歩み去った。
振り返ると土気色の顔をした主人と娘が立っていた。瞳は不安に曇っていたが、もちろん奴らとは違う曇り方だった。
「ありがとうございました」
二人はそろって礼を言って頭を下げた。
「ふむ、静かなばかりという訳でもなさそうですね」
宿にはいると私は食堂の窓際の椅子に腰を下ろした。主人と娘は家じゅうの戸締まりをすると言ってしばらく姿を消した。二人は食堂に戻ってくると私から数卓離れた席に座って、自分の家だというのにやけに居心地悪そうな顔で黙りこんでいた。
「酒が欲しいな」
「へい」
主人が気のない返事をして娘に目顔で伝えた。ラープトは酒壜の並んだ棚へと足を運んだ。
「何になさいます」
「ディコンでいいよ」
ラープトは茶色の土壜と銅の杯を私の卓に置いた。一瞬、動作がとまってそれから杯に酒を注いだ。
私はラープトが立ち去る前に飲みほした。彼女がもう一杯注いだ。それも一息で飲みほした。三杯目を注いでもらうと、今度は一口飲んで卓上に置いた。
「さて、お話を聞かせてもらえませんかね」
また、しばらくの沈黙が続いた。
「私はこの街に住む友だちから街がどうにかなっちまったって手紙をもらって来た。ところがそいつは手紙は気の迷いだったという。奴は神様には縁のない男だったのに熱心なジクロイス教徒になっちまってる。街を歩けばどいつもこいつも死んだ魚の眼をしてるし、皆で仲よくジクロイスときたもんだ。そしてさっきの騒ぎだ! いったいこの街はどうなってるんだ。あの方ってのは何者だ。あんたらはまだまともらしいから、まともな話ができるだろう。私は知りたいんだ。何がイシャホトムをああしてしまったのかを! この街は何につかれちまったのかを!」
私は三杯目のディコンを飲みほした。
「わかったわ! みんな話してあげるわ」
赤い服の娘が叫んだ。
「ラープト、わしが話そう」
主人は棚から杯と酒壜をとり出すと一杯注ぎ、一口すすってしゃべりだした。
「一月程前までは、ここもさびれてはいるが、それなりの生活のにぎわいといったもののあるちゃんとした街だったんですよ。
「ところが一月前、妙な男が街はずれにある崩れかけた寺にやってきましてね。そいつは三人ばかり弟子みてえなのを連れてきてまして、そいつらといっしょにあっという間に寺を直して新しい寺院を開いたんです。ジクロイス教のね。で、その晩からもの珍しさもあってか集まった連中を相手に奴は説教だか何だか始めまして、それがあっという間に信者がふえたんですよ。奴のいうことはようするに現世でまっとうな暮らしをしていれば、死んでから永遠の魂とやらを約束される。そうでない奴は地獄に落ちるっていう単純なもんらしいんですが、どういうものか皆、ころりと信者になっちまうんです。一度寺院へ行った奴はもう次の日からは敬虔なジクロイス教徒、酒もやらないし女もダメ、朝晩寺院へ行って祈りをあげる。家が遠い奴らは集会所みたいなのを決めてそこでやったり、自分家でやるのもいますしね。とにかく、そんな具合なんですよ。
「それだけなら別に、まあいいんですが、信者はそれ、御客さんも言った通りああいう眼つきなんですよ。もう薄気味が悪くてねえ。しかもそのう戒律っていうのが日増しにきびしくなりましてね。女が肌見せちゃいけないってんで街歩いてる若い女に布袋かぶせたり、何でも夜の女たちを無理矢理寺院へ引きずりこんでって改宗させたり、無茶やるようになってきた。その頃には大方の人間はジクロイス教徒になってまして、残った奴らも手も足も出ない。私んところには護符があるせいか、奴らもあんまり手を出さねえようですが、今日みたいなことがあっちゃもういけません。
「これは噂ですがね。街の外の鉱山のあとで、奴らの言うところの異教徒、私たちのことですな、を焼いちまったっていう話もあるんですよねえ」
主人はぶるぶると体を震わせ首をすくめてみせ、酒をあおった。
「その教祖様はどんな奴なんだ」
「見たことはありません。ですが聞いた話じゃまだ若い男で、たいそうな美男だそうで、自分じゃジクロイスの使者だと名乗っているそうです」
「ふむ……」
どうやらこの街のジクロイス教徒はサンジェリィで見かける穏健な連中とは違う宗派らしい。それともポジュイルのが正体でサンジェリィのは仮面か。
いずれにせよポジュイルの街をこのままにしておくことは我慢ならないことだった。この街に蔓延しているものは人を生きながら死に追いやるものだった。何も考えない泥人形をつくり出す邪悪の権化がここにはびこっている。
病根を絶たねばならない。私の友人を廃人のような存在にした、ジクロイスの使者とやらを。
四
寺院は灰白色の石造りの小じんまりとした建物だった。三つの尖った屋根を持つこの寺がポジュイルの街を人形の街へ変える邪悪の城とは見た限りでは思えはしまい。
建物もその周囲の小さな庭園もきれいに掃除されており、安穏そのものといった風情だった。
正面の大扉は片方だけが開かれており、中からは低い詠唱がもれてきていた。私は幾つもの浮き彫りがとりつけられた扉の陰からそっと中をうかがった。幅が狭く奥行きのあるのはどこの寺院も同じだった。中央に細い通路があり両側に木の長椅子が並んでいる。今、そこには大勢の人々が座り、突き当たりの壁際にしつらえられた祭壇から発せられる声に従って祈りの文句を唱えていた。
堂内は柱の燭台に置かれた蝋燭の灯で照らされてはいたが、すでに夕闇濃い戸外よりもなお薄暗かった。私は足音をたてぬように忍び入ると最後列の椅子の横の太い柱の陰に立った。祭壇までは数十イートの距離があり、祈りの文句を唱えている男の顔はよくわからなない。祭壇にはその男と、右側に二人、左側に一人が立っていた。皆、白い長衣を身につけていた。
「聖なるジクロイス、父なるジクロイス、母なるジクロイスが我とともにあらんことを……」
彌撒が終わるとつめかけていた街の人々はぞろぞろと外に出ていった。誰も何もしゃべらなかった。彼らの顔に明かりをあてれば、ぼうっとした奇妙な満足に満ちた表情を見ることができただろう。誰も彼も同じ顔で同じことを想い同じよろこびに捕らわれていた。イシャホトムらしき男が帰りにつくのをちらりと見たが、すぐ眼をそらした。死んだ友の顔は見たくなかった。
ガランガランと鐘が鳴った。何処か狂気じみた律儀さで鐘は鳴っていた。やがて最後に一人が帰ると祭壇の男の一人がやってきて大扉を閉めた。
私は外套の下のファバーン剣の柄を握ってみた。剣は確かに私の手の中にあった。幽かなしびれにも似た感覚が伝わってくる。鞘と柄の間から淡い緑の光がもれていた。この堂内で魔道の力が働いているのだ。海中に没した古代王国で吹き込まれた魔力の残滓が私にそれを知らせていた。
いかにすぐれた説教師といえど一月ばかりで街中の人間を宗旨変えさせることなど可わざることに違いない。ごく特別な場合ででもなければ。ポジュイルの人々が今、熱心に神を必要とする理由などありはしない。
すなわちジクロイスの使者とやらは、何らかの尋常ではない手段をもってこの街での布教を行っていることになる。奴は魔道師であるのかもしれない。昨今では魔道士の存在を信じていない人も少なくはない。暗黒の力とは無縁の太平の暮らしを送っている人々にとってはそれは無理からぬことではあるが魔道師は実在する。彼らは隠然たる力を持ち、見えないところからこの世に様々の影を落としているのだ。サンジェリィ近辺ではエイマン王の力はゆるぎないように見え、戦も長きにわたって行われてはいない。だが、ログラフの山々を越えた東方の平野では諸王国が『東の玉座』を争って血みどろの戦を今も続けている。そこでは多くの魔道師たちが黒や紫、あるいはヌヨックの黄色い長衣のすそをひるがえして軍隊をもおびやかす超自然の力をふるっているのだ。
ともあれジクロイスの使者が神秘的力を使うものであることは信ずるに安いことだった。
「出て来なさい。柱の陰の異教徒よ、そこにいることは最前からわかっておるのだ」
男としてはかなり高い声がひびいた。剣をにぎる手が不用意に動いてガチャリと音がした。
今さらいないいないばあをやっても仕方ない。私は柱の後ろから出て、中央の通路に立った。
真正面の祭壇の上、黒い説教卓の後ろに白い長衣の男が立っていた。
「姿をあらわしましたね、異教徒よ」
「ああ、こんにちはだ」
「先程は信徒たちをひどい目にあわせたそうですね。何故、そのような乱暴を働くのです。私たちの父なるジクロイスは隣人にこぶしをあげるようなことはきびしく禁じておられます。隣人をなぐることは……」
奴は合唱団で独唱者になれそうなすんだ声でぺらぺらとまくしたてた。
「弱気を助け強きをくじいたつもりなんだがね。あんたの神様のお気には召さなかったようだ」
私はしゃべりながら祭壇に向かった。薄闇の中にいるジクロイスの使者の面を見ておきたいと思った。
私と彼は六イート程の距離で対峙した。彼は私と同じ位の背丈、つまり中背よりやや高く、白い長衣の丸いえりから生えたような頭は小さく、きれいな卵形をしていた。髪を短くかりこんでいるので頭の形がよくわかったのだ。顔は年齢不詳の妙な若々しさに満ちていた。確かに美しく整った顔立ちだった。古のエピカの彫像のように彫りの深いきっちりとした顔だちで女たち、あるいは男色家がよろこびそうなきらきらと光る潤んだ青い瞳を持っていた。薄い唇の端にはかすかなずるさがひっかかっていたが、笑えばあとかたもなくなることだろう。
「そのような言葉で聖なる君を辱めることはなりません。祈るのです。まだまにあいます。敬虔な祈りさえあればあなたも死後の……」
だんだん胸がむかついてきた。
「死後のことは死んでから考えるさ。どこの神様の世話にもなりたくないね。自分で考えるさ。そんなことより、この街の今を返せ。何をした!? どんな妖術を使ったんだい、魔法使いのお兄さんよ」
男は表情を変えず、青い眼には三文役者のように哀れみと理解の色をぬりつけたまま歯の浮く調子で言った。
「言いがかりはよしなさい。私は魔法など知りません。只、一心に聖なるジクロイスの教えを伝えているだけです。この街の心根の正しい人々は私の教えを素直に聞き、ジクロイスに心を開きました。まだ一部には異端の魔神をあがめる者も残っていますがいずれ我らが兄弟となることでしょう」
「誰が何を信じようが勝手だ。おまえはこの街を一色に染めようとしている。誰も彼もが同じ顔で同じ眼で同じ言葉をしゃべり同じことを考える泥人形の街に変えようとしている。おまえこそ邪教の徒だ! 悪鬼の手先だ! 何をねらっている? この街を思い通りにして何をしようというのだ。次なる目標の為の根城にでもするつもりか!?」
どうにもこいつと向かいあっていると私は感情を抑えることができなかった。胸の奥からどろどろとした熱いものがわきあがり、言葉となって吹き出していく。
「私はこの世を平和と愛で満たしたいだけです。皆がジクロイスに帰すれば争いもなくなり、人々の心には究極的な平穏がおとずれるのです。あなたも心をゆだねなさい。荒ぶる心を治め、全てを信じて受け入れるのです。神の世はあなたのものです」
「黙れ! そんなものは死人の平和だ。街はずれの鉱山あとにある黒焦げのものは何だ! おまえの仕業じゃないのかい? ジクロイスの為なら人殺しも許されるというわけか」
このはったりに、奴は一向に変わらぬ調子で答えた。
「あれは悪魔だったのです。私たちがいくら教えを説いても邪教をすてようとしませんでした。あれは三人も妻を持ち、邪な肉のよろこびにおぼれていました。どこぞでかじってきた学問をふりかざし神はいないなどとおそれおおいことを平然と口にしました。私たちの聖像につばを吐き、異教の呪文すらかけようとしました。このような者を放置しておけば、地上は悪魔のものとなるやもしれません。実際、彼は私たちに対する反乱すらあおりたてようとしたのです。我々は仕方なく彼を捕え、再三、改宗するようにすすめましたが、彼は聞き入れませんでした」
「なるほどね、結構なことさ」
この男とこれ以上話をしても意味はなかった。こいつは正真正銘の気違いだ。何世紀か前なら教祖として名をあげることもできたかもしれない。今、彼がこうしていられるのは彼がいまだ私に対しては行使しようとしない人間離れした力のせいなのだ。少なくともそう考えなければ、私は大声でわめきちらしただろう。
それで全てが解決するのか自信はなかった。しかし他にとるべき術はないように思われた。ファバーン剣を電光のように走らせ、奴の首に斬りつけた。
刃は奴にとどかなかった。背後から私の両腕をがっちりと押さえつけるものがあった。薄闇の中から私が宿屋で蹴散らした奴らが現れて私をとりまいた。彼らは傷ついたところから血をにじませて無言で私を見つめた。怒りと屈辱で体がわなわな震えた。ジクロイスの使者が祭壇をおりて私の前に立った。細い腕をのばし、私の頬にふれた。眼の前が急にゆらめき、蜃気楼のように現実が消え失せた。
五
ろくでもない夢を見ていた。私は白い長衣を着て、手には聖典を持ち、街頭で説教を垂れていた。最初は鼻を垂らした子どもが三人、珍しそうな顔で見ているだけだった。そのうち一人二人と人数がふえていった。髪結い帰りの婦人が足をとめ、大きな箱を背負った行商人が荷物を置いて聞きいった。人の輪がどんどんひろがっていく。皆、一様な熱心さで私の話を聞いていた。しゃべっている私には自分が何を言っているのかさっぱりわからなかった。無意味な音のつながりが次々と口から出ていく。それを人々は王の言葉を賜るようにじっと聞きいっているのだった。
聴衆は休みなくふえ続け、ついには道いっぱいになったが、止めに来る警邏もいっしょになってしまうので、さらにふえ続けた。私は自分の口から出る声音に吐き気がしてたまらなかったが説教をやめることはできなかった。人々の山はふくれあがり、サンジェリィの全市民が私の話を聞いているかのようだった。すぐにもそれは全世界の人々になりそうだった。私はますます気分が悪くなった。胸の中を焼き焦がされるような感覚が走り、絶叫をあげようとしたが、それは祈りの言葉となってほとばしった。聴衆はいっせいに同じ言葉を唱え、大地と私の耳はうち震えた。そこで眼がさめた。
せまい、そっけない部屋だった。私はごつごつとした木の長椅子にねかされていた。両手は背中で縛られていた。腰の剣は、ない。天井近くの明かりとりからは朝の光がさしこんでいた。体のあちこちが痛かった。今晩は寝るべきところで寝たい。
あの鐘の音が聞こえてきた。朝の礼拝の時刻だろうか。
部屋の中には私しかいなかった。ひとつしかない扉の外でぶつぶつと祈る声が聞こえた。見張りはそこで礼拝のようだ。
「おい、外の兄さんよ」
ぶつぶつ言う声が中断され、不機嫌な声が言った。
「何だ、異教の徒よ」
「一晩考えて気が変わったよ。私も礼拝に参加させておくれ。ジクロイスにおすがりしたいのだよ」
「偽りを申すと為にならんぞ。聖なるお方は虚偽をおきらいで……」
「うそじゃないさ、もう刃物三昧はごめんだ。私も神の世に生きたいのさ」
しばらく沈黙が訪れたが、やがて鍵を回す音が聞こえた。
扉が開いた。奴は無用心にも真ん前に立っていた。私は思いきりその男の腹を蹴りあげた。後ろ手に縛られたままなので、ついよろめいて転びそうになったが、何とか立って、ひっくり返ってうめいている男をもう一度蹴とばした。奴はうなって動かなくなった。
改めて見るとその男はジクロイスの使者の側に立っていた白衣の男の一人のようだった。宿屋の主人が言っていた最初に『あのお方』についてやってきた信徒の一人だろう。近くで見るこいつの顔は妙につやがなく、厚化粧でもしたような色あいだった。全体にしまりのない彫りの浅い顔だちで、何ともいえない不快さがあった。首に一筋、深いしわが刻まれていた。まるでそこからすっぽり頭がぬけ落ちそうな感じさえした。
だが今はこいつの正体を詮索しているひまはない。白馬亭の親子のことが先だった。二人には戸じまりを固くするように言って出て来たのではあるが、おそらく朝の彌撒のおさそいがかかったに違いあるまい。手ひどく拒絶された後、彼らがどういう手段をとるかはあまり考えたくなかった。
ファバーン剣は、見張りの男が座っていたとおぼしき椅子にたてかけてあった。私に味方する神も何処かにいるのかもしれない。誰もあらわれないことをその物好きな神に祈って、後ろ手のまましばらく悪戦苦闘した末、剣を使って、縄をさき、両手を自由にすることができた。縄が落ちたかと思うと、床につっぷしていた男がもぞもぞと動き出した。私が再び眠ってもらう為、蹴とばそうとすると、奴はごろりと転がって私の沓をよけた。
男は立ちあがった。何も言わなかった。仮面のような表情のない顔は信徒たちの顔つきの意地の悪い戯画だった。黒い穴ぼこのような落ちくぼんだ眼の奥で何かが光った。手にしたファバーン剣からある種の感覚がはっきりと伝わってくる。私は剣を抜いた。四角ばった複雑なファバーン文字が淡い緑に光っていた。
おぞましい事が起こっていた。男の無表情な顔は突然泣き顔に変じた。もちろん奴は泣いてなどいなかった。顔面そのものが歪み、それらしい形に見えるのだ。顔は護謨のようにぐにゃりと歪み、下の方へとたれさがっていった。もはやそれは人間の顔ではなかった。かつて眼であり鼻であり口であったものは、肉色の流れるものの中の深いみぞのひとつにすぎなくなった。肌色の粘土の固まりをこねまわしたようなそこからぼつぼつと赤い突起があらわれ、見る見るうちに手指程の大きさの幾本もの蠢く触手となった。
化け物と化した男は両腕をつき出し、私に襲いかかってきた。長衣からのぞく手も顔同様の気味の悪い固まりとなっている。
私はあまりのおぞましさに思わず後退り、剣を構え直した。奴は追って来る。かつて右腕だったものがひゅうとうなり、触手が鞭のようにのびてからみつこうとする。既のところで剣をふるい、手首から先を切り落とした。切り口からは、恐ろしいことに液状のものは流れ出ない。腐った肉のような橙色のどろどろしたものが、ぼたりと落ちた。いやな臭いがする。
化け物も痛みは感じるらしく切り落とされた片手を振り回し、後退しようとする。頭や腕の深い肉のしわから赤い液がじくじくとしみ出している。悪臭がひどくなった。これ以上、こいつが生きて動いているのを見るのは耐えられなかった。
頭を切り落とすと、そいつは倒れて動かなくなった。切断した部分からは、ねばつく中身が流れ出して、寺院のきれいにみがかれた床にしみをつくっていった。
私は奴の死体を後に、彌撒が行われているとおぼしき方へ走り出した。私を閉じこめておいた部屋は礼拝堂の後ろに位置するようだった。部屋と礼拝堂の間に私が今いる廊下があるというわけだ。白い壁が天窓からの朝日で四角い斑模様になっていた。壁の向こうからは低い詠唱がひびいてくる。角をひとつ曲がり礼拝堂の側面の通廊に出た。右側には大きな窓が幾つも切りとられ、左側には十数イート置きに両開きの扉がある。一番私に近い方が開いていた。祭壇のすぐ横だろう。忍び寄って中をうかがった。
天井の窓からさしこむ光が堂内にそれらしい雰囲気を造り出していた。壇上にジクロイスの使者がおり、両側には白い長衣の弟子が一人ずつ立っている。こいつらも面の皮をひんむけば見るもおぞましい異形をさらけだすのだろう。
中央の男はよく通る高い声でしゃべっていた。街の連中は静まりかえって、時おり祈りの文句をくり返していた。
祭壇の前には一組の男女が立っていた。男は白馬亭の主人、女はその娘のラープトだった。ラープトは昨日と同じ真紅の胸のあいた服だった。白や黒、茶、灰等地味な服の人々の中にあって墓場に咲いた一輪の花のように見えた。二人の顔は青ざめており、恐怖が彼らをむしばんでいた。
ジクロイスの使者が言った。
「この者たちは我らが聖なる街ポジュイルに残った最後の異教の者たちです。肉屋のイクトも農夫ブロカナムも聖なるお方に心を開きました。しかるにこの二人、白馬亭の主ノクプト、その娘ラープトはいまだに邪悪なる異教の神に帰依し、度重なる私たちの善意の手を雑言と流れ者の暴力によってうち払ったのです。この罪深い者たちは、本来ならそのはかりしれない罪により重い罰を受けねばなりますまい。しかし、慈悲深いジクロイスは私にひとつの啓示を賜りました。今一度、この二人に機会を与えよ、と。何というありがたきお言葉なのでしょう。ヘザル、イムコ、マヤス」
聴衆がいっせいに「ヘザル、イムコ、マヤス」と唱える。異様なざわついた音が、私の耳をゆり動かした。
「今、ここで悔い改めなさい。邪神を捨てて、聖なるジクロイスに心を開くことを誓うのです。さあ、神の世があなたを待っています。永遠の死と生とどちらを選ぶのです? さあ、誓いなさい、二人」
私の側にいた長衣の男が二人のところに行き、無理矢理祭壇の方を向かせた。主人の顔には無念の怒りが渦巻き、娘はきつく唇をかんでいた。
「さあ、心を開くのです」
光のかげんか、私にはジクロイスの使者の頭が黄金色のもやのようなもので包まれているように見えた。一瞬、強いしるしが剣から私に伝えられた。
「いやよ! あんたのいやらしい教えなんてまっぴらだわ! 何が神の平穏よ、みんな死人みたいな顔して、ぶつぶつ祈ってるだけじゃない! 永遠の魂なんてまっぴらごめんだわ!」
「ああ、娘の言う通りだ。きさまは、きさまは魔法使いに違いない。街のみんなをこんなにしやがって! みんな眼をさませ! そんな木偶人形みてえな面して祈ったって何も変わりはしねえんだぞ!」
ジクロイスの使者は黙って二人の言葉を聞いていたが、ぴくりと口元を歪ませていやらしい笑いを浮かべた。
「そうですか。あなた方は神の世には不要の人々のようですね。哀れむべき人たちです。ですがあなた方は害毒です。私たちの世を惑わす異教の徒です。そしてジクロイスを冒涜した罪はこの世に比すべきものがない重い罪です。あなた方を磔にして清めの炎で包むことにいたしましょう」
私は剣を抜くと堂内にとびこんだ。はねるように祭壇まで駆けあがる。最前列の信徒が椅子から腰をあげたときには、宿屋の親子の側にいた白衣の弟子を斬り倒していた。奴は赤い半透明の血ではないもので服を汚し、ひっくり返った。
「逃げるんだ!」
一瞬、何が起こったかわからないでいる二人をひっぱたき、反対側の戸口に向けて走らせる。
堂内の人々はどうしてよいかわからずに立ちあがってもまごまごしていた。壇上でジクロイスの使者が叫んだ。
「捕えるのです。異教の輩を捕えるのです」
ざわざわと群衆が動き出した。彼らにつかまるわけにはいかない。扉まではほんのわずかだ。
前に立ちふさがる者があった。残った一人の弟子だった。怒りの為か何かは知らないが奴の顔はもはや人間離れしたものになりつつあった。赤い膿のようなものが流れおちていた。
「どけ! 化け物!」
頭を一刀両断する。腐敗臭のする汚物をまき散らして奴の首級は信徒たちの方へとんでいった。人間らしい悲鳴があがった。思わず顔がほころんだ。
戸口をぬけて、そのまま廊下の窓を蹴やぶる。派手な音をたてて硝子と木片がとびちった。
庭の草花を踏みちらかして私たちは逃げた。背後からはジクロイスの使者のかん高いわめき声と街の住人の騒ぐ音が追ってくる。
「主人、この近くに馬はいないか」
窓をぬけるときにつくった傷で血まみれの顔でぜいぜい言いながら彼は答えた。
「へい。オポニッセの馬屋が一番近いはずです」
「そこまで走れ!」
誰もいない街路を私たちは走った。寺院にはいりきらない多くの人々は家の中で朝の礼拝をしているのだろう。私たちに気をとめる人はいなかった。
寺院からの追手は現れない。あの化け物のおかげで混乱がおきているのだろうか。あの忌まわしいものが呪縛を破ってくれたのであれば、全く皮肉なものだ。
主人と娘の足がもつれてきた頃、オポニッセの家についた。街の東のはずれに近いそこは旅人に馬を用立てるのが商売だが、この街の様子ではたいして商売になるとは思えなかった。
木の柵に囲まれていて元気そうな馬が四頭ばかり草をはんでいた。柵はすぐこわれた。物音に気づいて家の中から中年の男が出てきた。こいつもあらぬ方を見る眼をしていた。
「馬を三頭貸してほしいんだがね」
「馬? こんな時間にどうするんだ。今は礼拝の時刻のはずだ。敬虔なジクロイス教徒なら寺院か家で祈りをあげている時刻のはずだ。おや、おまえは宿屋のノクプトではないか。娘もいる。ジクロイスにおすがりしないお前たちなら話もわからないでもないか。ふむ」
「俺たちは急いでいるのさ。早いところしてくれないか」
オポニッセは口の中でもぐもぐ言いながら灰色の木の母屋にとって返し、馬具を持ってあらわれた。
「代金だ」
私は懐から適当に金をひっぱり出すと男にわたし、あまり馬に乗りなれないらしい二人をつれて、そこを後にした。
「一番近い市の門は?」
「東の二の門よ」
乾いた風の中を私たちは門にむかって馬を走らせた。
門の近くには廃屋が目立った。朽ちた灰色の小屋が立ち並び、緑のうすい草がかつてのポジュイルの栄えの上に根をおろしていた。追手はまだ姿を見せなかった。ジクロイスの使者は信徒の混乱をおさめきれないでいるのだろうか。
灰褐色の石造りの門は、ひどく風化しており左右の門柱の頭についていたであろう飾り石は全て崩れ落ち、路上に転がる大小の石くれとなっていた。門といっても扉はなく、只、石の柱が四角い空間を形造っているだけなのだった。
「ああ、あれは」
娘が声をあげて門の中を指さした。薄く灰色の雲がかかった青空を背にして、白い長衣の男が立っていた。足元には朱肉色に汚れた衣をまきつけた蠢く固まりがうずくまっている。
六
門の手前で私たちは馬をとめた。ジクロイスの使者は美しい顔を埃と汗で汚し、私たちを見つめていた。
「おまえたちを街から出すわけにはいきません。異教徒はしかるべき罰を受けるのです」
「ずい分、おはやいお着きだね。空でもとんできたのかい」
「私にはわかるのです。おまえたちの邪悪な臭いが。聖なるジクロイスのお導きです」
「その化け物もジクロイスとやらが貸してくれたのかい」
奴の足下のそれは不定形の体じゅうから突き出した赤い触手をぐねぐねと蠢かしていた。
「これは私が北の荒野で修業をつんでいるときに、聖なるお方のお導きにより見い出したものです。深い地割れの底の石室にこれは眠っておりました。偶然にも足をすべらせて落ちこんだ私はこれを見い出しました。そして、これが私の意志に従うことを知ったのです。姿こそ醜いけれども、これは天の父上が私の為にお使わしになったものです。それをおまえは不浄の刃で斬った」
「寺院の連中はそんな説明で納得してくれたかね。大分騒がしかったようだがね」
奴はよどみない口調で話し続けた。
「彼らは心を開いた私の子どもたちです。私の言葉を信じないわけがありましょうか」
「そうかい、追手は現れないな」
「オエル、カレ、マレゾ、天上の聖なるものよ、この悪辣きわまる異教徒に罰を!」
男の足下のものがゆらゆらと蠢き、再び人間のような形をとった。まるで見えない大きな手が肉色の粘土をこねて、人型を作ったかのようだった。肉の固まりのようなものは、三人分だったのか、その背丈は門柱の頭にとどかんばかりだ。白い衣がところどころにまつわりついてその体をかくしているのが、なおのことそいつを忌まわしく見せていた。何本もの赤い触手が長虫のようにのたうち、ひどい臭いが鼻をつく。
私は抜いたままのファバーン剣を見た。陽光の下で緑の神秘文字はほとんど光っていることがわからない。剣の活性化はあてにはできなかった。
「俺が走れといったら馬のしりを思いっきりひっぱたけ。どこまでもつっ走れ」
私は主人と娘にそう告げると懐に手をやった。化け物が重い体をずるずるとひきずるように動かし迫って来た。ひゅんと空気を裂く音がして触手がのびた。同時に私の懐からぎらりと光るものが飛び出した。
「走れ!」
馬はいななき、私たちは走った。化け物は頭とおぼしき部分に突きささった四本の手裏剣をひきぬこうと苦悶している。食いっぱぐれたら大道芸人になることにしよう。
「おおっ」
ジクロイスの使者は驚きの声をあげ、必死で馬のひずめをさけた。門柱の下に倒れた男に砂塵がふりかかった。
私は街の外へ出ると馬首をめぐらせた。女の声がひびく。
「どうする気なの、一緒に逃げましょう!」
「奴の片をつける。半日も行けば宿場がある。さあ行け」
ラープトはまだ何か言っていたが、私は聞こえぬふりをして門にもどった。もうもうたる砂埃がわきおこっていた。化け物が痛みに暴れまわっていた。私の手裏剣はまだ二本突きささっている。傷口からはじくじくと朱色の膿のようなものが流れ出していた。こいつは姿を変えることのできるほとんど不死身の怪物かもしれないが、痛みは感じるし、大きな傷を受ければしばらくは動けなくなるのだ。寺院での対決が私に味方していた。
暴れる怪物の足下で、ジクロイスの使者がその巨大な足をさけて地面を転げまわっていた。祈るひまはなさそうだった。埃の中で奴の顔はひきつり、恐怖にあえいでいたが、それはジクロイスからのおくりものであるはずの弟子が自分を害しようとしている為か、あるかは単なる死に対する恐怖なのか、私にはわからなかった。
化け物はどしんどしんと巨体を門にぶつけ、その度に門はゆらぎ、ばらばらと石塊を男の上にふりおとした。
男は何とかして怪物から逃れて市外へ出ようとしていたが、盲滅法に振り回される怪物の触手と、落下する石がそれを妨げていた。男は血まみれだった。
化け物のくぐもった異様な鳴き声が聞こえた。太い腕のようなものが東の二の門の梁に叩きつけられた。門はひときわ大きく、ぐらぐらとゆれ動き、一瞬とまったかに見えたが、すぐに恐ろしい大音響とともに崩れ落ちた。梁の部分が抜け落ち、左右の門柱が斬られた人のようにがくがくと崩れた。大小の石がはじけとび、もうもうとした砂埃が巻きあがる。化け物のうなるような叫びが、私の腸を震わせた。砂塵の中、肉色のものがとび散り、赤い細いものがちぎれてあたりに散らばった。
荒れ野を吹きわたる風が破壊の砂埃を吹き払った。門は周囲の塀とともに完全に崩壊し瓦礫の山と化していた。ぐしゃぐしゃに押しつぶされ、ますます訳のわからない形になった怪物は動こうとはしなかった。ものすごい腐敗臭がただよっていた。私は吐き気をこらえて近づいた。
男の上半身が眼にはいった。あおむけになり、血みどろの顔で私の方を見ていた。腹から下は大きな石の下にあり、どうなっているのか見えなかった。体の下に赤いしみがひろがっていた。
男は動かすことのできる右手を天に向けて、血反吐を吐きながら何か言おうとしていた。
「……カレ、マレゾ……天よ、何故私をお見すてになる……のですか……」
ひどいかすれ声だった。腕が地面に落ち、ジクロイスの使者は死んだ。一陣の風が吹き、悪臭を薄れさせた。私は空を見上げた。
青く晴れわたった空には、薄い灰色の雲が幾筋か流れていくだけだった。
七
サンジェリィへ帰って七日後、イシャホトムから手紙が来た。相変わらず汚い字だったが書いてあることはまともだった。
ポジュイルの住民の宗教熱はほどなく消え去り、人々は元の猥雑な暮らしにもどった。商人は通りすがりの者から金子をまきあげるのに懸命になり、女たちは趣味の悪さを見せびらかすのに忙しく、子どもは訳もなく騒ぎまわっている。
イシャホトムの詩は一段と麻薬の夢のような毒々しさを増し、生命の神秘とやらは彼の手で斬り裂かれようとしている。
白馬亭の親子はポジュイルにもどり再び宿屋をはじめた。ラープトはサンジェリィに来られなかったが、いずれあこがれが彼女を都へ向かわせるかもしれない。
私はサンジェリィのジクロイス寺院をかぎ回ったが、ポジュイルのような異様さは見い出せなかった。ジクロイスの使者は異端者であったのだろうか。ポジュイルの寺院には「真っ当な」宣教師がやって来て礼拝を始めたというが、果たして何人の人が集まったのかは知らない。
怪物はよみがえらなかった。ジクロイスの使者も。彼とあれが何者だったのか、彼が本当に不可思議な力を使う魔道師だったのか、私は知らない。
彼は自分の神については熱心に理解につとめていたのかもしれないが、ひとつだけ大事なことを見落としていた。神はそれほど信用のおける相手ではないということを。