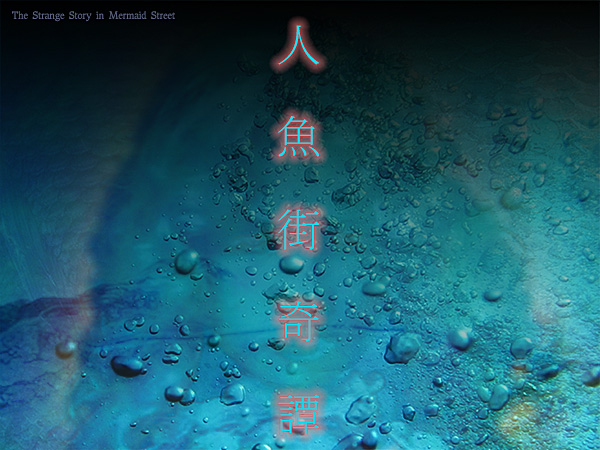
私はその街で人魚に出会った。多分、本物の人魚だったのだと思う。もしかすると幻影だったのかも知れないが。
〈人魚の街〉は昔はもっと賑やかだった。馴染みの女もいたが、今はどうしているのか知らない。久しぶりに訪れた〈人魚の街〉は白い塗りが剥げた灰色の褪せた木造の娼家が並んでいる寂れた街になっていた。
見世物小屋は小振りの楼閣と潰れた舞踏場の間にあった。入り口の一段高くなった台に萎れた花のような老人が座っていた。看板は灯りが暗くてよく見えない。幾許かの木戸銭を払って私は中に入った。
間口はごく狭いが、洞窟のように奥に続く建物だった。通廊の左右にぼんやりとした洋灯と蝋燭の明かりに照らされて、怪しげな生き物の木乃伊や骨が並んでいた。曰く、アニャチ帝国北東の海で獲れた人面蟹(海に沈んだファバーンの民人の怨霊が乗り移っているのだそうだ)、曰く、西の大洋の真ん中に現れる竜神のものだという巨大な爪。曰く、東部の沖合に出没するという悪魔の蛸の脚の干物。曰く、メルカー南部のテクメクス湾の先で無人のまま発見された商船マールセレート号の陶器の皿と銀の匙。
真偽のわからない、いや、限りなく嘘に近いであろう品々が暗い廊下の左右に展示されていた。私の他には誰も客はいないようだった。
通廊の一番奥にはくたびれた赤い垂れ幕が掛かっていた。それを潜ると少し広い部屋になっていた。隅の方に置かれた大振りの洋灯には、薄緑や水色の硝子が嵌め込まれていて、不思議な緑色じみた光を放っていた。壁には岩場や珊瑚や海草、魚や蟹や海老、海星などが描かれているようだが、絵の具は色褪せ、剥げ落ちて、床の上に滓のように溜まっていた。
床の上には物が置かれていたらしい四角い跡が幾つもあったから、かつては他にも見世物が並んでいたのだろう。今は十イート(約三メートル)ばかりある水槽が一つ置かれているだけだった。水槽は膝ぐらいの高さの台に載っており、高さは胸ぐらいまであった。半分くらい濁った水が入っており、強い潮の匂いがした。
水槽の中には人魚がいた。中に置かれた岩に腰をかけ、両腕で水槽の縁にもたれて、縁の赤い澱んだ緑色の瞳でこちらを見ていた。
くしゃくしゃに乱れた髪の毛は金色で、本物の黄金のような輝きがあった。白い肌は滑るような艶がある。緑の瞳はこぼれ落ちそうに大きく、ふっくらとした頬の下に小さな頤がついている。まくれた唇は珊瑚のような鮮やかな桃色だった。
頽廃的で扇情的と言える顔立ちだったが、人魚はまだ子どもだった。少し上を向いた鼻が愛らしかった。人魚の成長の仕方は知らないが、人間ならば十かそこいらのように見える。硝子越しに膨らみかけの乳房が見えた。
臍の下のあたりからうっすらと鱗が見え始め、滑らかな曲線を描く下半身は銀に青と緑の入った輝くような魚の姿だった。透き通った尾鰭を、彼女は退屈そうに動かしていた。
「人魚見たことないの?」
珊瑚色の唇が動くと、口の中に鋸のように尖った歯が見えた。子どもにしては低い、少し嗄れた声だった。
「ないわけじゃないがね。君みたいな子どもの人魚は初めてだね」
「子どもじゃないのよ」
そう言って、彼女はふふんと鼻で笑った。
「これは失礼」
人魚は長命だという話は聞いたことがあるが、目の前にいる十くらいの娘のような人魚がどれだけ生きてきたのかなど、わかるはずもない。
「君の名前はミ=ヌェットというのか」
人魚はこくこくと頭を動かして薄笑いを浮かべた。
「そう呼ぶ人が多いわね。でも、人魚に名前なんか聞いてどうするの? この街にはそんなにたくさん人魚がいるの?」
「ここは〈人魚の街〉だからね」
ミ=ヌェットはまた頭を上下に動かして笑った。それが癖なのだろうか。今度は口を少し開いたので、また鮫のような歯が見えた。
「あなた、誰? 人に名前を聞く時はまず自分から名乗るのが礼儀なんでしょう、人間は」
「これはまた失礼を。僕はスナブ・ランケン。探偵だ。君を捜して連れてきてほしいと頼まれてるんだ」
「へえ、いったいどこの誰が?」
「ガルル・メグワスという老人だ。君を盗まれたので取り戻してほしいと言っている」
人魚は興味なさそうに小さな腕を振って見せた。同時に尻尾が水槽の中でぱちゃぱちゃと音をたてた。
「そんな人知らないわ。いつから私はその人のものになったの?」
「ガルル・メグワス老人は世界中の珍奇なものを集めるのが趣味だ。若い時分には商船を率いて西の大洋を渡り様々な驚異と出会ったそうだ。だが、人魚にだけは出会う機会がなかった。老人は配下の船長たちを動かして、人魚を捜し出そうとした。そして、捕えられたのが君だ」
ミ=ヌェットはまた頭を小さく振って、ふふんと笑った。笑うたびに尖った歯が見えるのが、だんだん魅力的に見えてきた。
「そのお年寄りは勘違いをしているわね。私は誰かに捕まった覚えはないわ。私は人間の世界がおもしろそうだから、陸に来てみただけよ」
「ふむ、君から見ればそういうことなのかも知れないね。だが、僕の依頼人はようやく捕まえた人魚を盗まれた、横取りされたと思っている」
「ふうん、ああ、あの男の子のことね」
子どもの人魚は水槽の岩の上に出てきた小蟹を目にも留まらぬ速さで捕まえると、愛らしい珊瑚色の口の中に放り込んだ。ばりばりと甲羅が砕ける音がした。
「あなたも食べる? おやつにちょうどいいわよ」
「遠慮しておくよ。男の子っていうのは?」
「慎み深いのね、探偵さん。私が乗り込んだ船にいた男の子よ。茶色い髪の毛と茶色い目玉で、ひょろっとしていたわ。ちょっと可愛らしかったから、いろいろお話ししていたら、次の港で私を樽に入れて連れ出したのよ」
人魚は額にたれかかる金糸のような髪の毛をかき上げた。こめかみの生え際に小さく光る銀の鱗が見えた。
「それで、どうしたんだい」
「小舟で別の島に行って、入り江の奥の小屋でしばらく暮らしたわ」
「それで?」
「月が丸くなって、また細くなった頃に、また樽に入れられて、別の島の港に行ったわ。樽から出たら、大きなお屋敷にいたの」
「ほう」
「お屋敷には大きな池があって、しばらくはそこで暮らしたわ。水もきれいで魚もおいしいのが毎日出てきたわ」
ミ=ヌェットはまた小蟹を一匹噛み砕いた。白い喉が蟹を飲み込んで動く様が、妙に艶めかしかった。口元に持っていった手には透き通った水掻きがあった。
「髭の生えた太った男の人がお屋敷の主で、たくさんの人を集めて何度も宴を開いたわ。そして、池にお客さんを集めて、私を見せて自慢するのよ」
人魚はにやりと笑うと水槽の縁に載せていた白い腕を広げて、少女のような姿態を自慢するかのように小さな乳房を突き出して見せた。
「また月が太ったり痩せたりした頃、真夜中にこっそり忍んできた人がいたわ。お坊さんっていうのかしらね。赤い衣をまとって痩せこけた男の人。池から水槽に私を入れて連れ出したのよ。仲間が何人かいたわ。そして、また違う島に船で行ったのよ。洞窟の奥に海の水が入り込む淵があって、そこで私は神様になったの」
「神様だって?」
「赤い衣のお坊さんや他にもたくさんの人が、赤い蝋燭を持って集まってきて、洞窟の地面に這いつくばって歌ったり祈ったり、願い事をしたりよ。そういうのを聞いたり見たりするのを神様っていうんでしょ」
「まあ、そんなところかも知れない」
「ここでも、おいしい魚を持ってくる人がいたわ。まあ、海とつながっている洞窟だから、小魚は不自由なく自分で捕れたけれど。蟹もいたわ」
少女の姿をした人魚は三匹目の蟹を捕まえてぎざぎざの歯の間に放り込んだ。
「蟹が好きなのかい」
「そうね。かなり好きよ」
「僕も百鬼蟹は好きだよ」
「ああ、あれはちょっと大きすぎるわ。一口で噛み砕けるくらいのが好きよ」
私は頷いたが、彼女の癖が移ったのか、二度三度首を振っていた。
「赤い衣の坊さんというのは、シベニールの島々の連中かな。海神ダッコーニを崇めてるからな。娘か孫だと思ったんだろう」
「そんなの知らないわ」
私はダッコーニについて少し説明した。紫色の海牛のような姿で体中に吸盤がついている。それに黄色い蛸のような脚が十三本も生えていて、大鯨を食べる。
「そんなもの、いないわ。それに私、蛸はきらいよ」
「そうかい。僕は蛸は好きなんだけどね。それで、その島でどうしたんだい」
「二回目くらいの満月の時−洞窟は天井に穴が開いていたのよ−お坊さんの中でも一番年寄りの人がやってきて、私の血を飲ませてくれというの。私の血を飲むと海の神様と一つになれて、永遠に生きられるんだって」
その手の話はアニャチあたりで幾度か聞いたことがあったが、シベニールの坊さんたちは西の大洋の彼方の言い伝えを知っていたのだろうか。
「飲ませてあげたのかい」
彼女は初めて首を横に振った。細い濡れた金色の髪が、揺れる薄緑の灯に煌めいた。人魚も人間と同じ仕草をするのだろうか。いや、彼女は抑揚や語調はともかく、はっきりとしたウォモレン(共通語)を話しているではないか。
「そんなの気持ち悪いし、第一、血が出たら痛いじゃない」
「うん、それはそうだね」
「それで、洞窟の中の淵を逃げ回っていたら、私を洞窟に連れて来た若いお坊さんがやってきて、歳を取ったお坊さんを殺したの。後ろから石で頭をぶったのよ。血がどくどく出て、水の中にも入ってきて、私、飲んじゃったわ。人間の血を飲むと長生きできるなんて、聞いたことないのに」
小さな人魚は尖った歯の間からやけに鮮やかな桃色の舌を突き出して、吐くような仕草をした。小蟹の甲羅の欠けらが水槽の外に落ちた。
「そのお坊さんが私を洞窟から連れ出して、また別の所へ行ったわ。今度は島じゃなくて、大きな船がたくさん浮かんでいる大きな港だったわ」
「この街の港かな。ここはサンジェリィっていう街だよ」
人魚はまた、こくこくと頷いた。
「ああ、そうよ。そういう名前の街だって言ってたわ」
「それで、そのお坊さんは君をどうしたんだい」
「港の近くの−潮の匂いと腐った魚の臭いがしたわ−汚い小屋で、しばらく一緒に暮らしたわ。あんまりおいしい魚は持ってきてくれなかったわね。海でちょっと泳がせてって言っても、連れていってくれなかったわ。私が逃げると思ってたみたい」
少女は不満そうな顔になって桃色に光る唇を突き出して見せた。よく考えられた媚態のようにも見えた。やはり十歳というわけではないのだろう。
「それで?」
ミ=ヌェットは小狡そうな笑いを浮かべて、水掻きのついた小さな手で私を差し招いた。
「内緒話でもするつもりかい」
「大丈夫よ。人間なんて食べないから。ほら、気分が大事って言うでしょ」
私は水槽の娘に近づいた。手が触れるまで近づくと、潮の匂いに入り交じって甘酸っぱい香りがした。彼女は愛らしい唇から尖った歯をちらちら見せて、囁き声で話を続けた。
「彼はね、私のことを愛してるって言ったわ。私のことを抱きたいって言ったわ」
それほどおもしろい話でもないような気がしたが、人魚はくっくっくと小さな肩を震わせて笑った。
「それで、彼の思いを遂げさせてあげたのかい」
私の台詞がおかしくて堪らないとでも言う風に、彼女はさらに笑った。
「だって、ほら、私、人魚でしょう。彼の思うようには行かなかったわ」
そんな品のない冗談を人魚自身から聞くとは思わなかった。
「それで、彼ったらね、私を売り飛ばしたのよ。ううん、この小屋じゃないの。彼の神様とは別の神様を崇めてる人たちがいて……」
ミ=ヌェットの話は延々と続いた。別の神様を崇める連中は彼女を使って西の大洋からク=ジュール=ジュルの神とやらを呼び出そうとしたがうまくいかなかった。失望した連中は、彼女の肉を食らおうとしたが、一人の僧侶が追いすがる仲間を殺して、彼女を奪って逃げ出した。その僧侶は奇形の女を集めている大金持ちに彼女を売り飛ばした。大金持ちは彼女と情交しようとしたが、やはり思惑通りには行かず、怒って見世物一座に売った。見世物一座と(恐らくは)東岸の街を幾つか廻ったが、一座の主と〈蛸男〉(関節を外す見世物をするらしい)とで、彼女の取り合いとなり、〈蛸男〉は座長を殺して彼女と逃げた。だが、〈蛸男〉は座長と争った時の傷が元で死に、彼女も水槽の水がなくなって死にかけたが、偶然通りかかったオイスト男爵なる貴族に助けられた。オイスト男爵は彼女を深く愛したが(ミ=ヌェットがそう言ったのだ)、夫人の嫉妬に絶えられなくなり、彼女を裕福な商人の元へ預けた。男爵は夫人を殺して自殺した。商人は彼女を無理矢理抱こうとしたので(どうやって?)、彼女は男の耳朶を噛み千切った。商人は彼女を殺そうとしたが、番頭がとりなして(彼もまたミ=ヌェットを愛していたのだ)〈人魚の街〉の娼館に売り飛ばした。娼館ではしばらく客寄せに彼女を使っていたが、客が取れるわけではないので、巡回動物園に売った。巡回動物園では、園長とその十五歳の息子と〈蟹女〉(いったいどういう見世物だったのかは、語らなかった)とで、彼女の取り合いになった。十五の少年が他の恋敵を皆殺しにしたが、気が狂って彼女も殺そうとした。だが、傴僂の飼育係が少年を殺して彼女を救った。傴僂男は彼女を愛そうとしたが、魚の臭いが嫌いで、結局は売り飛ばした。その後、幾つかの見世物小屋を経て、今、この小屋にいるのだと言う。
「それで、どうするつもりなの?」
今度は人魚が私に尋ねた。
「どうするって?」
「ぼんやりしているのね。私を連れて帰るのがあなたの仕事なんでしょう」
「ああ、つい君の話に聞き入っていたよ。小屋の主はどこにいるんだい。木戸銭を取っていた爺さんじゃあるまい」
ミ=ヌェットは目を細めてひどく下卑た笑いを浮かべた。
「マッコール爺さんはね、ときどき市場で買った魚を持ってここへ来るのよ。小屋を開ける前にね。それで、魚をあげるから体をさわらせてくれって言うの」
彼女が本当に体をさわらせているのか、少し気になったが、また話が長くなりそうなので、訊くのはやめておいた。
「爺さんは小屋主じゃないんだな」
「エムグレシュコは小屋が跳ねた頃に来るわ。ほら、そろそろ時間よ」
どこかで店仕舞いを告げるカランカランという鐘の音が聞こえた。通廊を近づいてくる足音がして、振り向くと垂れ幕を開けて男が入ってきた。
「お客さんかい。今日はもう店仕舞いなんだ。またのご来場をお待ちしておりますよ」
そう言って男は顎で出口を指し示した。もう一度来てほしいとは思ってはいないようだった。
「あんたがここの主かね」
「いかにも。世界の海の奇跡へようこそ、エムグレシュコの海の宮殿へ」
小屋主は髪に白いものが交じる背の低い男だった。くたびれた黒い夜会服を着ている。突き出た腹が釦を弾き飛ばしそうだった。頬と目元は弛みが目立ち、油を塗った髪は額から天辺まで薄くなっていた。
「スナブ・ランケン、探偵だ。この人魚を取り戻してくれという依頼を受けている。もちろん、只とは言わない」
私は腰に下げた革袋をとり出して、中のダズン金貨を何枚か見せた。
エムグレシュコは澱んだ黒い目で金貨と革袋を見つめた。特に目が輝いた、ということはなかった。
「ほう、この私の海の宝石に幾ら払うというのかね」
「私の」という部分は幾らか強調されていたように聞こえた。私は金額を言った。見世物小屋が立て替えられるような額だ。
「ほほう、それはたいした金額だな。いったい、どこの誰が私の宝石を奪い取ろうとしているのだ」
依頼人の名は明かしても良いという話だった。むしろその方が取引がうまくいくと老人は考えているようだった。
「ガルル・メグワスという商人だ。名前ぐらい聞いた事があるだろう」
「船が十三、蔵も十三のメグワス船長だろう。この港で知らない奴はおるまい。だが、そんな端た金で私がこの宝石を手放すとでも思っているのか。第一、取り戻すっていうのはどういう意味だ。私はまっとうにこの奇跡の生き物を手に入れたのだ。メグワス老人だろうが誰だろうが、とやかく言われる筋合いはない」
私は人魚にした話の最初の部分をもう一度してみたが、小屋主の答えは「そんなことは知ったことじゃない」だった。私は金額を少しずつつり上げてみた。無論、依頼人が示した額の範囲でだが。
「探偵さんよ、私は売らないって言ってるんだよ。わかるだろう」
エムグレシュコは私と水槽の間に割って入り、金色の髪の娘を自分の背に隠すようにした。私は腰から革袋を外して、丸ごとではどうだと言ってみたが、小屋主は首肯かなかった。
「金じゃないんだよ、探偵さん。私はね、私はこの宝石を……」
小男の後ろで人魚が笑い声をあげた。
「何が! 何がおかしい! 私は、私は!」
エムグレシュコは激昂して振り返り、人魚に手を上げようとした。私が止めるよりはやく、男の悲鳴が部屋の中に谺した。
ぎざぎざのミ=ヌェットの牙が男の腕に食い込み、血が流れ出していた。
「何をする! この売女め! 私がお前のことを、お前のことを!」
その後は何だかよくわからない呻き声とどたばたする物音になった。私がようやく小屋主を引き離すと、腕の肉が千切れたらしく、血が噴き出した。人魚は口に残った男の腕の肉の欠けらを吐き出した。
「こんな不味い肉食べたことないわ! マッコール爺さんのくれる魚の方がずっといいわ! お前に私を抱く資格なんかあるとでも思ってるの! そのお金持ちのきれいな水槽に住んでみたいものだわ! 」
「何だと、貴様、あの爺と! 売女め、許さん!」
エムグレシュコは血まみれの腕でもう一度人魚につかみかかろうとしたが、私は彼の横腹に拳を入れた。男は呻いて床に転がった。
「糞! 何てことだ! 大枚をはたいて手に入れたのに! 高い魚ばかり買い与えていたのに! 畜生め!」
見世物小屋の主は薄汚れた床の上で太った体を捩らせながら、そうわめいた。彼もまた見世物の一つのように見えた。
「貴様、私の宝石を盗み出すつもりだな!」
男は血まみれの腕で私の足をつかみ、興奮した様子で言った。
「そんなことはしない。折り合わないのなら、依頼人にそう報告するだけさ」
「嘘をつけ! 金持ち連中のやり口は知っているぞ! 金の力で従わせられなければ、力尽くだ! 役人はいつでも奴らの味方だからな!」
「スナブ・ランケン、私をその何とかいう人のところへ今すぐ連れてって! もうこんな薄汚い水槽はまっぴらなのよ! あんたがどこかに行っている間にこの豚は、私を連れて逃げ出すに決まってるわ! 今よ! 今すぐ、私を連れて逃げて! この豚男は殺して! 殺して! 殺すのよ!」
ミ=ヌェットは尾鰭で水を跳ね散らかせて、水槽の縁から身を乗り出してそう叫んだ。上気した頬は赤く染まり、大きな瞳は潤んで血を流しそうだった。反らせた胸の上の小さな乳房が素晴らしく美しく見えた。自らの声に奮える白い喉は、小娘のものとは思えない艶めかしさだった。
「そうはいかんぞ! そうはさせんぞ!」
立ち上がったエムグレシュコの手にはいつの間にか、刃渡り一イート(約三十センチ)はある短刀が握られていた。トリフェザの海賊がよく持っている類のものだ。元はそういう商売なのかも知れない。
「そんなものはしまうんだ。僕はここに殺し合いに来たわけじゃない」
「うるさい! 貴様らのやり口はわかっているんだ! 騙されると思うか!」
貴様ら、というのは私も依頼人も含んでいるのかと思うと、嫌な気分になった。この仕事は引き受けるべきではなかったのだろう。
小屋主は短刀を振りかざして襲いかかってきた。抜くまでもないかと思ったが。意外と素早い動きだ。私は最初の一撃を避けると、ファバーン剣を抜いた。刀身の神秘文字は薄暗い見世物小屋の中で淡い光を放っていた。やはり人魚は魔性の生き物なのだろう。青や緑で海中を模した部屋に、緑色の燐光は妙に似合っていた。
エムグレシュコは臆する様子もなく再び短刀を突き入れてきた。ぎらぎらとした目付きは尋常なものとは思えなかった。私はファバーン剣で海賊の刀を打ち落とし、束で男の腹を打った。小男はよろよろと後退り、人魚の水槽に背中がぶつかった。
水槽から身を乗り出したミ=ヌェットが男の短い首筋に噛みついた。鮫のように鋭いぎざぎざの歯が肉に食い込み、どくどくと血が溢れ出した。エムグレシュコは何かわめこうとしたが、口からは赤い泡がごぼごぼと噴き出しただけだった。人魚が放すと、男は床に倒れて、血を噴きながらひくひくと動いた。
私は思わず溜め息をついた。
「どうするつもりだ」
血は流れ続けていたが、男の体は動きを止めた。
「私を連れて逃げて。ここから連れ出して」
人魚は口の中の血を水槽の外に吐き出し、血まみれの顔を水槽の水で洗った。
「海へ帰りたいのか」
「違うわ。あなたと一緒にいたいの」
彼女が目を細めると、暗い影の中で翠玉の瞳が強い光を発した。ファバーン剣を握った手に、魔力の存在を示す痺れるような感じが伝わってきたが、人魚の目から視線をそらすことは難しかった。
「あなたと一緒に暮らしたいのよ。あなたに抱いてほしいの」
ミ=ヌェットは水槽の縁に手をかけて、上半身を大きく乗り出させた。私はふらふらと吸い寄せられるように水槽に近づいた。甘酸っぱい香りが潮の匂いをかき消すかのように感じられた。
「私を連れ出して」
人魚は水槽の縁から両の腕を伸ばして私に体を預けた。小さな乳房が揺れて、私の肩の辺りに押し付けられた。細く思いの外暖かい腕が首に巻き付いた。
銀の鱗に覆われた下半身が水飛沫をあげて水槽から飛び出した。思わぬ重みに私は床の上に倒れ込んだ。ファバーン剣が手から離れ、がらんがらんと音をたてて床に転がった。ミ=ヌェットは私の上に覆いかぶさり、滑る柔肌を押し付けてきた。
「スナブ・ランケン、私を抱いて、ねえ、抱いて」
やはり人魚の歳の取り方は人間とは違っているのだろう。十の娘とはまるで思えぬ生々しい吐息とともに、人魚は全身を私に擦りつけた。
「抱いて、私を抱いて」
幼い小さな唇が私の唇にかぶさり、ぎざぎざの歯が私の舌を噛んで、鋭い痛みが走った。奇妙に甘美な痛みだった。
下半身に押し付けられた銀鱗の体に変化が表れていた。何か粘つく液汁のようなものが鱗の隙間からなのだろうか、滲み出ていた。滑らかな紡錘形の体に節ができて蠢き、私の足にあたった。
「ほら、もうすぐよ。もうすぐ、あなたを受け入れられるような体になるわ」
ミ=ヌェットは艶めかしい声で耳元で囁き、尖った歯で私の耳朶を噛んだ。痛みと快感がないまぜになった妖しい感覚が耳朶から足の先まで走った。下半身に暖かく湿った感触があった。見れば、人魚の下半身は赤い血にまみれていた。鱗に覆われた体から鮮血がじくじくと湧き出しているのだ。透き通った尾鰭が苦痛なのか快楽なのか、ひくひくと痙攣していた。その尾鰭の真ん中に赤い線が走ったかと思うと、鰭は二つに裂けた。銀色に光るものがちらちらと落ちていくのは、鱗が剥がれ落ちているのだろうか。
私の体の上にのしかかった魚の体が、血を流しながら左右に裂けていく。二つになった尾鰭には厚みが生じて人間の足のような形になっていく。左右別々に、膝のようなものが動いて私の足に当たる。ミ=ヌェットはとても十やそこいらの子どものものとは思えない淫靡な息をもらし、呻き声をあげ、私の上で恍惚の面持ちで体をのけ反らせた。
「もうすぐよ、もうすぐよ……」
金色の髪の娘は私の上で小さな乳房を震わせながら、睦言のように呟き続けた。
甘美な−いや、醜怪なと言うべきだろうか−幻想−いや、現実だったのかも知れない−に、鋭い叫び声が大きな亀裂を入れた。
「この餓鬼は! まだそんなことやってるのかい! 今度という今度は承知しないよ!」
部屋の入り口に背の低いひとりの女が立っていた。灰色の髪を振り乱し、黄ばんだ肌には染みが浮いている。何色かよくわからない襤褸をまとい、歪んだ口から泡を飛ばして、叫んでいた。
「今度こそ許しゃしないよ! ああっ! あんた、あんた!」
女はよたよたとした足つきで、倒れている小屋主の方へ駆け寄った。血みどろの男の肩を抱き起こし、号泣する。
「おまえが、お前が殺したんだね! この淫売の人殺しめ! 父親を狂わせてあたしから奪うだけじゃ事足りず、殺したのか! あの時、殺しておけば良かったんだ!」
ミ=ヌェットは私の体の上で身を捩らせ、女の方を向くと、恐ろしい濁声を出した。
「糞ばばあめ! お前のような女に満足する男がこの世にいると思うのかい。私は父様をお前の弛んだ肉と棘だらけの口から解放してあげたのさ! 父様は私に夢中になったよ! お前の腐った肉なんぞ、触れたくもなかったんだよ!」
女の発する声はもはや言葉にはならなかった。甲高い狂った鶏のような叫び声とともに、女は襲いかかってきた。手にはエムグレシュコの海賊の短刀が握られていた。
「ランケン、助けて!」
少女の幼い声が頭の中に谺した。甘美な酒に酔っていたような体に突然力が漲った。私は血まみれの人魚の体を抱いたまま床の上を転がった。海賊の刀が背中の皮を薄く切り裂き、鋭い痛みが走った。
ミ=ヌェットを部屋の隅まで押しやり、ファバーン剣を拾い上げて、女の二の太刀を打ち払った。
「物騒なものを振り回すのは止せ」
「ふん、ほんとに物騒なのはお前の後ろにいるその娘さ! お前も誑かされたのかい! 無理もないよ、そいつは自分の母親から色仕掛けで父親を奪い取る正真正銘の淫売なんだから!」
女は赤く濁った目を憎悪と憤怒でぎらつかせてわめいた。この女の言っていることは本当なのだろうか。後ろを振り向くと、ミ=ヌェットは血まみれの両足で立っていた。銀の鱗に覆われた腰から下はぬらぬらとした血にまみれた白い二本の足となっていた。
「ランケン、その女を殺して! そいつは気狂いだよ! 私と父様を酷い目に遭わせたんだ。だから、私は父様を助けたくて、助けたくて……」
「よくもそんな嘘を! お前があの人を誑かして、家は滅茶苦茶になったんだ! お前なんか産むんじゃなかったよ! お前は化け物だ! 二度と男に股を開けないように、両足を縫い合わせてやったのに、それでもあの人を騙くらかして……」
「気狂いの糞ばばあ! お前は私と父様を嬲りいたぶることしかしなかった! 化け物はお前だ! お前こそが化け物だ! 私を産み育てたのは、化け物のお前だ! だから、私は化け物になったのさ! お前がこの両足を縫い合わせて鱗の呪文を唱えたくせに!」
手にした太古の魔剣からは、痺れにも似た妖気を示す感覚が伝わってきた。だが、いったい誰が魔道を行う者なのだろう。少女ミ=ヌェットは本当に人魚なのだろうか、髪を振り乱した母親だという女は人体縫合と呪術で人魚を作り出したのだろうか。
人魚の芳香に惑わされていた私には、何が真実なのか見極めることは難しかった。母親だという女は、金物を擦り合わせたような叫び声をあげて、刃を振りかざして飛びかかってきた。
私はファバーン剣で海賊の短刀を弾き飛ばすと、彼女を蹴り飛ばした。海賊の刀はそれ自体が魔剣でもあるかのように、太古の神秘文字に触れると緑色の火花を散らした。
女は私が蹴った勢いで後退った。水槽の近くに横たわっていたエムグレシュコは死んではいなかった。人魚の父親だという男は、ごぼごぼと血の泡を噴きながら、女の足首をつかんだ。女は体の均衡を崩して、勢いよく水槽の方へ倒れ込んだ。
大きな音がして水槽の硝子が割れた。濁った水がどっと流れ出した。割れた硝子の破片が女の首筋に突き刺さった。噴水のように血が噴き出し、流れ出る水を赤く染めた。
血の臭いよりもずっと強い潮の匂いが部屋中に満ちた。水槽から水が溢れ出した。波立ち泡立ち、水が部屋中に広がっていく。
閉じた部屋でもないはずなのに、薄緑の水は沸き立つように嵩を増していく。水槽からは止めどなく水が溢れ出す。水嵩は見る間に脛の辺りまで達して、人魚の父母だという二人の体は水に浮き上がり、血を流しながら互いにぶつかり合った。
やがて水の流れが止まった。水槽の水は出尽くしたのだろうか。扉もないはずなのに、部屋の中は膝下までの渦巻く海水で満たされていた。
その水の下に幾つもの影が揺らめいた。水面を泡立てて、影は水中から立ち上がった。ずぶ濡れの襤褸を着た幾つもの黒い人影。腕や足に絡みついているのは海草だろうか、腐ってぶよぶよとした肉の穴に出入りしているのは蟹だろうか。
「ミ=ヌェット、僕のかわいい人魚……」
ほっそりとした人影が歪んだ口からそう聞こえる言葉を吐き出した。
「ここにいたのか。ひどく捜したぞ……」
太った人影が、かろうじて残っている顎のまわりの髭を動かしながらそう言った。
「海神の娘よ、青い水の妖精……」
頭から赤い長衣を被った痩せた人影が、擦れた声を出した。するともう一人、赤い衣の人影が現れ、痩せた影を水中に引きずり込もうとする。
二人の影がもつれ合っていると、近くの別の影が「ウングルア、グルヌーア、イア、ク=ジュール……」と呪文のようなものを唱えながら、人魚に近づこうとする。
他にも幾つもの人影が、人魚の名を恋しく呼び、あるいは怨嗟のこもった声を出し、あるいはすすり泣きを漏らし、部屋を満たした水の中から立ち上がり、人魚の方へ歩み寄ろうとしていた。
手足の関節が不自然に曲がっている影、宝石を鏤めた上着を被っている影、背中に瘤のある影なども見えたような気がする。
ミ=ヌェットは部屋の隅に背中を貼り付けるようにして、強ばった面持ちで迫ってくる影たちを見つめていた。大きく見開かれた緑玉の瞳と恐怖に奮える小さな珊瑚色の唇は、彼女の姿を歳相応−と言っていいのだろうか−に見せた。私は剣を構えなおして、影たちと人魚の間に割って入った。ファバーン文字の緑光が、ひときわ強まっているように感じられた。
「ミ=ヌェット、ミ=ヌェット、ミ=ヌェット……」
影たちの声はいつしか重なり合い、一つの奇怪な詠唱のようになり、部屋の中に谺した。色硝子からの揺らめく光が足下を洗う水に映り、色褪せた壁の絵をゆらゆらと照らし出す。朽ちた海底の絵模様の中を黒い朽ちた人影が、身悶えし、争いながらも迫ってくる。
「ランケン、怖いわ、助けて」
耳元で奮える声がする。水掻きのある小さな手が肩に触れる。
「君とご縁のあった人たちかね」
「いやよ、みんな死んだはずよ、みんな死んだのよ!」
人魚は引きつった声で叫んだ。
「仲間入りはご免だな。歩けるのか」
「無理よ、歩くようにはできてないのよ」
人魚はかろうじて壁にもたれて立ってはいたが、血にまみれた足は力なく不自然に曲がっているように見えた。
「僕に負ぶされ」
ミ=ヌェットは白く濡れた両腕を私の首に回した。私は少女の小さな尻を片手で持ち上げた。思いの外、重かった。
私は片手で剣を振り回し、影たちの間に突進した。魔剣の刃が触れると、黒い影から白煙が上がり、腐肉が飛び散った。
四方八方から黒い手が伸びてくる。私は剣を振り回し、何本もの腕を切断した。腹を斬り裂くと、腐った臓物がこぼれ落ちて水音を立てた。首を斬れば、なおも恋慕と呪詛の言葉を吐きながら頭は落下した。
背中では人魚が小さな悲鳴を上げながら、必死で私の首にかじりついていた。部屋の出口の赤い垂れ幕が途方もなく遠く感じられた。
何かが私の足首をつかんだ。危うく転びそうになり、足下に剣を振り下ろそうとした。血まみれの顔のエムグレシュコが私の足をつかんでいた。私はその脳天に剣を叩き込んだが、その隙にぶよぶよとした何本もの黒い腕につかまれ、背中からは強い力で引っぱられた。
ミ=ヌェットの叫び声が耳元で響いた。また足首をつかむものがあった。灰色の髪の女がおぞましい笑い声をあげながら、私の足をつかんでいた。私は四方からの力に絶え切れずに転倒した。背中から少女が引き離されるのを感じた。濁った海水の中に頭を突っ込まれ、息が苦しくなった。何かぬるぬるとしたものが首を締めつけ、頭をひどく殴られた。青と緑の渦潮が頭の中に渦巻き、何もわからなくなった。
強い潮の匂いがした。私はずぶ濡れで横たわっていた。頭がずきずきと痛んだが、瘤ができているわけでもなく、血が流れているわけでもなかった。すぐ側にファバーン剣が転がっていた。刀身の神秘文字は鉛色にくすんでいた。
目の前には割れた大きな水槽があった。水はなく、乾ききっていた。破れた屋根の隙間から黄色い鈍い陽光が差し、部屋の中を照らし出していた。壁はひび割れ、色褪せた海中の絵はほとんど剥落している。板張りの床は波打ち、穴が開いているところもある。大振りの洋灯は錆びつき、色硝子の火屋は割れて床に落ちていた。
私は立ち上がり、壊れた水槽の中を覗き込んだ。岩の上にも水色に塗られた底にも、埃が積もっていた。干涸びた小さな蟹の死骸が一つ転がっていた。
部屋の隅に茶色い塊が二つあった。近づいて見ると、一つは小振りの人間の木乃伊だった。色褪せてはいるが、まだ金色がわかる髪の毛が残っていた。小さな口元からはぎざぎざの尖った歯がのぞいていた。胸には小さな乳房の跡があるのがわかった。木乃伊には下半身がなかった。
少し離れたところにもう一つの茶色い塊があった。それも木乃伊には違いなかったが、異様な形をしていた。魚の下半身を無理矢理二つに引き裂いたような形をしており、端には尾鰭とも足ともつかないものがついていた。わずかに銀色に光る鱗も残っており、真ん中あたりでは膝を曲げたかのように折れ曲がっていた。裂け目には女陰のようにも見える小さな肉の割れ目が見えた。ぶつぶつと小さな穴が左右に分かれた半身に並んでいた。鱗の跡にも肉を縫った跡のようにも見えた。
私は剣を拾い上げると、ぼろぼろの赤い垂れ幕をくぐって、通廊に出た。洞窟のような廊下は暗く、左右の壁龕には埃が積もっているだけだった。
見世物小屋の外に出ると、曇り空の切れ目から日が差していた。木戸番の老人の姿はなかった。番台の上には傾いだ看板が倒れかかっていた。『魅惑の人魚の館−エムグレシュコの海の宮殿』、看板はかろうじてそう読むことができた。
通りの向こうから、朝市で仕入れた魚を売る行商人の声が聞こえてきた。商船の出帆を知らせる銅鑼の音も聞こえる。ガルル・メグワスには木乃伊を持ち帰るべきなのだろうか。老人はこんな奇怪な話を聞いておもしろがるのだろうか。腰のダズン金貨は重かったが、この仕事が金になるのかどうか、私には皆目わからなかった。