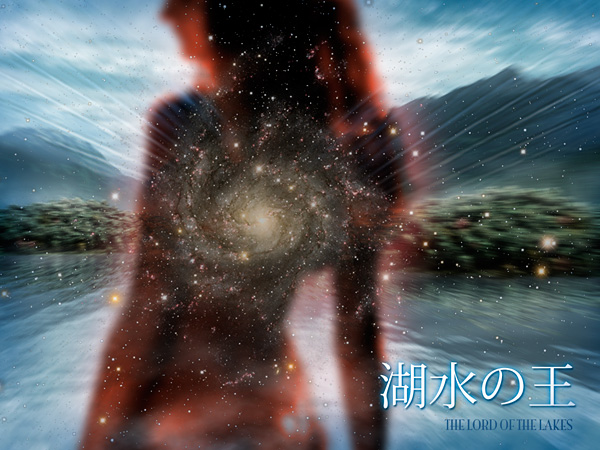
私は、一人、旅に出ることがある。大都サンジェリィの喧騒に飽いたとき、我が意に反して近づいてくる魍魎妖魅の類いにうんざりしたとき、あるいは、醜怪な欲望と情念にまみれた人の世に嫌気が差したとき、私はクーリカフ街の仕事場兼住み処に掛かるスナブ・ランケン探偵局と書かれた札を裏返して、一人で旅に出る。
そのとき私は、灰緑の薄手の外套を羽織って、サンジェリィから北西に延びる青翠街道を旅していた。
サンジェリィと並ぶ大都フランジースコとの間を最短距離で結ぶ黄金街道は、引っ切りなしに隊商が行き交い、蹄の音、車輪の軋む音、絶えることはない。街道沿いの宿駅では、宿の呼び込み、物売りの声、女の嬌声、男の怒声などですこぶる賑やかだが、道筋の光景は、砂塵の舞う荒れた黄色い大地が広がり、殺風景という他はない。
そこへ行くと青翠街道は、サンジェリィ北西に広がる森林に覆われた湖水地方を通り、場所によっては西の大洋も見ることのできる風光明媚な道だった。
私はその緑濃い街道を歩いていた。左右には常緑の森が迫っているが、ところどころには黄と赤に色づいた木々が葉叢を広げ、美しい天然の絵画を描き出していた。青く澄んだ空は高く、白い筋雲の合間を大きな黒い猛禽が輪を描いて飛んでいた。
私は滅多に得られない心の平安を感じて、晩秋の心地よい冷気を吸い込んだ。
だが、安寧は一瞬にして破られた。行く手の街道が右に曲がった森影から、白刃交える金音と裂帛の気合い、怯えた馬の嘶きが聞こえてきた。
私は腰間のファバーン剣に手をやった。三千年前海中に没した国の魔剣は、歳月の内にほとんどの力を失っていたが、妖気を感じて持ち主に知らせる力はまだ残っていた。だが、異界のものや妖術の存在を示す、しびれにも似た感覚は伝わってはこなかった。
どうやら人間同士の争いのようだった。私はうんざりとした気持ちで、足を速めるでもなく道を進んだ。
道が折れた木陰から、ざざっと靴底をすらせる音をたてて、一人の小柄な剣士が姿を見せた。藍色の地味な上下にくすんだ青い引き回しだが、長沓や腰帯、籠手には金細工の飾り物、細身の長剣の鍔にも金銀が光る。
きっと敵を見据えた横顔は、鼻筋通り、白皙の美顔だが、白い頬は紅潮し、口は荒い息に喘ぎ、灰色の目には怯えの色があった。出で立ちは立派だが、こういう荒事には慣れていないと見える。
続いて森影から二人の男が後退って現れ、灰色の瞳の剣士を背後に匿うようにして、剣を構えた。一人は消し炭色の革鎧に灰色の引き回し、手に持つ大振りの長剣は血に塗れている。疎らに髭の生えた日焼けした顔は精悍で、それなりに場数を踏んでいるようだ。もう一人は暗い紅色の革鎧に身を包んだ痩身の男で、細身の長剣の切っ先はやはり血に染まっていたが、股のあたりに滴る赤い滴は剣先からのものではなく、自身の傷口から流れるものだった。この男も、目鼻立ちのくっきりとした美顔だった。
奇妙に静かな足音が三人を追い、取り囲んだ。ほとんど黒に近い緑色の装束が目だけを残して顔まで覆っている。足音を消す軟らかい短沓、手にする剣は短剣と長剣の間ぐらいの長さのもので、柄はおろか、刀身までも艶のない黒に塗られていた。人数は八人。一人だけ、額に細い弦月の印をつけた革鉢巻をしている。この男が首領なのだろう。道の奥には、二人が血を流して倒れていた。
私はこの手の男たちを知っていた。戦乱に明け暮れる東部で、間諜、暗殺、誘拐などに従事する男たちだ。〈影の刃〉などと呼ばれるが、蔑みも含んで〈影の犬〉などと言われることもある。西岸諸都市で暗躍することのある暗殺士とはまた異なる、戦が生み出した闇の男たちだった。
戦は途絶え、交易で繁栄するメルカー西岸では見ることはないものと思っていたが、クァロニアン戦役の頃の一族がまだ生き残っていたのだろうか。
「貴様ら、メッテルジーグの手の者だな! 一人残らず成敗してくれる!」
消し炭色の革鎧の剣士が硬い声を発した。だが、敵方からは何の応えもなかった。無言のまま、ただじりじりと間合いを詰める。
「卑怯者め! 名乗ることもできぬのか!」
青い引き回しの美剣士が、甲高い声を浴びせたが、そんな挑発に動ずる者たちではなかった。
私はぶらりぶらりと闘いの場に近づいた。左手は腰に添えたが、まだ剣を抜くには早いだろう。双方が私に気づき、こちらに素早い目線を送る。
「おやおや、街道の真ん中で斬り合いかね。無粋な場面に出くわしたものだ」
私はいい加減な台詞をはいてみたが、誰も喜んではくれなかった。どちらにとっても私は邪魔者らしい。
「命が惜しくば立ち去れ!」
革鉢巻の首領らしき男が押し殺した声でそう言った。頭巾の中からわずかにのぞく氷のように冷たい目が、わずかに動いた。
私に一番近いところにいた黒装束の男がやにわに振り向き、剣を突き入れてきた。私は身を反らして黒い刃を避け、ファバーン剣を抜いた。
「気が短いな。通り過ぎた後で、後ろからばっさりかと思ったよ」
私が台詞を最後まで言い終わらぬうちに、その場にいた全員が動き出し、激しい剣戟が始まった。
私に剣を振るった男は、二の太刀、三の太刀を凄まじい速さで打ち込んできた。私は身を左右に振って刃をかわし、わずかに奴が踏み込み過ぎたのを見て、胴を払った。黒衣の下には鎖帷子の手応えがあったが、ファバーン剣は尋常ではない強さで、その鎧を斬り裂いた。腹から血を噴き出して、奴は頽れた。
休む間もなく次の敵が斬りかかってくる。仲間の死に動揺などしないのは当然のことだったが、少しだけ慎重に刃を突き入れてきた。短めの刀身が矢継ぎ早に繰り出されたが、私はことごとく跳ね除け、一瞬の隙をついて剣先を奴の脇腹に突き刺した。呻き声とともに血を吐いて、二番目の敵は死んだ。
見れば、灰色革の鎧の剣士は相当の手練、優男と傷ついた男をかばって、すでに彼のまわりには二人の黒衣の戦士が屍を晒していた。
残りの四人が三人を取り囲み、じわじわと間合いを詰める。どうやら黒衣の男たちの目当ては藍の衣装に身を包んだ美男らしい。しかも生きて捉えようとしているのだ。殺すだけなら飛び道具を斉射するなど、幾らでも手段を知っているはずの奴らだ。
つまりそれは奴らに弱みがあるということだった。三人の斜め後ろから迫ろうとした黒衣の戦士は、私にも気を取られて半身の構えを示したが、そんな半端な構えを放っておくほど私は慈悲深くはない。奴の目が流血の剣士に一瞬泳いだ隙に、私は引き回しの影に仕込んだ手裏剣を投げつけた。半イート(約十五センチ)ほどの小刀が奴の首筋に突き刺さった。覆面の下からのぞいた血走った目が、信じられないという表情で、首筋に突き立っている刃を見た。奴はそのまま倒れて動かなくなった。
その間に別の黒衣の男と灰革鎧の剣士は刃を交わし、互いの血で自らの剣をぬめらせようとしていた。
もう一人の黒衣の男は、傷ついた紅い鎧の剣士に斬りかかった。紅色鎧の痩身の剣士は、血を滴らせながら、必死の形相で黒衣の男の刃を打ち返し、藍色の服の男を守ろうとした。
紅色鎧の男は、自らの血を振りまきながら、黒衣の男に一撃を与えたが、その間に相手の剣も紅い胸甲を斬り裂いた。どちらも致命傷ではないようだったが、次の一手で赤い鎧の男が倒れるのは明らかだった。
藍色の服の男は、高価そうな剣を手にした構えはしっかりとしたもので、何とか一矢報いようという意志は感じられたが、間合いを計りかねていた。刃を生身の血肉に浸したことはないのだろう。
私は黒衣の男が紅い鎧の男の腹に剣先を突き入れようとした刹那、間に割って入り、短い剣を打ち払った。藍色の服の男が、引きつった声を上げて、黒衣の男に斬りかかったが、紅い鎧の男はそれを遮るように身を投じ、自らの刃を敵に突き刺そうとした。
だが、それより一瞬早く、ファバーン剣の鉛色の刃が、黒衣の男の首を打ち刎ねた。噴泉のように真っ赤な血潮を噴き上げて、男は頽れた。
その間に、消し炭色の鎧の男の前には、もう一人の敵が血まみれの骸となって横たわっていた。
闘いは終わった。一人残った新月の印をつけた首領らしき男は、舌打の響きを残して、猿のような素早さで森の中へと姿を消した。街道の土は血を吸ってどす黒く汚れ、その上に九つの黒装束の死骸が無残に転がっていた。
「かたじけない。貴殿の加勢で命を救われた。追って相応の礼はするつもりだが、ひとまずはこれで我らの謝意を受けていただきたい」
まだ息も整っていないというのに、灰色革の鎧の剣士は、腰の巾着から何枚ものダズン金貨を取り出して、私に差し出した。
「これは加勢の礼であるとともに、ここで起きたことを誰にも漏らさぬことへの礼でもある。心して受け取られよ」
灰革鎧の男は、やけに大層ぶった台詞を口にした。口止め料込みで百ダズンなら、それは結構な仕事と言えるだろう。有無を言わさぬ気配で、男は私の手の中に金を押し込むと、すぐに背を向けて立ち去ろうとした。
「お名前をお聞かせください。追って礼をするにも、お名前をお聞かせください」
紅い鎧の剣士の傷の手当てをしていた藍色の服の美男が、こちらを向いて声を発した。煙るような灰色の瞳に長い睫毛が影を落とした憂い顔は、ガルニエ座あたりの舞台に立てば、たちまち取り巻きが何十人もできるだろう。
「人に名を尋ねるのなら、まずは自分が名乗るもんじゃないのかね。まあ、そうは行かない事情があるんだろうがね」
私は手の中の金貨を日にかざしてみた。金色の輝きは、偽物とは思えなかった。消し炭色の革鎧の男が一瞬鋭い視線を送ったが、それを無視して藍色の服の男は答えた。
「私は、コルザ、コルザ・アルジェーンです。故あって、今はそれ以上のことを明かすことはできませんが、このお礼はきっといたします」
「スナブ・ランケン、サンジェリィはクーリカフ街の探偵だ」
コルザと名乗った男は、私の名を聞いて一瞬はっとしたような表情を見せたが、すぐに憂愁の中にそれを隠して、もう一度丁重な礼を言い、立ち去った。
私はしばらく三人の後ろ姿を見送った。彼らの馬はとうにどこかに逃げ去っていた。先を急ぐ体だったが、手負いの紅い鎧の男を抱えていては、そう早足というわけにはいかないようだった。
森の中の道には、九つの〈影の刃〉の死骸が残された。青翠街道のこのあたりに、巡察使が回ってくることなど滅多にあるはずはなかったが、他の旅人に出会っても面倒ごとになりそうだった。三人の後ろ姿を遠くに見ながら、私はゆっくりとした歩調で歩き出した。
高い空の上で、黒い大鳥が鋭い鳴き声をあげた。
そのとき私は、灰緑の薄手の外套を羽織って、サンジェリィから北西に延びる青翠街道を旅していた。
サンジェリィと並ぶ大都フランジースコとの間を最短距離で結ぶ黄金街道は、引っ切りなしに隊商が行き交い、蹄の音、車輪の軋む音、絶えることはない。街道沿いの宿駅では、宿の呼び込み、物売りの声、女の嬌声、男の怒声などですこぶる賑やかだが、道筋の光景は、砂塵の舞う荒れた黄色い大地が広がり、殺風景という他はない。
そこへ行くと青翠街道は、サンジェリィ北西に広がる森林に覆われた湖水地方を通り、場所によっては西の大洋も見ることのできる風光明媚な道だった。
私はその緑濃い街道を歩いていた。左右には常緑の森が迫っているが、ところどころには黄と赤に色づいた木々が葉叢を広げ、美しい天然の絵画を描き出していた。青く澄んだ空は高く、白い筋雲の合間を大きな黒い猛禽が輪を描いて飛んでいた。
私は滅多に得られない心の平安を感じて、晩秋の心地よい冷気を吸い込んだ。
だが、安寧は一瞬にして破られた。行く手の街道が右に曲がった森影から、白刃交える金音と裂帛の気合い、怯えた馬の嘶きが聞こえてきた。
私は腰間のファバーン剣に手をやった。三千年前海中に没した国の魔剣は、歳月の内にほとんどの力を失っていたが、妖気を感じて持ち主に知らせる力はまだ残っていた。だが、異界のものや妖術の存在を示す、しびれにも似た感覚は伝わってはこなかった。
どうやら人間同士の争いのようだった。私はうんざりとした気持ちで、足を速めるでもなく道を進んだ。
道が折れた木陰から、ざざっと靴底をすらせる音をたてて、一人の小柄な剣士が姿を見せた。藍色の地味な上下にくすんだ青い引き回しだが、長沓や腰帯、籠手には金細工の飾り物、細身の長剣の鍔にも金銀が光る。
きっと敵を見据えた横顔は、鼻筋通り、白皙の美顔だが、白い頬は紅潮し、口は荒い息に喘ぎ、灰色の目には怯えの色があった。出で立ちは立派だが、こういう荒事には慣れていないと見える。
続いて森影から二人の男が後退って現れ、灰色の瞳の剣士を背後に匿うようにして、剣を構えた。一人は消し炭色の革鎧に灰色の引き回し、手に持つ大振りの長剣は血に塗れている。疎らに髭の生えた日焼けした顔は精悍で、それなりに場数を踏んでいるようだ。もう一人は暗い紅色の革鎧に身を包んだ痩身の男で、細身の長剣の切っ先はやはり血に染まっていたが、股のあたりに滴る赤い滴は剣先からのものではなく、自身の傷口から流れるものだった。この男も、目鼻立ちのくっきりとした美顔だった。
奇妙に静かな足音が三人を追い、取り囲んだ。ほとんど黒に近い緑色の装束が目だけを残して顔まで覆っている。足音を消す軟らかい短沓、手にする剣は短剣と長剣の間ぐらいの長さのもので、柄はおろか、刀身までも艶のない黒に塗られていた。人数は八人。一人だけ、額に細い弦月の印をつけた革鉢巻をしている。この男が首領なのだろう。道の奥には、二人が血を流して倒れていた。
私はこの手の男たちを知っていた。戦乱に明け暮れる東部で、間諜、暗殺、誘拐などに従事する男たちだ。〈影の刃〉などと呼ばれるが、蔑みも含んで〈影の犬〉などと言われることもある。西岸諸都市で暗躍することのある暗殺士とはまた異なる、戦が生み出した闇の男たちだった。
戦は途絶え、交易で繁栄するメルカー西岸では見ることはないものと思っていたが、クァロニアン戦役の頃の一族がまだ生き残っていたのだろうか。
「貴様ら、メッテルジーグの手の者だな! 一人残らず成敗してくれる!」
消し炭色の革鎧の剣士が硬い声を発した。だが、敵方からは何の応えもなかった。無言のまま、ただじりじりと間合いを詰める。
「卑怯者め! 名乗ることもできぬのか!」
青い引き回しの美剣士が、甲高い声を浴びせたが、そんな挑発に動ずる者たちではなかった。
私はぶらりぶらりと闘いの場に近づいた。左手は腰に添えたが、まだ剣を抜くには早いだろう。双方が私に気づき、こちらに素早い目線を送る。
「おやおや、街道の真ん中で斬り合いかね。無粋な場面に出くわしたものだ」
私はいい加減な台詞をはいてみたが、誰も喜んではくれなかった。どちらにとっても私は邪魔者らしい。
「命が惜しくば立ち去れ!」
革鉢巻の首領らしき男が押し殺した声でそう言った。頭巾の中からわずかにのぞく氷のように冷たい目が、わずかに動いた。
私に一番近いところにいた黒装束の男がやにわに振り向き、剣を突き入れてきた。私は身を反らして黒い刃を避け、ファバーン剣を抜いた。
「気が短いな。通り過ぎた後で、後ろからばっさりかと思ったよ」
私が台詞を最後まで言い終わらぬうちに、その場にいた全員が動き出し、激しい剣戟が始まった。
私に剣を振るった男は、二の太刀、三の太刀を凄まじい速さで打ち込んできた。私は身を左右に振って刃をかわし、わずかに奴が踏み込み過ぎたのを見て、胴を払った。黒衣の下には鎖帷子の手応えがあったが、ファバーン剣は尋常ではない強さで、その鎧を斬り裂いた。腹から血を噴き出して、奴は頽れた。
休む間もなく次の敵が斬りかかってくる。仲間の死に動揺などしないのは当然のことだったが、少しだけ慎重に刃を突き入れてきた。短めの刀身が矢継ぎ早に繰り出されたが、私はことごとく跳ね除け、一瞬の隙をついて剣先を奴の脇腹に突き刺した。呻き声とともに血を吐いて、二番目の敵は死んだ。
見れば、灰色革の鎧の剣士は相当の手練、優男と傷ついた男をかばって、すでに彼のまわりには二人の黒衣の戦士が屍を晒していた。
残りの四人が三人を取り囲み、じわじわと間合いを詰める。どうやら黒衣の男たちの目当ては藍の衣装に身を包んだ美男らしい。しかも生きて捉えようとしているのだ。殺すだけなら飛び道具を斉射するなど、幾らでも手段を知っているはずの奴らだ。
つまりそれは奴らに弱みがあるということだった。三人の斜め後ろから迫ろうとした黒衣の戦士は、私にも気を取られて半身の構えを示したが、そんな半端な構えを放っておくほど私は慈悲深くはない。奴の目が流血の剣士に一瞬泳いだ隙に、私は引き回しの影に仕込んだ手裏剣を投げつけた。半イート(約十五センチ)ほどの小刀が奴の首筋に突き刺さった。覆面の下からのぞいた血走った目が、信じられないという表情で、首筋に突き立っている刃を見た。奴はそのまま倒れて動かなくなった。
その間に別の黒衣の男と灰革鎧の剣士は刃を交わし、互いの血で自らの剣をぬめらせようとしていた。
もう一人の黒衣の男は、傷ついた紅い鎧の剣士に斬りかかった。紅色鎧の痩身の剣士は、血を滴らせながら、必死の形相で黒衣の男の刃を打ち返し、藍色の服の男を守ろうとした。
紅色鎧の男は、自らの血を振りまきながら、黒衣の男に一撃を与えたが、その間に相手の剣も紅い胸甲を斬り裂いた。どちらも致命傷ではないようだったが、次の一手で赤い鎧の男が倒れるのは明らかだった。
藍色の服の男は、高価そうな剣を手にした構えはしっかりとしたもので、何とか一矢報いようという意志は感じられたが、間合いを計りかねていた。刃を生身の血肉に浸したことはないのだろう。
私は黒衣の男が紅い鎧の男の腹に剣先を突き入れようとした刹那、間に割って入り、短い剣を打ち払った。藍色の服の男が、引きつった声を上げて、黒衣の男に斬りかかったが、紅い鎧の男はそれを遮るように身を投じ、自らの刃を敵に突き刺そうとした。
だが、それより一瞬早く、ファバーン剣の鉛色の刃が、黒衣の男の首を打ち刎ねた。噴泉のように真っ赤な血潮を噴き上げて、男は頽れた。
その間に、消し炭色の鎧の男の前には、もう一人の敵が血まみれの骸となって横たわっていた。
闘いは終わった。一人残った新月の印をつけた首領らしき男は、舌打の響きを残して、猿のような素早さで森の中へと姿を消した。街道の土は血を吸ってどす黒く汚れ、その上に九つの黒装束の死骸が無残に転がっていた。
「かたじけない。貴殿の加勢で命を救われた。追って相応の礼はするつもりだが、ひとまずはこれで我らの謝意を受けていただきたい」
まだ息も整っていないというのに、灰色革の鎧の剣士は、腰の巾着から何枚ものダズン金貨を取り出して、私に差し出した。
「これは加勢の礼であるとともに、ここで起きたことを誰にも漏らさぬことへの礼でもある。心して受け取られよ」
灰革鎧の男は、やけに大層ぶった台詞を口にした。口止め料込みで百ダズンなら、それは結構な仕事と言えるだろう。有無を言わさぬ気配で、男は私の手の中に金を押し込むと、すぐに背を向けて立ち去ろうとした。
「お名前をお聞かせください。追って礼をするにも、お名前をお聞かせください」
紅い鎧の剣士の傷の手当てをしていた藍色の服の美男が、こちらを向いて声を発した。煙るような灰色の瞳に長い睫毛が影を落とした憂い顔は、ガルニエ座あたりの舞台に立てば、たちまち取り巻きが何十人もできるだろう。
「人に名を尋ねるのなら、まずは自分が名乗るもんじゃないのかね。まあ、そうは行かない事情があるんだろうがね」
私は手の中の金貨を日にかざしてみた。金色の輝きは、偽物とは思えなかった。消し炭色の革鎧の男が一瞬鋭い視線を送ったが、それを無視して藍色の服の男は答えた。
「私は、コルザ、コルザ・アルジェーンです。故あって、今はそれ以上のことを明かすことはできませんが、このお礼はきっといたします」
「スナブ・ランケン、サンジェリィはクーリカフ街の探偵だ」
コルザと名乗った男は、私の名を聞いて一瞬はっとしたような表情を見せたが、すぐに憂愁の中にそれを隠して、もう一度丁重な礼を言い、立ち去った。
私はしばらく三人の後ろ姿を見送った。彼らの馬はとうにどこかに逃げ去っていた。先を急ぐ体だったが、手負いの紅い鎧の男を抱えていては、そう早足というわけにはいかないようだった。
森の中の道には、九つの〈影の刃〉の死骸が残された。青翠街道のこのあたりに、巡察使が回ってくることなど滅多にあるはずはなかったが、他の旅人に出会っても面倒ごとになりそうだった。三人の後ろ姿を遠くに見ながら、私はゆっくりとした歩調で歩き出した。
高い空の上で、黒い大鳥が鋭い鳴き声をあげた。
