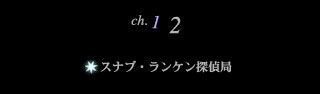機械時計の音が真夜中を告げた。雛形の歪んだ鐘の音が、静まり返った広い邸内に鳴り響いた。
膝の上に置いたファバーン剣は鯉口を切り、わずかに刀身を覗かせてある。佶屈怪異な古代の神秘文字はまだ鉛色のまま、魔道の力が働いている証の燐光はない。柄を握った右手にも、痺れるような感覚は伝わってこない。
私はジャンバール邸の一室に座っていた。広い部屋の中には、ル・コッブ・ジャンバール氏が長年にわたって財を投じてきた蒐集品が飾られている。南部アニャチ風、あるいはマゼスタンらしき数々の焼き物、東部の職人の手になる精緻な細工が施された甲冑や刀剣、無数の燭光を浴びて煌めく、貴石、宝石、金銀をちりばめた首飾りや宝冠等々。
私が背にしている硝子張りの大きな箱の中には、その宝物の中でも最も価値ある大物が収まっていた。
〈レイスキンの宝冠〉と呼ばれるその冠は、黄金のごつい頭環に、大振りの紅玉、翠玉、黄玉、青玉をちりばめ、真ん中には指先ほどもある金剛石を配した代物だった。最悪の成金趣味ということもできるが、宝石の数と大きさを考えれば、その価値は瞭然だ。
だが、この冠の価値はそこだけにあるわけではなかった。金剛石は陽光を表す十六本の黄金の光の矢に囲まれている。この宝冠の元の持ち主、サメグル・レイスキンはクァロニアン帝国最後の皇后なのだ。
クァロニアン帝国は、二百年の昔メルカー西岸一帯を支配していた。強大な軍隊と暗黒の魔術、そして残虐な暴政と世界帝国への野望で人々の心を支配した。私が探偵業を営むこの街、サンジェリィはクァロニアン帝国の都であり、市民は暫しの年月、全世界を制する世界帝国、世界皇帝プラジナーオ誕生の夢に酔った。
だが、帝国は東部諸国との戦に疲弊し、各地で圧制に反乱が起こった。わずか数十年で数多の犠牲を残して幻のような帝国は滅んだ。三代皇帝サメグル・ジョジヴークとその妃レイスキンは、暴政に怒り狂った市民に処刑され、死体は凱旋広場で晒し者にされた。
賊はその帝国最後の皇后の宝冠を盗み取ると書状を送り付けてきた。いや、盗み取るとはそこには書かれていなかった。「取り返す」と書かれていた。書状の署名は〈クァロニアン党〉とあり、十六の光条を持つ日輪の紋章が刻印されていた。
「ランケン君、真夜中を過ぎたぞ。本当にクァロニアン党は現れるのかね」
ル・コッブ・ジャンバール氏は灰色の口髭を震わせていた。大きな両耳の後ろにだけ、髭と同様の強ばった灰色の髪が残っている。近ごろの流行りに合わせて眉毛は抜いて、薄紫で描いており、どうやらそれはこの緋色に金糸銀糸の紐飾りのついた上衣と揃えたものらしかったが、私には落ちぶれた道化役者のように見えて仕方なかった。
部屋に飾られた数々の宝物は命よりも大切なものだ、と彼は語っていたが、そんなことはまるきり嘘っぱちだった。この部屋にある物は彼の財産のごく一部だし、この男に自分の命より大切なものがあるとは思えない。勿論、私もそうだが。
「ランケン君、奴らは本当にこの宝冠が狙いなのか。ならば譲ってやっても良いのだが……無論、対価の交渉は必要だが……」
「お静かに。金で片が付くことなら最初から奴らはそうしていたでしょう。そうはいかないから、僕を雇う理由ができた」
ジャンバール氏は不安と苛立ちで、髭だけでなく、緋色の高価な衣装の下のでっぷりした腹まで震わせ始めた。
「それはそうだが、ランケン君、私は……」
「お静かに。奴らはどんな方法で侵入してくるか、わかりません。あなたの両脇を固めているそのお二人は、腕が立つのでしょう。何も心配はいりませんよ、多分ね」
ジャンバール氏が座っている、ふっくらとした繻子の椅子の両隣には、頬のこけた男が一人ずつ立っていた。黒ずくめの地味な服を着た二人は兄弟でもなかろうに、よく似た顔立ちをしていた。誰でもない、目立たない顔立ち。暗殺士組合の者には有りがちな、特徴がないという特徴だ。
資産家は私の皮肉に不愉快そうな表情を見せたが、両隣の二人組が黙って頷いたのを見て、自分も口をつぐんだ。
機械時計の刻む規則的な音だけが部屋の中に響いた。精緻な歯車と振り子と発条が発する小さな音が、豪奢な邸宅の中にひりひりとした気持ちの昂ぶりを作り出していた。
クァロニアン党は刻限まで予告していたわけではなかった。「真夜中に」と書状の文言にあったからといって、彼らを約定を守らないと責めるわけには行かない。
ファバーン剣を握った掌に、むず痒いような幽かな感覚が伝わってきた。機械時計の音に、何か別の金物の軋むような音が加わったような気がした。
私は二人の暗殺士−今日は命を守る役目だが−に目顔で合図を送った。魔剣は持っていなくても、彼らも何かの気配を感じた様子だった。
邸宅の内外には多くの衛士が置かれ、誰もこの館に入り込むことはできないはずだった。
軋む音が急に高まった。しばらく動いていなかった蝶番が無理に動かされたような音が響き渡った。
私も暗殺士も部屋の中を見回した。どこにも侵入者の姿はない。だが、異変は起こっていた。
甲冑が動いていた。壁際に木の支え棒で立ち姿になっていた甲冑が、二体いや三体、耳障りな軋みをたてながらゆっくりと動き始めていた。
三人の剣が鞘走るのと、三体の甲冑が剣を振り上げたのは、同時だった。ファバーン剣の神秘文字は緑色の光を放っていた。
奇怪な剣戟が始まった。耳障りな音を立てながらがらんどうの腕が振り回され、古びた重い剣が斬りかかってくる。
二人の暗殺士は針のように細い剣を、目にも留まらぬ速さで動かし、甲冑に攻撃を加えた。相手が生身の人間なら、必殺の突きが鎧の隙間を突き刺し、瞬時に勝負は決していたかもしれない。しかし、鋼の鎧の下には、柔らかい肉はなかった。鎧の中には、何もなかった。
一人が突き入れた切っ先は、そのまま鎧の裏側にあたり、甲高い音を立てた。肉体無き騎士が体をひねると、細身の剣は脆くも折れてしまった。もう一人の剣は弓のように反り返り、反動で弾き飛ばされた。
暗殺士たちは、驚きを抑えて、すぐさま反り身の剣を抜いた。接近戦用に刀身は短い。大振りしてくる主なき鎧の長剣をかいくぐり、攻撃を加える。
私に襲いかかってきた甲冑は他の二体とは、いささか意匠が異なっていた。全身が真っ赤に塗られ、胴鎧の真ん中には金色に輝く日輪の紋章が打ち出されている。これは東部の鎧職人の手になるものではなく、クァロニアン帝国の遺物だった。
広刃の長剣と古代の魔剣が刃を交えると、火花が飛び散り、ファバーン文字が幽鬼のような緑の光を放った。
甲冑の動きはぎくしゃくとした操り人形のようだった。素早い動きや格別の剣技があるわけではない。だが、鎧の隙間に刃を突き刺しても、死ぬことはないのだ。
肩当てに食い込んだファバーン剣を抜かずにそのまま押し倒そうとすると、目庇が揺れて兜の中が覗いた。殺意に満ちた目がそこにあることを、私は半ば期待した。だが、何もない。兜の中はやはり空っぽだった。
赤い鎧の騎士は、手脚の関節をあり得ない角度に曲げながら倒れた。長剣が宝冠の硝子箱に当たり、派手な音を立てて硝子が砕け散った。恐怖の余り声も出なかったらしいジャンバール氏の笛の音のような悲鳴が聞こえた。
私は倒れた甲冑の膝に剣を打ち込んだ。留め金と革帯がちぎれて外れた臑当てを蹴飛ばした。体のない騎士は立ち上がろうともがくが、磨き上げられた床石に傷を付けるだけだった。
他の二体の甲冑も、暗殺士たちの攻撃で手や足をもがれて戦えない状態になっていた。
騒ぎを聞きつけて、数名の衛士が抜き身を下げて屋敷の中から駆けつけてきた。床に散らばる甲冑を見て、驚きの表情を見せる。
「お前たち、何をしていた!儂の命が奪われたら、お前たちの家族の命もないものと思え!」
ジャンバール氏はとりあえず衛士たちを怒鳴りつけてから、蒼白な顔に脂汗を滲ませて震える声で言った。
「ランケン君、これは、これはいったいどういうことなんだ」
「敵方には魔道士がいるということです。僕を雇うよりも、トリプロ街で魔道士を探したほうが良かったかも知れません。それから、まだ事が終わったとは限りません。あなたの蒐集品はまだ動いている」
富豪はひいっという声を上げて、床の上で蠢いている鋼鉄の骸から後退った。がらんどうの鎧の中から、何かが流れ出していた。それは幽かな陽炎のような揺らめきに見えた。もがれた手足から、鎧の継ぎ目から、何か揺らめくものが流れ出している。それは次第に白い霞のようなものとなり、床の上をゆっくりと広がっていった。
やがて甲冑は動きを止め、白い霞は中庭に面した大扉の方へ集まっていった。霞は這いうねり、無数の蛇のように絡まりあい、膝ほどの高さまでが乳色の海のようになった。その向こうから声が聞こえてきた。
「帝国の至宝を私する者よ、己が罪の深さに恐れおののくが良い」
英雄的とも言えるような良く響く朗々たる声だった。月が昇ったのか、大扉の硝子窓からは青白い光が差してくる。乳色の霧と青白い光の向こうから、その声は聞こえてくる。
「おまえはその蓄えた財を如何なる目的に使ったのか。この国この都の弥栄を願って用いたか」
声はジャンバール氏の財宝を集めた部屋の中に響き渡った。彼がそのような目的でこの部屋を作ったはずはない。サンジェリィ有数の金満家は、恐怖の頂点から突然小勇に駆られたようだった。
「ふざけるな!誰が国のため都のためを思って財を成すと思うか!儂は儂のため、この自分のためだけに、財を成したのだ!腐れ役人や暗愚な貴族王族など、儂の財に触れる資格などありやしない!増してや、貴様らのような面の皮の厚い盗人に渡す物など、この屋敷には塵一つない!」
ジャンバール氏は灰色の口髭に泡を吹き出しながら、一気にわめきたてた。どれ程の嘘偽りを積み重ねてこれだけの財を築いたのかわかりはしないが、今の彼の台詞はきっと真実の声なのだろう。
霧の中の声は、喉の奥でたてるような詰まった嘲笑で答えた。威厳さえ感じさせた先ほどの声とは別人のような、下卑た感じのする嫌な笑い声だった。
「国あってこそ生かされることを解せぬ下賎の輩よ、帝国の光輝を知らぬ不敬の男よ、クァロニアン帝国の威光をその命と引き換えに知るが良い!」
今度の声は、まるで地獄の奥底につながっている井戸から立ち上ってきたかのような、底知れぬ暗さと無慈悲な暴力をみなぎらせていた。
掛け金の外れる音がして、中庭側の大扉が開いた。霞が庭に流れ出し、渦巻き、立ち上り、その中から人影が現れた。
鎧兜に身を固めた男たちが影絵のように十人ほど並んでいる。古風な兜は耳の辺りまでを覆い、端がわずかに跳ね上がっている。胸と胴を覆う革鎧には鉄色の菱形の札が並び、真ん中には十六の矢を持つ日輪の紋章があった。兜の頂には短い角、反り身のがっしりした剣を手にしている。朽ちた史書から抜け出てきたかのような、〈帝国〉の兵士たちだった。兜の下の顔は、灰色がかった枯草色の覆面で覆っており、血走った双眼しか見えない。
兵士たちの先頭には、異なる出立ちの姿があった。暗い灰色の頭巾付きの長衣をまとっている。長衣には袖や裾周りに深紅の蛇腹の線が走り、左胸に金糸で帝国の紋章の縫い取りがある。頭巾が深く顔に影を落とし、容貌は見て取れない。だが、黒い影の中に熾火のように輝く深紅の瞳は、尋常な人間のものとは到底思えなかった。
「こいつらを殺せ!殺せ!一人残らず殺せ!」
品の良い趣味人として社交界で知られているジャンバール氏は、時々裏返る引きつった声で叫んだ。
二人の暗殺士が音もなく前へ出た。異様な敵の出現にも顔色一つ変えないのは、流石というべきなのだろうか。衛士たちは恐る恐るといった足つきで、少しずつ間合いを詰める。
「帝国の敵に天誅を加えよ!」
赤い目の男が恐ろしい声で命を下した。白い霞をかき乱して〈帝国〉の兵士たちが斬りかかってきた。
ジャンバール氏自慢の宝の部屋は、たちまちのうちに血みどろの戦場と化した。帝国兵たちの動きは、主なき甲冑とは違って手練れの剣士のものだった。無駄のない静かな動きの中に必殺の気迫を込めて、鋭い剣先を繰り出してくる。衛士たちは、あっという間に一人が腕を失い、もう一人は足を失った。鮮血を噴き出してのたうち回り、鏡のような敷石を汚していく様は、立ち上がれずにもがいていた甲冑の意地悪な戯画のようだった。
だが、暗殺士たちはそうはいかなかった。舞踏のような巧みな動きで兵士たちの長剣をかわし、懐に飛び込むと鋭い一撃を鎧の隙間に叩き込んだ。
今度は切っ先が空を斬ることはなかった。血飛沫を上げて、一人の兵士が倒れ伏した。古代の亡霊のような兵士たちも傷つき血を流す存在なのだ。
残った数人の衛士たちは、おおっという短い声を上げて、新たな勢いで帝国の兵士たちに襲いかかった。白刃がぶつかり合う鋭い音、肉を斬る鈍い音、噴き出す鮮血の飛沫の音、呻くような怒声と悲鳴が谺した。
私はただ剣を振るい、目の前の敵を屠ることに集中した。ファバーン剣の神秘文字は、甲冑が倒された後も緑色の光を放ち、何らかの魔法の力がこの場に働いていることを示している。
ファバーン文字が刻まれた刃が、一人の兵士の首筋に食い込んだ。兵は噴水のように血を噴いて倒れた。彼が倒れると同時に、その後ろからもう一人の兵士が立ち上がった。脇の傷口からどす黒い血が流れ落ちている。つい先刻、暗殺士が倒したはずの兵士だ。
死んだはずの兵士は異様に体を震わせながら、剣を振り回した。覆面に覆われた顔から覗く両眼は、奇怪な赤い光を放っていた。
言葉にならない声を発して、彼は斬りかかってきた。覆面の口の辺りには、泡でも吹いているのだろうか、染みが浮かび、顎からはよだれが滴り落ちている。
肩口に降り下ろされた奴の剣を受け止め、跳ね返そうとしたが、予想外の力に私は後退った。赤い目が光る男の背後に、首筋から血を流しながら、立ち上がるもう一人の死人の姿が見えた。古代の魔剣の神秘文字がひときわ鮮やかな緑の光を放っていた。
私は恐怖に囚われそうな心を何とか押さえつけ、死んだはずの兵士に刃を突き刺した。革鎧を突き通して、背中まで剣先が突き抜けた。覆面の染みはどす黒い血の染みへと変わった。剣を引き抜こうとしたはずみに奴は私の方へ倒れかかってきた。そのすぐ後ろから、首筋に大きな傷口を開けた男が剣を振り下ろしてきた。
反り身の剣が私の肩先に触れようかという刹那、鈍い音がして奴は動きを止めた。もう一人と折り重なるように倒れた奴の背中には大振りの卍手裏剣が突き刺さっていた。
見遣ると、中庭から新手の剣士が戦いに加わっていた。細身の体を白銀と紫の鎧に包んだ剣士が、銀の柄に紫の房飾りの剣を振るい、帝国兵を斬り刻んでいた。磨き上げられた銀の兜の頂からは、馬の尾のような長い黒髪が流れ出し、白刃と血飛沫と呼応するように死の舞踏を踊っている。銀の兜には面頬はなく、紫の覆面がその顔を隠している。わずかに覗いた切れ長の黒い双眸は、役者絵から切り抜いたかのような美しさで、同時に鉄のような眼力をも放っていた。
〈白銀と紫衣の剣士〉と私は初めて遭遇したのだ。この三月ばかり、サンジェリィの酒場は彼の話題で持ちきりだった。夜の闇に紛れて姿を現し、盗賊、暴漢、あるいは権力を笠に着て無理難題を押し付ける貴族や金持ちに血の制裁を下す「正義」の剣士。誰もその正体は知らず、警邏隊も捕らえることはできなかった。その謎の剣士が、今、目の前で剣を振るっているのだ。
〈白銀と紫衣の剣士〉は、流麗な剣捌きで次々に帝国の兵たちを倒していった。戦いの趨勢は明らかに変わり、クァロニアン党一味はじりじりと中庭の方へ押し戻されていった。“復活”した兵の動きは明らかに鈍く、主なき甲冑のようだった。二度、三度の斬撃で彼らは動かなくなった。
帝国兵の最後の一人を〈白銀と紫衣の剣士〉が斬り伏せた。起き上がる間も無く、剣士はそいつの首筋に刃を振り下ろし、二度と立ち上がれぬように止めを刺した。
灰色の頭巾を被った男はいつの間にか中庭の奥まで後退していた。彼の周囲には乳色の霞が渦を巻くように取り囲み、ゆるゆると回っていた。
私が小刀を投じるのも、〈白銀と紫衣の剣士〉が卍手裏剣を投げつけるのも、ほぼ同時だった。二つの刃は灰色頭巾の男を覆った霞の中でぶつかり合い、落下した。
霧の帳の中で赤い凶眼だけが光り、耳障りな笑い声が響いた。
「今宵はこれにて退散するとしよう。だが覚えておくがいい。我がクァロニアン党は帝国のすべてを取り戻す。帝国の威光にひれ伏さぬ輩は、一人残らず己の命と引き換えにその光輝を知ることとなるのだ。その日を心して待つが良い!」
霞が激しく渦巻き、朗とした、しかし底知れぬ嫌悪を引き起こす高笑いが響き渡った。霞は消え、中庭にはもはや誰もいなかった。
「ふざけるな!疾うに滅んだ帝国の威光など、誰が恐れるものか!儂の築いた財産は儂のものだ!気の狂れた魔術師風情に渡すものか!」
ジャンバール氏は、滅茶苦茶になった彼の宝物殿の中に座り込み、金切り声をあげていた。震える手には〈レイスキンの宝冠〉をしっかりと握りしめていた。とりあえずは、私も二人の暗殺士も、契約を果たすことができたようだった。
足下には幾人もの帝国の兵士がどす黒い血にまみれて倒れていた。私は剣先で恐る恐るその覆面を剥ぎ取った。現れたのは髑髏や木乃伊ではなく、取り敢えずは普通の人間の顔だった。だがその顔は、土気色というよりは青みを帯びた鉛色とでも言った方がいいのか、まっとうな人間とは思えない色合いだった。死人の顔は無数に見ているが、こんなにひどい顔色の死人はいない。落ちくぼんだ目の回りは、黒ずんだ赤紫色に変色し、その中に異様に赤い目が見開かれたままになっていた。
風を切る音がして振り向くと、中庭の木立の向こうに銀と紫の鎧姿が消えるところだった。しばしの間を置き、駆け去る蹄の音が聞こえた。〈白銀と紫衣の剣士〉は、私たちとは違って、今宵の働きの代価をジャンバール氏に求める気はないようだった。
膝の上に置いたファバーン剣は鯉口を切り、わずかに刀身を覗かせてある。佶屈怪異な古代の神秘文字はまだ鉛色のまま、魔道の力が働いている証の燐光はない。柄を握った右手にも、痺れるような感覚は伝わってこない。
私はジャンバール邸の一室に座っていた。広い部屋の中には、ル・コッブ・ジャンバール氏が長年にわたって財を投じてきた蒐集品が飾られている。南部アニャチ風、あるいはマゼスタンらしき数々の焼き物、東部の職人の手になる精緻な細工が施された甲冑や刀剣、無数の燭光を浴びて煌めく、貴石、宝石、金銀をちりばめた首飾りや宝冠等々。
私が背にしている硝子張りの大きな箱の中には、その宝物の中でも最も価値ある大物が収まっていた。
〈レイスキンの宝冠〉と呼ばれるその冠は、黄金のごつい頭環に、大振りの紅玉、翠玉、黄玉、青玉をちりばめ、真ん中には指先ほどもある金剛石を配した代物だった。最悪の成金趣味ということもできるが、宝石の数と大きさを考えれば、その価値は瞭然だ。
だが、この冠の価値はそこだけにあるわけではなかった。金剛石は陽光を表す十六本の黄金の光の矢に囲まれている。この宝冠の元の持ち主、サメグル・レイスキンはクァロニアン帝国最後の皇后なのだ。
クァロニアン帝国は、二百年の昔メルカー西岸一帯を支配していた。強大な軍隊と暗黒の魔術、そして残虐な暴政と世界帝国への野望で人々の心を支配した。私が探偵業を営むこの街、サンジェリィはクァロニアン帝国の都であり、市民は暫しの年月、全世界を制する世界帝国、世界皇帝プラジナーオ誕生の夢に酔った。
だが、帝国は東部諸国との戦に疲弊し、各地で圧制に反乱が起こった。わずか数十年で数多の犠牲を残して幻のような帝国は滅んだ。三代皇帝サメグル・ジョジヴークとその妃レイスキンは、暴政に怒り狂った市民に処刑され、死体は凱旋広場で晒し者にされた。
賊はその帝国最後の皇后の宝冠を盗み取ると書状を送り付けてきた。いや、盗み取るとはそこには書かれていなかった。「取り返す」と書かれていた。書状の署名は〈クァロニアン党〉とあり、十六の光条を持つ日輪の紋章が刻印されていた。
「ランケン君、真夜中を過ぎたぞ。本当にクァロニアン党は現れるのかね」
ル・コッブ・ジャンバール氏は灰色の口髭を震わせていた。大きな両耳の後ろにだけ、髭と同様の強ばった灰色の髪が残っている。近ごろの流行りに合わせて眉毛は抜いて、薄紫で描いており、どうやらそれはこの緋色に金糸銀糸の紐飾りのついた上衣と揃えたものらしかったが、私には落ちぶれた道化役者のように見えて仕方なかった。
部屋に飾られた数々の宝物は命よりも大切なものだ、と彼は語っていたが、そんなことはまるきり嘘っぱちだった。この部屋にある物は彼の財産のごく一部だし、この男に自分の命より大切なものがあるとは思えない。勿論、私もそうだが。
「ランケン君、奴らは本当にこの宝冠が狙いなのか。ならば譲ってやっても良いのだが……無論、対価の交渉は必要だが……」
「お静かに。金で片が付くことなら最初から奴らはそうしていたでしょう。そうはいかないから、僕を雇う理由ができた」
ジャンバール氏は不安と苛立ちで、髭だけでなく、緋色の高価な衣装の下のでっぷりした腹まで震わせ始めた。
「それはそうだが、ランケン君、私は……」
「お静かに。奴らはどんな方法で侵入してくるか、わかりません。あなたの両脇を固めているそのお二人は、腕が立つのでしょう。何も心配はいりませんよ、多分ね」
ジャンバール氏が座っている、ふっくらとした繻子の椅子の両隣には、頬のこけた男が一人ずつ立っていた。黒ずくめの地味な服を着た二人は兄弟でもなかろうに、よく似た顔立ちをしていた。誰でもない、目立たない顔立ち。暗殺士組合の者には有りがちな、特徴がないという特徴だ。
資産家は私の皮肉に不愉快そうな表情を見せたが、両隣の二人組が黙って頷いたのを見て、自分も口をつぐんだ。
機械時計の刻む規則的な音だけが部屋の中に響いた。精緻な歯車と振り子と発条が発する小さな音が、豪奢な邸宅の中にひりひりとした気持ちの昂ぶりを作り出していた。
クァロニアン党は刻限まで予告していたわけではなかった。「真夜中に」と書状の文言にあったからといって、彼らを約定を守らないと責めるわけには行かない。
ファバーン剣を握った掌に、むず痒いような幽かな感覚が伝わってきた。機械時計の音に、何か別の金物の軋むような音が加わったような気がした。
私は二人の暗殺士−今日は命を守る役目だが−に目顔で合図を送った。魔剣は持っていなくても、彼らも何かの気配を感じた様子だった。
邸宅の内外には多くの衛士が置かれ、誰もこの館に入り込むことはできないはずだった。
軋む音が急に高まった。しばらく動いていなかった蝶番が無理に動かされたような音が響き渡った。
私も暗殺士も部屋の中を見回した。どこにも侵入者の姿はない。だが、異変は起こっていた。
甲冑が動いていた。壁際に木の支え棒で立ち姿になっていた甲冑が、二体いや三体、耳障りな軋みをたてながらゆっくりと動き始めていた。
三人の剣が鞘走るのと、三体の甲冑が剣を振り上げたのは、同時だった。ファバーン剣の神秘文字は緑色の光を放っていた。
奇怪な剣戟が始まった。耳障りな音を立てながらがらんどうの腕が振り回され、古びた重い剣が斬りかかってくる。
二人の暗殺士は針のように細い剣を、目にも留まらぬ速さで動かし、甲冑に攻撃を加えた。相手が生身の人間なら、必殺の突きが鎧の隙間を突き刺し、瞬時に勝負は決していたかもしれない。しかし、鋼の鎧の下には、柔らかい肉はなかった。鎧の中には、何もなかった。
一人が突き入れた切っ先は、そのまま鎧の裏側にあたり、甲高い音を立てた。肉体無き騎士が体をひねると、細身の剣は脆くも折れてしまった。もう一人の剣は弓のように反り返り、反動で弾き飛ばされた。
暗殺士たちは、驚きを抑えて、すぐさま反り身の剣を抜いた。接近戦用に刀身は短い。大振りしてくる主なき鎧の長剣をかいくぐり、攻撃を加える。
私に襲いかかってきた甲冑は他の二体とは、いささか意匠が異なっていた。全身が真っ赤に塗られ、胴鎧の真ん中には金色に輝く日輪の紋章が打ち出されている。これは東部の鎧職人の手になるものではなく、クァロニアン帝国の遺物だった。
広刃の長剣と古代の魔剣が刃を交えると、火花が飛び散り、ファバーン文字が幽鬼のような緑の光を放った。
甲冑の動きはぎくしゃくとした操り人形のようだった。素早い動きや格別の剣技があるわけではない。だが、鎧の隙間に刃を突き刺しても、死ぬことはないのだ。
肩当てに食い込んだファバーン剣を抜かずにそのまま押し倒そうとすると、目庇が揺れて兜の中が覗いた。殺意に満ちた目がそこにあることを、私は半ば期待した。だが、何もない。兜の中はやはり空っぽだった。
赤い鎧の騎士は、手脚の関節をあり得ない角度に曲げながら倒れた。長剣が宝冠の硝子箱に当たり、派手な音を立てて硝子が砕け散った。恐怖の余り声も出なかったらしいジャンバール氏の笛の音のような悲鳴が聞こえた。
私は倒れた甲冑の膝に剣を打ち込んだ。留め金と革帯がちぎれて外れた臑当てを蹴飛ばした。体のない騎士は立ち上がろうともがくが、磨き上げられた床石に傷を付けるだけだった。
他の二体の甲冑も、暗殺士たちの攻撃で手や足をもがれて戦えない状態になっていた。
騒ぎを聞きつけて、数名の衛士が抜き身を下げて屋敷の中から駆けつけてきた。床に散らばる甲冑を見て、驚きの表情を見せる。
「お前たち、何をしていた!儂の命が奪われたら、お前たちの家族の命もないものと思え!」
ジャンバール氏はとりあえず衛士たちを怒鳴りつけてから、蒼白な顔に脂汗を滲ませて震える声で言った。
「ランケン君、これは、これはいったいどういうことなんだ」
「敵方には魔道士がいるということです。僕を雇うよりも、トリプロ街で魔道士を探したほうが良かったかも知れません。それから、まだ事が終わったとは限りません。あなたの蒐集品はまだ動いている」
富豪はひいっという声を上げて、床の上で蠢いている鋼鉄の骸から後退った。がらんどうの鎧の中から、何かが流れ出していた。それは幽かな陽炎のような揺らめきに見えた。もがれた手足から、鎧の継ぎ目から、何か揺らめくものが流れ出している。それは次第に白い霞のようなものとなり、床の上をゆっくりと広がっていった。
やがて甲冑は動きを止め、白い霞は中庭に面した大扉の方へ集まっていった。霞は這いうねり、無数の蛇のように絡まりあい、膝ほどの高さまでが乳色の海のようになった。その向こうから声が聞こえてきた。
「帝国の至宝を私する者よ、己が罪の深さに恐れおののくが良い」
英雄的とも言えるような良く響く朗々たる声だった。月が昇ったのか、大扉の硝子窓からは青白い光が差してくる。乳色の霧と青白い光の向こうから、その声は聞こえてくる。
「おまえはその蓄えた財を如何なる目的に使ったのか。この国この都の弥栄を願って用いたか」
声はジャンバール氏の財宝を集めた部屋の中に響き渡った。彼がそのような目的でこの部屋を作ったはずはない。サンジェリィ有数の金満家は、恐怖の頂点から突然小勇に駆られたようだった。
「ふざけるな!誰が国のため都のためを思って財を成すと思うか!儂は儂のため、この自分のためだけに、財を成したのだ!腐れ役人や暗愚な貴族王族など、儂の財に触れる資格などありやしない!増してや、貴様らのような面の皮の厚い盗人に渡す物など、この屋敷には塵一つない!」
ジャンバール氏は灰色の口髭に泡を吹き出しながら、一気にわめきたてた。どれ程の嘘偽りを積み重ねてこれだけの財を築いたのかわかりはしないが、今の彼の台詞はきっと真実の声なのだろう。
霧の中の声は、喉の奥でたてるような詰まった嘲笑で答えた。威厳さえ感じさせた先ほどの声とは別人のような、下卑た感じのする嫌な笑い声だった。
「国あってこそ生かされることを解せぬ下賎の輩よ、帝国の光輝を知らぬ不敬の男よ、クァロニアン帝国の威光をその命と引き換えに知るが良い!」
今度の声は、まるで地獄の奥底につながっている井戸から立ち上ってきたかのような、底知れぬ暗さと無慈悲な暴力をみなぎらせていた。
掛け金の外れる音がして、中庭側の大扉が開いた。霞が庭に流れ出し、渦巻き、立ち上り、その中から人影が現れた。
鎧兜に身を固めた男たちが影絵のように十人ほど並んでいる。古風な兜は耳の辺りまでを覆い、端がわずかに跳ね上がっている。胸と胴を覆う革鎧には鉄色の菱形の札が並び、真ん中には十六の矢を持つ日輪の紋章があった。兜の頂には短い角、反り身のがっしりした剣を手にしている。朽ちた史書から抜け出てきたかのような、〈帝国〉の兵士たちだった。兜の下の顔は、灰色がかった枯草色の覆面で覆っており、血走った双眼しか見えない。
兵士たちの先頭には、異なる出立ちの姿があった。暗い灰色の頭巾付きの長衣をまとっている。長衣には袖や裾周りに深紅の蛇腹の線が走り、左胸に金糸で帝国の紋章の縫い取りがある。頭巾が深く顔に影を落とし、容貌は見て取れない。だが、黒い影の中に熾火のように輝く深紅の瞳は、尋常な人間のものとは到底思えなかった。
「こいつらを殺せ!殺せ!一人残らず殺せ!」
品の良い趣味人として社交界で知られているジャンバール氏は、時々裏返る引きつった声で叫んだ。
二人の暗殺士が音もなく前へ出た。異様な敵の出現にも顔色一つ変えないのは、流石というべきなのだろうか。衛士たちは恐る恐るといった足つきで、少しずつ間合いを詰める。
「帝国の敵に天誅を加えよ!」
赤い目の男が恐ろしい声で命を下した。白い霞をかき乱して〈帝国〉の兵士たちが斬りかかってきた。
ジャンバール氏自慢の宝の部屋は、たちまちのうちに血みどろの戦場と化した。帝国兵たちの動きは、主なき甲冑とは違って手練れの剣士のものだった。無駄のない静かな動きの中に必殺の気迫を込めて、鋭い剣先を繰り出してくる。衛士たちは、あっという間に一人が腕を失い、もう一人は足を失った。鮮血を噴き出してのたうち回り、鏡のような敷石を汚していく様は、立ち上がれずにもがいていた甲冑の意地悪な戯画のようだった。
だが、暗殺士たちはそうはいかなかった。舞踏のような巧みな動きで兵士たちの長剣をかわし、懐に飛び込むと鋭い一撃を鎧の隙間に叩き込んだ。
今度は切っ先が空を斬ることはなかった。血飛沫を上げて、一人の兵士が倒れ伏した。古代の亡霊のような兵士たちも傷つき血を流す存在なのだ。
残った数人の衛士たちは、おおっという短い声を上げて、新たな勢いで帝国の兵士たちに襲いかかった。白刃がぶつかり合う鋭い音、肉を斬る鈍い音、噴き出す鮮血の飛沫の音、呻くような怒声と悲鳴が谺した。
私はただ剣を振るい、目の前の敵を屠ることに集中した。ファバーン剣の神秘文字は、甲冑が倒された後も緑色の光を放ち、何らかの魔法の力がこの場に働いていることを示している。
ファバーン文字が刻まれた刃が、一人の兵士の首筋に食い込んだ。兵は噴水のように血を噴いて倒れた。彼が倒れると同時に、その後ろからもう一人の兵士が立ち上がった。脇の傷口からどす黒い血が流れ落ちている。つい先刻、暗殺士が倒したはずの兵士だ。
死んだはずの兵士は異様に体を震わせながら、剣を振り回した。覆面に覆われた顔から覗く両眼は、奇怪な赤い光を放っていた。
言葉にならない声を発して、彼は斬りかかってきた。覆面の口の辺りには、泡でも吹いているのだろうか、染みが浮かび、顎からはよだれが滴り落ちている。
肩口に降り下ろされた奴の剣を受け止め、跳ね返そうとしたが、予想外の力に私は後退った。赤い目が光る男の背後に、首筋から血を流しながら、立ち上がるもう一人の死人の姿が見えた。古代の魔剣の神秘文字がひときわ鮮やかな緑の光を放っていた。
私は恐怖に囚われそうな心を何とか押さえつけ、死んだはずの兵士に刃を突き刺した。革鎧を突き通して、背中まで剣先が突き抜けた。覆面の染みはどす黒い血の染みへと変わった。剣を引き抜こうとしたはずみに奴は私の方へ倒れかかってきた。そのすぐ後ろから、首筋に大きな傷口を開けた男が剣を振り下ろしてきた。
反り身の剣が私の肩先に触れようかという刹那、鈍い音がして奴は動きを止めた。もう一人と折り重なるように倒れた奴の背中には大振りの卍手裏剣が突き刺さっていた。
見遣ると、中庭から新手の剣士が戦いに加わっていた。細身の体を白銀と紫の鎧に包んだ剣士が、銀の柄に紫の房飾りの剣を振るい、帝国兵を斬り刻んでいた。磨き上げられた銀の兜の頂からは、馬の尾のような長い黒髪が流れ出し、白刃と血飛沫と呼応するように死の舞踏を踊っている。銀の兜には面頬はなく、紫の覆面がその顔を隠している。わずかに覗いた切れ長の黒い双眸は、役者絵から切り抜いたかのような美しさで、同時に鉄のような眼力をも放っていた。
〈白銀と紫衣の剣士〉と私は初めて遭遇したのだ。この三月ばかり、サンジェリィの酒場は彼の話題で持ちきりだった。夜の闇に紛れて姿を現し、盗賊、暴漢、あるいは権力を笠に着て無理難題を押し付ける貴族や金持ちに血の制裁を下す「正義」の剣士。誰もその正体は知らず、警邏隊も捕らえることはできなかった。その謎の剣士が、今、目の前で剣を振るっているのだ。
〈白銀と紫衣の剣士〉は、流麗な剣捌きで次々に帝国の兵たちを倒していった。戦いの趨勢は明らかに変わり、クァロニアン党一味はじりじりと中庭の方へ押し戻されていった。“復活”した兵の動きは明らかに鈍く、主なき甲冑のようだった。二度、三度の斬撃で彼らは動かなくなった。
帝国兵の最後の一人を〈白銀と紫衣の剣士〉が斬り伏せた。起き上がる間も無く、剣士はそいつの首筋に刃を振り下ろし、二度と立ち上がれぬように止めを刺した。
灰色の頭巾を被った男はいつの間にか中庭の奥まで後退していた。彼の周囲には乳色の霞が渦を巻くように取り囲み、ゆるゆると回っていた。
私が小刀を投じるのも、〈白銀と紫衣の剣士〉が卍手裏剣を投げつけるのも、ほぼ同時だった。二つの刃は灰色頭巾の男を覆った霞の中でぶつかり合い、落下した。
霧の帳の中で赤い凶眼だけが光り、耳障りな笑い声が響いた。
「今宵はこれにて退散するとしよう。だが覚えておくがいい。我がクァロニアン党は帝国のすべてを取り戻す。帝国の威光にひれ伏さぬ輩は、一人残らず己の命と引き換えにその光輝を知ることとなるのだ。その日を心して待つが良い!」
霞が激しく渦巻き、朗とした、しかし底知れぬ嫌悪を引き起こす高笑いが響き渡った。霞は消え、中庭にはもはや誰もいなかった。
「ふざけるな!疾うに滅んだ帝国の威光など、誰が恐れるものか!儂の築いた財産は儂のものだ!気の狂れた魔術師風情に渡すものか!」
ジャンバール氏は、滅茶苦茶になった彼の宝物殿の中に座り込み、金切り声をあげていた。震える手には〈レイスキンの宝冠〉をしっかりと握りしめていた。とりあえずは、私も二人の暗殺士も、契約を果たすことができたようだった。
足下には幾人もの帝国の兵士がどす黒い血にまみれて倒れていた。私は剣先で恐る恐るその覆面を剥ぎ取った。現れたのは髑髏や木乃伊ではなく、取り敢えずは普通の人間の顔だった。だがその顔は、土気色というよりは青みを帯びた鉛色とでも言った方がいいのか、まっとうな人間とは思えない色合いだった。死人の顔は無数に見ているが、こんなにひどい顔色の死人はいない。落ちくぼんだ目の回りは、黒ずんだ赤紫色に変色し、その中に異様に赤い目が見開かれたままになっていた。
風を切る音がして振り向くと、中庭の木立の向こうに銀と紫の鎧姿が消えるところだった。しばしの間を置き、駆け去る蹄の音が聞こえた。〈白銀と紫衣の剣士〉は、私たちとは違って、今宵の働きの代価をジャンバール氏に求める気はないようだった。