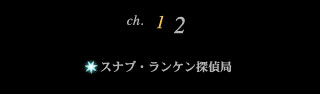民議員ブリュッケ・ゼム・ゲイルゼンの屋敷の前には、煌々と篝火が焚かれて、城門のような鉄鋲のついた門扇を照らし出していた。槍を持った二人の衛士の他にも、数名の警邏らしき男たちが辺りに目を光らせていた。
私たちの馬車が止まり、〈夜の執事〉ホッピーズが目顔で合図を送ると、門衛は重い扉の小脇についている、小さな通用門を開けようとした。
「ちょっと待て、この屋敷に出入りする者は、何人であろうと誰何することになっている。名を名乗れ」
裾の短い外套の下に鎖帷子を着込んだ警邏が、手に持った角灯を上げて私たちの顔を覗き込んだ。
ホッピーズは警邏に対する嫌悪をむき出しにして顔を背け、苛立ち声で言った。
「当家の筆頭執事ジャムランク・ホッピーズを疑うと言うのか!」
警邏はますます疑り深そうな顔になって、角灯を掲げ持った。
「当家の執事の名前はそうは聞いておらん。お前の顔はどうもどこかで見たような気がする。はて、どこであったか……」
「門衛たちは我らに何の疑念も抱いていないようだが、警邏殿。それにこの明かりは眩しすぎる」
私はホッピーズと警邏の間に体を押し込み、角灯を手で押し下げた。
「何だ、お前は!」
「スナブ・ランケン、当家に雇われた探偵だ。令嬢フィオレーム殿の探索にあたる」
警邏はぎろりと私の顔を睨め付けた。長年、その顔で街の破落戸を従わせてきたのだろうか。あるいは小心な市民を痛めつけてきたのだろうか。
「そんな名前は聞いておらん。探偵風情が今宵このお屋敷に用事があるはずはない」
残念ながら「サンジェリィ随一の魔道探偵」の名声は、この警邏の耳には入っていないらしかった。
「ふむ、今夜は余程重要な謀が当家では行われるということだね。ホッピーズ、今夜は誰が集まるんだい」
〈夜の執事〉は、不機嫌な吐き出すような口調で今宵の参会者を告げた。
「お頭、いや、ゲイルゼン様御本人に、オーガセット卿シェミト・ブリカ・カルトーニア伯爵様、剣術師範ネクツァン・カサラ様、警邏隊南部局長ノップラント・デラ・ジェギン様、それに……」
長い付き合いだったが、ノップラントの名前の方を聞いたのは初めてだった。ジェギンと呼んだら、青筋を立てて怒るのだろうか。
警邏はノップラント〈閣下〉の名前が出て、すでに動揺の色を見せていたが、私は意地悪くホッピーズに先を言うよう促した。
「それに……誰だい。この警邏殿は、全部言わないときっと納得してくれない。全部聞いた後では、きっと後悔するんだろうけどね」
警邏は不安と憎悪がないまぜになった目で、私とホッピーズを交互に睨んだ。どちらかと言えば、弱い市民を踏み付けにしてきた口なのだろう。
「それに、王宮の……ルムチャ・オークル道士だ」
ルムチャ・オークルという名は私も聞いたことはなかった。そもそも宮廷魔道士の名前なんて、誰も知るはずもない。だが、王宮からきた道士というだけで、警邏には十分すぎる効能があったようだった。
「聞いた通りだ。門衛を邸内に確認にやってもいいんだが……」
角灯の明かりの中でも警邏の顔色が悪くなるのがわかった。左目の縁がひくひくと震えていた。
「通れ」
警邏は短くそれだけ言うと、通りの向こう側の方へ目線を反らした。
通用門を潜ると、ホッピーズが小声でぶつぶつと言った。
「いけ好かねえ野郎だ。俺の顔を知ってたのか」
「元海賊としては、顔が売れてて誇りに思ってもいいんじゃないか」
「お前もいけ好かねえ野郎だ。お許しがあれば鱶の餌にしてやるところだ」
お頭の許しがあれば、きっとこの男は世界中の半分くらいの人間をあの世に送ってしまうのだろう。
私たちは明かりの落とされた暗い廊下を通って、客間に向かった。ホッピーズの持つ手燭が、磨かれた艶のある鏡板や黒い敷石に映って、虚ろな光を投げかけた。
山獅子の浅浮き彫りのある扉を抜けて、以前通された客間に入った。
正面の鉛色の人間の戯画を描いた壁の前には、ブリュッケ・ゼム・ゲイルゼンが座っていた。顔を断ち切るような大きな傷跡に交錯するように、小さなまだ新しい傷が幾つもついているのは、先日の襲撃によるものだろう。黒い目の厳しい光は衰えてはいなかったが、顔色は灰色じみており、撫で付けられた髪は数日で随分と白くなったように見えた。
左側の真紅の絵を背にした席には、ノップラントと見知らぬ女、右側の青い絵を背にした席には、カルトーニア伯爵と見知らぬ男が座っていた。
ノップラントはあばた面にいつものしかめっ面、左腕にはまだ包帯を巻いていた。向かい合う青い絵のせいか、傷のせいか、顔色は青黒く見える。ディパル・シェミトことカルトーニア伯爵は袖先の膨らんだ葡萄茶色の長衣をまとい、イオロープの魔道士を気取っているらしかったが、飛び出した薄い色の目は落ち着きなく部屋の中を見回していた。
赤い絵を背にした女は黄色い服を着ていた。低い襟の立った半袖の短上位は肉付きの良い体の線を露にしている。肩から乳首の上を通って裾まで続く黒い縞模様が、それをさらに強調していた。覗く二の腕の薄い褐色の滑らかな肌の下には、強くしなやかな筋肉が隠されているようだった。
黒い巻き毛は短く切られ、いささか角張った輪郭の顔は、女虎を思わせるものがある。吊り上がった真っすぐな眉と強い光を湛えた鳶色の瞳は得物を狙う獣のよう、肉の厚い暗桃色の唇は濃厚な色香を放っているが、開けばそこからは太い牙が飛び出してきそうだった。
青い絵を背にした男は、薄い乳色の長衣を着ていた。極端に広がった袖口には紫の何重にもなった三画模様が染め抜かれている。小さな頭に載った黒い帽子は高さが二イート(約六十センチ)近くもあり、金糸銀糸で複雑な渦巻や星型の紋様が施されていた。
小柄でひどく痩せこけていたが、奇妙なことに顔にはほとんど皺がなかった。細い筋のような目と口、薄い鼻、細く尖った顎、頭に張り付いたような小さな耳は、その姿をまるで木彫りの像のように見せていた。相当な高齢なのだろうが、尋常な齢の重ね方をしてきたとは思えなかった。
ホッピーズは私に虎のような女の隣の椅子に座るよう促すと、自分は部屋の隅の暗がりに姿を消した。
黄色い服の女は私に目もくれなかった。濃密な香水の匂いがした。
「顔ぶれが揃ったようだな。案件は二つだ。クァロニァン党を壊滅させること、我が娘フィオレームを取り戻すこと。南部局長、情勢はどうなっておる」
ゲイルゼンは顔色は悪かったが、声には強い響きがあった。
「今のところ、何の動きもありません。脅迫状の類は来ておらず、鼠の化け物を見たという話もありません。サンジェリィ全市の下水道、地下道、地下墓所を調べている最中で、幾つか鼠人間が掘ったと思しき横穴は発見されましたが、もぬけの殻でした」
ノップラントの濁声が重苦しく部屋に響いた。ふと私はこの男が子どもの頃はどんな様子だったのだろうかと思った。まさか生まれた時から苦虫を噛み潰したような顔をしていたわけではないだろう。
「うむ、御苦労だろうが続けてくれ。市中に奴らの拠点がないとは思えぬ」
ノップラントは黙って頷いた。サンジェリィの地下には幾つもの古の都の遺跡が眠っていると言われている。時には地震で地面に穴が開き、埋もれていた遺跡が姿を現わすこともある。私がファバーン剣を太古の戦士から譲り受けたのも、そうした偶然の為せる技だった。
「カルトーニア伯、クァロニァン党は今後どのように動くと思われる?」
シェミトの前には数冊の古びた書物が開かれていた。クァロニァン党襲撃の後、屋敷の蒐集物を整理し直すのは大変な苦労だったに違いない。
「奴らは、黒玻璃の器、『アー・ボーンの灰の書』を奪い取り、〈力の秘密〉の一端を手中にしたと思われる。当家を襲撃した巨人戦士はその成果だ。ジャンバール邸や我が城館に侵入した時は、甲冑や書物など生命なきものを幻術で操っていたようだが、巨人は血肉らしきものを持った存在だった。鉛の心臓に秘められた〈力〉がそれを動かしていたのだ。
「奴らがもしまだどこかで勢力を保っているのならば、その〈力〉を使ってまた何かおぞましい化け物を造り出すだろう。あの巨人戦士はおそらくは試作品のようなものだ。今度は完全な不死の兵士を造り出し、帝国復興の先兵とするかもしれない。あるいはさらに恐ろしい〈力〉の使い方があるのかもしれない。いずれにせよ、手に入れた〈力〉を使わずにいることはあり得ない。力とは例えそれがどんな力であってもそう言うものだ」
シェミトはまるでそうしていれば安全とでも言うように、古い書物の頁をめくりながら、話した。
「それにだ、また私の大切な蒐集品に手を出してくるかもしれない。断じて許せないことだ!」
伯爵は古書の頁から手を放し、細い指で握り拳を作り、弱々しく振り上げた。帝国の復活の阻止と蒐集品を守ることは、彼の中では少なくとも同列の価値を持っているようだった。
「アストル・グロウルは死んだ。誰がクァロニァン党を率いる?あの鼠野郎か」
私の問いに、自称〈魔道士の弟子〉は首を振って訝しげな表情を作った。
「黒のニケンジェは、クァロニァン帝国そのものには何の興味もないだろう。奴は地上の世界の混乱に乗じて、死と破滅と苦しみを撒き散らすことに生き甲斐を感じているんだ。それに鼠が頭目では流石に帝国の信奉者もついてはいかないだろう」
「だが、市中では奴らの演説に人だかりができている。今日、ここに来る途中でも奴らの演説会に出くわした。アストル・グロウル以外にも、率いる者がいるのか」
ノップラントが仏頂面で答えた。
「それも探っているところだ」
ゲイルゼンがその言葉を引き継いだ。
「王宮や民議会の中にも、クァロニァン党に与する手合がいると儂は睨んでいる。だが、そいつらが、首謀者に近いのか、単なる協力者なのか、あるいは儂を陥れるための手段として利用しているのか、それはまだわからん」
ノップラントの言葉が何とは無しに歯切れが悪く感じられたのは、宮廷や議院の中では警邏隊もそうは動けないということなのだろう。
「今宵はルムチャ・オークル道士にもお越し頂いておる。道士殿、あの奇っ怪なる心の臓はどうなっておりますか」
オークル道士の細い木のひび割れのような口が幽かに動いた。出てきた声は、見た目とは裏腹に太く響きのあるものだった。
「心臓は壊れてしもうた」
「何と!壊れたと申されるか!」
シェミトが飛び出た目を丸くして、驚きの声を上げた。魔道士を気取った格好をしていても、隣席の本物とはいささか違いがあるようだ。
「いかにも。幾重にも結界を張った中に厳重に封じておったが、調べようとする間もなく、漏れでる青い光が異様に明滅したかと思うと、恐ろしい光と熱を発して心の臓全体がどろどろと溶け出してしもうた。封じておった地下室は石壁まで灰となり、二人の道士も灼熱に包まれて灰となった」
宮廷魔道士は淡々と語ったが、細い裂け目のような瞼の奥で、灰色の目が強い感情を押し隠しているように見えた。
「すべてを焼き尽くし灰に変える力か」
道士は私の方を見ずに答えた。
「左様、アー・ボーンの〈力〉じゃ。〈大いなる厄災〉を引き起こした〈力〉じゃ」
ゲイルゼン邸の客間をしばし沈黙が支配した。銀の燭台で蝋燭の芯が焦げるじじっという音が、やけに大きく聞こえた。
再び口を開いたのは、オークル道士だった。
「アストル・グロウルの術による制御を失い、鉛の心臓は自らの〈力〉で自壊に至ったと思われる。おそらくは、クァロニアン党はまだアー・ボーンの〈力〉を完全に制御する術を会得しておらぬのだろう」
「〈力〉を完全に制御する魔術は存在するのだろうか、道士殿。我が〈真実の書庫〉より奪われた『アー・ボーンの灰の書』には、その秘密が記されているのだろうか」
自称隠秘学者の伯爵が、どこか他人事のような、ぼんやりとした口調で言った。
「それは我らにもわからぬ。『アー・ボーンの灰の書』にいかなる秘術が記されているのか、それはわからぬ。じゃが、我らに古より伝わる秘事によれば、〈黄金の鍵〉を手にした者が〈力〉を制する、とされておる」
道士の言葉にシェミトは驚きの声を上げた。
「何と〈黄金の鍵〉と仰るか。かの『万象秘帖』に一説のみ言及されている森羅万象の秘密を解くとされる〈黄金の鍵〉か!」
道楽貴族の感嘆は魔道士には何の関係もないもののようだった。
「万有の秘密を説く鍵などというものは存在しない。『万象秘帖』は後代の偽書じゃ」
「おお!『万象秘帖』が偽書だと仰るのか!これは驚き、宮廷の奥にはいかなる魔道の秘密秘儀が隠されているのやら。しからば『ファシルモ文書』の真偽も疑問となってくるではないか、いや『マナルカ神代記』の成立年代の問題も……」
私の隣席でそれまで黙りこくっていた女が口を開いた。
「私は古文書の信憑性について議論をするためにここに来たわけではない。当家御令嬢を、フィオレーム嬢を魔物の手より救い出す算段をしに来たのだ」
女の声は低く抑えたものだったが、さながら女虎の唸り声を思わせるものがあった。
「これは失礼、師範の言う通りではあるが、フィオレーム嬢を救い出すには、クァロニアン党の動きをつかむことが何より肝要ではないか。道士殿、〈黄金の鍵〉はどこにある?奴らの手に落ちる恐れはあるのか?」
「わからぬ。〈黄金の鍵〉の所在については何も伝わってはおらぬ。もし、それが現今も存在しているのであれば、何処か、古の遺跡の中であろうが……」
ルムチャ・オークル道士の言葉は低い響きの中に消えていった。再び客間に沈黙が押し広がったが、それを破ったのは部屋の隅の暗がりからの声だった。
「ご主人様、その〈黄金の鍵〉ってのは、あの〈黄金の鍵〉のことですかね」
〈夜の執事〉が明かりの輪の中に姿を表し、唇の端に歪んだ笑みを浮かべた。
「ホッピーズ、御客人にわかるように話さんか!」
お頭の一喝にも臆する様子もなく、〈夜の執事〉は話を続けた。
「へい、〈黄金の鍵〉ってのは西の海の古参船乗りに伝わる話でね、それさえあれば世界中のどんな宝箱、どんな錠前も開けることができるって言う代物さ。片腕ナグロン船長の時代には、血眼になってトリフェザの海賊連中が探し回ってたって話だね。どんな宝箱も開くってんだから、そりゃあ海賊には夢みたいなもんだ」
偶然なのかどうなのか、ノップラントが渋い顔で咳払いをした。ゲイルゼンはいささか呆れ気味の面持ちだったが、話を止めることはしなかった。
「だがね、〈黄金の鍵〉は見つからなかった。西の大洋に点々と浮かぶ曰く付きの怪しげな島々を片端から海賊どもは探し回った。〈失われた神々〉の禁忌の廃墟を荒らした奴らもいたが、突然の嵐で船ごと沈んだり、恐ろしい疫病みで死んだりした。恐ろしい呪いがかかっていて、〈鍵〉を手に入れようとする者は残らず死ぬ、と言う噂が広がった。その内に〈黄金の鍵〉なんて話は出鱈目だって誰かが言い出した。それで、ここ半世紀ばかりは手を出す海賊はいなくなった。
「だがね、あんまり知られてはいねえが、もう少し違う話も、青鮫号筋あたりの古老には伝わってる。〈黄金の鍵〉ってのは、宝箱を開けるためのもんじゃなくて、〈力の秘密〉を解くためのもんだって話だ。果たして、お偉い坊様が仰ってるもんと同じもんかどうかは、知らねえがな」
宮廷魔道士は何も語らず、何の表情の変化もなかった。
「それで、トリフェザの海賊どもは、〈鍵〉捜しを諦めたままなのか?」
カルトーニア伯は、どうやら話に合点が行かない様子だった。
「海賊は、そんな得体の知れない力なんぞに興味はないからねえ。カチッと目の前の錠前が開くことが滅法大事ですからねえ」
ホッピーズの言葉にはいささかの皮肉が込められていたが、道楽貴族には通じなかったようだった。
「西の海か。ならば海軍の助けも入り用になるのか……」
ノップラントの独り言のような苦り切った台詞は、警邏隊と王の軍隊の折り合いの悪さを如実に表していた。
「海軍には昵懇の者がない訳でもない。南部局長、そう腐ることはない」
ゲイルゼンの言葉に、ノップラントは渋々といった表情で頷いた。海賊上がりの民議員が海軍に近しい者を持っているとは、流石は民議殿というべきなのだろう。あるいはゲイルゼン交易商会の仕事振りに感嘆すべきなのか。
「海軍の方には儂から手を回す。局長は港湾局に働きかけて欲しい」
「わかりました」
「さて、我が娘の行方だが、ようとして知れん。そうだな、局長」
傷痕で二分された顔は、表情を押し殺していたが、その声には沈痛な響きがあった。
「残念ながら、まだ何の手掛かりも。全力を尽くしてはおりますが……」
フィオレームの父親は頷き、私の方へ視線を向けた。
「スナブ・ランケン、フィオレームは生きていると思うか」
まったく以て答えに窮する問いだった。虚しい希望も無意味な絶望も私は嫌いだった。
「わかりません。その場で殺さずに地下に引きずり込んだのは、何か意図があるのかもしれない。あるいは単に混乱の中で鼠穴の中に埋もれてしまったのかもしれない。わからない、としか答えようがありませんね。いずれにしても、生きて奪還するか、骸を葬るかするまで、捜すだけです」
ゲイルゼンは黙って頷いた。
「奴らが勢力を保っているなら、黒のニケンジェが脅しの書状を持ってきそうなものだが……」
シェミトは自分の台詞が、フィオレームの死の可能性を語っていると気付いたらしく、途中で言葉を切った。
「ネクツァン・カサラ師範、そして探偵スナブ・ランケン、二人には我が娘の探索に当たってもらいたい。必要な物、人、金子は遠慮なくホッピーズに言ってほしい。すべて滞りなく手配させる」
そう言って民議員は〈夜の執事〉をじろりと見た。
「当校の門弟たちをすでに捜索に当たらせております。フィオレーム嬢は、当校でも最も優れた剣技の持ち主であるばかりでなく、自由闊達に生き、正義を重んじる様は、門弟たちの憧れでもあります。必ずや捜し出して見せます」
女師範の口調は熱っぽく、拳は固く握りしめられていた。
私は特に語る台詞はなかったので、黙って頷いた。
私たちの馬車が止まり、〈夜の執事〉ホッピーズが目顔で合図を送ると、門衛は重い扉の小脇についている、小さな通用門を開けようとした。
「ちょっと待て、この屋敷に出入りする者は、何人であろうと誰何することになっている。名を名乗れ」
裾の短い外套の下に鎖帷子を着込んだ警邏が、手に持った角灯を上げて私たちの顔を覗き込んだ。
ホッピーズは警邏に対する嫌悪をむき出しにして顔を背け、苛立ち声で言った。
「当家の筆頭執事ジャムランク・ホッピーズを疑うと言うのか!」
警邏はますます疑り深そうな顔になって、角灯を掲げ持った。
「当家の執事の名前はそうは聞いておらん。お前の顔はどうもどこかで見たような気がする。はて、どこであったか……」
「門衛たちは我らに何の疑念も抱いていないようだが、警邏殿。それにこの明かりは眩しすぎる」
私はホッピーズと警邏の間に体を押し込み、角灯を手で押し下げた。
「何だ、お前は!」
「スナブ・ランケン、当家に雇われた探偵だ。令嬢フィオレーム殿の探索にあたる」
警邏はぎろりと私の顔を睨め付けた。長年、その顔で街の破落戸を従わせてきたのだろうか。あるいは小心な市民を痛めつけてきたのだろうか。
「そんな名前は聞いておらん。探偵風情が今宵このお屋敷に用事があるはずはない」
残念ながら「サンジェリィ随一の魔道探偵」の名声は、この警邏の耳には入っていないらしかった。
「ふむ、今夜は余程重要な謀が当家では行われるということだね。ホッピーズ、今夜は誰が集まるんだい」
〈夜の執事〉は、不機嫌な吐き出すような口調で今宵の参会者を告げた。
「お頭、いや、ゲイルゼン様御本人に、オーガセット卿シェミト・ブリカ・カルトーニア伯爵様、剣術師範ネクツァン・カサラ様、警邏隊南部局長ノップラント・デラ・ジェギン様、それに……」
長い付き合いだったが、ノップラントの名前の方を聞いたのは初めてだった。ジェギンと呼んだら、青筋を立てて怒るのだろうか。
警邏はノップラント〈閣下〉の名前が出て、すでに動揺の色を見せていたが、私は意地悪くホッピーズに先を言うよう促した。
「それに……誰だい。この警邏殿は、全部言わないときっと納得してくれない。全部聞いた後では、きっと後悔するんだろうけどね」
警邏は不安と憎悪がないまぜになった目で、私とホッピーズを交互に睨んだ。どちらかと言えば、弱い市民を踏み付けにしてきた口なのだろう。
「それに、王宮の……ルムチャ・オークル道士だ」
ルムチャ・オークルという名は私も聞いたことはなかった。そもそも宮廷魔道士の名前なんて、誰も知るはずもない。だが、王宮からきた道士というだけで、警邏には十分すぎる効能があったようだった。
「聞いた通りだ。門衛を邸内に確認にやってもいいんだが……」
角灯の明かりの中でも警邏の顔色が悪くなるのがわかった。左目の縁がひくひくと震えていた。
「通れ」
警邏は短くそれだけ言うと、通りの向こう側の方へ目線を反らした。
通用門を潜ると、ホッピーズが小声でぶつぶつと言った。
「いけ好かねえ野郎だ。俺の顔を知ってたのか」
「元海賊としては、顔が売れてて誇りに思ってもいいんじゃないか」
「お前もいけ好かねえ野郎だ。お許しがあれば鱶の餌にしてやるところだ」
お頭の許しがあれば、きっとこの男は世界中の半分くらいの人間をあの世に送ってしまうのだろう。
私たちは明かりの落とされた暗い廊下を通って、客間に向かった。ホッピーズの持つ手燭が、磨かれた艶のある鏡板や黒い敷石に映って、虚ろな光を投げかけた。
山獅子の浅浮き彫りのある扉を抜けて、以前通された客間に入った。
正面の鉛色の人間の戯画を描いた壁の前には、ブリュッケ・ゼム・ゲイルゼンが座っていた。顔を断ち切るような大きな傷跡に交錯するように、小さなまだ新しい傷が幾つもついているのは、先日の襲撃によるものだろう。黒い目の厳しい光は衰えてはいなかったが、顔色は灰色じみており、撫で付けられた髪は数日で随分と白くなったように見えた。
左側の真紅の絵を背にした席には、ノップラントと見知らぬ女、右側の青い絵を背にした席には、カルトーニア伯爵と見知らぬ男が座っていた。
ノップラントはあばた面にいつものしかめっ面、左腕にはまだ包帯を巻いていた。向かい合う青い絵のせいか、傷のせいか、顔色は青黒く見える。ディパル・シェミトことカルトーニア伯爵は袖先の膨らんだ葡萄茶色の長衣をまとい、イオロープの魔道士を気取っているらしかったが、飛び出した薄い色の目は落ち着きなく部屋の中を見回していた。
赤い絵を背にした女は黄色い服を着ていた。低い襟の立った半袖の短上位は肉付きの良い体の線を露にしている。肩から乳首の上を通って裾まで続く黒い縞模様が、それをさらに強調していた。覗く二の腕の薄い褐色の滑らかな肌の下には、強くしなやかな筋肉が隠されているようだった。
黒い巻き毛は短く切られ、いささか角張った輪郭の顔は、女虎を思わせるものがある。吊り上がった真っすぐな眉と強い光を湛えた鳶色の瞳は得物を狙う獣のよう、肉の厚い暗桃色の唇は濃厚な色香を放っているが、開けばそこからは太い牙が飛び出してきそうだった。
青い絵を背にした男は、薄い乳色の長衣を着ていた。極端に広がった袖口には紫の何重にもなった三画模様が染め抜かれている。小さな頭に載った黒い帽子は高さが二イート(約六十センチ)近くもあり、金糸銀糸で複雑な渦巻や星型の紋様が施されていた。
小柄でひどく痩せこけていたが、奇妙なことに顔にはほとんど皺がなかった。細い筋のような目と口、薄い鼻、細く尖った顎、頭に張り付いたような小さな耳は、その姿をまるで木彫りの像のように見せていた。相当な高齢なのだろうが、尋常な齢の重ね方をしてきたとは思えなかった。
ホッピーズは私に虎のような女の隣の椅子に座るよう促すと、自分は部屋の隅の暗がりに姿を消した。
黄色い服の女は私に目もくれなかった。濃密な香水の匂いがした。
「顔ぶれが揃ったようだな。案件は二つだ。クァロニァン党を壊滅させること、我が娘フィオレームを取り戻すこと。南部局長、情勢はどうなっておる」
ゲイルゼンは顔色は悪かったが、声には強い響きがあった。
「今のところ、何の動きもありません。脅迫状の類は来ておらず、鼠の化け物を見たという話もありません。サンジェリィ全市の下水道、地下道、地下墓所を調べている最中で、幾つか鼠人間が掘ったと思しき横穴は発見されましたが、もぬけの殻でした」
ノップラントの濁声が重苦しく部屋に響いた。ふと私はこの男が子どもの頃はどんな様子だったのだろうかと思った。まさか生まれた時から苦虫を噛み潰したような顔をしていたわけではないだろう。
「うむ、御苦労だろうが続けてくれ。市中に奴らの拠点がないとは思えぬ」
ノップラントは黙って頷いた。サンジェリィの地下には幾つもの古の都の遺跡が眠っていると言われている。時には地震で地面に穴が開き、埋もれていた遺跡が姿を現わすこともある。私がファバーン剣を太古の戦士から譲り受けたのも、そうした偶然の為せる技だった。
「カルトーニア伯、クァロニァン党は今後どのように動くと思われる?」
シェミトの前には数冊の古びた書物が開かれていた。クァロニァン党襲撃の後、屋敷の蒐集物を整理し直すのは大変な苦労だったに違いない。
「奴らは、黒玻璃の器、『アー・ボーンの灰の書』を奪い取り、〈力の秘密〉の一端を手中にしたと思われる。当家を襲撃した巨人戦士はその成果だ。ジャンバール邸や我が城館に侵入した時は、甲冑や書物など生命なきものを幻術で操っていたようだが、巨人は血肉らしきものを持った存在だった。鉛の心臓に秘められた〈力〉がそれを動かしていたのだ。
「奴らがもしまだどこかで勢力を保っているのならば、その〈力〉を使ってまた何かおぞましい化け物を造り出すだろう。あの巨人戦士はおそらくは試作品のようなものだ。今度は完全な不死の兵士を造り出し、帝国復興の先兵とするかもしれない。あるいはさらに恐ろしい〈力〉の使い方があるのかもしれない。いずれにせよ、手に入れた〈力〉を使わずにいることはあり得ない。力とは例えそれがどんな力であってもそう言うものだ」
シェミトはまるでそうしていれば安全とでも言うように、古い書物の頁をめくりながら、話した。
「それにだ、また私の大切な蒐集品に手を出してくるかもしれない。断じて許せないことだ!」
伯爵は古書の頁から手を放し、細い指で握り拳を作り、弱々しく振り上げた。帝国の復活の阻止と蒐集品を守ることは、彼の中では少なくとも同列の価値を持っているようだった。
「アストル・グロウルは死んだ。誰がクァロニァン党を率いる?あの鼠野郎か」
私の問いに、自称〈魔道士の弟子〉は首を振って訝しげな表情を作った。
「黒のニケンジェは、クァロニァン帝国そのものには何の興味もないだろう。奴は地上の世界の混乱に乗じて、死と破滅と苦しみを撒き散らすことに生き甲斐を感じているんだ。それに鼠が頭目では流石に帝国の信奉者もついてはいかないだろう」
「だが、市中では奴らの演説に人だかりができている。今日、ここに来る途中でも奴らの演説会に出くわした。アストル・グロウル以外にも、率いる者がいるのか」
ノップラントが仏頂面で答えた。
「それも探っているところだ」
ゲイルゼンがその言葉を引き継いだ。
「王宮や民議会の中にも、クァロニァン党に与する手合がいると儂は睨んでいる。だが、そいつらが、首謀者に近いのか、単なる協力者なのか、あるいは儂を陥れるための手段として利用しているのか、それはまだわからん」
ノップラントの言葉が何とは無しに歯切れが悪く感じられたのは、宮廷や議院の中では警邏隊もそうは動けないということなのだろう。
「今宵はルムチャ・オークル道士にもお越し頂いておる。道士殿、あの奇っ怪なる心の臓はどうなっておりますか」
オークル道士の細い木のひび割れのような口が幽かに動いた。出てきた声は、見た目とは裏腹に太く響きのあるものだった。
「心臓は壊れてしもうた」
「何と!壊れたと申されるか!」
シェミトが飛び出た目を丸くして、驚きの声を上げた。魔道士を気取った格好をしていても、隣席の本物とはいささか違いがあるようだ。
「いかにも。幾重にも結界を張った中に厳重に封じておったが、調べようとする間もなく、漏れでる青い光が異様に明滅したかと思うと、恐ろしい光と熱を発して心の臓全体がどろどろと溶け出してしもうた。封じておった地下室は石壁まで灰となり、二人の道士も灼熱に包まれて灰となった」
宮廷魔道士は淡々と語ったが、細い裂け目のような瞼の奥で、灰色の目が強い感情を押し隠しているように見えた。
「すべてを焼き尽くし灰に変える力か」
道士は私の方を見ずに答えた。
「左様、アー・ボーンの〈力〉じゃ。〈大いなる厄災〉を引き起こした〈力〉じゃ」
ゲイルゼン邸の客間をしばし沈黙が支配した。銀の燭台で蝋燭の芯が焦げるじじっという音が、やけに大きく聞こえた。
再び口を開いたのは、オークル道士だった。
「アストル・グロウルの術による制御を失い、鉛の心臓は自らの〈力〉で自壊に至ったと思われる。おそらくは、クァロニアン党はまだアー・ボーンの〈力〉を完全に制御する術を会得しておらぬのだろう」
「〈力〉を完全に制御する魔術は存在するのだろうか、道士殿。我が〈真実の書庫〉より奪われた『アー・ボーンの灰の書』には、その秘密が記されているのだろうか」
自称隠秘学者の伯爵が、どこか他人事のような、ぼんやりとした口調で言った。
「それは我らにもわからぬ。『アー・ボーンの灰の書』にいかなる秘術が記されているのか、それはわからぬ。じゃが、我らに古より伝わる秘事によれば、〈黄金の鍵〉を手にした者が〈力〉を制する、とされておる」
道士の言葉にシェミトは驚きの声を上げた。
「何と〈黄金の鍵〉と仰るか。かの『万象秘帖』に一説のみ言及されている森羅万象の秘密を解くとされる〈黄金の鍵〉か!」
道楽貴族の感嘆は魔道士には何の関係もないもののようだった。
「万有の秘密を説く鍵などというものは存在しない。『万象秘帖』は後代の偽書じゃ」
「おお!『万象秘帖』が偽書だと仰るのか!これは驚き、宮廷の奥にはいかなる魔道の秘密秘儀が隠されているのやら。しからば『ファシルモ文書』の真偽も疑問となってくるではないか、いや『マナルカ神代記』の成立年代の問題も……」
私の隣席でそれまで黙りこくっていた女が口を開いた。
「私は古文書の信憑性について議論をするためにここに来たわけではない。当家御令嬢を、フィオレーム嬢を魔物の手より救い出す算段をしに来たのだ」
女の声は低く抑えたものだったが、さながら女虎の唸り声を思わせるものがあった。
「これは失礼、師範の言う通りではあるが、フィオレーム嬢を救い出すには、クァロニアン党の動きをつかむことが何より肝要ではないか。道士殿、〈黄金の鍵〉はどこにある?奴らの手に落ちる恐れはあるのか?」
「わからぬ。〈黄金の鍵〉の所在については何も伝わってはおらぬ。もし、それが現今も存在しているのであれば、何処か、古の遺跡の中であろうが……」
ルムチャ・オークル道士の言葉は低い響きの中に消えていった。再び客間に沈黙が押し広がったが、それを破ったのは部屋の隅の暗がりからの声だった。
「ご主人様、その〈黄金の鍵〉ってのは、あの〈黄金の鍵〉のことですかね」
〈夜の執事〉が明かりの輪の中に姿を表し、唇の端に歪んだ笑みを浮かべた。
「ホッピーズ、御客人にわかるように話さんか!」
お頭の一喝にも臆する様子もなく、〈夜の執事〉は話を続けた。
「へい、〈黄金の鍵〉ってのは西の海の古参船乗りに伝わる話でね、それさえあれば世界中のどんな宝箱、どんな錠前も開けることができるって言う代物さ。片腕ナグロン船長の時代には、血眼になってトリフェザの海賊連中が探し回ってたって話だね。どんな宝箱も開くってんだから、そりゃあ海賊には夢みたいなもんだ」
偶然なのかどうなのか、ノップラントが渋い顔で咳払いをした。ゲイルゼンはいささか呆れ気味の面持ちだったが、話を止めることはしなかった。
「だがね、〈黄金の鍵〉は見つからなかった。西の大洋に点々と浮かぶ曰く付きの怪しげな島々を片端から海賊どもは探し回った。〈失われた神々〉の禁忌の廃墟を荒らした奴らもいたが、突然の嵐で船ごと沈んだり、恐ろしい疫病みで死んだりした。恐ろしい呪いがかかっていて、〈鍵〉を手に入れようとする者は残らず死ぬ、と言う噂が広がった。その内に〈黄金の鍵〉なんて話は出鱈目だって誰かが言い出した。それで、ここ半世紀ばかりは手を出す海賊はいなくなった。
「だがね、あんまり知られてはいねえが、もう少し違う話も、青鮫号筋あたりの古老には伝わってる。〈黄金の鍵〉ってのは、宝箱を開けるためのもんじゃなくて、〈力の秘密〉を解くためのもんだって話だ。果たして、お偉い坊様が仰ってるもんと同じもんかどうかは、知らねえがな」
宮廷魔道士は何も語らず、何の表情の変化もなかった。
「それで、トリフェザの海賊どもは、〈鍵〉捜しを諦めたままなのか?」
カルトーニア伯は、どうやら話に合点が行かない様子だった。
「海賊は、そんな得体の知れない力なんぞに興味はないからねえ。カチッと目の前の錠前が開くことが滅法大事ですからねえ」
ホッピーズの言葉にはいささかの皮肉が込められていたが、道楽貴族には通じなかったようだった。
「西の海か。ならば海軍の助けも入り用になるのか……」
ノップラントの独り言のような苦り切った台詞は、警邏隊と王の軍隊の折り合いの悪さを如実に表していた。
「海軍には昵懇の者がない訳でもない。南部局長、そう腐ることはない」
ゲイルゼンの言葉に、ノップラントは渋々といった表情で頷いた。海賊上がりの民議員が海軍に近しい者を持っているとは、流石は民議殿というべきなのだろう。あるいはゲイルゼン交易商会の仕事振りに感嘆すべきなのか。
「海軍の方には儂から手を回す。局長は港湾局に働きかけて欲しい」
「わかりました」
「さて、我が娘の行方だが、ようとして知れん。そうだな、局長」
傷痕で二分された顔は、表情を押し殺していたが、その声には沈痛な響きがあった。
「残念ながら、まだ何の手掛かりも。全力を尽くしてはおりますが……」
フィオレームの父親は頷き、私の方へ視線を向けた。
「スナブ・ランケン、フィオレームは生きていると思うか」
まったく以て答えに窮する問いだった。虚しい希望も無意味な絶望も私は嫌いだった。
「わかりません。その場で殺さずに地下に引きずり込んだのは、何か意図があるのかもしれない。あるいは単に混乱の中で鼠穴の中に埋もれてしまったのかもしれない。わからない、としか答えようがありませんね。いずれにしても、生きて奪還するか、骸を葬るかするまで、捜すだけです」
ゲイルゼンは黙って頷いた。
「奴らが勢力を保っているなら、黒のニケンジェが脅しの書状を持ってきそうなものだが……」
シェミトは自分の台詞が、フィオレームの死の可能性を語っていると気付いたらしく、途中で言葉を切った。
「ネクツァン・カサラ師範、そして探偵スナブ・ランケン、二人には我が娘の探索に当たってもらいたい。必要な物、人、金子は遠慮なくホッピーズに言ってほしい。すべて滞りなく手配させる」
そう言って民議員は〈夜の執事〉をじろりと見た。
「当校の門弟たちをすでに捜索に当たらせております。フィオレーム嬢は、当校でも最も優れた剣技の持ち主であるばかりでなく、自由闊達に生き、正義を重んじる様は、門弟たちの憧れでもあります。必ずや捜し出して見せます」
女師範の口調は熱っぽく、拳は固く握りしめられていた。
私は特に語る台詞はなかったので、黙って頷いた。