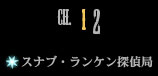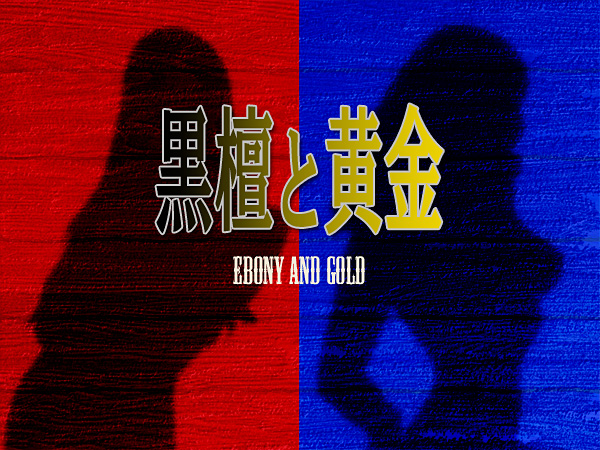
町の入り口には傾いだ木の門があった。門柱の上の方に白く乾ききった板が打ち付けられていて、消えかけた文字はどうやら「エルソパルドへようこそ」と書かれているようだった。門扉は片方しか残っておらず、壊れかけた蝶番が荒れ野を吹く風に軋み、侘びしい歌を奏でていた。
やけに広い往来(といっても、石畳も何もない只の乾いた土だが)の両側に古びた木造の家々が並んでいた。色褪せ消えかけた看板には、宿屋や食事処、食料品屋、鍛冶屋、雑貨屋等々、様々な店の名前が読み取れた。だが、店を開けている所はほとんどないようだった。幾つかの開いた窓の中に、干涸びたような年老いた顔が幾つか見えた。懐疑と恐れに満ちた視線を感じたが、私がそちらに目を向けると皆そそくさと窓を閉じた。誰も歩く者もない町に風の音だけが響いていた。
町の真ん中あたりと思しき所に、開いている店があった。かつてはけばけばしい色彩で塗られていたであろう看板には、真ん中に〈黒檀と黄金〉と大書きされ、左端には黒髪の、右端には金髪の女の姿が描かれていた。下の方には「宿と食事、酒、そして女」という文字が残っていた。
私は疲れた馬を店の脇の厩につなぐと、軋む扉を押し明けた。店の中央は通路であるのか、空けてあり、左右に小振りの円卓が幾つか並んでいた。正面奥には止まり木と帳場があった。左手奥には年代物の大型の風琴、右手奥には二階の、恐らくは客室に通じる階段があった。
店には先客がいた。左右に別れた席に各々五人ばかりの男が陣取り、銅の杯から酒をすすっていた。左側に座った男たちは、みな真紅の布を首や頭に巻いていた。右側に座った男たちはみな青く染めた革胴着を着ていた。どちらの男たちも、内からにじみ出る欲望と暴力で薄汚く脂ぎっているように見えた。
奥の止まり木には誰も座っていなかった。帳場の向こう側には褐色の肌に灰色の縮れ毛の男がいた。灰色の潤んだような目はやけに小さく、口髭に隠された口元と相まって、表情が読み取り難い。視線は私の方に向いているようであり、どこにも向いていないようにも感じられた。
私は止まり木の真ん中の席に座った。背中に男たちの視線が集まるのが感じられた。帳場の中の男は歪んだ銅杯を磨いていた。赤金に映る私を見ているような気もした。
「親父、ピンニャだ。ピニャポンデルにできるか」
「無理な話だね、エルパソルドでする話じゃない。ピンニャがあるだけ幸せだと思いな」
主は私に目を合わせず、凹んだ銅杯に薄い金色の酒を注いだ。
「ああ、まあ、そんな所だろうね。仙人掌に乾杯だな」
主は銅杯に酒を三分の一ほど注ぎ、仙人掌の漬物の欠けらを申し訳のように添えた。ピンニャはひどい安物で舌がぴりぴりとした。仙人掌はそう不味くはなかった。
「開いている宿屋はここだけかい」
「そうさね」
「泊めてもらおうか」
主はすぐには答えず、別の銅杯を磨き始める素振りを見せた。
「部屋はあるだろう。とりあえず、一泊分の金はある」
私は懐から銀貨の入った革袋を取り出し、帳場に音を立てて置いた。あまり迫力のある音ではなかったが。
「もう少し金子はあった方がいいだろうな」
「いい儲け話を聞かせてやろうか」
左右からほとんど同時に声がかかった。主は聞こえないふりをしていた。私は銅杯に映る左右の男たちの姿を見た。どちらも大きく歪んで、それでなくとも獣じみた容貌がさらに醜く歪んで見えた。もう一口ピンニャをすすって、黙っているとまた声がかかった。
「おい、兄さん、金が欲しくはないのかい」
「ここいらじゃ、なかなかいい話はないぜ」
私は主に視線を送ったが、主の視線の行方は知れなかった。
「遠慮しておくよ。ここに長居をするつもりはない。一宿一飯で十分さ。お前さんたちが慈善事業者には見えないしな」
「何だと、この野郎!おう、この町に来たからにゃあ、そうは行かねえのさ!ラスヴィップの旦那につくのか、薄汚え青豚野郎につくのか、はっきりしろ!」
「利いた風な口をきかせやがって!屍肉食らいの犬野郎につくのか、ブランディギロン様につくのか、二つに一つだ!」
私は銅杯のピンニャを飲み干した。喉がひりひりするので、仙人掌の漬物をかじったが、あまり効き目はなかった。
「親父、水をくれ。杯に一杯、それから桶に一杯だ。こいつらの頭を冷やすのに入り用だ」
「何だと、てめえ!ふざけるのもいい加減にしろ!」
「そういうことなら、てめえの死体を役に立てるだけよ!」
左右から剣を抜く音が聞こえた。銅杯に映る歪んだ男たちの手に鈍く光る刃が現れた。左右の男が剣を振りかざすのが見えた。
私は剣を抜き、二人を斬った。抜き様に右手の男の首から肩を斬り裂き、返す刀で左の男の胴を斬り払った。左右から盛大に鮮血が噴き出した。首を竦めたが否応無しに血飛沫が降りかかった。
二人の男は血をまき散らしながら、床の上に頽れた。
「親父、すまんな。杯を代えて、水をくれ」
主は黙ったまま無表情に一瞥をくれ、水を注いだ。左右の男たちが騒めき立った。剣を抜く音が幾重にも谺して聞こえた。その音に混じって、酒場の扉が軋んで開く音が聞こえた。女の匂いが足音と共に近づいてきて、私の右隣の席に座った。
「私はコルデよ。あなたは」
コルデと名乗った女は透き通った青い瞳で私を見据えた。少しだけ目を細めて、珊瑚色の唇にしわを寄せ、微笑んだ。そうすれば世界中の男が平伏すとでも、思っているのだろう。
輝くような金色の髪が波打っている。胸の大きく開いた白い服には、赤と黄の砂漠の花が刺繍され、幅広の光る青い繻子の腰帯をきつく締めていた。帯の上下では乳房と尻がそれぞれ前後に大きく突き出していた。
「スナブ・ランケン、旅の者だ」
コルデと名乗った女は「私にもピンニャね」と言って、主に微笑みかけた。無愛想に差し出された酒杯をあおり、床の上の死体を一瞥した。
「腕が立つのね。ブランディギロンにつきなさいよ、私が口を利いてあげるわ。強い男には金を惜しまないわよ」
金髪の女はそう言って私の膝に手を置いた。私は注意深く彼女の白く肉付きの良い手をつかみ、帳場の上に戻した。女はくすくすと笑って、これ見よがしに乳房を震わせてみせた。
また扉の軋む音がして、足音が近づいてきた。コルデの笑いが止み、冷たい視線が私を通り越して、新しい客に注がれた。足音は私の背後で一度止まった。銅杯に映る歪んだ女の姿は床の上の死体を見ているようだった。女は私の左隣に座った。
「ルッカ、ピンニャをちょうだい」
女は囁くような声で言い、影の濃い大きな鳶色の瞳が私を見据えた。にこりともしなかったが、その視線に男が平伏すと思っているのは、彼女も金髪女と同様らしかった。
女は差し出された銅杯から一口酒をすすり、不機嫌そうに赤い唇を歪めた。痩せていて青白い肌をしていた。肌に張り付くような黒い服はあちこちが透かし刺繍になっていて、白い肌に絵模様を描き出していた。漆黒の髪に真紅の布で作られた花飾りを刺していた。細い腰帯も真紅だった。
「あなたが斬ったのね、大した太刀筋ね。私はイヴォーン、あなたは?」
黒髪の女は細い指先を私の肩に這わせて囁いた。私は左手で水の入った杯を持ち、注意深く彼女の手を払ってから答えた。
「スナブ・ランケン、旅の者だ」
「そう、おもしろい名前ね。うちの頭目もおもしろい名前なのよ。ラスヴィップって言うの。この腕なら稼げるわよ。うちに来なさいよ」
私は生ぬるい水を一口飲んだ。右側のコルデという女は残っていたピンニャを一気に飲み干した。左側のイヴォーンという女は銅杯を口に運んで静かに傾けた。
「何しに来たのさ、この雌犬!」
コルデが語気鋭く言った。
「雌豚には関係のないことよ!」
イヴォーンがひどく冷たい声で返した。
蝿の羽音がした。女たちにはひと足遅れたが、蝿たちが死骸の臭いを嗅ぎつけて、どこからか飛んできたらしい。
「旦那、どっちに付くか決めたらいい」
主が相変わらず、私の方を見ないままそう言った。
「この町ではどっちにつくか、決めなきゃいけねえ。そうでない者はさっさと出て行くかだ。でも、旦那はもう斬っちまったからな、そうはいかねえな」
「やれやれ、二人斬ったら百人斬る羽目になるのかね」
「旦那が斬られちまえば、それでお仕舞いだよ」
二人の女が立ち上がり、私から離れた。左右の男たちが剣を構え直す音がした。私も立ち上がって、帳場を背にして剣を構えた。
「お兄さん、もう一度聞くわ。ブランディギロンにつきなさいよ。そうね、一日四十ペイゾスでどう?」
「豚小屋になんて行くことないわ。うちに来れば五十ペイゾス出すわ。ラスヴィップにつきなさいよ」
「うちも五十ペイゾス出すわ。犬小屋に繋がれるなんて、真っ平でしょ!」
どうやら一日五十ペイゾスというのが、この町での相場らしい。確かに実入りはいいかも知れないが、命を懸ける意味がある仕事が待っているとは思えなかった。
「さあ、兄さん、はっきりしてちょうだい」
コルデという金髪の女は青い靴で床を鳴らした。
「うちに来るんでしょう、旅の御方」
イヴォーンという黒髪の女は赤い爪で私を差し招いた。
人間たちの下らない騒ぎには関係なく、蝿たちは死骸の上で忙しそうだった。彼らの仕事を一気に増やすことになるのかも知れない。青でも赤でも金髪でも黒髪でも、もちろん旅の者でも、彼らには何の関係もない。
「来ないのならあの世に行きな!」
「うちじゃなけりゃ、地獄行きね!」
二人の女が同時に叫んだ。二人で芝居の稽古でも積んでいるのかも知れない。左右で鋼の刃が振り上げられたその時、鐘の音が聞こえた。陰鬱な低い響きのある鐘が鳴り渡った。皴でも入っているのか、びりびりと震える濁った音が入り混じり、頭の芯に鉄の杭でも打ち込むかのような、暗い力強さに満ちた鐘の音だった。
途端に酒場の中に奇妙な気配が広がった。破落戸どもは顔を見合わせて、剣を下ろした。不満と不安が野卑な顔には浮かんでいるように見えた。二人の女はもう少しうまく表情を隠していたが、心地よくない何かが彼女たちの心中にも沸き起こっているのは確かなようだった。
「命拾いしたようね、兄さん。でも、これでお仕舞いじゃないよ」
「私たちが戻ってくるまでに、どっちにつくか決めておくのよ、いいこと?」
二人の女は仲良く台詞を分け合うと、それぞれ青と赤の男たちに視線を送った。やくざ者たちは私が斬った二人の死骸を引きずり、陰気な顔つきで酒場から出て行った。鐘の音はまだ鳴り響いていた。
「どこに行くんだ、奴らは?」
「ダムンファンの神殿さ。町の南の外れにある。お前さんが斬った二人を神様にお供えするのさ」
主は帳場から出てきて、床の血溜まりの掃除を始めた。酒場の真ん中あたりの床には幾つも黒ずんだ染みがあった。
「そんな神の名前は聞いたことがないな」
「ダムンファンってのは祭司の名前さ。神様の名前は知らんよ」
「奴らはその名無しの神の信者なのかい」
主は柄雑巾を動かす手を止め、こちらを見て乾いた笑い声をあげた。
「奴らが崇めるのは金だけさ。お目当ては神殿にあるっていう宝石でできた神像だよ。祭司に取り入って、そいつを手に入れようとしてるのさ」
私は杯に残っていた水を飲み干すと、立ち上がった。
「今の内に町からでた方が身のためだ。食い物なら少し分けてやる」
「晩飯の用意を頼むよ。僕も名無しの神の御利益に与ってみよう」
主はあきれ顔で手を振り、床の掃除に戻った。私が軋む扉を押し明けると、背中で声がした。
「くたばるんなら店の外にしてくれ。掃除が大変なんだ」
「ああ、そうするよ」
私は町の南の方に急ぎ足で向かった。
やけに広い往来(といっても、石畳も何もない只の乾いた土だが)の両側に古びた木造の家々が並んでいた。色褪せ消えかけた看板には、宿屋や食事処、食料品屋、鍛冶屋、雑貨屋等々、様々な店の名前が読み取れた。だが、店を開けている所はほとんどないようだった。幾つかの開いた窓の中に、干涸びたような年老いた顔が幾つか見えた。懐疑と恐れに満ちた視線を感じたが、私がそちらに目を向けると皆そそくさと窓を閉じた。誰も歩く者もない町に風の音だけが響いていた。
町の真ん中あたりと思しき所に、開いている店があった。かつてはけばけばしい色彩で塗られていたであろう看板には、真ん中に〈黒檀と黄金〉と大書きされ、左端には黒髪の、右端には金髪の女の姿が描かれていた。下の方には「宿と食事、酒、そして女」という文字が残っていた。
私は疲れた馬を店の脇の厩につなぐと、軋む扉を押し明けた。店の中央は通路であるのか、空けてあり、左右に小振りの円卓が幾つか並んでいた。正面奥には止まり木と帳場があった。左手奥には年代物の大型の風琴、右手奥には二階の、恐らくは客室に通じる階段があった。
店には先客がいた。左右に別れた席に各々五人ばかりの男が陣取り、銅の杯から酒をすすっていた。左側に座った男たちは、みな真紅の布を首や頭に巻いていた。右側に座った男たちはみな青く染めた革胴着を着ていた。どちらの男たちも、内からにじみ出る欲望と暴力で薄汚く脂ぎっているように見えた。
奥の止まり木には誰も座っていなかった。帳場の向こう側には褐色の肌に灰色の縮れ毛の男がいた。灰色の潤んだような目はやけに小さく、口髭に隠された口元と相まって、表情が読み取り難い。視線は私の方に向いているようであり、どこにも向いていないようにも感じられた。
私は止まり木の真ん中の席に座った。背中に男たちの視線が集まるのが感じられた。帳場の中の男は歪んだ銅杯を磨いていた。赤金に映る私を見ているような気もした。
「親父、ピンニャだ。ピニャポンデルにできるか」
「無理な話だね、エルパソルドでする話じゃない。ピンニャがあるだけ幸せだと思いな」
主は私に目を合わせず、凹んだ銅杯に薄い金色の酒を注いだ。
「ああ、まあ、そんな所だろうね。仙人掌に乾杯だな」
主は銅杯に酒を三分の一ほど注ぎ、仙人掌の漬物の欠けらを申し訳のように添えた。ピンニャはひどい安物で舌がぴりぴりとした。仙人掌はそう不味くはなかった。
「開いている宿屋はここだけかい」
「そうさね」
「泊めてもらおうか」
主はすぐには答えず、別の銅杯を磨き始める素振りを見せた。
「部屋はあるだろう。とりあえず、一泊分の金はある」
私は懐から銀貨の入った革袋を取り出し、帳場に音を立てて置いた。あまり迫力のある音ではなかったが。
「もう少し金子はあった方がいいだろうな」
「いい儲け話を聞かせてやろうか」
左右からほとんど同時に声がかかった。主は聞こえないふりをしていた。私は銅杯に映る左右の男たちの姿を見た。どちらも大きく歪んで、それでなくとも獣じみた容貌がさらに醜く歪んで見えた。もう一口ピンニャをすすって、黙っているとまた声がかかった。
「おい、兄さん、金が欲しくはないのかい」
「ここいらじゃ、なかなかいい話はないぜ」
私は主に視線を送ったが、主の視線の行方は知れなかった。
「遠慮しておくよ。ここに長居をするつもりはない。一宿一飯で十分さ。お前さんたちが慈善事業者には見えないしな」
「何だと、この野郎!おう、この町に来たからにゃあ、そうは行かねえのさ!ラスヴィップの旦那につくのか、薄汚え青豚野郎につくのか、はっきりしろ!」
「利いた風な口をきかせやがって!屍肉食らいの犬野郎につくのか、ブランディギロン様につくのか、二つに一つだ!」
私は銅杯のピンニャを飲み干した。喉がひりひりするので、仙人掌の漬物をかじったが、あまり効き目はなかった。
「親父、水をくれ。杯に一杯、それから桶に一杯だ。こいつらの頭を冷やすのに入り用だ」
「何だと、てめえ!ふざけるのもいい加減にしろ!」
「そういうことなら、てめえの死体を役に立てるだけよ!」
左右から剣を抜く音が聞こえた。銅杯に映る歪んだ男たちの手に鈍く光る刃が現れた。左右の男が剣を振りかざすのが見えた。
私は剣を抜き、二人を斬った。抜き様に右手の男の首から肩を斬り裂き、返す刀で左の男の胴を斬り払った。左右から盛大に鮮血が噴き出した。首を竦めたが否応無しに血飛沫が降りかかった。
二人の男は血をまき散らしながら、床の上に頽れた。
「親父、すまんな。杯を代えて、水をくれ」
主は黙ったまま無表情に一瞥をくれ、水を注いだ。左右の男たちが騒めき立った。剣を抜く音が幾重にも谺して聞こえた。その音に混じって、酒場の扉が軋んで開く音が聞こえた。女の匂いが足音と共に近づいてきて、私の右隣の席に座った。
「私はコルデよ。あなたは」
コルデと名乗った女は透き通った青い瞳で私を見据えた。少しだけ目を細めて、珊瑚色の唇にしわを寄せ、微笑んだ。そうすれば世界中の男が平伏すとでも、思っているのだろう。
輝くような金色の髪が波打っている。胸の大きく開いた白い服には、赤と黄の砂漠の花が刺繍され、幅広の光る青い繻子の腰帯をきつく締めていた。帯の上下では乳房と尻がそれぞれ前後に大きく突き出していた。
「スナブ・ランケン、旅の者だ」
コルデと名乗った女は「私にもピンニャね」と言って、主に微笑みかけた。無愛想に差し出された酒杯をあおり、床の上の死体を一瞥した。
「腕が立つのね。ブランディギロンにつきなさいよ、私が口を利いてあげるわ。強い男には金を惜しまないわよ」
金髪の女はそう言って私の膝に手を置いた。私は注意深く彼女の白く肉付きの良い手をつかみ、帳場の上に戻した。女はくすくすと笑って、これ見よがしに乳房を震わせてみせた。
また扉の軋む音がして、足音が近づいてきた。コルデの笑いが止み、冷たい視線が私を通り越して、新しい客に注がれた。足音は私の背後で一度止まった。銅杯に映る歪んだ女の姿は床の上の死体を見ているようだった。女は私の左隣に座った。
「ルッカ、ピンニャをちょうだい」
女は囁くような声で言い、影の濃い大きな鳶色の瞳が私を見据えた。にこりともしなかったが、その視線に男が平伏すと思っているのは、彼女も金髪女と同様らしかった。
女は差し出された銅杯から一口酒をすすり、不機嫌そうに赤い唇を歪めた。痩せていて青白い肌をしていた。肌に張り付くような黒い服はあちこちが透かし刺繍になっていて、白い肌に絵模様を描き出していた。漆黒の髪に真紅の布で作られた花飾りを刺していた。細い腰帯も真紅だった。
「あなたが斬ったのね、大した太刀筋ね。私はイヴォーン、あなたは?」
黒髪の女は細い指先を私の肩に這わせて囁いた。私は左手で水の入った杯を持ち、注意深く彼女の手を払ってから答えた。
「スナブ・ランケン、旅の者だ」
「そう、おもしろい名前ね。うちの頭目もおもしろい名前なのよ。ラスヴィップって言うの。この腕なら稼げるわよ。うちに来なさいよ」
私は生ぬるい水を一口飲んだ。右側のコルデという女は残っていたピンニャを一気に飲み干した。左側のイヴォーンという女は銅杯を口に運んで静かに傾けた。
「何しに来たのさ、この雌犬!」
コルデが語気鋭く言った。
「雌豚には関係のないことよ!」
イヴォーンがひどく冷たい声で返した。
蝿の羽音がした。女たちにはひと足遅れたが、蝿たちが死骸の臭いを嗅ぎつけて、どこからか飛んできたらしい。
「旦那、どっちに付くか決めたらいい」
主が相変わらず、私の方を見ないままそう言った。
「この町ではどっちにつくか、決めなきゃいけねえ。そうでない者はさっさと出て行くかだ。でも、旦那はもう斬っちまったからな、そうはいかねえな」
「やれやれ、二人斬ったら百人斬る羽目になるのかね」
「旦那が斬られちまえば、それでお仕舞いだよ」
二人の女が立ち上がり、私から離れた。左右の男たちが剣を構え直す音がした。私も立ち上がって、帳場を背にして剣を構えた。
「お兄さん、もう一度聞くわ。ブランディギロンにつきなさいよ。そうね、一日四十ペイゾスでどう?」
「豚小屋になんて行くことないわ。うちに来れば五十ペイゾス出すわ。ラスヴィップにつきなさいよ」
「うちも五十ペイゾス出すわ。犬小屋に繋がれるなんて、真っ平でしょ!」
どうやら一日五十ペイゾスというのが、この町での相場らしい。確かに実入りはいいかも知れないが、命を懸ける意味がある仕事が待っているとは思えなかった。
「さあ、兄さん、はっきりしてちょうだい」
コルデという金髪の女は青い靴で床を鳴らした。
「うちに来るんでしょう、旅の御方」
イヴォーンという黒髪の女は赤い爪で私を差し招いた。
人間たちの下らない騒ぎには関係なく、蝿たちは死骸の上で忙しそうだった。彼らの仕事を一気に増やすことになるのかも知れない。青でも赤でも金髪でも黒髪でも、もちろん旅の者でも、彼らには何の関係もない。
「来ないのならあの世に行きな!」
「うちじゃなけりゃ、地獄行きね!」
二人の女が同時に叫んだ。二人で芝居の稽古でも積んでいるのかも知れない。左右で鋼の刃が振り上げられたその時、鐘の音が聞こえた。陰鬱な低い響きのある鐘が鳴り渡った。皴でも入っているのか、びりびりと震える濁った音が入り混じり、頭の芯に鉄の杭でも打ち込むかのような、暗い力強さに満ちた鐘の音だった。
途端に酒場の中に奇妙な気配が広がった。破落戸どもは顔を見合わせて、剣を下ろした。不満と不安が野卑な顔には浮かんでいるように見えた。二人の女はもう少しうまく表情を隠していたが、心地よくない何かが彼女たちの心中にも沸き起こっているのは確かなようだった。
「命拾いしたようね、兄さん。でも、これでお仕舞いじゃないよ」
「私たちが戻ってくるまでに、どっちにつくか決めておくのよ、いいこと?」
二人の女は仲良く台詞を分け合うと、それぞれ青と赤の男たちに視線を送った。やくざ者たちは私が斬った二人の死骸を引きずり、陰気な顔つきで酒場から出て行った。鐘の音はまだ鳴り響いていた。
「どこに行くんだ、奴らは?」
「ダムンファンの神殿さ。町の南の外れにある。お前さんが斬った二人を神様にお供えするのさ」
主は帳場から出てきて、床の血溜まりの掃除を始めた。酒場の真ん中あたりの床には幾つも黒ずんだ染みがあった。
「そんな神の名前は聞いたことがないな」
「ダムンファンってのは祭司の名前さ。神様の名前は知らんよ」
「奴らはその名無しの神の信者なのかい」
主は柄雑巾を動かす手を止め、こちらを見て乾いた笑い声をあげた。
「奴らが崇めるのは金だけさ。お目当ては神殿にあるっていう宝石でできた神像だよ。祭司に取り入って、そいつを手に入れようとしてるのさ」
私は杯に残っていた水を飲み干すと、立ち上がった。
「今の内に町からでた方が身のためだ。食い物なら少し分けてやる」
「晩飯の用意を頼むよ。僕も名無しの神の御利益に与ってみよう」
主はあきれ顔で手を振り、床の掃除に戻った。私が軋む扉を押し明けると、背中で声がした。
「くたばるんなら店の外にしてくれ。掃除が大変なんだ」
「ああ、そうするよ」
私は町の南の方に急ぎ足で向かった。