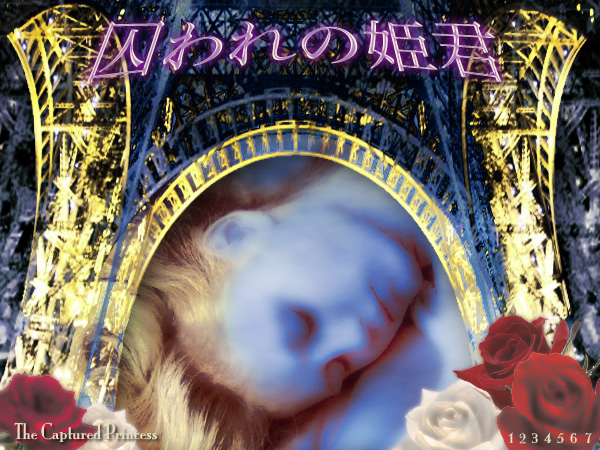
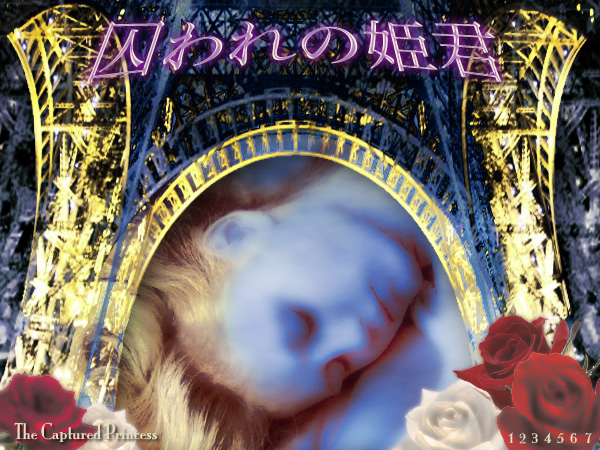
イオロープの地は荒廃の地だ。ウーリャンの山々を越えて西の彼方に広がるその地はかつて世界をおおった大いなる悲劇によって大層な痛手をうけ、長い年月が過ぎた今日でも、その傷が土地とそこに住む人々から消える事がないのだという。
イオロープと一口にいってもそれは相当に広い地を指しており、北には雪におおわれたナールヴェーンやゼーデン、南には豊かな果実がみのるタラエリーなど様々な国があるのだが、いったいに人の数は少なく、痩せた土地を耕し、あるいは獣を追って─イオロープにはほかの土地では御目にかかれない、あきらかに異常な姿をした獣が見受けられた─細々と暮らしていた。
人々は迷信深く、部族ごとに様々な神々を崇めていた。ただひとつジュザースという神はどこに行ってもその名を耳にする事が出来たが、それは忌み嫌われる不吉の神の名なのだった。
私は世界を放浪する当て所ない旅の途中で、この地に入り込んだ。数カ月の旅の後、鋼の街ダーチェンを後にして、パアリシュと呼ばれる街─より正確には街の跡だろうか─にたどりついていた。
既に故郷のサンジェリィの街を旅立ってから、かなり長い月日が過ぎており、私の心には旅の途中で出会った幾つもの事件によってある種の淀み、澱、といったものが溜まってきていた。世界にはおぞましい物事が多すぎる。何故、人々は暗黒の申し子どもと関りを持ちたがるのか。本当に醜いのは何者なのか。
ここはそういった憂鬱を抱えた私にはまさにうってつけの風景を提供してくれた。
パアリシュは廃虚の街だった。
そこにあるのは灰色と赤茶色の石とも金属とも見極めかねる固まりだった。どろどろに溶けた何物かが再度固まったかのような、ねじれた不安形の固まりが到るところに林立して、灰青色の空に向かっていた。その不可解な彫刻とも見える物は大きな家程の大きさの物から、人程の物まで何百、何千とあり、私を奇怪な異形のものの墓場に来たような気分にさせた。
誰も住むものはない廃都だと私は聞いていたが、無銘の墓標の中を馬で行く内、人のざわめきのような物音が聞こえてくることに私は気づいた。それもひとり二人の物音ではない。大勢の人間がこの街のどこかにいるようだった。
こんな死の街で大勢の人が一体何をするというのだろうか。私は音のする方角をめざして、馬を進めた。
冷たい風に乗ったその音は街の中央辺りにそびえる塔の方から聞こえてくるようだった。塔は高く街の外からでもよく見えた。高さ三百イート(約百メートル)もあろうか、街に建つ灰色と茶色の固まりと同じような物で出来ているらしく、錆びた鉄のような色合いだった。実際、大きな鉄か何かの柱を何百本も組み合わせて、そこに石の板を取り付けていったふうにも見えるが、きちんとした形という物はなく、全体の輪郭は大雑把に削られた巨大な石の柱といった感じだった。
塔に近付くにつれ、ざわめきは大きくなっていき、塔の周囲に多くの人間がいるのはもう確かなことのようだった。
やがて、建ち並ぶ物がふっとなくなり、視界が開けた。塔の周りは直径数百イートの大きな空き地になっておりそこに一隊の軍勢が野営をはっていた。
幾つもの白い天幕に青と紫に染め分けた三角旗を立て、数百人の兵士たちが鎧兜に身を固めていたのである。
私は好奇心に引かれるままに軍勢に近づいていった。兵士たちは各々の武具を磨いたり、馬の世話をしている者もいたが、草原に寝そべっている者や、カードで賭けごとにいそしんでいる者も見受けられた。戦を前にしてのしばしの休息といった所なのだろうか。
彼らの甲冑はきらきらと光る銀色に磨き上げられ、青と紫の羽飾りを幾つもつけた派手な物だったが、中には傭兵らしい、黒ずんだ傷だらけの鎧姿の者もいるようだった。
私がひとつの天幕の方へ行こうとすると、近くに立っていたひとりの兵士が声をかけてきた。
「おい、おまえ、とまれ、とまるんだ」
「僕のことですか」
「ぼ・く?何を珍妙なことをいってる。おまえは宮廷詩人か何かのつもりか」
まだ若い髭面の背の低い男だった。黒と赤の鎧は彼には少々大きすぎるように見える。眉間にしわを寄せた顔は余りこわもてのするものではなかったが、目付きは鋭いものがあった。
「詩はあまり得意じゃなかった。ドニエル先生にはおまえは散文的人間だといつも言われてたね」
兵士はうさんくさげに髭をなでた。
「学のあるのはわかったが、何しにここに来た。答えろ」
「何でもない、物見遊山の旅人さ」
「こんなところに物見に来る奴はいない。いるとしたら頭のおかしな詩人ぐらいだ。もう少し学のあるところを見せろ」
男は広刃の剣を抜いた。
「詩人に恨みでもあるのか。自分の理解出来ないものをけぎらいするのは学のない証拠だ」
「なんだと」
剣が振りかぶられ、繰り出された。私は手綱を引いたが、剣先が馬の脇腹をかすめ、馬は竿立ちとなった。
私は振り落とされた。兵士の剣が振り下ろされてくる。地べたを転がって切っ先をよける。足をのばして、男の足首を引っ掛けた。
奴がよろける合間に私は立ち上がって、剣を抜いた。
「物見遊山だといってるだろう」
「そんな台詞を信用する程馬鹿じゃない。ヌーヴァルーの手の者だろう、きさま」
兵士の一撃が襲ってきた。右へとんでよけ、奴の左肩に斬りつける。広刃の剣が私の剣をはねつける。背は低いが膂力はあるようだ。
我々は互いに有効な一撃を与えようと斬り結んだが、かすり傷を互いに幾つか負わせただけでなかなか決着を付けることが出来なかった。そのうちに騒ぎを聞きつけた周りの兵士たちが集まり出した。加勢するかと思ったが、彼らは我々の周りを取り囲み口々にはやし立てた。
「行け!ユイス、そこだ」
この男の名はユイスというらしい。
火花が散って、私とユイスの剣が組み合った。奴の方が力はある。私はじりじりと押し戻された。何人もの血が染み着いているであろう、少々刃こぼれのした刃が迫ってくる。
「くたばれ」
ユイスが口から唾をとばした。
「やめろ、やめないか二人とも」
太い声がして、鞭が飛んできた。背中に焼けるような痛みがはしって、私はひっくり返った。ユイスもすぐそこで肩を押えている。
黒い馬に乗った騎士が立っていた。ぴかぴかに磨かれた銀の鎧に身を包み、兜にはやたらといっぱい羽飾りを付けている。位の高い奴のようだった。
「これは何事だ、そこの傭兵、説明してみよ」
ユイスが答えた。
「この男が天幕の周りをうろうろしていましたので、誰何したところ、物見遊山だなどと怪しげなことを言いますもので……ヌーヴァルーの手の者かと」
「ふむ、確かに怪しげな風体の者だ。異国人のようだな。塔の魔道師の使いか、きさま」
「さっぱり話がわからない。僕は遥か大洋の向こうのサンジェリィという街から来たスナブ・ランケンというものだ。パアリシュに来るのは初めてだし、塔のことも知らない」
羽飾りの騎士は鞭の柄を握り直した。
「サンジェリィ?そんな街のことは聞いたことがないぞ。地図でも見たことがない。きさま、やはり怪しげな奴だ……」
「ピールエ、私は知っているぞ、その名の街を。父君の本で読んだことがある。西の地の遥か彼方、大いなる海を越えたさらなる彼方にそういう名の街があり、たいそう栄えていると書かれていた」
「はっ、殿下」
集まっていた兵士たちがさっと左右に退き、真っ白い馬に乗った男が現われた。やはり銀の鎧姿だったが、鞭の男のそれに比べて、はるかに優美で繊細な細工が施されており、実戦に使うよりは城の壁龕に飾っておいたほうがいいような代物だった。胸甲には翼を広げた優美な鳥の姿が打ちだされ、そこここに宝石がきらめいていた。両頬を上げた兜の中の顔は少年といってもいい若さだった。青白く繊細な感じのする美しい整った顔だ。水色の瞳はどこか物憂げに曇っている。
「ピールエ、その男の話が聞きたい」
「はっ、しかし、殿下、この男は素性の知れぬ怪しい奴でして……」
「ピールエ、その男がヌーヴァルーの手の者であればもう少しましな別の手口を使い我らを謀るであろう。こやつは我らを謀っているようには見えぬ」
「ははっ」
美青年は抑揚の少ない感情を隠した声で私を放すように命じた。
私は天幕のひとつへ連れていかれた。一番大きな天幕というわけではないが一番豪華な物であるのは間違いない。深い紫の絨毯が敷かれた中は、どれもこまやかな名匠の技で造られた芸術品といえる調度がいろいろ置かれていた。
その奥の一段高い所に熊でも座れそうな銀と金をちりばめた椅子が置かれ、“殿下”が座った。
小柄な彼はその椅子に抱かれているように見えた。
「名は何といったかな」
白絹を纏った少年が、葡萄酒らしい赤いものがはいった酒杯を銀の盆にのせ、はこんで来た。
「スナブ・ランケンと申します」
「スナブ…ランケンか。響きが面白い。おまえの祖先はダーチェンあたりの出ではないか」
「さあ、イオロープの人間の血がはいっているという話は聞いたことがありません。三代前くらいにアニャチかどっかの血がはいってるとは聞かされたことがありますが……」
「そうか。スナブ・ランケン、私はヴォナプ・アロン、フラーテン王国の第八王子だ」
フラーテン王国はパァリシュから南部のかなりの土地を支配している国だった。その王子様がこの廃都で何をしているのだろうか。
「スナブ・ランケン、遠い異国の男よ、さあ、フラーテン自慢の酒を試すがよい。神の恵みで我が国の土は実りが豊かなのだ」
酒は酢っぱく、サンジェリィの酒場では安酒といわれそうな物だった。癖のある苦みも舌に残った。
「さあ、スナブ・ランケン、おまえのやってきた街の話をしてくれ、サンジェリィの街の話を。人々はどんな暮らしをしている?」
私はサンジェリィが交易によって富を得て栄えていること、ここ数十年、戦はなく、一応の平和が続いていること。民議会があり、王と権力を分かち合っていること、ラグラン大通りの賑やかなさま、ロキオネンス大祭の大騒ぎ、共存する幾多の神々と宗教のことなどを話した。
王子は時折うなずき、短い質問をはさんだが、ほとんどのときは天幕の向こうを見通すような目付きで私の話に聞きいっていた。心は肉体を抜け出てサンジェリィの街をさ迷っているかのようだった。私もまたどこか夢見ているような心地になり、知らず知らずのうちに言葉が滑らかに口から出ていった。どうもこの酒には何か特別の効用があるらしい。
「殿下、殿下はこのような土地で一体何をしておられるのですか。この軍勢は一体何のため、御見受けしたところあの奇怪な塔を取り囲んで攻めようとしておられるようですが、あの塔には何があるのでしょうか」
ヴォナプ・アロンは小姓から二杯目の酒を受け取るとひと口飲んだ。視線が天幕の中に戻り、私の顔を見た。
「おまえは物見遊山で世界を旅しているといったな。そのような奇特な男なら私の話も理解し得ることだろう。スナブ・ランケン、私は囚われの姫を救いだすつもりなのだ」
そう言った王子の声にはまさしく夢見るものの響きがあった。私はこの若い王子が政に携わる姿を思い描くことが出来なかった。
「あの塔には何処ぞの姫君が閉じ込められているのですか」
「名はイマーニュ姫という。私と姫は数奇な運命の糸で結ばれている。姫はあの塔にすむ邪悪な魔道師ヌーヴァルーによって捕えられているのだ。私と姫とはアビュリエの定めた二人なのであり、ヘヴァンの天界に至るまで分かち難い仲なのだが、ヌーヴァルーは私からイマーニュ姫を奪った。彼もまた姫の天上人のような美しさと魂の気高さに心を奪われてしまったのだ」
「それはさぞかし姫の身の上がご心配でしょう」
「ヌーヴァルーはイオロープでも指折りの力を持った魔道師だと聞いている。人の心を自由にあやつるくらいの術は奴にとっては指をはじくだけの問題だともな。だが私は信じている。如何な邪悪な力に満ちた魔術であろうともイマーニュ姫の心を私から引き離すことは出来ぬ。妖術使いが怪しの技を使えば使うほど姫の心は私と堅く結びついていくのだ。それがアビュリエの白い羽根に愛でられた愛の力というものだ」
若き王子は青白い頬を幾分紅潮させ、声音もかんだかい物となっていた。
「殿下、この私を殿下の軍勢に加えていただけはしませんか、今のお話しを聞き、ぜひ、私も魔道師を打ち、姫君をとり戻すのに力を添えたくなってきました」
「おお、スナブ・ランケン、おまえも我が軍に加わってくれるか。おまえの異国の知恵が役に立つこともきっとあることであろう。そうか、私と戦ってくれるのか。そうか、そうか」
ヴォナプ・アロンは本当に嬉しそうに、美しい顔を崩した。その笑みは余りに無邪気とも思えた。
