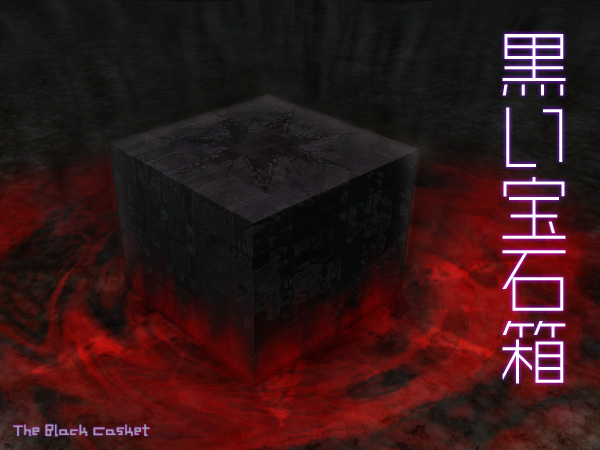
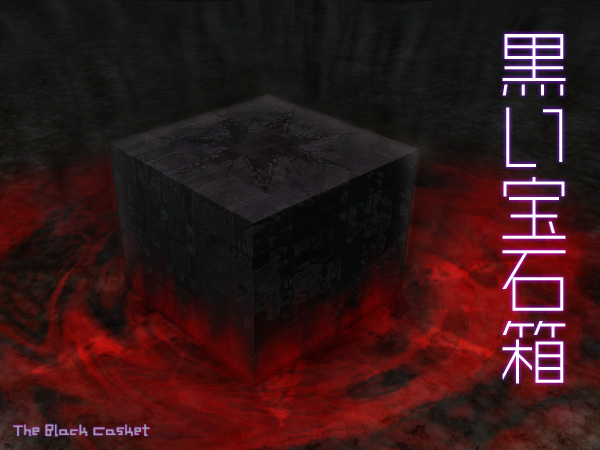
夜更けに扉を叩く音がした。私は春雷の轟きに目を覚まし、染みの浮いた天井を眺めて、寝床の中で春先の生ぬるい空気を吸っていた。小さく弱々しい音は、雷鳴の隙を縫うように聞こえてきた。
寝台の横の机に放り出してあったしわくちゃの灰青色のシャツをはおり、私は来客を出迎えた。顎髭のざらざらとした手触りが、何となく気になったが、この刻限に密会する約束は今日はなかった。
玄関の扉を開けると、女が立っていた。夜目にもわかる冴えた月光のような青白い肌をしている。濡れた黒髪は乱れ、額と肩にかかり、灰白色の飾り気のない長衣にはところどころ染みがある。
女は私が手に持った洋燈の明かりにたじろいだように、眉根を寄せ、ほっそりした手を顔に当てた。
「明かりを、明かりを下げてください。まぶしい……」
女は幾分しゃがれた細い声で言った。私が洋燈を下げると、安堵の吐息をもらしたが、それは喘息患者の苦しげな息の音のようだった。
外は細い雨が降っており、稲妻が時折、濡れた石畳を光らせている。
「御用件は?話によっては、中へどうぞと言うことも出来る」
女は顔を上げ、私と視線が合った。灰色がかった薄い青色の瞳は、氷のように冷たく、春の夜の暖かさを一瞬でかき消す力を持っていた。
細面の美しい女だったが、化粧が濃すぎるのか、白い仮面をつけているかのように、表情が乏しかった。薄い唇には、どぎつい真紅の紅を塗っている。その塗り方がひどく無器用というか乱雑で、本来は整った形をしているらしい唇を、歪んだものに見せている。私はその歪んだ赤い唇が、なぜか、ひどく恐ろしいものに思われた。
その唇がぎごちなく動いて、しゃがれ声で彼女は話した。
「ここで、結構です。話はすぐに済みます。あなたがスナブ・ランケンさん、探偵をしていらっしゃるのですね」
私はそうだと答えた。
「あなたに仕事をお願いしたいのです。これをある男に届けてほしいのです」
そう言う彼女の手にはいつの間にか、黒い小箱が載っていた。
掌ほどの大きさで、ニアインク(約五センチ)程の厚み、方形をしている。黒く艶がない。天鵞絨張りのようにも見えるがよくわからなかった。
「これをインジャンクス街のオル・モルという男に渡してください。ガラッジュ館という屋敷に住んでいます」
「なぜ、自分で渡さない。それから、この箱は何かね。引き受けるのはそれを聞いてからにする」
一際、激しい電光が閃き、彼女は青紫の光の中に立つ細く黒い影になった。氷のような青い双眸とねじれた赤い唇だけが、その中で奇怪にもくっきりと浮き上がって見えた。
「私はオル・モルの恋人です。これは彼への贈り物です。ある貴重な宝石が入っています。私は……失われた愛を取り戻したいのです。ですが、オル・モルと私はある特別な力で隔てられています。それは私には越えられない淵なのです。あなたは、これまでに、たくさんの不可思議な事件を解決なさっていると聞きました。何の力もない私には、あなたにお頼みするしかありません。どうか、お引き受けになってください」
彼女の台詞は、言葉は哀願調のものだったが、およそ抑揚というものに乏しかった。だが、青い氷の瞳から放たれる氷柱のような鋭い光が、それを充分に補っていた。
「一日四十ダズン、他に必要な経費をいただく」
彼女のもう片方の手には、手品のように鈍く光る金色のものが現われた。
「仕事を終えていただいたらば、もう二枚お支払いします」
彼女は私の手の中に大振りの金貨を二枚落とした。
そして、黒い宝石箱を私に差し出した。
「とても大切な物です。間違いなくオル・モルに手渡してください」
「わかった、そうしょう。君の名前は?何とオル・モルに告げたらいい」
「ブラウ・エズと言います」
私は黒い小箱を受け取った。それは紙で出来ているかのように軽く、不快な湿り気があった。
一瞬、ブラウ・エズの指先が私の手に触れた。ひどく冷たかったが、彼女の青い瞳ほどではないと、私は思った。
彼女は一礼すると、背を向けた。横を向いたときに稲妻が光り、黒い輪郭を照らしだした。私には、彼女の腹が妊婦のように、少しばかり突き出しているように見えた。
女は小雨がそぼ降る中を足音もたてずに去っていった。
ガラッジュ館を捜し当てるのは容易いことだった。館は、インジャンクス街では幽霊屋敷として名高いところだったのである。
インジャンクス街自体も、昔は羽振りのいい商人や小金を溜め込んだ小貴族の屋敷が立ち並ぶ街だったのだが、今ではすっかり住人も減り、門扉を鎖した荒れ果てた家が目立つ。数十年前に井戸から悪い水が出て、多数の住人が死んだのが、荒廃の源だとされているが、東部から移り住んだ妖術師が取り行った、ある秘儀によって呼び出されたものの恐怖が原因だという噂もあった。
ガラッジュ館はインジャンクス街でもとりわけ人気のない、周囲を灰褐色の異様にねじれた木々に囲まれた地所に建っていた。木々の梢は、春というのに新芽が芽吹く気配もなく、ただ、薄灰色の空にひね曲がった無数の指先を伸ばしている。空気は湿って生暖かかったが、私はどこからともなく忍び入る奇妙な冷気を感じて、灰緑色の外套の襟を立てた。
緑青が吹いた青銅の門扉は半ば開いており、赤錆びた鉄の鎖が地面に転がっている。乱れた短い砂利道が、雑草と手入れされていない植え込みの間を館まで走っていた。
建物は二階建の四角い比較的小さなもので、傾斜のきつい切妻屋根を戴く木造のものだった。私のわずかな建築に関する知識では、いつ建てられたものか断定できなかったが、百年以上前、クァロニアン帝国時代に遡るものであることは確かなようだった。屋根の四隅には何かの彫像が置かれていたらしい浮き彫り付きの台座が残っていたが、像そのものは打ち壊されて無い。大本は館全体に塗りが施されていたようだが、今はその名残として黒い刷毛跡らしきものだけが残り、それがかえって館に荒れ果てた風情を与えているのだった。
庭に入るとき、門扉の下の足元に、白墨で何かが描かれていることに気づいた。昨夜の雨で形が崩れ、よくわからなかったが、幾つかの歪んだ星型や十字が認められた。あまりお目にかかれない奇怪な意味を持っ文字や印形の類のようだ。何らかの結界がこの屋敷には張られているのかも知れない。
腰に吊ったファバーン剣に手をやった。かすかなしびれるような感覚が伝わってきた。この古代の魔剣はその霊力のほとんどを三千年の歳月により失っていたが、超自然の力を感じて持ち主に伝える力は未だ保っていた。もっとも昨夜、黒い小箱を近付けたときにも、刀身のファバーン文字は緑色の燐光を放った。私の懐にはその黒い箱が入っているわけだから、この屋敷に何かの力が働いているものかは明断できない。
玄関の扉は往時は美しく彩色されていたのであろうが、今は黒ずんだ灰茶色に沈んでおり、この時刻には破風の影になり、四角く暗い窖のような体を成していた。扉と框にも白石灰で、幾つかの象形文字のようなものが描かれていた。東部を旅していたとき幾度か出会った魔道士たちが暗黒の術に用いていた絵文字に、似ているようにも思えた。
どこかで犬が力ない遠吠えを繰り返していた。
私は扉を叩く前に、今日知った事柄をもう一度思い返した。
ブラウ・エズと名乗る幽鬼じみた女がくれた金貨は、すでに使われなくなって久しい古ダズン金貨だった。もちろん黄金としての価値はあるが、それより古銭商に持ち込む方が得策かもしれない。百年は昔の代物なのだ。
警邏隊とヨーコック新聞商会を回ったが、ブラウ・エズという名もオル・モルという名も、事件には係わっていないようだった。ノップラントはトリプロ街で起きた強盗殺人に忙殺されていてひどく機嫌が悪かった。ヨーコックは若い者を使って調べてくれることを約束してくれたが、すぐにという訳にはいかないようだった。
インジャンクス街の『錆びた鎌』という奇妙な屋号の居酒屋では、昼から飲んだくれている二人の酔っ払いと、祖父の代までは貴族だったという主から話を聞き出すことができた。
ガラッジュ館にまつわる奇怪な噂には二種類ある。ひとつは古くからのもので、すなわちインジャンクス街の荒廃をもたらした東方の魔道士の邪悪な術はガラッジュ館で行われたというものだった。館には、そのとき地獄の最深から呼び出されたものが未だに潜み棲み、時折、犠牲者を館に引きずり込んでは貧り食っているというのである。
もうひとつの噂は新しいものでここ一月ばかりに広まったものだった。ガラッジュ館には新しい亡霊が移り棲み、夜な夜なぞっとするような宴を繰り広げているという。誰もいないはずの窓に明かりが灯る。しかも、ただの蝋燭や洋燈の光とは思えない紫じみた稲光の如き明滅や、血のように赤い光が窓から洩れ出ることがあるという。あるいは深夜に聞こえてくる女の苦しげな悶える声、地震かと誤りそうな低い響きのある音。そして窓に浮かび上がる狂った舞踏を続ける朧な人影。
わかったのはそれだけだった。いま少し、館について調べるべきかも知れない。ヨーコックがオル・モルとブラウ・エズについて調べてくれるのを待つべきかも知れない。
しかし、私はこの一件をできるだけはやく、片付けてしまいたかった。より正確に言うと、私は黒い宝石箱を一刻もはやく手放したかったのだ。
この軽い小箱が何でできているのか、私には見当がつかなかった。その軽さからすればごく薄い板でできているとも思われたが、叩いてみた響きからは金属のようにも思わる。表面の天鵞絨のようなものは一夜明けても奇妙な湿り気を失くさなかった。
さらに奇怪なことには、この箱にはどこにも継ぎ目や蝶番がなかった。どうやって開けるのかまったくわからない。上面とおぼしき所には、そこだけ艶のある黒で何かの文字か紋章のようなものが描かれていた。くねくねとした曲線で構成された複雑な歪んだ星型のようなものだ。見比べてみれば、それはガラッジュ館に白墨で描かれた図形と似ていなくもないものだった。
ブラウ・エズは宝石が入っていると言ったが、振ってみても何の音もしない。ただ、耳を近付けてみると、風の捻る音か、海鳴りのようにも聞こえるかすかな音が中から聞こえるのだった。
日輪を意匠化したクァロニアン風の叩き金に手をかけた。鈍い音がする。答えはない。もう一度叩く。やはり答えはなかった。叩き金を引くと扉は簡単に開いた。
薄暗い屋敷の中は蜘蛛の巣と埃の城だった。小さな広間のような部屋には奥に二階へ続く階段が、左右に扉があった。化粧板には古くは彩色模様であったらしいどす黒い渦巻きのようなものが染み付いている。色褪せ、分厚い埃が積もった絨毯の絵模様もまた、黒ずんだ染み状のものと化していた。
埃の上には、幾つもの足跡があった。最近、この屋敷に棲みついた亡霊は、ともかくも二本の足で歩く奴らしい。
人の気配はない。左側の扉が半ば開いている。剣の鯉口を切り、扉を開いた。
そこは、食堂に使われていた部屋のようで、大きな食卓に背もたれの高い椅子が何脚か置かれていた。黄ばんだ食卓布の上にはすっかり曇った銀の燭台が倒れている。奥には台所があったが、やはり曇った銀の食器と黒ずんだものがこびり付いた鍋が幾つかあるだけだった。
玄関に引き返し、閉じているもうひとつの扉を開けた。がらんとした部屋には朽ち果てた椅子が二脚、ぼろ切れのようになった掛幕越しに差し込む灰色じみた陽光を浴びていた。足跡が壁に作り付けになった棚の前に続いていた。棚には古びた小さな洋燈があるきりだったが、埃の積もり具合からして、最近まではそこに恐らくは本がたくさん置かれていたようだった。
棚のすぐ下には、銅貨が一枚落ちていた。昨夜、ブラウ・エズがくれた古ダズン金貨によく似たクァロニアン風の絵模様が刻印されている。
窓硝子には、まだ新しい白い絵の具で、この館では見慣れたものになりつつある絵文字状のものが描きつけられていた。
窓に近寄り詳しく調べようとしたとき、私は背中に何かを感じた。冷えきった氷のような手で首筋をつかまれたような気がした。振り向くのを身体が拒絶していたが、手をかけたファバーン剣の柄から伝わる警告が私を動かした。
剣を抜きながら振り向いた。鉛色の刀身に、角張った神秘文字が緑色の光を放っていた。一イート(約三十センチ)程の扉の隙間から、黄色く光る目が私を見ていた。小さく、吊り上がった獣の目だ。ただし、この世の獣ではない。その目は四つあり、まったく不規則な付き方をしているのだ。顔や身体がどうなっているのかは良くわからなかった。扉の向こうからのぞいているのは、蠢く黒い泥のようなものだった。黄色い目は一つひとつが生き物であるかのように、その生きた泥の中をゆっくりと動いていた。
黄色い目と視線があった瞬間、私の脳髄にも氷の触手が入り込んできた。まるで脳味噌の皺の中に氷を突っ込まれたような不快感があった。
私はすぐさま、行動に出た。黄色い目はそれだけで私を殺すことが出来るのだ。ならば、私が先に、奴を生れ故郷の暗い深淵に蹴落とすしかない。
私の指先を離れた手裏剣は、獣の目のひとつに命中した。琥珀色と白緑色の体液が飛び散る。奴は、気の触れた猿のような叫び声を上げた。扉が木端を散らして裂け、奴は黒い全身を現わしてこちらに突進してきた。
そいつが何に似ているかと言われれば、ナクシャッツの密林に棲む大猿とでも言うしかないだろう。太く長い腕、広い肩、瘻のような曲がった背中、短く湾曲した脚をそれは持っていた。だが、その黒い身体に毛は一本もない。全身を濡れたように光る泥状のものに覆われていた。黒い鉤爪のついた三本指の先からは、その黒い汚泥がしたたり落ちている。それには正確な意味での顔と呼べるものはなかった。頭らしき歪んだ卵型の部分の前に、今は三つになった黄色い目と、口らしき黒い穴が開いているだけなのだ。潰れた目には手裏剣を突き刺したままだ。
埃だらけの床の上にべっとりと黒い染みをつけながら、そいつは襲いかかってきた。黒い爪が猛烈な速さで振り回される。私は後退り、棚のある壁際に逃れた。爪が棚を引き裂き木屑に変える。
奴が勢い余って壁にぶつかる間に、私はもう一本の手裏剣を投げ付けた。三分の一イート程の短刀は化け物の頭の後ろに、まるで頭蓋骨などないかのように深々と突き刺さった。怪物はさらにおぞましい叫び声を上げ、後頭部に刺さった手裏剣を抜こうとしたが、奴の三本指は自分以外のものの命を奪うためにしかつくられていなかった。
私は奴の脇腹にファバーン剣を叩き込んだ。明らかに生身のものとは異なる手答えがあった。深く長い傷からは白濁した汚液がほとばしる。
怒り狂った奴の長い腕が私をとらえた。強烈な一撃に私は五イートも吹き飛ばされ、壊れかけていた椅子の上に落ちて、それを薪に変えた。口の中に塩辛い味が拡がる。
化け物は頭と顔に短刀を突き立てて、迫ってくる。口からは黒い泡が吹き出し、腹から流れる白緑色の体液と混ざり、汚らしい灰色のしたたりを振りまいている。
六本の爪をのばす奴の腹を私は蹴り上げた。一瞬、沓底が粘つく黒い皮膚にはりつく。黒い爪が頬をかすめ、血がにじむ。埃まみれになって、床の上を転げて避け、玄関の広間に転がり込んだ。半壊した扉を蹴って閉める。
奴が扉をばらばらの木片に変える間に、私は立ち上がってファバーン剣を構え直した。
狂気じみた叫びと共に黒い化け物が飛び込んできた。私はこれ以上はない正確さで、鈍ることのない刃を奴の脳天に深々と食い込ませた。
喉まで斬り裂かれた奴は、絶叫の代わりに膿のような白い液を飛び散らせて、目茶苦茶に手足を振り回した。羽目板を叩き破り、絨毯を引き裂き、それでもなお黄色い目に憎悪と殺意をぎらつかせて、向かってくる。
私は食堂への扉に後退し、手裏剣をさらに二本、投げつけた。一本は長い腕に阻まれたが、もう一本は分厚い胸板に突き刺さった。
この地獄の淵から這い昇ってきたかのような獣にも心の臓というものがあるのだろうか?信じ難いことに奴は死の舞踏を止め、手擦りを打ち壊しながら、階段に倒れ込んだ。
私は自分の心の臓が十回ほど脈打つ間、奴を見ていた。仰向けに倒れた化け物は手足を痙攣させ、ごぼごぼと泡を吹くような声を発している。黒い身体の下には大量の白緑色と薄い黄色の体液が溜まりをつくっていた。
ゆっくりと近づき、止めの一撃を加えるべく、剣を振り上げた。
そのとき、奴の背中が裂けた。一イートばかりも、ぱっくりと黒い肉が裂けて、白濁した液が吹き出したのだ。
傷口からは、黒い塊が飛び出した。私は反射的に剣を振ったが、黒いものは恐ろしい速さで、階段を上がっていった。
ほんの一時しか、そいつを目に留めることはできなかったが、私にはそれは蜘蛛のような何本もの脚をもった心の臓のように見えた。
足元では、怪物の身体がおぞましい変化を始めていた。主を失った黒い身体は、見る見るうちに溶けだした。身体中に大きな水泡状のものが盛り上がり、それがはじけて、白と黄色の膿のような体液が流れ出した。やがて、ぬめる皮膚も形を失い、黒い汚泥の塊になった。三本の手裏剣が灰色の液体の中に残ったが、拾いあげる気にはならなかった。
注意深く死骸(と言えるのだろうか)をよけて階段を昇った。小さな踊り場があり、扉がひとつだけある。ここにも奇怪な呪文のようなものが描かれている。扉は少しばかり開いていた。框に身を隠し、中を覗いた。薄暗い部屋には動く影はないようだった。
足で扉を蹴り、中に入った。剣を構え、左右を見渡す。動くものはない。
二階全部を占めている広い部屋は奇怪な品々で満ちていた。左右の壁には大量の古びた書物と巻物が並んでいる。大小の机の上には、硝子と青銅、鉄と銀の環状、管状、椀状、その他形容できない形の器具が所狭しと置かれ、錬金術かそれに類する実験が行われていたことを示していた。
部屋の中央には大きな鉄の寝台のようなものがあり、その周りには、白石灰で、あの東部風の怪異な文字が、円を描いて書きつけられていた。寝台の四隅には鎖と手錠らしきものが取付けられている。化学の研究ではすまない何か異常な行為がこの部屋であったことは間違いないようだった。
右手には大きな水槽があり、中にはどす黒い濁った液が入っている。その液体がかすかに揺れていた。水槽の縁には黒と白の粘液状のものがまだ濡れて光っている。中で動くものがある。
突然、黒い水が吹き上がった。天井近くまで柱のように昇り立ち、生命あるもののように形をつくろうとする。不確かな人型とも見える十字形になり、頭頂部に黄色い光点が揺らめき始める。
私は全力で水槽に駆け寄り、黒い十字の真ん中にファバーン剣を突き刺した。きいーつという甲高い鳴き声のような音がして、黒い液体は形を失い、水槽の中に崩れ落ちた。
切っ先には、ひくひくと蠢く黒い塊が突き刺さっていた。それは文字通り、脈打つ心の臓に蜘蛛の脚をつけたものだった。細長い八本の脚をばたつかせ、上部からのびている大小の触手(血管?)は蚯蚓のようにのたうっている。
私はそれを剣に串刺しにしたまま、床に叩きつけた。それは潰れて真二つになり、白と黒の汚液を飛び散らせて動かなくなった。
背中で息を飲むような音がした。鉄の寝台の陰に何かが隠れた。黒っぽい長衣の裾が目に留まった。どうやら今度の相手は人間であるらしい。
「オル・モルか。君の恋人から頼まれてある物を届けに来た。これを渡せば、僕の仕事は終りだ。受け取ってくれ」
また、息を飲み込むような音がした。寝台の陰の人物はひどい恐怖にさいなまれているようだった。
「ブラウ・エズは君と縒りを戻したいようだ。とにかく、これを受け取ってくれ。これ以上黒くてべたべたした奴のお相手はご免だ」
寝台の向こうから、痩せた男が立ち上がった。背は高いが猫背気味なので、不健康そうな青い顔色と相俟ってひどく貧相に見える。着ている黒っぽい長衣は、埃と様々な薬品かあるいは何ものかの体液の染みで覆われ、繿布のようだった。萎びた指には青や紫、紅の石がはいった怪しげな意匠の指輪を幾つもしている。
「あいつに頼まれただと?あいつに頼まれた!あいつに!」
オル・モルは、薄い唇を奮わせ、涎をたらしながらわめいた。灰色の目は黒い化け物の黄色い目と同程度の狂った光を湛えているようだった。
「おお、ジルズよ、ヴァッターよ、いや聖なるジャクレン師よ、私をお救いください。私は、私は命を創りたかったのだ。この手で生命を!この世で最も大いなる秘跡に挑みたいと考えることのない魔道の徒が何処にいようか?貴様、私の黒い心臓を殺したな!地獄の第六層から、私が十年の歳月をかけて、現界に引き上げたものを!我が力満ちたる時ならば、貴様を地獄の第六層まで突き落とし、グレイエンの住人の餌食としてやるものを!おおう、貴様のその剣は何だ!ファバーンの神秘文字ではないか!それを私に譲れ!その剣の力借りれば真の生命を創りだせるやも知れぬ。女の腹など借りなくともすむやも知れぬ!ああ!ブラウ!私を助けてくれ!」
狂気と恐怖に捕われた魔道士は支離滅裂な台詞をわめき散らした。私の心は、狂乱する男の言葉を聞くうちにひどく静まったものになっていった。この一件の全容がおぼろげな形を取り、幾つかの事柄が嵌め絵のようにつながっていった。
「ブラウ・エズは君の子供を孕んでいるのか?」
オル・モルは勝手にしゃべり続けていたが、私の言葉に一瞬口をつぐんだ。灰色の濁った瞳を大きく見開き、口の端をわなわなと奮わせた。
「私の子かだと?そうだ、私の子供だ!私がこのはかない現し身を賭して創ろうとした命だ!私の子供でなくていったい何だというのだ!ああ!だが、貴様、あいつが孕んでいるといったな?今でも、孕んでいるのか!」
「僕にはそう見えた」
魔道士は何かの発作を起こしたかのように、口から泡を吹き、東部で信仰されている精霊や神々、聖人の名を闇雲に口走った。
私は隠しから、黒い宝石箱を取り出した。掌の中でそれは、低い捻りをあげ、命あるもののように脈打っていた。
「止めろ!それをしまえ!持って帰って西の大洋に投げ捨てろ!止めろ!そうだ、この宝石をやろう、これはどれも只の石ではないぞ!これで貴様も異界の力を手に入れることができる。この街でならば、どんな望みも能うようになる!さあ、これを持って失せろ!」
オル・モルは震える手で指輪をはずそうとしたが、中々うまくいかなかった。私はその間に、宝石箱を鉄の寝台の上に置いた。間近で見ると寝台には赤黒い染みが幾つも浮かんでいた。
魔道士は東部の秘語で、意味不明のことをわめき散らした。
黒い小箱は、生き物のようにぶるぶると震え、輪郭がぼやけて見える。その周囲の空気が陽炎のように揺らめき、黒い光が、地獄の闇が箱から放射され始める。
「あいつめ、我が子と契約を結んだのだ!あああ!よくも、こんなものを!墓場の地の底から……ああ、おおう、助けてくれ!」
私は振り返らずに部屋を出て扉を閉めた。階段の上の汚物はもう乾燥して灰色の土塊になっていた。
背中で世にもおぞましい絶叫を聞きながら、私はガラッジュ館を後にした。宝石箱の中身は知りたくもなかった。あたりはすっかり夕闇が迫っていた。
人気のない通りをしばらく歩くと、背後から灰色がかった黄色い光が射してきた。明らかに雲間から射す残光とは異なるその光は、私が大きく息を三回吸い込む間続いて、不意に消えた。私は足を速めて、荒廃したインジャンクス街を抜け出した。
トリプロ街のワコフの店を回って、クーリカフ街に戻る頃には、星のない真黒な夜空が頭上を覆っていた。食欲はなかったが、向かいの安料理屋でシェアを一杯と肉と豆の煮込みを胃に流し込んだ。家に戻ると、机の一番下の引き出しから『古鴉』の壜を取り出し、杯に注ぎ、二杯飲み干した。
それから腰に下げていた革袋の中身を机の上に開けた。お馴染みのダズン貨がざらざらと山になった。闇の宝石屋は古ダズン金貨二枚に三百ダズンの値をつけた。
洋燈の光が銅貨の山に当たって鈍く光るのを眺めながら、私は盃を重ねた。ディコンの酔いは、なかなか回らなかった。外では、春雷が不機嫌な声を轟かせ始めた。
時間がゆるゆると流れて、激しい雨音が聞こえてきた。ダズン貨を二つの山に分け、大きい方の山を革袋に戻した。『古鴉』は半分ほど空になった。
扉を叩く音がした。小さな弱々しい音だ。私は立ち上がり、扉を開けた。
ブラウ・エズがずぶ濡れになって立っていた。「中へ」と言おうとしたが声が出てこなかった。青い凍る瞳が私を見据えていた。
雨で濃い化粧が流れて、彼女の顔には醜い斑模様ができていた。絵の具を塗りたくったような白い部分と、青黒く紫じみてさえいる部分とがおぞましい対照をなしている。口紅だけは塗り直したようだったが、塗り方は昨夜にもまして乱雑で、まるで生肉を貧り食い血まみれになったかのように見えた。
「宝石箱はオル・モルに渡したよ。君の目的は恐らく達成できたと思う」
ブラウ・エズは黙ってうなずいた。それから真っ赤な唇を歪ませて苦しげにかすれ声を搾り出した。
「……ありがとう……これはお約束の残りの報酬です……」
女は古い金貨を二枚差し出した。細い指にも青紫のおぞましい斑点が浮きだしていた。彼女の腹は昨夜の倍ほどに、臨月の妊婦のように膨らんでいた。
「いらない。料金は一日四十ダズンなんだ。これは昨日のお釣りだ。手裏剣を三本駄目にした。その分はもらう」
私は彼女に革袋を差し出した。
「私もいりません……私には……必要が…ないもの……」
次に彼女の口から吐き出されたのは言葉ではなくて、どす黒い血の塊だった。長衣の膨れた腹の部分が、信じ難いほど激しく動き、白い服がたちまち朱に染まる。足元にびしゃびしゃという音がして、股間から大量の血とねばつく黄ばんだ液体が流れ落ちる。
「ブラウ・エズ!」
私は彼女の名を叫んだが、どうすることもできなかった。彼女は口許を手で覆ったが、指の間から、血が休みなく滴り落ちた。
「大丈夫よ……出口が…わからないのね……どこからでも……約束通り…あなたのものだわ……」
ブラウ・エズは鼻からも耳からもどす黒い血を吹き出した。青く冷たい目からさえ、真紅の雫が滴っていた。腹は異様に膨れ突き出し、内側から激しく突き動かされている。
電光が漆黒の夜空を紫に染め、生ける亡者の無残な姿をくっきりと照らし出した。ブラウ・エズの左の眼球は血に染まり、泥から沓を引き抜くときのような音をたてて、眼窩から飛び出した。真紅の血の穴から、何本もの真っ黒い蚯蚓のようなものが覗き、くねくねと蠢く。
「大丈夫よ……私の…子供だから……」
くぐもった声でそう言う彼女の口からも、黒いぬめぬめした無数の触手が蛇の舌のように飛び出した。
私は遂に耐え切れずに扉を閉めた。
何かが破裂する音が聞こえた。扉に重くて柔らかいものがぶつかった。
雨と雷が一層激しくなり、扉の向こうから聞こえてくる尋常ならざる恐怖の音の大部分をかき消した。だが、雷鳴と雷鳴の短い合間に洩れ聞こえるのは、ずるずると何かを啜るような音、ばりばりと肉と骨が噛み砕かれるような音、そして何よりもおぞましい、さも美味そうに、何かを飲み込む喉を鳴らすような音だった。
私は何もすることができずに、只、扉の向こうの地獄の宴の音に、耳をすませているだけだった。
弱々しい曙光が射すころ、雷雲が去り、雨音が消えた。扉の向こうからはもはや何の物音も聞こえては来なかった。私はどうしようもない嫌悪感と吐き気をこらえて、扉を開けた。
黒ずんだ血に染まった、ずたずたのぼろ切れが落ちている。どうやらそれはブラウ・エズが着ていた長衣のようだった。二枚の古ダズン金貨が、雨に洗われて、本来の輝きの幾分かを取り戻したように、石畳の上に転がっていた。
淡い桃色の朝日が、家々の屋根の向こうに顔を出した。だが、陽光はこの惨劇から逃げるかのように、すぐに灰色の雲の中に引きこもってしまった。
ヨーコックからの使いが来たのは次の日の昼過ぎだった。オル・モルについては、二ヵ月ばかり前に東部から流れてきた妖術師らしいということしかわからなかった。だが、彼については不可思議な符合がひとつある。数十年前にガラッジュ館で暗黒の術を取り行った魔道士の名はオウ・ルモールだという、不確かな話があると言うのだ。
ブラウ・エズについてわかったことは只ひとつだった。そういう名の女が、市の共同墓地に病死として一週間前に葬られていたということである。
雨は路上の血は洗い流してくれたが、扉に染みついた赤いものまで落としてはくれなかった。私は大工を呼んで新しい扉に付け変えた。それから共同墓地のブラウ・エズの墓に、小さいが少し値の張る墓碑を立てた。
それでも古い金貨はまだ一枚残っていた。私は空っぽの彼女の棺に、血が乾いてかたくなった長衣の代わりに、ラグラン大通りのキュークの店で、一番値の張る舞踏会用の服を収めた。そんなものを彼女が喜ぶかどうか、皆目わからなかったが、私には他にできることがなかった。