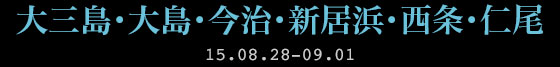
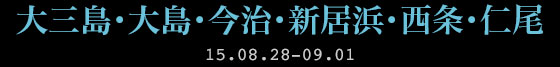

|
 |
 |
 |
|
塩田邸の雨どい。
|
屋根の重なりも美しい。 | ただの自治会館ですが、石碑を見ると、菊池寛の母親の生家跡とあります。 |
 |
 |
 |
| 賀茂神社。この一の大鳥居は1706年に丸亀藩主を迎える時に歓迎のために建立したとか。 | 賀茂神社の創建は1084年。仁尾は元は京都の下賀茂神社へ寄進した荘園だとか。そのご縁で京都から勧請。 | 賀茂神社の注連石(しめいし)。明治時代に漁船の通行の邪魔になっていた岩を海から引き揚げ、ここに運んで奉納したものとか。 |
 |
 |
 |
| 何やら意味あり気な井戸ですが、由来はわかりませんでした。 | 賀茂神社本殿。 | 境内にある羽衣の松。樹齢三百年とか。云われは不明。 |
 |
 |
 |
| 灯籠が並んだ向こうは叶座跡、人形芝居発祥の地とありました。 | 賀茂神社境内の水路は運河経由で海とつながっているようです。 | 塩竈神社近くにあったトイレです。木製の金隠しとは、いつごろのものなのでしょうか。 |
 |
 |
 |
| 埋め立て地との間を流れる運河。雨風激しく、海まで行くのは断念。 | 流下式塩田竣工記念の碑。昭和三十二年とあります。大正、昭和は塩田が街を支える産業でした。 | 金毘羅灯籠。江戸中期のものを近年復元したもの。石垣は昔のもの。かつてはこのあたりまで海。 |
 |
 |
 |
| 古い倉庫が残る一角。 | この石段は船着場の跡のようです。 | 古い塀が残るお屋敷。 |
 |
 |
 |
| こちらも古い家。左端に一つだけの虫籠窓がカッコいい。 | 雨がすごくて図書館に避難。人形浄瑠璃の諸々の品が展示されていました。 | 雛人形や武者飾り、張り子の虎など。八朔祭りの飾りとして作られてきたもの。 |
 |
 |
 |
| 辻の札場。江戸時代の高札場。何と1979年まで役場の掲示板として現役だったとか。 | 行きと同じみかん色のバスで託間駅に到着。曽保地区の曽保みかんは特産品。 | 帰りの車窓から見た瀬戸内海と讃岐富士です。 |