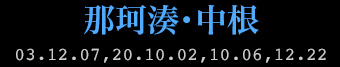
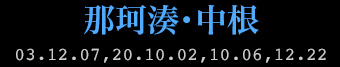

|
 |
 |
 |
|
人骨、太刀や勾玉、蕨手刀などが出土しているそう。こうした横穴が付近一帯に三百以上あるとか。
|
端の方はアーチ状になっていました。十五郎穴というのは曾我兄弟の仇討ちの五郎・十郎が隠れ住んでいたという伝説から。 | 八重崎秋月というのは、中根八景の一つの碑。ここから見る月が美しいということらしいです。 |
 |
 |
 |
| 元はこちら側にも岩があったのでしょうか。 | すぐ近くの虎塚古墳。全長五十六メートル。赤い彩色壁画のある石室があります。七世紀前半のものらしいです。 | 石室の入り口。年二回公開されています。 |
 |
 |
 |
| すぐ側にあるひたちなか市埋蔵文化財調査センター。 | 出土した埴輪や土器が展示されていました。上の小さいのは模型? | 乳飲み児を抱く埴輪。 |
 |
 |
 |
| 虎塚古墳石室の模型です。非常にきれいに残っているようです。 | 虎塚古墳第4号墳。石室だけが残っています。戦後になって削られて畑になってしまったようです。 | 芋畑に夕陽が差していました。 |
 |
 |
 |
| ここから十二月二十二日の分。ちょっと落ち穂拾いをしました。これは那珂湊駅の待合室。ベンチが置かれ、いろいろグッズや展示物も。 | 駅の前にはクリスマスの電飾なのでしょうか。アンコウやタコ、クラゲが鮮やか。 | 湊公園近くの鍾馗神社。由来等は不明。すぐ脇に金龍水松映の井戸というものがあります。 |
 |
 |
 |
| 金龍水松影の井戸。通称大井戸。い賓閣の御用水としても使われ、枯れたことがないとか。震災で断水したときは、町の人たちはここに汲みに来たそう。 | 湊公園にある葵稲荷神社。水戸光圀がい賓閣を建設した時に伏見稲荷から勧請。元治甲子の乱で炎上し、場所を変えて再建されたもの。 | 海門橋近くの黒門銭座稲荷神社。由緒等は不明。 |
 |
 |
 |
| 稲荷神社だけど、狐じゃなくて狛犬です。 | 金山神社。由緒は不明ですが、金物や鍛冶のの神様なのでしょうか。 | 川をはさんで反対側には豊川稲荷。 |
 |
 |
 |
| これは那珂湊天満宮の古い手水石。どちらから鎌倉時代からのもので、どちらかが1714年に奉納されたものらしいです。 | 天満宮から近い宇賀魂神社。稲荷神社の祭神は宇迦之御魂神なので、ここも稲荷神社なのでしょうか。 | 銭座稲荷と同様の狛犬がいました。 |
 |
 |
 |
| 四郡奉行勢屯営跡の碑。元治甲子の乱で、ここにあった造り酒屋を大発勢(天狗党鎮圧のはずが途中から天狗党側に)が屯所として使ったようです。 | 明石家安源七商店。団扇やカレンダーのお店。まちかど博物館の一つ。大正時代の建物。 | 店内には団扇や扇子が並んでいました。 |